はじめに「最新作から厳選!!」
芥川賞受賞作品まとめ ・1950年代「芥川賞」おすすめ9選 ―戦後文学の全盛― ・1960年代「芥川賞」おすすめ7選―女性作家の台頭― ・1970年代「芥川賞」おすすめ6選―文学に吹く新しい風― ・1980年代「芥川賞」おすすすめ3選―空前絶後の❝暗黒時代❞― ・1990年代「芥川賞」おすすめ6選 ―現代女流作家の躍進― ・2000年代「芥川賞」おすすめ10選 ―個性派ぞろいの作家たち― ・2010年代「芥川賞」おすすめ10選 ―バラエティ豊かな傑作たち― ・2020年代「芥川賞」おすすめ7選 -直近全作品を読んだ上で厳選―
芥川賞を年代ごとに紹介するこのシリーズ。
2020年代ということで、いま最もホットな芥川賞作品の中から特におすすめの7作品を厳選して紹介しようと思う。
この記事を読んで少しでも興味を持った方は、ぜひ“次の1冊”の参考にしていただければと思う。
それでは、最後までお付き合いください。
『破局』(遠野遥)
あらすじ
2020年上半期受賞作。
主人公「陽介」は、都内の私立大学(おそらく慶應義塾大学)に通う4年生。
高校時代からラグビーをしていて、鍛え抜かれた肉体を持っている。
強すぎる性欲を持っていて、自慰やセックスに耽る日々を送っている。
女性には事欠かず、麻衣子という交際相手がいる。
いまは就職活動中で、公務員を志している。
一見して、真っ当な社会生活を送っているように見える陽介だったが、麻衣子とぎくしゃくし、灯という女性と出会ったことで、彼の「異常性」が徐々に露呈していく。
考察「絶妙な異常さ」を持つ主人公
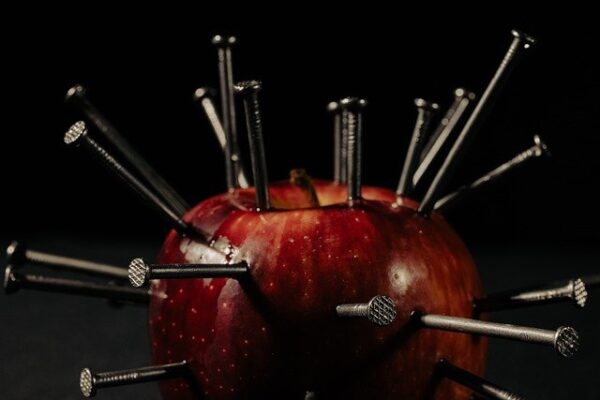
陽介は一見して、真っ当な学生生活を送っているように見える。
友人との交流、彼女とのデート、就職活動……どれをとっても不自由なくやれているかに見える。
少なくても外面的には、間違いなくその辺の大学生か、いやむしろ「高学歴エリート」といった感じで、別段気になる点はない。
ただ、彼の内面には、言葉にするのが難しい「不穏さ」や「異常さ」といったものが隠されている。
本書『破局』は、陽介の「一人称」での語りを中心に描かれていくのだが、物語の序盤からして、読者はかすかな「違和感」を感じるはず。
そして、その違和感は次第に強まっていき、そして、こう確信する。
この陽介という男、何かが変だ。
では、いったい、何が変だというのか。
いくつかあげられるのだが、最も大きいものが「不自然な論理と思考」だといえる。
たとえば、彼はセックスについて、こんな風に述懐する。
セックスをするのが好きだ。なぜなら、セックスをすると気持ちがいいからだ。セックスほど気持ちのいいことは知らない。(P68より)
どうだろう、この「あほな高校生」が書いたような文章。
「セックス」に関してもっともらしく説明しているわりに、その実、なんの説明にもなっていないではないか。
陽介の思考には、こんな感じの、
「え、いります、その説明?」
といった論理が本当に多い。
こうした不自然な論理が、陽介の語りによって描かれていくのだが、それが彼の「不穏さ」とか「不気味さ」とかいった印象を徐々に強めていく。
実はこれは、作者の企みであり、1つの叙述トリックなのだけれど、案外その点に気が付かない読者は多く、ネットなんかを見てみると、
「作者には文才がない」
「登場人物に共感ができない」
とか、割と好き放題に批判している。
だけど、そもそもこの作品に「共感」とか、「面白さ」とかを求めるべきではない。
むしろ、この陽介という人物の絶妙な「異常さ」にゾクゾクしながら読み進めていく
敢えて言えば、これが、本書の“正しい”読み方なのだろう。
「正常と異常の絶妙なバランス」
その妙を、ぜひ本書で味わってみてはいかがだろう。
【 参考記事 解説・考察『破局』(遠野遥)ー「つまらない」その隠された理由に迫るー 】
スポンサーリンク
『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)
あらすじ
2020年下半期受賞作。
主人公は女子高生の「あかり」
彼女はその存在をかけて、「上野真幸」というアイドルを推している。
ある日、真幸がファンを殴って炎上する。
炎上後のファン投票で、真幸は最下位に転落。
現実を受け入れられないあかりに追い打ちをかけるように、「グループの解散」、「真幸の芸能界引退」が報道されてしまう。
そして、記者会見に臨む真幸の指には、婚約指輪が光っていた。
ある日あかりは、ネットで拡散された情報を頼りに、真幸の自宅へと向かう。
すると、真幸の洗濯物を干す、ショートボブの女性を目にするのだった。
考察「推し」に見られる宗教性

本書が発表されたとき、作者の宇佐見りんは現役の大学生。
ということで、SNSを通じた若者たちの交流や「推しごと」に励む若者の心理とが、作家の実感に基づいて、よりリアルに描かれている。
しかも、宇佐見りんの「文学的感性」は天才的で、それは多くの作家や選考委員たちが認めるところ。
特に、作家の高橋源一郎氏は、宇佐見りんを非常に高く評価してるのだが、彼は宇佐見りんを評して、
文学的な絶対音感がある
と言っている。
彼女の才能は「天賦のもの」だということだろう。
さらに高橋源一郎が称賛するのは、作品の冒頭2行。
推しが燃えた。ファンを殴ったらしい。
いわく、「ここを読んだ瞬間、芥川賞受賞を確信した」だそうだ。
文章力だけでなく、世界を切り取る「感性」も、瞠目すべき彼女の才能の1つだろう。
本書はとかく、
「推しを推す人の心理を描いた作品」
と、浅く表層的に解釈されがちだけれど、実はもっと人々に開かれた普遍性があると僕は思う。
つまり、本書は「推し」という特定の文脈で語られるだけの作品ではなく、「生きづらさ」を感じるすべての人に突き刺さる作品なのだ。
主人公のあかりもまた「生きづらさ」を抱えた女性なのだが、その生きづらさはとても切実で、真幸を求めざるをえない彼女の姿には、ある種の「宗教的なもの」さえ見て取れる。
本書『推し、燃ゆ』を読むと、推しを推す「切実さ」や「尊さ」について考えさせられる。
僕は読後、大げさではなく、次のような結論にいたった。
畢竟、生きるとは「何かを推すこと」なのだ。
【 参考記事 考察・解説『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)ー推しに見られる宗教性- 】
『彼岸花が咲く島』(李琴美)
あらすじ
2021年上半期受賞作。
舞台は彼岸花が咲き乱れる、とある〈島〉
その浜辺に、記憶を無くしたある少女(宇実)が漂着する。
自分がどこから来たのかも覚えていない宇実は、そのまま〈島〉で生活することになる。
そして、宇実は〈島〉の実態について知っていく。
- 〈島〉では、男女が異なる言葉を学ばされるらしい
- 〈島〉では、「ニライカナイ」という楽園を信仰しているらしい
- 〈島〉では、「ノロ」と呼ばれる女たちが、共同体を統率しているらしい
宇実は「大ノロ」という最高権力者に会う。
大ノロは宇実に対して、「ノロとなって〈島〉の歴史を担うこと」を命令する。
宇実はノロになるために、「女語」と呼ばれる言葉の習得をめざす。
ただ、〈島〉の実態を知れば知るほど、宇実の疑問は膨らんでいく。
なぜ〈島〉では、男女が違う言葉を学ぶのか。
なぜノロは、女性だけしかなれないのか。
その答えは驚くべきものだった。
考察「美しい日本語」を強烈に風刺

なんといってもこの作品の魅力は、「言語にとって自覚的」な点だ。
物語には3つの言語が登場する。
- ニホン語
- ひのもとご
- 女語
物語では、それぞれの言語や島の歴史が明かされるわけだが、それらは間違いなく「日本語」の歴史を風刺している。
ご存じの通り、日本語は「漢字」や「外来語」や「やまとことば」のハイブリット言語である。
そんな日本語だが、実はその歴史に「漢字を排除しよう」という運動があったことを、あなたは知っているだろうか。
根っこには、「美しい日本語」とか「純粋な日本語」を求める思い(とか、韓〇や中〇といった国にマウントを取りたいという思い)があるのだが、果たして「漢字の排除」で、本当に「美しい日本語」が実現できるだろうか。
本書『彼岸花が咲く島』は、ストーリーとしてもとても面白く、芥川賞らしからぬ「エンタメチック」な小説である。
だけど、内包するテーマはとても深く、とても興味深い。
とりわけ、言語とか日本語に興味関心が強い読者には、とってもオススメできる作品となっている。
【 参考記事 考察・解説『彼岸花が咲く島』(李琴峰) —美しい日本語を問うー】
スポンサーリンク
『ブラックボックス』(砂川文次)
あらすじ
2021年下半期受賞作。
主人公は28歳の男性“サクマ”
コミュ力に乏しく、癇癪持ち。
感情のコントロールが効かない彼は、これまで数多くの対人トラブルを巻き起こし、職を転々としてきた。
現在は「メッセンジャー(自転車便)」をして生活をしのいでいる。
そんな中、同棲している円佳が妊娠。
サクマは改めて「ちゃんとしなきゃ」と思い始める。
ある日、自宅アパートに税務官がやってきて、サクマは脱税を指摘される。
癇癪を起こしたサクマは、税務官らに暴行を加え、駆けつけた警察に現行犯逮捕される。
刑務所の中でも、相変わらずトラブルが絶えないサクマ。
同房の男に暴行を加えたことで、50日間も独房に閉じ込められる罰を受ける。
だが、このとき初めてサクマは自分自身と向き合うことが出来た。
「自分の半生」とは、「これからの人生」とは、「自分はいったいどう生きていくべきか」
そんな内省の果てに、彼がたどり着いた「答え」とは……
考察「ゴール」の見えない現代社会

本作『ブラックボックス』は、選考会で多くの選者から高い評価を得た。
その中でも「飾り気がない」という言葉は、この作品の本質をよく表していると思う。
たしかに、この作品には「優れたテクニック」とか「高い芸術性」とか「斬新なテーマ」といったものはないかもしれない。
ただ、その一方で、人間を真正面から捉えようとする「ストレートさ」があって、読む者の心に刺さる作品だといえるだろう。
「本作には、書かれねばならなかった切実さがある」
という選者の言葉は、その点を言い当てたものだ。
日々、自転車をこいで金を稼ぎ続けるサクマの生活は、文字通り「自転車操業」さながら。
そんな彼を捉えて離さないのは、次の問いだ。
――幸福な人生とは、いったい何なのだろう——
――おれは何を目指して生きていけばいいのだろう――
彼は自分自身が目指すべき「ゴール」が分からない。
ゴールが分からないのに、生活に追われるように、走り続けているのだ。
だけど、僕たちもよく考えてみたい。
じゃあ、幸福な人生って、一体なんだ?
万人に通用する「幸せ」なんて、果たしてあるのだろうか?
実際に僕たちだって、何が幸福で、何が正解で、何がゴールか分からないでいる。
この世界に生まれた瞬間から、よーいドンと、なぜか走らされているのが僕たちだ。
だけど、そのゴールがどこなのか、僕たちには分からない。
僕たちとサクマと、いったい何が違うのだろうか。
きっと、本質的には変わらない。
この世界はまるで「ブラックボックス」のように謎に包まれていて、それを生きているのは僕たちだって同じなのだ。
本書は、そんな現代人の姿を「サクマ」という男に投影させて、見事に描き切った佳作だ。
選考会では、本書は次のように評された。
「現代における、プロレタリア文学」
まさに、この一言が、本書の本質を鋭く言いえている。
【 参考記事 解説・考察『ブラックボックス』(砂川文次)―誰もが“サクマ”である現代― 】
『おいしいごはんが食べられますように』(高瀬隼子)
あらすじ
2022年上半期受賞作。
舞台は「食品パッケージ」を請け負う会社。
主人公の「二谷」は、そこで働く29歳の男性。
仕事でミスをした「芦川」という女性同僚を慰めたことで、周囲には内緒の「職場恋愛」が始まる。
いつも喜怒哀楽が豊かで、手の込んだ料理をふるまってくれる芦川。
だけど、「食事なんてカップ麺で十分」といった価値観を持つ二谷は、そんな彼女の振る舞いに困惑と嫌悪を抱く。
なにかと会社を早退しがちな芦川は、そのお詫びとして職場に「手作りお菓子」を持参するようになる。
「おいしい、おいしい」と好意的に受け入れる職場の人たち。
それとは裏腹に、二谷は芦川の振る舞いに困惑と嫌悪を強めていく。
その後も、早退を繰り返す芦川。
「お詫びのお菓子」は、その都度、手間とクオリティを高めていく。
「んーっ」「うまあっ」「すごっ」と、感動を表す職場の人たち
二谷もそれに合わせて「すげえ、おいしそう!」とお菓子を受け取る。
だけどその深夜。
残業で会社に残った二谷。
彼は、誰もいなくなった会社でお菓子をグチャグチャに踏みつぶす……
考察「おいしい」の社会通念を解体

もしも“純文学”に「意義」があるとすれば、その1つに「当たり前」を解体することが挙げられると思う。
「人と仲良くしなくちゃいけません」
「人に優しくしなくちゃいけません」
「人を傷つけちゃいけません」
例えば、そうした生活における“常識”に対して、
「本当にそうなの?」
「いつ、誰が、そう決めたの?」
「常識で割り切れない価値があるんじゃないの?」
と、強烈に問題提起をしてくるのが、純文学だといっていい。
では、この作品が問うているものは何か。
それは「ゆたかな食事」である。
「ご飯は味わって食べましょう」
「ご飯は感謝して食べましょう」
「ご飯は大勢で楽しく食べましょう」
そうした、“食”にまつわる世間の常識に対して、作者は
「それって、本当なの?」
「それって、正しい価値観なの?」
と、読者にクエスチョンを投げかけ、多くの人たちが価値を置いている「おいしい」をジワジワと解体していく。
『おいしいご飯が食べられますように』は、「おいしい」を問う文学なのである。
さて、本書で解体される「食」に関する常識とは以下のようなものだ。
・ごはんは大勢で食べるのが良い ・ごはんは感謝して食べるのが良い ・ごはんは「おいしく」食べるのが良い ・ごはんは残さず食べるのが良い ・ごはんは健康的なものを食べるのが良い
これらは全て「やさしい言葉」であり「心地よい言葉」であり、だからこそ「否定しがたい言葉」である。
だけど、いやだからこそ 食に対する常識的な価値観を持つ人たちは、そこになじめない人間を非難し、蔑み、そして排除しようとする暴力性を持っている。
本書における主人公「二谷」の言葉は、それを端的に言い表している。
「ごはん面倒くさいって言うと、なんか幼稚だと思われるような気がしない? おいしいって言ってなんでも食べる人の方が、大人として、人間として成熟しているってみなされるように思う」(本書より)
食にまつわる常識を共有しない人は幼稚で未熟な人間として非難される。
こうした社会の暴力性を、よく言い当てた言葉だと思う。
主人公の二谷は、まさにそうした「暴力性」に生きづらさを感じる1人である。
本書ではそうした「生きづらさ」を感じる個人の姿も印象的に描かれる。
『おいしいごはんが食べられますように』は「生きづらさ」を抱える人間の内面や生活を「食」という身近なモチーフを採用して描いた佳作だといえる。
【 参考記事 解説・考察「おいしいごはんが食べられますように」―”おいしい”を解体する文学― 】
スポンサーリンク
『この世の喜びよ』(井戸川射子)
あらすじ
2022年下半期受賞作。
「あなた」はショッピングセンターの喪服売り場で働いている。
ひょんなことから、フードコートを出入りする少女と知り合った「あなた」は、その少女とひんぱんに話しをするようになる。
少女は小さな弟の世話を両親から任されており、その姿から、「あなた」はかつての子育ての記憶を思い出していく。
自分の経験から少女にアドバイスをする「あなた」だったが、ある日、少女とちょっとした言い合いをしてしまう。
少女との間に距離が生まれてしまったものの、それでも少女に近づき話しをしようとする「あなた」。
そして、少女に「何かを伝えられる喜び」を感じるのだった。
考察「私」に寄り添う二人称の語り

『この世の喜びよ』のテーマは、ずばり「子育て」である。
ただ、本作が他の作品と一味違う点は、子育てを現在の視点からリアルタイムで描くのではなく、子育てを終えた母の視点から、かつての「子育ての記憶」を描く点だ。
主人公はショッピングセンターの喪服店で働く女性。
ひょんなことから知り合った少女と交流する中で、かつての子育ての記憶を思い出していく。
その記憶の中には、子育ての辛さに関するものもある。
「娘が訳も分からず泣き出した」であるとか
「娘を昼寝させるためにとにかく出歩いた」であるとか
「娘が頭を打ったので脳神経科へ連れて行った」であるとか。
こうしたエピソードは、当時の「主人公」がいかに必死で、いかに気を張り詰めていたかを物語るものだ。
ここで僕があえて言うまでもないが、子育てに苦労はつきものだ。
「どんなに自分ががんばったとしても、それを見てくれている人は誰もいない」
「どんなに子どもに尽くしたとしても、子どもから感謝されることはない」
子育てというのは喜ばしいことではあるものの、こうした孤独があるのもまた事実だ。
だけど、もしも、そんな孤独を見守ってくれている存在がいたら。
人知れぬ努力を、ちゃんと認めてくれている存在がいたら。
本書『この世の喜びよ』が、芥川賞にふさわしいのは、そうした存在を「二人称」という文体を使って暗示し、そしてその企みを見事に成功させていることなのだ。
作中で、主人公は「あなた」と表現されている。
主人公の努力や孤独を、何者かが「あなた」と呼んで見守っているのだ。
この作品の静かな感動は、間違いなくこの「二人称」という体裁がもたらすものだ。
二人称小説という一風変わった作品を楽しみたい方や、子育て真っ最中の方、あるいは子育てが終わった方などは、本書を一読してみることをオススメしたい。
【 参考記事 解説・考察『この世の喜びよ』(井戸川射子)—二人称小説がもたらす静かな感動—】
『ハンチバック』(市川沙央)
あらすじ
2023年上半期受賞作。
重度の筋疾患(ミオパチー)を患う伊沢釈華は、人工呼吸器と電動車椅子がなければ生きていくことができない。
両親が終の棲家として残してくれたグループホームの、たった十畳ほどの一室が彼女の生活範囲のほぼ全てで、社会との接点と言えば、「某有名私大の通信過程」と、「風俗ライターのアルバイト」ぐらいのもの。
そんな彼女は「紗化」という零細アカウントを持っていて、「子どもを宿して中絶するのが私の夢です」といった、いかにも炎上しそうなツイートをした。
ある日、ヘルパーの田中にTwitterのアカウントを特定され、それをきっかけに釈華は「1億5500万」で、田中と妊娠のための性行為をすることになる。
しかし、釈華の肺の中に田中の精液が入ってしまったことで、誤嚥性肺炎となって入院する。
その後、田中はヘルパーをやめ、やがて釈迦は退院した。
田中に渡すはずだった「1億5500万」は結局自分の手元に残り、釈華は田中からの同情を改めて思い知った。
考察「文学の力」を感じさせる快作

芥川賞作品を含め、多くの純文学作品を読んできた僕だが、
「久々にすげえのが出てきたぞ」
と、そんな風に思える、個人的に数年に一度の傑作だと思う。
主人公は先天性ミオパチーという難病指定されている筋疾患を患った女性であるが、作者の市川沙央自身も同疾患を患っている。
作中の随所に描かれる「身体的な苦痛」や「身体のままならなさ」、「世間からの疎外感」、「自己否定や自暴自棄」……そうした細部には、ありありとしたリアリティと切実さとがあって、それも本作の魅力の1つだと思う。
とはいえ、本書が持つ強烈な「熱量」を説明するには、それだけでは全然足りない。
本書のタイトル「ハンチバック」とは、「せむし」を英訳したもので、せむしというのは背骨がかがまって弓なりに曲がる病気や、または、その病気の人を指す言葉だ。
そして、本書では「せむし」は、主人公の「釈華」を指している。
それが最初に明かされるのは、次の場面である。
せむしの怪物の呟きが真っ直ぐな背骨を持つ人々の呟きよりねじくれないでいられるわけもないのに。(単行本P21より)
こんなふうに、釈華は自らの姿形を「せむしの怪物」と呼ぶ。
「せむし」という差別用語に「怪物」という言葉までくっつける釈華、その背後にはいったいどんな思いがあるのか。
まさに、それを読み解くことが本書「ハンチバック」を読み解くことなのだが、本書を読み進めていくと「小説の力」というものを改めて実感させてくれる。
本書を読んで僕は思った。
「小説というのは、弱者の負け惜しみなのかもしれない」
だけど、本書は、すぐにこうも思わせてくれるのだ。
負け惜しみがなんぼのもんじゃい!
僕はこの『ハンチバック』を読んで再認した、確信した。
小説って、弱者の負け惜しみの言葉の集積なのだ。
だけど、それは「尊い言葉の集積」だ。
そんなことを改めて教えてくれた『ハンチバック』に僕は感謝している。
とにかく、本書は「生きづらさ」を抱えて生きる全ての人間に刺さる、そんな小説だといっていい。
【 参考記事 解説・考察『ハンチバック』ラストの意味は?―自らの尊厳を守るための言葉― 】
すき間時間で”芥川賞”を聴く

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・
芥川賞をもっと読みたい人はこちら
以下の記事で、さらに作品を紹介している。
「受賞作品をもっと読みたい」と思う人は、ぜひ参考にどうぞ。
【 次の記事を読みたい方はこちら 】
【 芥川賞作品の「テーマ別」記事はこちら 】
芥川賞【テーマ別】おすすめ5選
・【本当におもしろい】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➀-
・【テーマが深い】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➁-
・【ハートウォーミング・日常系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➀-
・【暗い・怖い・ドロドロ】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➁-
・【暴力・アンモラル系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➂-
・【個性的・独自の世界観】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➃-
・【玄人ウケする本格小説】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➀-
・【古典級の名著】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➁-



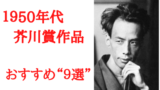

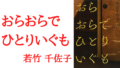
コメント