「おもしろい」作品を5つに厳選
芥川賞、それは日本でもっとも認知度の高い文学賞だといってもいい。
あまり読書に興味がない人でも、この賞の名前くらいは知っていると思う。
毎年、夏に1度、冬に1度受賞作品が決まるのだが、(読書に馴染みのない人にとって)アタリハズレがあるというのが現実だ。
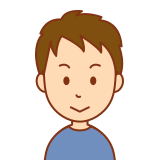
芥川賞くらい、読んでみるか
と、思い立ってせっかく読んだ本が難解な作品で、
「やっぱ、文学って小難し、めんどくせ」
と、豊かなはずの読書ライフから遠のいてしまうとしたら、それはあまりにもったいない。
そこで、今回は、芥川賞に挑戦したいという人に向けて、とくに「おもしろい」芥川賞作品を5つ厳選して、ランキング形式で紹介したい。
第5位『おいしいごはんが食べられますように』(高瀬隼子)

痛快!「おいしい」の美徳を解体
2022年の受賞作。
もしも“純文学”に「意義」があるとすれば、その1つに「当たり前」を解体することが挙げられると思う。
「人と仲良くしなくちゃいけません」
「人に優しくしなくちゃいけません」
「人を傷つけちゃいけません」
例えば、そうした生活における“常識”に対して、
「本当にそうなの?」
「いつ、誰が、そう決めたの?」
「常識で割り切れない価値があるんじゃないの?」
と、強烈に問題提起をしてくるのが、純文学だといっていい。
では、この作品が問うているものは何か。
それは「ゆたかな食事」である。
「ご飯は味わって食べましょう」
「ご飯は感謝して食べましょう」
「ご飯は大勢で楽しく食べましょう」
そうした、“食”にまつわる世間の常識に対して、作者は
「それって、本当なの?」
「それって、正しい価値観なの?」
と、読者にクエスチョンを投げかけ、多くの人たちが価値を置いている「おいしい」をジワジワと解体していく。
『おいしいご飯が食べられますように』は、「おいしい」を問う文学なのである。
さて、本書で解体される「食」に関する常識とは以下のようなものだ。
・ごはんは大勢で食べるのが良い ・ごはんは感謝して食べるのが良い ・ごはんは「おいしく」食べるのが良い ・ごはんは残さず食べるのが良い ・ごはんは健康的なものを食べるのが良い
これらは全て「やさしい言葉」であり「心地よい言葉」であり、だからこそ「否定しがたい言葉」である。
だけど、いやだからこそ 食に対する常識的な価値観を持つ人たちは、そこになじめない人間を非難し、蔑み、そして排除しようとする暴力性を持っている。
本書における主人公「二谷」の言葉は、それを端的に言い表している。
「ごはん面倒くさいって言うと、なんか幼稚だと思われるような気がしない? おいしいって言ってなんでも食べる人の方が、大人として、人間として成熟しているってみなされるように思う」(本書より)
食にまつわる常識を共有しない人は幼稚で未熟な人間として非難される。
こうした社会の暴力性を、よく言い当てた言葉だと思う。
主人公の二谷は、まさにそうした「暴力性」に生きづらさを感じる1人である。
本書ではそうした「生きづらさ」を感じる個人の姿も印象的に描かれる。
『おいしいごはんが食べられますように』は「生きづらさ」を抱える人間の内面や生活を「食」という身近なモチーフを採用して描いた佳作だといえる。
もちろん、ストーリー自体も とても面白いのでオススメ。
【 参考記事 解説・考察「おいしいごはんが食べられますように」―”おいしい”を解体する文学― 】
第4位『蹴りたい背中』(綿矢りさ)

人間の“謎の衝動”にスポット
2003年の受賞作。
綿矢りさの授賞はセンセーショナルだった。
作者が19歳の女子大生だったからだ。
それまでの最年少記録は丸山健二の23歳。
実に37年ぶりに更新となった。
また、同時受賞した金原ひとみも20歳という若さだったこともあり、『蛇にピアス』と『蹴りたい背中』が掲載された『文藝春秋』はミリオンセラーを達成。
ただし、勘違いしないでほしいのは、「若さ」とか「かわいらしさ」は、彼女への評価とは全く関係ないということだ。
『蹴りたい背中』で書かれているのは、人間の「抑えがたい衝動・欲求」だ。
- 主人公は女子高校生のハツ。
- 彼女は女子にありがちな「グループ交際」を拒絶している。
- その1つの理由は、彼女は誰かといるときこそ強烈な孤独を感じてしまうから。
なるほど、ぼくたちは、とかく、一人でいる時よりも、誰かと一緒にいるときにこそ、強烈な孤独に襲われることがある。
とはいえ、1人でいたって、孤独は孤独なのだ。
実際にハツも、1人でいることに「自分の存在が完全に消えてしまう恐怖」を感じている。
人ともダメ、1人もダメ。
そう、ハツはめんどくさい子なのだ。(※注 「めんどくさい」は文学では褒め言葉)
そして、とにかく頭のなかでいろいろと考えをめぐらせ、自分を正当化していく。
心配して近づいてくる同級生にも憎まれ口をたたき、彼らを見下し優越感にひたる。
当然、彼女は、いわゆるスクールカースト最底辺に位置づけられる。
で、同じくスクールカースト底辺男子「にな川」と、奇妙な連帯関係を育んでいく。
そして彼に対してサディスティックな衝動をおぼえていく。
タイトルの『蹴りたい背中』とは、この「にな川」の背中のことなのである。
ところで、こんなことを感じたことはないだろうか。
人の無防備な背中って、どうしてこうも想像や欲望を掻き立てるのだろう……
ぼくも「偉いひと」の背中を見て、
「ああ、いま、あの後頭部を思いっきりブッ叩いたら、おれは一体どうなるのかなあ」
そんなことを思うことがある。
それはなぜだろう。
単純に想像をもてあそび楽しんでいるようにも思えるし、日々のうっ憤を爆発させたい欲求があるようにも思えるし、すべてを台無しにさせたい破壊衝動(いわゆるタナトス)の発動のような気もする。
とにかく『蹴りたい背中』を読むと、ぼくは妙に共感してしまうのだ。
ああ、そうそう、なぜか、蹴りたいよね、背中。って感じで……
さて、このプライドが高く、めんどくさい主人公のハツ。
いったい、いつ、どんな状況で「にな川」の背中を蹴りたくなるのか。
そして、その衝動は いったいどんな感情に由来しているのか。
それは、ぜひこの本を読んで確かめていただきたい。
第3位『推し、燃ゆ』(宇佐見りん著)

”推し”への愛ってなに?
2021年の受賞作。
いま、若者たちの間で「推し」という現象というか、ムーブメントというか、がある。
この「推し」現象をよくよく観察してみると、じつに奥深く、「推しを推す(推しごと)」彼らの心理もとても興味深いものがある。
そういう意味でも、まさに生まれるべくして生まれた、現代の「推し」文学とも言える。
本書の主人公「あかり」も「上野真幸」というアイドルを推しているのだが、その推しっぷりは並大抵のものではない。
推しを押すことがあたしの生活の中心で絶対で、それだけは何をおいても明確だった。中心っていうか、背骨かな。
「推し」=「背骨」という、言葉の選び方に唸らされる。
どうして、そこまでの熱量で推しを推すのか、本書を読めばその理由が見えてくるだろう。
ちなみに、この作品の最大の魅力は、まず現代ならではの「推し」をテーマにした点だとは思うのだが、それ以上にぼくは、宇佐見りんの言語能力、表現力にあると思っている。
寝起きするだけでシーツに皺が寄るように、生きているだけで皺寄せがくる
たとえば、この表現、巧みな比喩表現にうならされる。
とにかく、本書をよんで体感してほしいのだが、彼女のことばには、頭ではなく、内臓につきささる不思議な力がある。
それは、読む人それぞれに違うと思うのだが、ぼくは宇佐見りんの作品を読んで、「また、おそろしい才能が発掘されたもんだ」と思った。
作者は現役女子大生、21歳という若さでの受賞は『蛇にピアス』に続く歴代、第3位の早さ。
選考委員ほぼ満場一致での受賞。
「文学的偏差値が高い」
選考委員の島田雅彦の言葉である。
作家の高橋源一郎も、彼女を「天才」と絶賛している。
まあ、とにかく彼女を「天才」と絶賛する人が多いのだ。
いまも爆発に売れ行きを伸ばしている。
ぜひ、早熟の天才が生んだ本作を読んでみてほしい。
ちなみに、『推し、燃ゆ』については別記事で詳しく扱っているので、そちらも参考に読んでほしい。
【 参考記事 『推し、燃ゆ』宇佐見りん著 - 何かを「推す」という尊さ - 】
スポンサーリンク
第2位『コンビニ人間』(村田沙耶香)

“異常”の彼方へ突き抜けろ!
2016年の受賞作。
ミリオンセラー達成の、超人気作。
- 主人公は古倉恵子36歳。
- 大学時代から18年間、ずっとコンビニでバイトしている。
- コミュ力不足で、マニュアルがなければ働けない。
- 人の気持ちを想像することができず、幼少の頃からトラブルが絶えなかった。
- 彼氏いない歴 = 年齢で、結婚する気なんて全くない。
- 友人・家族をはじめ、周囲はそんな彼女を「異常」と呼ぶ。
たしかに、今の社会において、彼女を「異常」とみなす人たちは多いのかもしれない。
だけど、本書『コンビニ人間』には、
「異常がなんぼのもんじゃい!」 というメッセージが横溢している。
「異常、異常って、いったい誰が、いつ、どんな権威のもと、そう決めたの?」
と、読者らに強烈な異議申し立てをしてくるのだ。
たしかに、そう問われると、はっきり答えることができる人はほとんどいないのではないか。
もし今、あなたが誰かから「普通じゃない」とか「変わってる」とか、「異常」のレッテルを貼られているとしても、実はそこに絶対的な正当性も妥当性も存在していない。
コンビニ人間は、その哲学的真理を、おもしろおかしく表現している。
選考委員の山田詠美の
「候補作を読んで笑ったのは初めて」
との選評は、この作品の魅力をよく語っているだろう。
ただ「おもしろい」だけではなく、この作品には読者を強烈に揺さぶるエネルギーが溢れている。
その熱量が評価されて、選考会では文句なしの受賞だった。
村田紗耶香の作品はどれも、常識とか社会通念を木っ端微塵に破壊するパワーがあるので作品を読んだ後で、「価値観が180度変わりました」なんてことはざらじゃない。
他の作品には、
- 殺人が容認された世界
- 他人とのセックスが当たり前の世界
- 死体を食うのが当たり前の世界
を書いたものなどがあり、それがあまりにぶっ飛んでいるので、作家仲間からは「クレイジー紗耶香」と呼ばれている。
ちなみに、村田自身も大学卒業以来コンビニのバイトを続けていたり、マニュアルがなければ働けなかったりといったことを公言している。
彼女もまた、彼女が描く主人公と同様に「普通」とか「当たり前」といった世間の価値観の中で「生きづらさ」を感じ続ける人なのだろう。
「普通」の中で居心地の悪さを感じている人。
「普通」を思いっきり壊してみたい人。
そういう人たちに村田文学はおすすめだ。
【 参考記事 解説・考察『コンビニ人間』村田沙耶香)ー異常だなんて誰が決めた? ー 】
第1位『むらさきのスカートの女』(今村夏子)

この“語り手”ほんとに信じていいの?
2019年の受賞作。
装丁(本の表紙)から、不穏な空気がただよってくる。
そこに加えて『むらさきのスカートの女』という、「口裂け女」風のタイトルである。
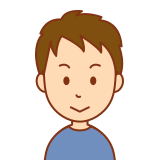
え、都市伝説か何かですか?
そう感じた人、あなたの勘は鋭い。
これは純文学的「都市伝説」といってもいい。
うちの近所に、「むらさきのスカートの女」と呼ばれている人がいる。いつもむらさき色のスカートをはいているのでそう呼ばれているのだ。
どうだろう、冒頭からして、なにやら不穏な空気が立ち込めてはいないだろうか。
これは今村夏子の作品の全般にいえることなのだが、彼女の作品には大なり小なり「ことばにできない不穏な空気」が漂っている。
読み進めていくと、登場人物に対して、
この人ってまともな人なの? それともやばい人なの?
と感じること頻り。
「正常」か「異常」か……
本書は、そのバランスが絶妙だ。
ただ本書の最大の魅力は別にある。
それは、小説でなければ絶対にできない演出だ。
いわゆる「信頼できない語り手」という叙述トリックがそれである。
まず、読者は小説の序盤からなにやら違和感を覚える。
さらに読み進めていくと、その違和感がどんどん強くなっていく。
やがてそれは、確信へと変わる。
「この語り手の言うことを、簡単に信じちゃダメだぞ」
どこまでが本当で、どこまでが嘘なのか。
そんな風に読者は「信頼できない語り手」に翻弄されていく。
そして、衝撃のラストシーン。
その巧さに唸りつつも本を閉じる。
そして誰もがきっと、こう思うのだ。
「で、一体だれを信じればいいわけ?」
この演出が選考委員にも高く評価され、ほぼ「満場一致」で受賞。
選考委員の多くが口をそろえて言うのは、「正常と異常のバランス」だ。
特に宮本輝は、
「正常と異常の垣根の曖昧さは、そのまま人間の迷宮へとつながっていく」
としたうえで、
「(以前の候補作でも才能を感じたが)今回の作品で本領を発揮して、わたしは受賞作として推した」
と絶賛した。
ぼくは今村夏子の大ファンで、彼女の作品を全部読んでいる。
どの作品の文章も分かりやすく、読書ビギナーも安心して読むことができる。
それでいて、行間に、言葉にできない不穏な空気を隠している。
多くの読者を楽しませ、玄人たちもうならせる凄まじい作品を書いてしまう今村夏子は、まちがないく、今後の文学を牽引していく作家の1人だと思う。
蛇足だが、ぼくはこの本を読んだとき、「間違いなく、この本は芥川賞を受賞する」と直感した(ので受賞を聞いて嬉しかった)。
【 参考記事 解説・考察『むらさきのスカートの女』―「語り手」を信じてよいか― 】
すき間時間で”芥川賞”を聴く

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。
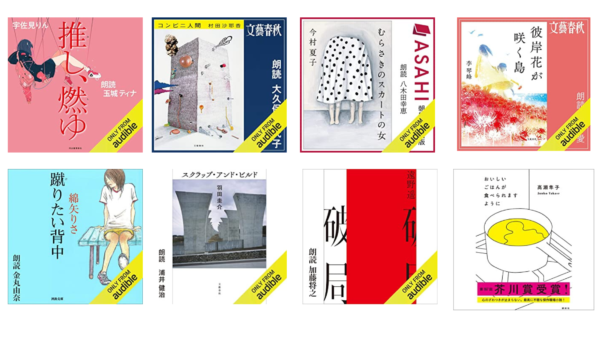
『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。
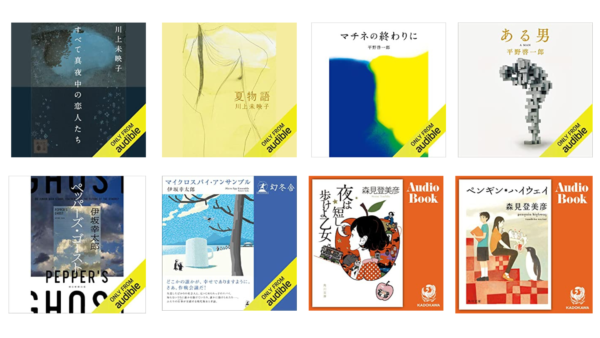
その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・
芥川賞をもっと読みたい人はこちら
以下の記事で、さらに作品を紹介している。
「受賞作品をもっと読みたい」と思う人は、ぜひ参考にどうぞ。
【 次の記事を読みたい方はこちら 】
【 芥川賞作品の「テーマ別」記事はこちら 】
芥川賞【テーマ別】おすすめ5選
・【本当におもしろい】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➀-
・【テーマが深い】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➁-
・【ハートウォーミング・日常系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➀-
・【暗い・怖い・ドロドロ】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➁-
・【暴力・アンモラル系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➂-
・【個性的・独自の世界観】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➃-
・【玄人ウケする本格小説】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➀-
・【古典級の名著】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➁-
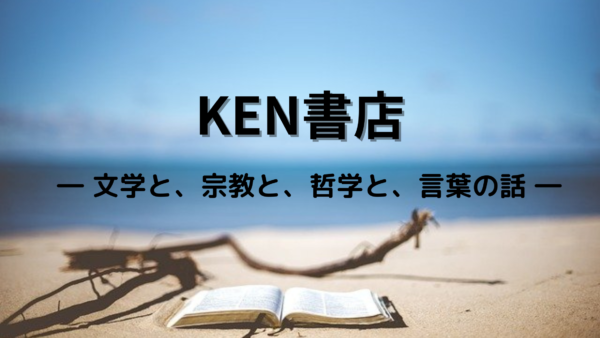
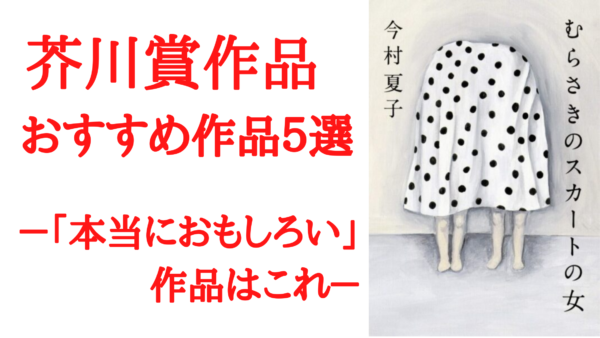


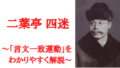

コメント