はじめに「簡単な自己紹介」

はじめまして「KEN書店」を運営しているKENといいます。
思春期あたりから主に“家族関係”で悩み、
「いったい僕は何のために生きてるんだろう……」
そんなふうに自問自答をするような人間でした。
「陰か陽か」
そう問われれば、間違いなく僕は“陰”側の人間です。
基本的には、僕の半生はずっと無気力でした。
だけど、「読むこと」と「書くこと」と出会えたことで、大げさではなく「自分が存在する意味」を感じることができました。
以来、「読書」と「執筆」で自分の「生きづらさ」を慰めています。
そんな僕ですが、以下、少しだけ詳しく自分のことを紹介しようと思います。
僕と読書との出会い
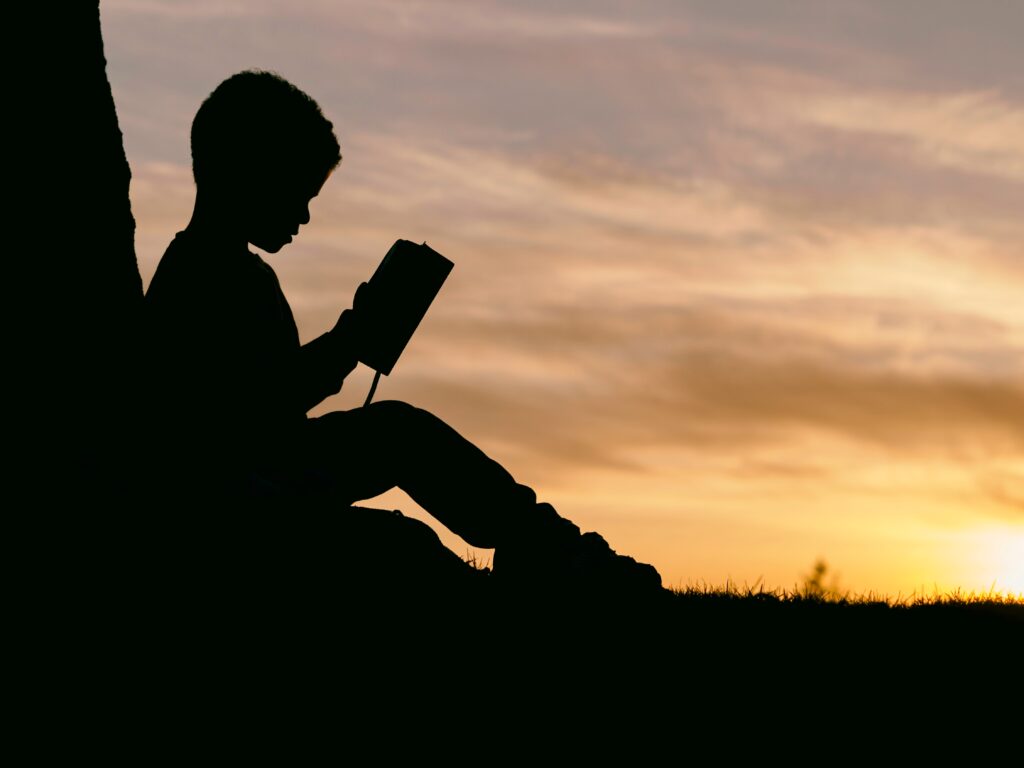
僕と読書との出会いは18歳のこと。
「孤独だわー」
「生きづらいわー」
「救われたいわー」
そんなネガティブな思考が慢性化していた時、当時の国語の先生が、
「勉強とかどうでもいいから、とりあえず本でも読んどけ」
と、僕に1冊の本をくれました。
それが、夏目漱石の『それから』でした。
読書をしていると、まれに、
「これは自分のために書かれたんじゃないのか?」
と、思える一冊に出会うことがあります。
あるいは、その出会いは
「まるで、自分のために書かれた言葉」だったり、
「まるで、自分自身だと思える登場人物」だったりします。
とにかく、そういう出会い、そういう読書体験をしたとき、人は間違いなく本に魅了されます。
僕にとって、漱石の『それから』はそういう1冊でした。
「ここには、俺のことが書かれている」
しばし、そんなことを考える読書体験でした。
主人公代助の苦悩や葛藤に自分自身を見たし、代助が下した決断に自分の理想を投影した。
すべての責任を負ってでも自分であろうとした代助に胸が熱くなったし、そういう生き方もあるのだと背中を押された。
うん。大げさじゃない。
ぼくは漱石の『それから』に救われたのだと思います。
僕と執筆との出会い

ぼんやりとした孤独感、欠落感、そうしたものを埋めるため、僕は言葉を求めました。
当然のように、読書は僕の生活の一部となり、読書は僕の生きていく糧となりました。
読書するのが当たり前になり、大人になった、そんなある時。
フツフツと腹の底から「ある欲求」が湧き上がってきました。
「俺も書いてみてえ……」
自分も憧れの作家たちみたいな文章を書いてみたい、そんな欲求でした。
ただ、その時の僕には「書きたいもの」なんて、具体的にありませんでした。
だけど一度脳内で言葉になった「書いてみてえ」は、際限なく脳内でリピート再生されます。
「書いてみてえ書いてみてえ書いてみてえ書いてみてえええええぇぇぇ!」
じゃ、書けばいいじゃん、ああ、書いてみるか。
ということでその時の酒の手伝いもあり、PCを立ち上げ、3日ほどで一気呵成に書き上げたのは原稿用紙50枚くらいの短編小説でした。
「わー、こりゃまた、さむーいモノ書いちまったなー」
読み返してみて、率直にそう思いました。
だけど、その一方では、
「まぁ、せっかく書いたんだし、どこかに応募してみようか」
そんなことも思い、地元の小さな文学賞に応募してみました。
それがなんと、運よく受賞。
授賞式では選考委員の先生に「おもしろい!」と褒められ、自分の小説が活字となって書店に並ぶという初めての経験をして、いいようもない高揚感を得ることができました。
いまでも「あの時、受賞してホントによかったな」としみじみと思います。
たとえ小さな文学賞だったとしても、なんとなくあの時「お前は書き続けろ」と言われた気がしたし、それ以前に書くことの楽しみや喜びを知ることができたからです。
その後も細々と書き続け、様々な賞に応募してきました。
一応、執筆や出版について、僕の主な実績を紹介してみます。
小説を書き始めて、わりとトントン拍子にこんな実績がくっついてきてくれました。
こうなってくると「俺って才能あんじゃね?」と勘違いするのも無理からぬこと。
「作家デビューとか出来ちゃうんじゃね?」
そううぬぼれた僕は、いよいよ大手出版社の新人賞に応募し始めることとなりました。
その結果を以下に紹介してみます。
大手への投稿をはじめ数年間、多くの賞で「一次選考落選」という結果でしたが、上記の3つの賞で「二次選考」まで残ることができました。
自分としては、いわゆる「純文学」を書いているつもりだったのですが、この結果を見て、「どうやら自分の小説はエンタメ系なのかもしれない」と考えました。
そこで次に書き上げたのが、僕自身の半生をモチーフにした原稿用紙300枚弱の長編小説でした。
よし、もう出し切った、書き切った、やり切ったぞ俺は! 的な作品になったので、
「これでダメならもうダメだ」
という思いを抱きつつ、応募先を検討しました。
「これを五木寛之に読んでもらいたい」
そんな理由で応募を決めたのが、集英社が主催する「小説すばる新人賞」でした。
その結果は
二次選考で落選。
あちゃー、やっぱダメだったか―。
でも、完全燃焼。
「とりあえず、全国区はハードル高すぎ!」
数年間頑張って、そんな経験的真理を得て、しかも記念に小説をkindleで自費出版とかしちゃったりして、あるていど満足した僕は、大手の新人賞への応募にいったん一区切りをつけました。
その後はずっと地方文学賞に細々と応募し、たまに活字になって自分の本が近所の書店に並んでは小さな満足を得たりしていました。
だけど、
「やっぱり、高みを目指したい!」
という思いを否定できず、再び大手の新人賞への投稿を始め、作家デビューという夢を追いかけています。
そうした努力が奏功してか、最近では一次選考を通過することが増えてきました。
(執筆エピソード長すぎですね、すみません)
このブログの理念

最後に、このブログについて少しだけ書いておきます。
ブログを始めたのは、
「やっぱり、何か書きたい」
と思ったからです。
もちろん、先述の通り、今でも小説とか、エッセイとか、たまには詩とか短歌なんかも創作しては投稿したりしています。
だけど、そこではどうにも「自分の言葉が誰かに届いている!」といった実感を得られません。
「なんか、もっとこう、沢山の人に自分の言葉や思いを届けられる場はないものか」
そんなことをぼんやり考えて、表現の場を探していました。
実は、もともと「読書メーター」という読書用SNSで本の感想をまとめていて、
「せっかくだから、もっとたくさんの人に、素晴らしい本を紹介したい」
と常々思っていました。
- 表現の場がほしい!
- 素晴らしい本を紹介したい!
そんな思いが合わさってたどり着いたのが「書評ブログ」の運営という答えでした。
だから、このブログの根っこには「多くの人たちに、沢山の良書にふれてほしい」という思いがあります。
ちなみに、僕は大学で人文学を専攻し「文学・哲学・宗教・言語」について学んできました。
これらの学問は全て「人間とはなにか?」「生きるとは何か?」を追究する学問だと、僕は考えています。
ブログでは、その辺の本を紹介していきます。
世の中にはきっと、僕みたいに、いや僕以上に慢性的な「空虚感」とか「欠落感」を抱えている人がたくさんいる。
生きる意味を模索していたり、存在することが苦しかったり、自分と世界とがチグハグでもどかしかったり――そうした「生きづらさ」を感じている人が、この世の中にはたくさんいる。
もしも僕のつたない言葉が、そんな人たちの「生きづらさ」に寄り添うことができたなら、これ以上に嬉しいことはありません。
「読むこと」が、そして「書くこと」が、人間にとって大きな生きる意味になるのだ。
そんな僕の思いが、1人でも多くの人に届くといいなーと思いながら、このブログを運営していきたいと思います。
「KEN書店」管理人 KEN
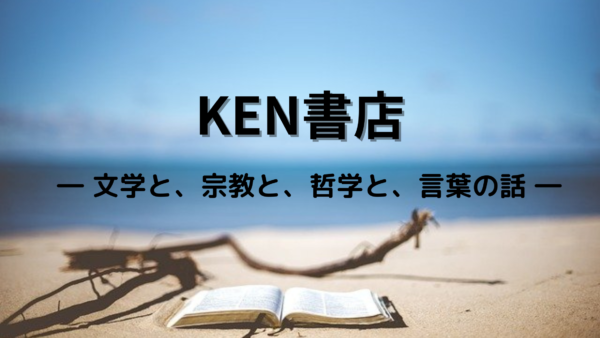

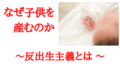
コメント
こんにちは。哲学のページをいくつか読ませていただき、大変勉強になっております。ありがとうございます。
2022年で止まってしまっているようなのですが、お忙しいのでしょうか?
できれば更新お願いしたいです。
よろしくお願いします。
いむさんへ
コメントありがとうございます。なかなか本業との両立が難しく、最近の関心が執筆や文学や言葉に傾いていることも加わり、哲学方面が疎かになってしまっています。また、哲学のページは意外と需要がないっぽくて、PVが伸びないので、とりあえず更新を一旦ストップしている状態です。
ただ、いむさんの言葉にはとても勇気づけられました。とりあえず、落ち着き次第、まずは哲学史(アリストテレス)あたりから書き始められればと思います。まだまだ興味深い哲学者たちはたくさんいるので、彼らの魅力を地道ながら伝えていければと思います。ありがとうございます。
はじめまして。
「貝に続く場所にて」を読んだのですが、いまいち作者の言わんとすることがわからず、、、
ネットで検索していたところ、Kenさんの解説文に辿り着きました。
非常に鋭い考察力、噛み砕いた解説文に圧倒され、コメント残させていただきます。
Kenさんの書かれている本に興味が湧き、ぜひ読みたくなりました!
紹介していただければ幸いです。
Karlsruheさんはじめまして。
うれしいコメントありがごうとざいます。参考になったみたいで良かったです。
そして、なんと僕の小説にも興味を持っていただいたということで大変恐縮です!
何を紹介しようかなーと検討してみたのですが、それなりに自信のある作品が掲載されたものは残念ながらことごとく絶版でした。
唯一、紹介できそうなものがあるのですが、これが大して自信のないショートショートが収録されたアンソロジーくらいのものでして………。
一応、Amazonで1000円程度で購入可能です。それでもよければ、メールでお伝えします。(ここで紹介すると、知人にブログがばれてしまいかねないので)
とはいえです。とはいえ寒い作品だし、Karlsruheさんをガッカリさせてしまいそうなので、正直あまり気が進みません……同じく1000円払うなら、他の芥川賞作品を読んだ方が、はるかに満足できると思いますよー。
コメントのご返信、ご丁寧にありがとうございます!!!
自信のある作品が掲載されたものは、絶版とのことですが、なんとかして手に入れて、読みたいので、作品名を教えていただければありがたいです。古本屋や図書館、ヤフオク等、あらゆる手段を使って見つけ出し、是非とも読ませて頂きたいです。ご無理を言って申し訳ありません。
Kenさんの書評、本当に素晴らしく、才能に恵まれた方だと思うので、今後も楽しみに拝読させて頂きます!
返信ありがとうございます。
いやいや、そこまで言っていただけて、ただただ恐縮です。僕の作品が出版されたのは、ほとんど地方の新聞社からなので、おそらく古本屋でもメルカリ等でも見つけるのは厳しいと思います。ほんと、すみません。簡単に手に入る大手出版の書籍は先ほどのアンソロジーくらいなものなのですが、あまり自信がない作品なのです。
それでも拙作を読んでいただけるということなら、後ほど、メールにて書籍の名前を伝えようとは思います。というより、手っ取り早く作品原稿を送りましょうか? 差し出がましいマネを申し訳ないのですが。
ご返信、ご丁寧にありがとうございます!
やはり作品原稿をお送りいただくのは、申し訳ないので、KEN書店さんブログに掲載の「書評」をまずは拝読させて頂くにとどめることにいたします。
こちらが、無理なお願いをしたばかりに、Kenさんにご心配・ご配慮をいただく結果となり、申し訳なく思っております。
こちらこそ、ご期待に添えず申し訳ありませんでした。「小説を読みたい」だなんて、この上なく嬉しいお申し出だったのに。とはいえ、まだ執筆自体は細々と続けているので、いつか自信を持って作品をお届けできるように頑張りたいと思いますので、気長に待っていてくださると嬉しいです。
また、ブログの方にも遊びに来てくださいね!
はじめまして。
「海と毒薬」のタイトルの解釈を調べていて、こちらのサイトにたどり着きました。
過去に読んだことのある他の作品の解説も思わずいくつか拝見しましたが、その読みの深さやサイト訪問者に訴える表現の豊かさに、ただただ感激しました。
私自身は文学・小説や哲学への目覚めが遅く、いわゆる社会人の学びなおしレベルで純文や海外古典を読み進めている程度ですが、読み以上に「アウトプット」について大きな課題を感じています。たとえ読みが浅くても、自分が感じた感動を次の人に伝えたい・分からないものはわからないとして記録に残したいという思いがあるのですが、読んだはずのものがモヤモヤして自分の言葉でまとめられず、いったい自分は何を読んだのだろうと、日々自己嫌悪を感じています。KENさんのような読書の表現を身に着けるためには、どういった勉強や訓練をされてきたのでしょうか。ぜひアドバイスいただければ幸いです。
5さん
まずは大変嬉しいコメント、ありがとうございます。こういうお言葉をいただくときが、ブログをやっていてよかったなと思える瞬間です。
>自分が感じた感動を次の人に伝えたい・分からないものはわからないとして記録に残したい
とても共感します。僕自身も読書を始めたころから「感じたことを書いておきたい」という思いがあり、そうした思いは「せっかく書くなら誰かに読んでもらいたい」という気持ちにつながり、結果20代のころに無料ブログを開設して「書評ブログ」を始めました。このブログは、その延長みたいなものです。
>読書の表現を身に着けるためには、どういった勉強や訓練をされてきたのでしょうか
僭越ですが、「書く」ことについて、僕自身思うことをお伝えします。
まず、これについては、特別な方法や裏技はないと思います。
「読みまくって、書きまくる」
とにかく、この繰り返しが、すぐれた表現力につながるのだと僕は思っています。
読書をする5さんも実感されていることだと思いますが、本を読んでいると、まれに「自分のもやもやに言葉を与えられる」という経験をすることがあります。
そうした時に、僕は「ああ、俺の感情や思いは、こうした言葉で表現できるのか」と感じます。人生の半分以上にわたり読書をしてきた今でも、そう思うことは多いです。そして同時に、「ああ、自分もこんな言葉で書いてみたい」という欲求が生まれます。
プロフィールにも書いてある通り、僕自身いまでも「小説」や「エッセイ」を書いています。だけど、「100%思い通りにかけたな」と満足したことは一度もありません。やっぱり、どこかで「これじゃない」感があるのです。だけど、ひょっとしたら、自分の満足できる何かを書くことができたら、自分にとって書く必要はなくなるのかもしれません。いつまでも満足できないからこそ、書き続ける、そういうループの中に自分はいるのかもしれません。だからこそ、どんなに納得いかなくても、へたくそでも、「とにかく言葉にしたい」という欲求(時には執念ともいえるもの)が生まれるのでしょう。そして、僕自身、そうした感情を大切にしています。
まとまりのない文章で、えらそうに失礼しました。あえて「文章力」という言葉を使わせていただくなら、それを高めるために裏技はないと思います。
「とにかく、優れた文章と出会い、自分の内面を言葉にすること」
大切なのはこのことなのでしょう。
少なくても5さんのメッセージの中には、読書と向き合う誠実な姿勢が垣間見えます。まずは5さんの思うままに言葉にしてみる、そうした習慣を持ってみてはいかがでしょうか? ブログなどがハードルが高ければ、読書メーターという、読書管理のSNSを利用してみるといいと思います。沢山のひとの感想にふれつつ、自分の感想を誰かに読んでもらえるし、多くの読書家と交流ができる便利なコンテンツです。
個人的には、ぜひ小説を書いてみてほしいです。これが最も自分の内面とのつながりがあるからです。
それでは、またいつでも遊びにきてくださいね。
早速のお返事ありがとうございます。
「とにかく読んで書く」
ほんとにその通りで、実は聞くまでもなく自分の中でも答えは出ているのですが(笑)。
学部できちんとアカデミックな土台があって、プロを目指されるような方は、何か根本的な違いがあるのだろうかと、お聞きしてみました。
あまりにズレたものを書くのも恥ずかしいし、巻末の解説やほかの方の解釈にそのまま引っ張られるのも情けないし、どうしたものかと悩んでいましたが、まずは書きつづけなければ上達するはずがないのは当たり前のことですね。
正直言ってKENさんのブログを拝見すると、”ショック”を受ける面もあるのですが、、モチベーションと学びに変えて続けていきたいと思います!
5さん
たしかに僕自身、大学で文学について専門的に学びはしましたが、実際に書いてみると、むしろそうしたバックグラウンドは「書く」こととはほとんど別物だ実感しています。大切なのは、その人の深い人生経験と内面なのでしょうね。(こう書くと、僕に深い人生経験と内面があるような感じになってしまいますが……)。
それから「読んだ内容を言葉にする」ことそのものが、いいこととは決して言いきれないとも思います。言葉にすることには、豊かな読書体験に「枠組み」を与えて、むりやり固定化するという側面もあるからです。「混沌は混沌のままにしておいてもいい」という見方だってできるのです。5さんは「自分は何を読んでいたのだろう」と自己嫌悪になるとおっしゃいましたが、そこは心配なさらなくてもいいと思いますよ。たとえ言語化できなくても、読書体験は必ずその人の血となり肉となっているはずです。
僕のブログがモチベーションになるのなら、これ以上に嬉しいことはありません。同じ読書家として頑張っていきましょう!
KENさんへ
はじめまして、こんにちは。何度かこのサイトを繰り返し読ませていただいています。
私は書き始めて4年。一次選考を通ったこともありません。このサイトを時々読んで気持ちを新たにさせてもらっています。
KENさんの経歴を見て、すごいと思っています。KENさんの思いをこのサイトで拝読し、作品も読んでみたいなぁと思っています。
このサイト、とても好きです。ありがとうございます。
ピーターさん
ピーターさん。うれしいコメントありがとうございます。久しぶりの読者さんからのコメントなので、うれしくてちょっと長々コメント返しちゃいますね。
ピーターさんも僕と同じく、小説を書いていらっしゃるのですね。しかも4年も続いているなんてとてもすごいことです。忙しない日常の中、それでもパソコンに向き合ったり、ペンを取ったりすることは、誰でもできることではありません。たとえ今、結果に結びついていなくても、「4年間書き続けたこと」そのものは十分評価できることだと思いますよ。
それに、書き続けていれば、きっと何かを得ることができると思います。それは「大手の二次選考に進む」とか、「地方の文学賞を受賞する」とか、そういうレベルのものに限らないと思います。「じゃあそれが何なのか」、「書き続けていると何を得られるのか」と問われたら、実は僕もはっきり分からりません。だけど僕は「読む」ということと「書く」ということに必ず意味があると信じています。読むことと書くことへの信頼は捨てたくないと思っています。くさい言い方をすれば、書くことは「祈り」に近いのかもしれません。
ピーターさんにも、ぜひ読み続けて、書き続けてほしいと思います。「このサイトが好き」といってくださるピーターさんには、たぶん僕と同じような「生きづらさ」があるのかもしれませんね(笑)だけど、その生きづらさは、深く生きるために必要なことなんですよ、きっと。そうした感性を原動力に、これからもコツコツと書き続けていってください! 僕も頑張ります。