はじめに「作品の評価」について

2021年下半期、第166回芥川賞受賞した『ブラックボックス』(砂川文次 著)
本作は選考会で多くの選者から高い評価を得た。
その中でも「飾り気がない」という言葉は、この作品の本質をよく表していると思う。
たしかに、この作品には「優れたテクニック」とか「高い芸術性」とか「斬新なテーマ」といったものはないかもしれない。
ただ、その一方で、人間を真正面から捉えようとする「ストレートさ」があって、読む者の心に刺さる作品だといえるだろう。
「本作には、書かれねばならなかった切実さがある」
という選者の言葉は、その点を言い当てたものだ。
その他にも、
「古風なリアリズム」とか、
「現代のプロレタリア文学」とか、
本書の大きな特徴は、伝統的な“近代文学”の流れを汲んでいる点だといって良いかもしれない。
この記事ではそんな『ブラックボックス』の解説と考察をし、最後に、この作品が描かれた「現代的な必然性」についても考えてみたい。
それでは、ぜひ、最後までお付き合いください。
あらすじ

主人公は28歳の男性“サクマ” コミュ力に乏しく、癇癪持ち。 感情のコントロールが効かない彼は、これまで数多くの対人トラブルを巻き起こし、職を転々としてきた。 自衛官、不動産営業、引っ越し業者、コンビニ店員…… 現在は、彼の性に何となく合った「メッセンジャー(自転車便)」をして生活をしのいでいる。 とはいえ、今の「身体を張った」生活に、サクマは疑問を持っている。 「今はこれでいいとして、歳を取ったらどうなるんだろう」 彼のその内省は、しかし深まらず、すぐに思考は停止。 現実から目を背け続けるサクマ。 その一方で、「繰り返される日々」にも嫌気がさしている。 そんな中、同棲している円佳が妊娠。 サクマは改めて「ちゃんとしなきゃ」と思い始める。 ある日、自宅アパートに税務官がやってきて、サクマは脱税を指摘される。 癇癪を起こしたサクマは、税務官らに暴行を加え、駆けつけた警察に現行犯逮捕される。 刑務所の中でも、相変わらずトラブルが絶えないサクマ。 同房の男に暴行を加えたことで、50日間も独房に閉じ込められる罰を受ける。 だが、このとき初めてサクマは自分自身と向き合うことが出来た。 「自分の半生」とは、「これからの人生」とは、「自分はいったいどう生きていくべきか」 そんな内省の果てに、彼がたどり着いた「答え」とは……

サクマが“走りつづける”理由

メッセンジャーとして縦横無尽に、都内を走り続けるサクマ。
その姿は『ブラックボックス』の前半において、軽快な文体で描かれる。
歩行者の波に吞まれる前に、サクマはハンドルを右へと切ってそのままシャドウに入った。上げろ上げろ上げろ、と胸の内で小さくつぶやいく。ギアをもう一枚上げる。ペダルがまた重くなった。ここでようやくサドルに腰を下ろし、一瞬視線を下に落として身体と機材の調子を確認した。万事順調だ。視線を戻すと青看板が見えてきた。飯田橋。日本橋。半蔵門。外堀通り。青地に白の矢印。(単行本P39より)
スパン、スパン、スパン、と歯切れの良い文体は、確かに疾走感や爽快感を読み手に与える。
ただ実は、物語のこの前半からしてすでに「息苦しさ」とか「閉塞感」といったものが、否定しがたく存在している。
それは、まるでサクマが“生活”に追われるように自転車をこぎ続けるからだ。
今日の稼働率を考える。午前中いっぱいは多分潰れた。午後にどのくらい走れるだろうか。今日の取り分は、多分よくて八千円、実際は七千円前後だろう、と見積もる。(P19より)
こんな風に、彼が「稼働率」を何よりも優先して考えてるのは、このメッセンジャーの世界が「歩合制」であり、「待機」している間は一円も稼げないからだ。
食事時間も確保できないサクマにとって、食事などもはや「エネルギー以上の意味を持たない」(P45)
サクマはそれほど生活に追われている。
それはちょうど「自転車操業」さながらで、今の彼にとっては「身体」こそが資本。
身体が損なわれてしまえば、生活は成り立たないわけだ。
にもかかわらず、彼が所属する会社には、その「身体」を補償してくれるようなシステムは全くない。
身体には何かがあっても補償も何もなく、基本的には自己責任で片付けられてしまう(P28より)
ここから、サクマの“焦り”とか“恐怖”というものがムクムクとが顔をもたげてくる。
「今はいいとして、歳をとったら俺はどうなっちまんだろう」
そして、彼はこう思う。
――ちゃんとしなきゃな――
この焦燥や恐怖は、ふとした時にサクマを襲うわけだが、自転車をこいでいるときだけは、そういった屈託から彼は無縁でいられる。
自暴自棄になるのとは違う。ちゃんとしなきゃいけないのも分かる。でもちゃんとするっていうのが具体的にどうすることなのか、サクマにはまだ良く分からなかった。走っている時だけ、そこから逃れられる。(P17より)
そうやって自分を誤魔化し誤魔化し、彼はたいしてやりたいわけでもない「メッセンジャー」を続けざるを得ないのだ。
物語をまとう「息苦しさ」や「閉塞感」というのも、まさに、ここに由来している。
サクマが「走り続ける理由」、それは、
- 自らの生活を支えるため
- 現実から逃避するため
この2つだといっていいだろう。
スポンサーリンク
“ゴール”を模索するサクマ

現実直視をさけるサクマ。
だが、そうはいっても、自分自身を誤魔化し続けることはできない。
時間は刻一刻と過ぎていくし、自分は確実に歳を取っていく。
いつまでも自転車をこげるとは限らないのだ。
だから、サクマは正社員の道も、それなりに考えたりする。
だけど、どうにも踏ん切りが付かない。
それが本当に「幸せ」になれる道なのか、サクマには分からないからだ。
というか、彼には、そもそも「幸せ」が何なのかさえ分からない。
後輩の横田と、モスバーガーを食いながら、「仕事」について話しあうシーンがある。
サクマは横田から「そろそろちゃんと働きたいんですけど」という相談を受けるが、「ちゃんと」がどういうことなのか分からないサクマは困惑してしまう。
「つーかあと二年で三十になるおれにそういうこと言わねーだろフツー」
軽く小突いてやった。
「いや、サクマさんはいいんですよ、色々経験してるしもう同棲もしてるしなんかゴールみえてるっぽくないですか?」
「はあ? なんだよ、ゴールって」(P68より)
横田の口から唐突に飛び出た「ゴール」という言葉は、人々が目指す「幸福」と言い換えてもいい。
では、その「ゴール」とはなんだろう。
所帯を持つこと?
正規雇用されること?
体が資本の職から離れること?
自分が目指すべき「ゴール」が何なのか全く分からないサクマ。
横田の言葉をきっかけに、彼は次のように内省する。
こんな日々を積み重ねた先にあるものは、やっぱりゴールじゃないという気がしている。どんな日々を積み重ねたら納得できるゴールがあるのか分からない。ひょっとすると積み重ねるという行為はゴールから遠ざかっていくことなんじゃないか、とも思える。(P71より)
これまで様々な対人トラブルにより、職を転々としてきたサクマ。
いまは、なんとなく自分の性にあった「メッセンジャー」をして生活を凌いでいる。
だけど、これが果たして、「ゴール」への道なのか。
っていうか、そもそも「ゴール」ってなんなのだ。
そう自問自答する彼だったが、それでも一つだけはっきり言えることがあった。
それが、
「自分はやっぱりここから抜け出したい」
ということだった。
ずっと遠くに行きたかった。今も行きたいと思っている。(P72より)
こんな思いで28まで生きてきたサクマ。
いうまでもないが、ここでいう「遠くへ行く」というのは、繰り返される「満たされない日常」から脱却することを意味している。
だけど繰り返すが、サクマには「どこへ行くべき」なのか「どこへ行きたい」のか、それが全く分からない。
たとえば「自分にない物」それを手にしたとき、サクマは幸せになれるのだろうか。
実際にサクマは、オフィスビルに出入りしている「ホワイトカラー」の男女を見ては、羨望と憎悪の入り交じった複雑な感情を抱く。
ただ、彼らがいるその場所が、自分とは無縁な世界であることも知っている。
(彼らが)何をしているのか知ろうとしても絶対に触れられないものがその奥にあると言うことは共通している。そしてこの分からなさは、なんとなく帰路についている中でどこからともなく漂ってくるカレーとか煮物のにおいに似ていると思う。(P48より)
他人んちの夕飯のにおい……
そのにおいは「自分は部外者である」ということを、否が応でも意識させるものだ。
サクマもまた「ホワイトカラー」の連中に対して、「おれはどうせ部外者なんだ」という疎外感を持っていて、もっと言えば、それは劣等感でさえある。
後にサクマは税務官に暴行を加えることになるのだが、その根っこにも彼の「疎外感」や「劣等感」があるといっていい。
スポンサーリンク
世界は“ブラックボックス”

とはいえだ。
とはいえ、サクマには「ホワイトカラーこそ、ゴールだ」と言える確信があるわけでもない。
実際に彼は、タクシーにのるスーツ姿の女性を見て、
「彼女だって、自分と大差はないのかもしれない」
といったことを考え、
ちゃんとするってなんなんだ(p72)
と、改めて、「ゴール」とか「幸せ」について考え出してしまう。
――おれは何を目指して生きていけばいいのだろう――
こんな風に、サクマにとって、彼をとりまく“世界”は、どこまでも不可解なモノなのだ。
目に見える世界の姿は、あくまでも“表層的な部分”に過ぎない。
その奥底にある「ルール」とか「原理」とか「構造」といったものは、サクマの目には全く映らない。
ブラックボックスだ。昼間走る町並みやそこかしこにあるであろうオフィスや倉庫、夜の生活の営み、どれもこれもがあけすけに見えているようでいて見えない。張りぼての向こう側に広がっているかもしれない実相に触れることはできない。(P53より)
そう、まさにサクマにとって、この世界は「ブラックボックス」だといっていい。
目の前には、確かに具体的な人間が立ち動き、具体的な生活があって、具体的な世界が広がっている。
だけど、彼にはその世界の「実相」に触れることはできない。
「こうすれば幸せになれますよ」
そんな分かりやすい道標があるわけではないのだ。
遠くへいきたかった。なんとかしたかった。その方法が分からなくてずっと走り回った。(P92より)
「遠くに行きたい」と、サクマがどんなに願っても「遠く」へ行く方法も、そもそも「遠く」がどこなのかも、だれも教えてはくれないのだ。
スポンサードリンク
サクマが“うまくできない”理由

さて、ここでは、そもそもなぜサクマが”うまく“できないのかについて考えてみたい。
一つの環境にそれなりの期間身を置いた経験は少ない(P140より)
こうある通り、学生時代から、サクマは様々な対人トラブルを巻き起こし、そのつど居場所を変えてきた。
その理由はといえば、なんといっても、彼が持つ生来の“衝動性”が挙げられるだろう。
その引き金になるのは、たいていの場合は「人間関係のわずらわしさ」とか「他者からの悪意」みたいなものだった。
それらにうまく合わせて、愛想笑いの一つでも浮かべられれば、大概のトラブルは避けられたはずだった。
だけど、サクマは、人に合わせるということができない。
そもそも、サクマには、コミュニケーション能力というものが欠けているのだ。
ではもっと突っ込んで、なぜ彼は「コミュ力」がないのだろうか。
それは、彼の「言語能力」の低さにあると思われる。
サクマは、相手の話の「趣旨」とか、文章に書かれた「要旨」とか、そういったものを読み取ることがうまくできない。
たとえば、税務官に暴行を加える、その直前のシーン。
自分を訪ねてきた彼らの「意図」をくみ取れず、サクマは投げやりになる。
(税務官は)諸々の規則だとか今後の流れとかをしゃべっていて、もちろんサクマは始めの数秒を聞いただけで、ああこれは無理だ、わからない、ととっくに諦めていた。
最後に自分が払わなければならないとされる金額と貯金の額がほとんどイコールだったと知らされた。こういう分かりやすいことを先に言ってくれればいいんだ。(P109より)
それから、逮捕後、刑務所に届けられた「大家からの手紙」を読むが、その意図もつかむことができない。
サクマは十回以上読んで、ようやく家賃が半額になってそれもしばらく払わなくていいのか、と理解した。(P119より)
大家は、つかまってしまったサクマと、残された身重の円佳に同情し、「家賃は半額でいいから」といった手紙を送って来てくれたわけだ。
ところが、サクマは、そんな大家の意図や感情を読み取ることができない。
「10回以上」も読まなければ、大家の「優しさ」に気付くことができないのだ。
こんな風に、サクマの「コミュ力不足」の根っこには、この「言語能力の低さ」があると考えていいだろう。
さらに厄介なのは「言語能力」の問題により、彼が公的な文章を理解できないということなのだ。
「保険」とか「扶養」とか、見るだけで言葉の意味と音とが空中分解する(P96より)
こうある通り、サクマには役所から届く重要な書面を読解することが困難なのだ。
それはつまり、彼が社会システムやセーフティネットを利用することもできないことを意味している。
こうして、他者から切り離され、社会からも切り離されていくサクマ。
彼にとって、世界は、そして他者もまた、すべてが「ブラックボックス」なのである。
そんな世界にあって、「自分はこの世界の部外者なのだ」という意識を、彼はどんどん肥大化させていく。
学校、自衛官、会社、バイト、逮捕、そして牢獄……
そこでのトラブル全般において、原因となっているのは、間違いなく彼の“衝動性”だろう。
ただし、その“衝動性”の背景には、
- 言語能力の低さ
- コミュ力の欠如
- 社会からの孤立と疎外
- 焦り、恐怖、劣等感
そうした様々な要因が複合的に絡み合って存在している。
彼の“生きづらさの”根っこには、「能力因子」と「社会因子」とがあるわけだ。
スポンサーリンク
サクマの出した“答え”とは

ここまで書いてみると、サクマに“救い”が訪れるなんて、とてもじゃないけど思えない。
だけど、この作品の終盤には微かな光明が描かれる。
それは、刑務所で、サクマの心境に変化が生まれるからだ。
傷害罪で逮捕されたサクマは、刑務所内でも暴行を働く。
同房人(向井)に嫌がらせを続ける「伊地知」という男に対して、例の癇癪が発動。
カッとなって、ぶん殴って、噛みついて、肉を引きちぎってしまう。
結果、サクマは独房に50日閉じ込められるという罰を課されることとなる。
この懲罰は誰とも会話することができず、ただただ己と向き合うこととなる。(P125より)
外界の情報をすっかり遮断され、同房や刑務官との会話も禁じられると、当然に自分に意識が向く。(P130より)
こうして彼は、30年近い人生の中で、初めて自分自身と向き合うこととなる。
――これまでの人生、刑務所での生活、そしてこれからの人生――
50日に及ぶ内的生活を終え、再びもとの牢屋に戻されたサクマ。
そんな彼を待っていたのは、同房人たちの、サクマに対する意図せぬ評価だった。
サクマに関する、好意的な雰囲気が同房に広がっていたのだ。
彼らの心境をざっくりと代弁するならば、
「ムカつく伊地知に、いっぱつ食らわせてくれて、ありがとう」
ということになる。
ただ、サクマは釈然としない。
サクマにしてみれば、本当にただ頭にきて伊地知を殴ったりかみついたりしただけで、向井を守ろうという意図はこれっぽっちもなかった、ただ伊地知が向井にしてきた行為もムカついていて、そういうのが蓄積されて行動になっただけだ。(P156より)
サクマにしてみれば「自分の意図」とは無関係に、周囲の評価がガラッと変わってしまったわけだ。
――わからん、いよいよわからん――
だけど、サクマはこう思い至る。
この「分からなさ」というのは、別に、今に始まったことじゃない。外の世界でも同じだったじゃないか。
――世界はブラックボックスだ――
たしかに、これがサクマの世界認識だった。
それを改めて思い出したサクマ。
だけど、50日の内省生活を経た彼は、「世界は不可解だ」という前提に立ちつつも、こんなことを考える。
今にして思えば、これに順応することがまずちゃんとすることの第一歩だったのかもしれない。(P157より)
社会のことが分からなかった。
他者のことも分からなかった。
それが分からないから苦しかった、イライラした。
その原因は、俺じゃなくて、世界の方にある。
そんな風に、かつてのサクマは、自分の苦しみや苛立ちの原因は、自分の外にあると思っていた。
だけど、今のサクマは、そんな不可解な世界に「順応」することが、ちゃんとする第一歩だと考え初めている。
ずっと外に向いていた思考のベクトルが、初めて内に向かったわけだ。
サクマは、自分が「変わる」ことの必要性を感じているのだ。
“衝動性”についても同じだ。
自分はこれを押しとどめよう押しとどめようとしていたが、付き合っていくこともできたのではないだろうか、と急に思えた。(P159より)
――もしまだ間に合うなら――
サクマは、そんな風に願ってみる。
もしまだ間に合うなら、自分は変わらなくちゃいけいない、と。
もちろん、刑務所を出た彼が、すぐに変われるかは分からない。
サクマには、「身元引受け人」らしい存在がいない。
円佳は再び自分を受け入れてくれるだろうか。
自分は再び生活を取り戻すことができるだろうか。
それはサクマ自身にも、分からない。
だけど、彼のこの内面の変化は、サクマの大きな“成長”と言って良いだろう。
刑務所を出た彼は、きっとこれまでの彼とは違う。
この『ブラックボックス』という小説のラストは、こう締めくくられている。
「忘れよう」と決めた円佳からの手紙は、その隣に、ジャンプの1ページ目に挟んだままだ。
たとえ世界が不可解であっても、サクマはきっと、円佳との生活を取り戻そうとするんじゃないか・・・・・・
そう思わせてくれるこのラストシーンが、僕はすごく好きだ。
スポンサーリンク
・
おわりに「現代流プロレタリア文学」 とは

さて、『ブラックボックス』の解説と考察は以上となる。
この作品は、芥川賞の選評で「現代流のプロレタリア文学」と評されていた。
プロレタリア文学というのは、大正時代に起きた一つのムーブメントだった。
分かりやすく「強者」と「弱者」が別れた時代。
前者は「有産階級」と呼ばれ、後者は「労働者階級」と呼ばれた。
前者は「ブルジョアジー」と呼ばれ、後者は「プロレタリアート」と呼ばれた。
――強者は弱者を搾取する――
これが資本主義の原理である。
プロレタリアートたちは、
「そんな不平等な社会、ぜったいにおかしいだろ!」
と声高に叫び、「目指せ平等!打倒資本主義!」をスローガンに掲げ、社会主義革命運動を起こしていった。
「プロレタリア文学」ってのは、文学シーンにおける「社会主義革命運動」である。
要するに、彼らには、目指すべきものがあったし、幸福が何かを知っていたし、きちんとゴールも見えていたわけだ。
ひるがえって、現代という時代に眼を向けてみる。
社会主義は失敗し、資本主義は社会に多くのヒズミを生んでいる。
かつての「幸せ」の方程式みたいなものはガラガラと崩れ去り、人々は目指すべきものを見失ってしまったわけだ。
フランスの哲学者、ジャン・フランソワ・リオタールはこれを「大きな物語の終焉」と呼ぶ。
万人に通用する「幸せ」というものはもはや存在せず、現代人一人一人が、それぞれの幸せ(小さな物語)を模索しなければならない、と。
実際、僕たちだって、何が幸福で、何が正解で、何がゴールか分からないでいる。
この世界に生まれた瞬間から、よーいドンと、なぜか走らされているのが僕たちだ。
だけど、そのゴールがどこなのか、僕たちには分からない。
僕たちとサクマと、いったい何が違うのだろうか。
きっと、本質的には変わらない。
「ブラックボックス」を生きているのは、僕たちだって同じなのだ。
本書『ブラックボックス』は確かに「プロレタリア文学」と評すことはできると思う。
だけど、かつてのプロレタリア文学とは根本的に違っている。なぜなら、
目指すべき「ゴールが分からない」のが現代だからだ。
そういった意味でも、本作は“現代流”のプロレタリア文学だといっていい。
それは、「大きな物語」を喪失した現代における、一つの「小さな物語」でもある。
小人の説……、無名の個人のお話……
その別名が「小説」であるとすれば、『ブラックボックス』は現代に生まれるべくして生まれた正真正銘の「小説」なのだろう、
と、きちんとうまいこと言ってみて、この記事を終わりにしたい。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
すき間時間で”芥川賞”を聴く

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・
”おもしろい” 芥川賞作品はこれ!
以下で、芥川賞受賞作品の紹介をしている。
ぜひ ”次の1冊” の参考にしていたければと思います!



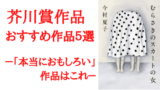


コメント