個性派ぞろいの時代

芥川賞受賞作品まとめ ・1950年代「芥川賞」おすすめ9選 ―戦後文学の全盛― ・1960年代「芥川賞」おすすめ7選―女性作家の台頭― ・1970年代「芥川賞」おすすめ6選―文学に吹く新しい風― ・1980年代「芥川賞」おすすすめ3選―空前絶後の❝暗黒時代❞― ・1990年代「芥川賞」おすすめ6選 ―現代女流作家の躍進― ・2000年代「芥川賞」おすすめ10選 ―個性派ぞろいの作家たち― ・2010年代「芥川賞」おすすめ10選 ―バラエティ豊かな傑作たち― ・2020年代「芥川賞」おすすめ7選 -直近全作品を読んだ上で厳選―
芥川賞受賞作品を年代ごとに紹介している。
今回はついに2000年代。
その顔ぶれは超豪華。
ここで受賞した多くの作家たちが今の文学を牽引していて、すでに選考委員として“重鎮”レベルにある作家も少なくない。
彼らの作品はどれも個性的で、これまでの芥川賞に見られない斬新なものが多い。
また作家の経歴も多岐にわたっている。
パンクロッカー、歌手、映画のシナリオライター、営業マン、フリーター、大学生……
2000年代は、本当に魅力的でおもしろい作品が多いのだ。
ということで、オススメ作品は10作品に及んでしまった。
本当はもっと厳選したかったのだけれど、こればかりは仕方ない。
とはいえ、10作品それぞれに違った魅力があるし、おすすめポイントもそれぞれ違う。
ぜひ この記事を参考に“次の1冊”を見つけていただければと思う。
『きれぎれ』(町田康)2000年

自由奔放の無重力文学
町田康の文学は、ハチャメチで読む人を選ぶ。
本書『きれぎれ』もかなりハチャメチャだ。
- 主人公の「俺」は売れない絵描き。
- 高校を退学。
- 定職に就かない。
- 労働が大嫌い。
- 浪費家で酒乱。
- 趣味はランパブに通うこと。
『きれぎれ』は、そんな「俺」を中心とするドタバタ喜劇なのだが、正直この作品をそんな言葉でまとめることなどできない。
自由奔放、縦横無尽、重力からも自由で、時間や空間概念を完璧に無視している。
活字でなければ、表現できない世界観なのだ。
マンガでも、アニメでも、映画でも、絶対に表現できないだろう。
「はあ? 言ってる意味がわからん」
と思うかも知れないが、だけど、そうとしか言いようがないのだ。
上記は比喩表現でも誇張表現でもない。
町田康は、ぼくたちの既成概念をことごとく無視したり、破壊したりする、驚きの作品を生み出す作家だ。
ぼくは、「文学」とは、言葉に依存しながらも、言葉では到達できないところへ向かう営みだと思っている。
「はあ? 言ってる意味がわからん」
と再び思うかも知れないが、そんな方へぼくはこう言いたい。
「とにかく町田康を読んでください」
繰り返すが、彼は既存の枠では理解することが難しい世界を生み出している。
「じゃあ、その世界というのは、まったく意味のないデタラメな世界なのか?」
そう思いきや、決してそんなことはない。
確かにメチャクチャな世界観なのだが、ふっと感傷を刺激されて涙が浮かんだり、すごすぎて鳥肌がたったり、馬鹿馬鹿しくて笑えてきたりと、不思議なことにちゃんと読み手の感情に訴えかけてくるのだ。
なぜなのか?
分からない。
なぜか、そうなのだ。
たぶん、その大きな原因は、町田康の独特の文体にあるのだろうと思っている。
基本的には大阪弁なのだが、極端に長い1文が頻出して、ところどころに、ファンから「町田節」と呼ばれる独特の言い回しが挿入される。
そして、登場人物の「自意識」がダラダラと垂れ流れてくる。
その文章が、ビックリするくらいクセになる。
一応、文学的には「饒舌体」と呼ばれる一つの手法で、太宰治なんかが得意とした文体の一種だといえる。
が、この文体は、絶対にだれにもまねできない、町田康唯一無二のものだ。
当然と言おうか、選考会でもこの文体をめぐって、賛否両論、まっぷたつだった。
- 石原慎太郎「ドラッグのような陶酔感」
- 池澤夏樹「リズミックで音楽的」
と評価する声もあれば、
- 宮本輝「ただただ不快」
- 河野多惠子「痛ましい」
と酷評する声もあった。
ぼくは、町田康の文体を支持する。
ここまで、読み手の感情を(良くも悪くも)揺さぶる作家は町田康以外にいないからだ。
「言葉を使って、言葉の届かない世界へ」
これが『きれぎれ』であり、町田康の文学だと言える。
『パーク・ライフ』(吉田修一)2002年

日常を丁寧に描いた秀作
代表作『悪人』や『怒り』は第一級の「エンタメ小説」であり、発表後は瞬く間にベストセラーになり映画化もされた。
稀代のストーリーテラーと言える吉田修一は、いまや「エンタメ畑の人」と人々から認知されているだろう。
だから「芥川賞」と聞くと違和感を持つかも知れないが、彼のデビュー作『最後の息子』は純文学作品だった。
その後『パーク・ライフ』で第117回芥川賞を受賞するが、同年『パレード』で山本周五郎賞を授賞する。
山本周五郎賞は「エンタメ小説」を対象にした権威ある文学賞だ。
1人の作家がこの2つの賞を受賞することは史上初。
吉田修一は、文學界の“二刀流”とも言える作家なのだ。
受賞作『パーク・ライフ』は、静かで淡々とした、まさに「純文学然」とした作品だ。
- 主人公の「ぼく」は入浴剤を売る営業マン。
- 趣味は日比谷公園のベンチに座って過ごすこと。
- ある日「ぼく」は電車の中で、間違って見知らぬ女性に声をかけてしまう。
- 赤面した「ぼく」とはうらはらに、気さくに返事を返す女性。
- たったそれだけの出来事だったが、後日「ぼく」はその女性と日比谷公園で再会する。
- それから2人は公園を介して、奇妙な交流を重ねていく……
『パーク・ライフ』にはこれといった事件も発展もない。
恋愛小説かと思いきや、「2人が恋仲になるか?」ってところで終わる。
ありきたりな日常にスポットを当てて、淡々と語っていくだけ。
だけど、読後不思議な余韻に包まれるが、それは吉田修一の丁寧で優しい文章が大きい。
選考委員の高樹のぶ子は、
「作意が見えない」
「人間を見る目が随所に光る」
と、その素直さと分析眼の鋭さを高く評価しているし、河野多惠子は、
「完成度が極めて高い」
「秀作と呼ぶのに、なんのためらいもない」
と諸手をあげて大絶賛している。
決して大風呂敷を広げることなく、小さな日常を丁寧に丁寧に拾い上げた好感の持てる作品。
ストーリーテラー吉田修一の、また違った側面を垣間見ることができるだろう。
『蛇にピアス』(金原ひとみ)2003年
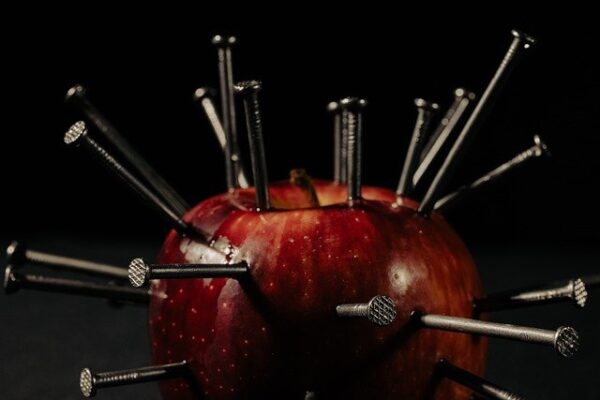
“痛み”こそ生きる証
物語はこう始まる。
「スプリットタンって知ってる?」
「何? それ。分かれた舌って事?』
「そうそう。蛇とかトカゲみたいな舌。人間も、ああいう舌になれるんだよ」
この冒頭で、読者の心はグッとつかまれる。
「スプリットタン」とは、舌に穴をあけて、それを少しずつ拡張していき、最後に糸で舌を二股に裂いて、「蛇のような舌」にするという、要するに“身体改造”の一つである。
タイトルにある「蛇」と「ピアス」は、このあたりに由来している。
2000年代は「ボディピアス」が流行った時代だ。
「ボディピアス」とは、耳や鼻や舌や眉やヘソ、そして強烈な人は「アソコ」にも、とにかく身体のいたる所にするピアスのことをいう。
これが、とにかく、痛い。
ちなみに、ぼくも耳にピアスを開けて拡張したが、痛すぎて中途半端でやめたクチである。
作者はピアスとか、タトゥーとか、SMとか、暴力とか、セックスとか、そうした若者の「痛み」にスポットをあてて、彼らの儚く繊細な心理を見事に描いている。
選考委員の黒井千次は、
「歯切れのよい短い文章が、痛覚や欲求や血の騒ぎや、脱力感までストレートに叩きつけてくる」
と評価した。
また村上龍は この作品を推そうと、選考委員を説得するためのメモを持って選考会に参加したという。
村上龍自身も『限りなく透明に近いブルー』で暴力とドラッグとセックスを描き芥川賞を受賞した作家だ。
「餅は餅屋」よろしく、その道の先達には『蛇にピアス』という作品の妙がよく分かったのだろう。
実際「痛み」を書かせたら、金原ひとみの右に出るものはいないとぼくも思っている。
実は金原自身、15歳のころリストカットを繰り返した経験を持っていて、その切実な経験が作品の元になっている。
生き伸びるために「痛み」が必要、「痛み」こそが存在証明。
作中には、そんなメッセージがみなぎっている。
作品は漫画家され、映画化され、翻訳されて世界105ヶ国で売られた。
ちなみに、受賞時の金原は20歳。
この若さで、これだけのものを書いたその才能に驚かされる。
が、次の綿矢りさもまた凄い。
『蹴りたい背中』(綿矢りさ)2003年

人間の“謎の衝動”にスポット
綿矢りさの授賞はセンセーショナルだった。
作者が19歳の女子大生だったからだ。
それまでの最年少記録は丸山健二の23歳。
実に37年ぶりに更新となった。
また、同時受賞した金原ひとみも20歳という若さだったこともあり、『蛇にピアス』と『蹴りたい背中』が掲載された『文藝春秋』はミリオンセラーを達成。
ただし、勘違いしないでほしいのは、「若さ」とか「かわいらしさ」は、彼女への評価とは全く関係ないということだ。
『蹴りたい背中』で書かれているのは、人間の「抑えがたい衝動・欲求」だ。
- 主人公は女子高校生のハツ。
- 彼女は女子にありがちな「グループ交際」を拒絶している。
- その1つの理由は、彼女は誰かといるときこそ強烈な孤独を感じてしまうから。
なるほど、ぼくたちは、とかく、一人でいる時よりも、誰かと一緒にいるときにこそ、強烈な孤独に襲われることがある。
とはいえ、1人でいたって、孤独は孤独なのだ。
実際にハツも、1人でいることに「自分の存在が完全に消えてしまう恐怖」を感じている。
人ともダメ、1人もダメ。
そう、ハツはめんどくさい子なのだ。(※注 「めんどくさい」は文学では褒め言葉)
そして、とにかく頭のなかでいろいろと考えをめぐらせ、自分を正当化していく。
心配して近づいてくる同級生にも憎まれ口をたたき、彼らを見下し優越感にひたる。
当然、彼女は、いわゆるスクールカースト最底辺に位置づけられる。
で、同じくスクールカースト底辺男子「にな川」と、奇妙な連帯関係を育んでいく。
そして彼に対してサディスティックな衝動をおぼえていく。
タイトルの『蹴りたい背中』とは、この「にな川」の背中のことなのである。
ところで、こんなことを感じたことはないだろうか。
人の無防備な背中って、どうしてこうも想像や欲望を掻き立てるのだろう……
ぼくも「偉いひと」の背中を見て、
「ああ、いま、あの後頭部を思いっきりブッ叩いたら、おれは一体どうなるのかなあ」
そんなことを思うことがある。
それはなぜだろう。
単純に想像をもてあそび楽しんでいるようにも思えるし、日々のうっ憤を爆発させたい欲求があるようにも思えるし、すべてを台無しにさせたい破壊衝動(いわゆるタナトス)の発動のような気もする。
とにかく『蹴りたい背中』を読むと、ぼくは妙に共感してしまうのだ。
ああ、そうそう、なぜか、蹴りたいよね、背中。って感じで……
さて、このプライドが高く、めんどくさい主人公のハツ。
いったい、いつ、どんな状況で「にな川」の背中を蹴りたくなるのか。
そして、その衝動は いったいどんな感情に由来しているのか。
それは、ぜひこの本を読んで確かめていただきたい。
スポンサーリンク
『グランド・フィナーレ』(阿部和重)2004年

“J文学の旗手”による本格純文学
1990年代に“J文学”という言葉が流行りだした。
この発信源は河出書房の文芸誌である『文藝』
『文藝』といえば、今や飛ぶ鳥落とす勢いの文芸誌で、多くの人気作家を輩出し続けている。
“J文学”というのも、当時『文藝』が日本の文学シーンに巻き起こしたちょっとしたムーヴメントだった。
この頃は“Jリーグ”とか“J-POP”を始め、日本のカルチャーに“J”を付けるのが流行り始めていたのだが、J文学というのも、その流れに乗っかったものといえる。
そして“J文学”と見なされた作家というのが、90年代に登場した新進気鋭の作家たち、すなわち藤沢周であり、町田康であり、そして阿部和重だった。
彼らの文学の共通点を指摘することは、正直言ってとても難しい。
強いていえば、これまでにないテーマや設定、表現方法、文体などを採用した点や、音楽や映画なんかのサブカルチャーを積極的に文学に取り入れた点だといえるかもしれない。
阿部和重はその“J文学の旗手”と呼ばれ、“最後の大物”とさえ言われた。
もともと映画監督を志していた阿部。
映画のシナリオを主に書いていたが、途中で小説家にシフトした。
1994年に群像新人文学賞を受賞し小説家デビューすると、その後の『インディヴィジュアル・プロジェクション』で注目を集めた。
彼の文学で扱われるのは、テロとかネットとかロリコンとか、当時流行りのトピックが多く、また物語の舞台も渋谷だったり、109やロフトなどの実在する場所だったりする。
そんなことから、阿部の文学は“渋谷系文学”ともいわれた。
前置きが長くなったが、そんな彼の芥川賞受賞作品が『グランド・フィナーレ』である。
- 主人公は「沢見」という男。
- 彼は少女のヌードを撮るのが趣味のロリコン。
- そのことが原因で妻と離婚し、娘の親権をなくす。
- 職も失った彼は、地元へ戻る。
- しかし、その後、娘の誕生日に合わせて上京。
- 誕生日プレゼントを渡そうと娘を待ち伏せする沢見だったが……
と、あらすじはこんな感じなのだが、なんといっても作品の見所は沢見(ロリコン)の心理描写だと言える。
選考委員の高樹のぶ子は、
「明るくて無邪気で不気味な小説」
と、この作品の独特のトーンについて形容している。
実際「沢見」の内面には、言葉にできない独特の明るさや不気味さがあり、それが本格的で存在感のある文体で綴られていく。
“ロリコン”というテーマと、格調の高い文体とが、独特の小説世界を作り上げ、不思議な余韻を読者に与える。
余談になるが、阿部和重の妻は、後ほど紹介する川上未映子で、彼らは世にも珍しい芥川賞カップルなのである。
(ひょっとして彼らの子どもも、10年後とかに芥川賞を受賞するかも?)
スポンサーリンク
・
『土の中の子供』(中村文則)2005年

世界が認める“不条理の文学”
中村文則は、2014年にアメリカの「David L.Goodis賞」を日本人で初めて受賞している。
彼は、今回紹介する中で、最も世界から評価されている作家だといっていい。
なぜ、彼の文学は世界で評価されるのか。
それは、彼の文学が普遍的なテーマを扱っているからなのだろう。
そのテーマとは「この世界の不条理」と「人間の自由意志」だ。
と聞いて、「ああ、ムリムリ」と思った方も多くいるかも知れない。
だけど、この「不条理」や「自由意志」は文学の宿命ともいえるテーマなのである。
世界に目を向けてみれば、ドストエフスキーとか、カミュとか、カフカといった、ラスボス級の作家達が、このテーマと格闘してきた歴史がある。
中村文則は、これらラスボス級の文豪達の影響を強く受けた作家なのだ。
そして、彼の作品の多くが翻訳されていて、海外の有名文学賞を受賞をしてもいる。
だから「本格的な文学を読んでみたい」と、思いつつ、「でも、ドストエフスキーとか、カミュとか無理」と思う人には、中村文則はオススメの作家なのだ。
さて、作品の話をしよう。
- 主人公は27歳のタクシードライバー。
- 幼少期に親から捨てられ、里親から虐待を受けて育つ。
- 深い森の土の中に埋められたという強烈なトラウマを持つ。
タイトルの『土の中の子供』は、ここに由来している。
ここで、「不条理」について、ちょっと説明させて欲しい。
ぼくたちは、生まれてくる時代も、場所も、選べない。
なぜか、この時代に、ここ日本の、この地域の、この家族のもと、この自分の身体で、この自分の意識を経験しながら、生きている。
考えてみれば、不思議だと思わないか。
「思わない」と思う人は、現状にある程度満足できている、恵まれている人なのかもしれない。
ここで、「もし自分がこの主人公のような境遇だったら」と想像してほしい。
耐えられないほど苦しくて不幸な人生……
どうして自分が?
この人生にはどんな意味が?
きっとあなたは、そう問わずにいられない。
だけど、それを背負ってしまったのには、あなたの落ち度なんて1ミリもないのだ。
「世界の不条理」や「自分の運命」が人生の主題として立ち上がってくるのは、こうした苦しみや悲しみに直面したときだ。
そして、苦しみや悲しみに直面しない人など、この世に存在しない。
いまは幸せだとしても、いつか必ず、苦しみや悲しみはやってくる。
だからこそ、「不条理」は人間にとって永遠不変のテーマなのだ。
そして、中村文則のほとんどの作品は、この「不条理」や「人間の運命」をテーマにしている。
代表作の『銃』も『遮光』も『掏摸』も『王国』も、そして受賞作の『土の中の子供』もそう。
日本の現代作家による本格的な「不条理の文学」、ぜひご一読を。
スポンサーリンク
『沖で待つ』(絲山秋子)2005年

心温まる“純文学ファンタジー”
いつか村上春樹を駆逐する存在になるのではないか。
そう言われるのが、絲山秋子だ。
そんな彼女は作家としては珍しい経歴の持ち主で、大学卒業後は住宅設備機器メーカーの営業職を10年ほどつとめていた。
ところが、1998年に躁鬱病を患って入院。
小説はこの時に書き始めた。
このときの体験を元に、精神病患者たちの姿を描いた『逃亡くそたわけ』は直木賞候補に上がった。
その同年『沖で待つ』で第134回芥川賞を受賞した。
これは30代女性による独白体を取る小説だ。
- 主人公の及川には信頼できる同僚がいた。
- 牧原太、通称「太っちゃん」
- 彼女は太っちゃんのためなら「何だってしてやる」と思えるほど、彼を信頼していた。
- ところが、太っちゃんは死んでしまった。
- 及川は太っちゃんとのある約束を果たすため、彼の部屋に忍び込む……
絲山秋子の作品は、純文学的でありながら、エンタメ要素がほどよく入った「面白い」ものが多い。
受賞作の『沖で待つ』も、2000年代の受賞作の中で、一際「おもしろい」作品だといえる。
難しさや深刻さとは無縁で、ハートウォーミングでもある。
友人でもない、恋人でもない、「同僚」という仕事を通して生まれた信頼を描いたのも良い。
愛着と信頼をよせる同僚の死
そんな彼との間に起こった ほの暖かい奇跡
そして明らかになるタイトル『沖で待つ』の意味……
それらがユーモラスで優しい言葉で描かれていく。
芥川賞作品で「泣ける」作品ってのはあまりないが、『沖で待つ』で不覚にもぼくは泣いてしまった。
心温まる純文学を読みたいという方にオススメの1冊。
スポンサーリンク
・
『八月の路上に捨てる』(伊藤たかみ)2006年

フリーターの1日を“文学”に
「2日前の夕食は?」
そう聞かれて、即答できる人は、きっと少ない。
“日常”というのはそういうもので、意識しなければ簡単に忘れ去られていってしまう。
優れた文学というのは、そんな日常のささやかな一コマを切り取って、その唯一性とか一回性とかを表現したものだと僕は思っている。
伊藤たかみの『八月の路上に捨てる』も、その1つの好例だ。
この物語は、あるフリーターの1日を描いている。
- 主人公「敦」の仕事は自販機の補充をすること。
- 今日“8月31日”が最後の仕事の日
- 彼は同僚の「水城」とトラックで配送に向かう。
- その道中で、2人は互いの身の上話をしていく。
- 敦は、翌日に妻と離婚をすることになっている。
- 夫婦には一言では言い尽くせない、紆余曲折があった……
物語は「バイト最後の1日」と「夫婦生活の回想」とが交互に語られていく。
彼ら夫婦の間に、大きな事件や劇的な展開があったわけではない。
それでも、彼らは“離婚”という結論に行き着いてしまった。
人間関係なんて、そんなものなのかもしれない。
どんなに些細な幸福を願っても、どこかで生まれた小さな歪が新たな歪を生む。
それらは複雑に絡まりあい、もはや修復不可能なまでになってしまう。
わかり合おうと言葉を尽くしても、それは相手に届かない。
孤独とは1人の時に感じるものとは限らず、むしろ誰かと一緒にいるときこそ強烈な孤独を感じるものなのだろう。
『八月の路上に捨てる』を読んでいると、日常の尊さと儚さとを改めて感じさせられる。
日常は決してあたりまえのことじゃない。
その誰もが知りながら、すぐに忘れてしまう事実を、改めて人々に伝えることも文学の役割ではないだろうか。
選考委員の黒井千次はこんな言葉を残している。
「八月の路上に、紛れもない現代の光景の一つが捉えられている。」
作品で描かれた“フリーターの日常”は、現代人が忘れ去っていく“自らの日常”を表現しているのだろう。
『乳と卵』(川上未映子)2007年

哲学と文学 奇跡の融合
唐突だが、哲学の伝統的な問いに「どうしてわたしは、わたしなのか」という問いがある。
この「わたし」ってのは、たとえば「こころ」と呼ばれていて、そして「こころ」を生み出しているのは、頭の中にある「この脳」らしいことを科学は明らかにしている。
だけど、よく考えてみれば、これって不思議じゃないだろうか。
この世界には、今まさに約70億の人々が生きている。
言い換えれば、70億の脳が同時に存在しているということだ。
そして、その70億の脳が、それぞれの「わたし」を生み出している(らしい)。
その内の1つの脳によって、ぼくの「こころ」は存在している(らしい)。
ただ、そう考えていくと、不思議に思わないだろうか。
どうして、ぼくを生み出しているのは「あの脳でも、あの脳でも、あの脳でも、あの脳でも、あの脳でも……(×約70億)……あの脳でもなく」、この脳だったのだろう。
ぼくはそれが、不思議でならない。
そして、これが「どうしてわたしは、わたしなのか」という、哲学の伝統的な問いである。
前フリが長くなってしまったが、川上未映子の文学の根っこには、つねにこの哲学的な問いがある。
受賞作『乳と卵』も例外ではない。
- 主人公「緑子」は、この「わたしがわたしである」ことの不思議に捉えられた少女だ。
- 彼女は、自分の身体の変化に違和感と抵抗感を持っている。
- 思春期の少女は、胸が膨らみ、陰毛が生え、初潮がくる。
自分の意識とは無関係に変化していく身体は、新たな生命を生み出すための変化でもある。
「自分が存在すること」にも「自分が変化していくこと」にも「緑子」は強烈な戸惑いを抱いている。
自分も、存在も、変化も、自分で選んだものではない。
気がついたときには、なぜかそこにあって、理由もわからずに突きつけられたそれに、彼女はただただ戸惑うしかないのだ。
この出所不明、原因不明のものを「不条理」という。
そう、川上未映子の文学も「不条理」が根底にあるのだ。
さらに、この作品の特徴を語れば、その独特の文体である。
関西弁の饒舌体。
さきほど、町田康の紹介でも触れたが、この「饒舌体」は、語り手の内面や自意識を表現するのに、とても効果的な文体だといえる。
『乳と卵』の最大の魅力は、この文体と「緑子」が抱える切実な問いとが絶妙にマッチし、ものすごい作品へと仕上がったという点だと思う。
『乳と卵』には、かたくるしい哲学書にはない、文学ならではの吸引力でもって、人々を引きつける強さがある。
そのすさまじさを、ぜひ体感してもらいたい。
【 参考 考察・解説『乳と卵』(川上未映子)ー存在と不条理を哲学する「文学」ー】
『ポトスライムの舟』(津村記久子)2008年

“現代流“プロレタリア文学
大正時代に一世を風靡した文学に「プロレタリア文学」なるものがある。
庶民の過酷な労働環境や生活苦をメインに描き、
「こんなんおかしいだろ!」
と、声高らかに社会の不正を訴える文学だ。
代表的作家には、小林多喜二(『蟹工船』)や、葉山嘉樹(『セメント樽の中の手紙』)がいる。
彼らの目的は、なんといっても不正な社会を正すことと、生活苦をなくすこと。
要するに彼らの文学は“革命の手段”だったわけだ。
さて、津村記久子もまた「労働」とか「生活苦」を描く現代の作家なのだが、かつてのプロレタリア作家みたいにイデオロギッシュでは全然ない。
登場人物が社会の不正を訴えたり、会社に噛みついたり、団体交渉をしたりすることは決してない。
彼らは自分に与えられた生活の中で、それでも小さな幸せを探して、けなげに生きようとする。
津村記久子の作品には、そんな一庶民のつましい生活の断片が時に切なく、時に愛らしく、時におかしく描かれているのだ。
第140回芥川賞受賞作『ポトスライムの舟』もまた、苦しい労働生活の中で、なんとか自分の幸せを探そうとする女性の話だ。
- 主人公は「ナガセ」という29歳の女性。
- 前職をパワハラで退職。
- 現在は工場の契約社員で、2つの副業を掛け持ち。
- 職場と自宅を往復するだけの毎日にほとほと疲れている。
- そんなある日、彼女は「世界一周旅行」のポスターを見つける。
- 費用はナガセの工場での年収と同じ「163万円」
- 世界一周しようと決断したナガセは、生活をさらに切り詰めていく。
と、あらすじを書くと、やはり心は重くなる。
低賃金とか、重労働とか、パワハラとか、ブラック企業とか。
それは今の時代だって負けていない。
というか、2000年代に比べ、今の方がかえって深刻になってるんじゃないだろうか。
そういう意味でも、本書はきっと現代を生きる若者たちの共感を呼ぶだろう。
物語は決して明るくはない。
だけど、タイトルの「ポトスライム」は”幸福の木”
わずかな救いを見いだせる最後がいい。
芥川賞受賞作の中でも、文章は読みやすいし、ストーリーも分かりやすい。
ちなみに、作者の津村記久子自身もパワハラによって仕事を辞めた経験を持っている。
ここまでのリアリティと説得力のある物語を書けたのは、彼女の苦しい体験があったからこそなのだろう。
すき間時間で”芥川賞”を聴く

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・
芥川賞をもっと読みたい人はこちら
以下の記事で、さらに作品を紹介している。
「受賞作品をもっと読みたい」と思う人は、ぜひ参考にどうぞ。
【 次の記事を読みたい方はこちら 】
【 芥川賞作品の「テーマ別」記事はこちら 】
芥川賞【テーマ別】おすすめ5選
・【本当におもしろい】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➀-
・【テーマが深い】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➁-
・【ハートウォーミング・日常系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➀-
・【暗い・怖い・ドロドロ】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➁-
・【暴力・アンモラル系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➂-
・【個性的・独自の世界観】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➃-
・【玄人ウケする本格小説】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➀-
・【古典級の名著】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➁-

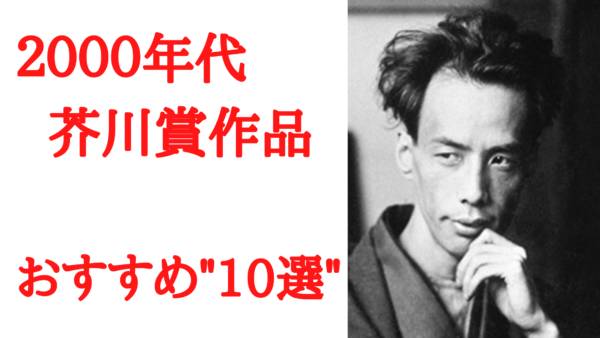




コメント