”世界クラス”の女流作家たち

芥川賞受賞作品まとめ ・1950年代「芥川賞」おすすめ9選 ―戦後文学の全盛― ・1960年代「芥川賞」おすすめ7選―女性作家の台頭― ・1970年代「芥川賞」おすすめ6選―文学に吹く新しい風― ・1980年代「芥川賞」おすすすめ3選―空前絶後の❝暗黒時代❞― ・1990年代「芥川賞」おすすめ6選 ―現代女流作家の躍進― ・2000年代「芥川賞」おすすめ10選 ―個性派ぞろいの作家たち― ・2010年代「芥川賞」おすすめ10選 ―バラエティ豊かな傑作たち― ・2020年代「芥川賞」おすすめ7選 -直近全作品を読んだ上で厳選―
年代別に、オススメ芥川賞作品を紹介している。
今回は1990年代。
1980年代は「受賞作なし」が連発した「暗黒の10年」だったが、90年代になると優れた作品が次々と登場してくる。
特に 女流作家の躍進がめざましい。
- 小川洋子
- 多和田葉子
- 川上弘美
- 柳美里
彼女たちは今や国内に限らず、国外においても注目されている作家たちだ。
また、現在数々の文学賞の選考委員もつとめ、若い才能を世に送り続けている。
現代の日本の文学シーンを牽引しているのは、彼女たちだといっても過言ではないだろう。
この記事では、そんな彼女たちを含め、90年代に登場した作家たちと、その受賞作について紹介していきたい。
もちろん男性作家の活躍も見逃せない。
厳選するのに骨が折れたが、なんとか6作品にしぼったので、「次の1冊」の参考にしていただければ幸いだ。
『妊娠カレンダー』(小川洋子)1990年

作者について
小川洋子は、ベテランというか、もはや大御所レベルの作家である。
たぶん、本をあまり読まない人でも、名前くらいは聞いたことがあると思う。
1962年に岡山県に生まれた小川洋子は、幼い頃から文学全集を読み、その先を空想するような「文学少女」だった。
早稲田大学の第一文学部に進学し、在学中は同人雑誌に作品を投稿した。
卒業後は地元岡山の大学病院の秘書室に勤務し、週末に小説を書く生活を続けた。
1998年、26歳で作家デビュー。
28歳の時に、『妊娠カレンダー』で第104回芥川賞を受賞した。
2004年『博士の愛した数式』で第一回本屋大賞を受賞、同作はミリオンセラーとなり、小川洋子の名前は一躍世間に知れ渡った。
2005年に、芥川賞受賞作『妊娠カレンダー』が英訳され、『ニューヨーカー』に掲載される。日本人で『ニューヨーカー』に掲載されるのは大江健三郎、村上春樹に次いで3人目。
小川洋子は、名実ともに世界クラスの作家だといえるだろう。
小説以外にも紀行文や対話集などを出版し、ラジオでは『メロディアスライブラリー』というレギュラー番組で世界の名著を紹介し、また現役の芥川賞選考員も務めている。
作品について
さて、受賞作『妊娠カレンダー』だが、タイトルからこんな想像をするかもしれない、
妊娠にまつわるロマンや感動
生命の尊さや誕生の奇跡
こういう、作品も世の中になくはない。
むしろ、こっちのほうが多いと思う。
けれど、小川洋子の作品は、そんなシンプルな話ではない。
なぜなら「妊娠はめでたいこと」という社会通念に対して、主人公たちはどこまでも懐疑的だからだ。
彼女たちと新しい生命との間には距離がある。
どこか、冷めた目で、妊娠と新たな生命を眺めているのだ。
それは、命に対するリアリティの欠如が根っこにあるからなのだろう。
恵まれた暮らし、物質的な豊かさを得た日本人は、その一方で、大切なものも失いつつあるのかもしれない。
それは、身体性とか、生きる実感とか、リアリティとかいったものだ。
1990年代というのは、ほんとうに動乱の時代で、とくに1995年と聞けば、だれもがピンとくるだろう。
自らを「透明な存在」とした少年や、高学歴エリートたちが陥った集団狂気。
きっと、この時代に起きた様々な事件ってのは、物質的な豊かさと引き換えに生まれた、社会のひずみや、人々の心の貧しさが根本にあるのだと思う。
そういう時代の中で、必然的に生まれてくる文学というものがある。
小川洋子の『妊娠カレンダー』には、「失われた生の実感」といえるものが、主題にある。
実際に、続く2000年代にかけて、芥川賞受賞作で身体性を扱った金原ひとみ『蛇にピアス』、川上未映子『乳と卵』という流れがやってくる。
小川洋子は、時代の洞察力や、社会や人間に対する感覚が、作家としてとても鋭敏に働くのだろう。
「妊娠もの」の作品は世の中に結構あるが、『妊娠カレンダー』はやはり、ぼくたちに訴えるものが多い1冊だと思う。
『犬婿入り』(多和田葉子)1992年

作者について
小学生のころから小説家を志し、高校生のころに文芸部で創作にはげむ。
大学は早稲田大学の文学部へ進学し、卒業後はドイツに移住し、その後に永住権を獲得した。多和田葉子といえば、その優れた言語能力である。
25歳のとき、ドイツで知り合った編集者に、ドイツ語で書いた詩を見せると、すぐに出版を提案され、1987年にドイツ語と日本語の2カ国語で詩集を刊行した。
その後、日本語で書いた小説がドイツ語に翻訳され出版される。
日本の文壇デビューは1991年、『かかとを失くして』で群像新人文学賞を受賞してのことだった。
そして翌年に『犬婿入り』で芥川賞を受賞。
その後の著作も20冊以上がドイツ語で出版されていて、それ以外に、フランス語、英語、イタリア語、スペイン語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ノルウェー語、デンマーク語、オランダ語などの翻訳も出ている。
いかに彼女の活躍が世界レベルかがお分かりになるだろう。
ちなみに、語学についても造詣が深い多和田葉子。
評論やエッセイなんかも数多く執筆している。
近年、ノーベル文学賞の候補として名前があがりだしてもいるので、こちらの動向にも注目があつまっている。
作品について
あらすじはこんな感じだ。
- 主人公北村みつこは家庭教師の先生。
- 教え子たちに繰り返し話すのは「尻をなめる犬の話」
- そんなある日、彼女の前に突如現れた男。
- 彼は「尻を舐める癖」を持ってた。
- 毎日のようにみつこの尻をなめる男。
- 現実とも思えない、2人の交流がおもしろく描かれていく……
日本の民話に「異類婚姻譚」というジャンルがある。
「人間ではない存在」と結婚する話のことだが、『犬婿入り』はその現代版だと言って良いだろう。
後で紹介するが、川上弘美の『蛇を踏む』と、作品の雰囲気はとても似ている。
『犬婿入り』の受賞が1992年
『蛇を踏む』の受賞が1996年
近年だと、2015年に本谷有希子の『異類婚姻譚』が受賞していて、「日常と異世界との交わり」を描いた作品が目につく。
こういう作品を「寓話」として解釈することもできるのだろうが、本書はそのまま「変態(?)しりなめ男」の話として読んだほうがおもしろい。
文章も独特な「饒舌体」でクセになる文章だ。
ちなみに物語は、男の妻が登場することで事態が段々と変わっていく。
そして最後は突拍子もない結末へ。
『蛇を踏む』(川上弘美)1996年

作者について
1958年、東京で生まれる。
小学生のころ病気で入院し、そこで本を読みはじめたことから次第に文学にのめり込んでいった。
お茶の水女子大学時代ではSF研究会に所属し、SF雑誌の編集アルバイトなんかもしていた。
卒業後は生物の教員を経て、専業主婦になり、小説の執筆を始めた。
1994年、36歳のときに『神様』でパスカル短編文学新人賞を取り作家デビュー。
2年後に『蛇を踏む』で第115回芥川賞を受賞した。
選考会では文章力はもちろん、その感性や想像力が高く評価された。
また、作品について、古典的な「変身譚」との関連が語られもした。
実際、川上弘美の作品には「異世界」の存在が書かれることがおおい。
鬼、妖怪、幽霊……
彼らの存在は、日本でも様々な文献で古くから言い伝えられている。
平安・鎌倉時代の『今昔物語』『宇治拾遺物語』に。
江戸時代の人気作家、上田秋成の『雨月物語』に。
明治時代のロマン主義作家、泉鏡花の『高野聖』に。
これらは『幻想文学』とよばれ、今も昔も、多くの人々を魅了し続ける文学ジャンルだ。
そして、川上弘美の作品にも、妖怪や、幽霊や、人魚など、『異界の住人』が、まったく、なんの違和感もなく溶け込んでくる。
彼女はまさに、現代の『幻想文学』の第一人者といっても良いだろう。
作品について
受賞作、『蛇を踏む』も川上的な幻想文学だといっていい。
蛇を踏んでしまった
という、さりげない書き出しから、読者はあっという間に異世界に足を踏み入れる。
- 主人公(私)は公園で蛇を踏んでしまう。
- 踏まれた蛇は「踏まれたので仕方ありません」と言い、女性の姿に変身する。
- そのまま〈私〉の部屋へやって来て、そのまま天井に住み着いてしまう。
- それからというもの、〈私〉が家に帰ると蛇がいて、彼女は家事を済ませて待っていた。
- 〈私〉は蛇に、恐怖と嫌悪感を抱いていく・・・・・・
こんなお話が、川上弘美の独特で透明感のある文章で綴られていく。
まがまがしい妖怪を扱いつつ、美しい世界を描き出すのは、まさに上田秋成や泉鏡花をほうふつとさせる。
ちなみに、こういう『幻想文学』は比喩とか、寓話とか、人間の解釈でもってムリヤリ合理化されてしまう運命にあるのだが、そういう読み方をぼくはあまり好まない。
むしろ、本当にそういう異世界があって、そういう異世界にコンタクトできる人がいるって思った方が、ゾクゾクするし、とってもスリリングじゃないだろうか。
いや、実際 泉鏡花なんかを読んでいると、彼らは本当に「異界の住人」が見えていたのだと思えてならない。
文学を読んでいると、冗談じゃなく、この世界がどんどん相対化されていく。
それこそ、ぼくは文学の1つの可能性だと思っているし、川上弘美の作品は、まさにそういう力を宿している。
スポンサーリンク
『家族シネマ』(柳美里)1996年

作者について
在日韓国人の劇作家であり、小説家。
今回紹介する作家の中で、間違いなく一番波乱に満ちた人生を歩んでいるのが、柳美里だ。
幼い頃から、彼女は孤独な日々を送っていた。
- 韓国からの来日。
- 祖父母の失踪。
- 母の深夜のホステス勤め。
- 母の不倫と家出。
- 父からの虐待。
- 学校でのいじめと退学。
そんな辛い経験をしてきた柳美里……
彼女が唯一落ち着ける場所は墓地で、死者と静かに対話することが彼女の慰めになっていたという。
高校中退後は、16歳でミュージカル劇団「東京キッドブラザース」に入団。
女優としての道を歩むが、当時同棲相手だった男性から、
「あなたは演じるより書きなさい」
といわれたことをきっかけに、女優から劇作家へ転身。
26歳のときに処女小説『石に泳ぐ魚』を発表し小説家デビュー……したのだが、ここでも一事件が起きてしまう。
顔に腫瘍を持つ実在の韓国人女性をモデルにしたことで、プライバシーを侵害されたとして訴訟問題に発展してしまうのだ。
結局、作品は出版さしどめ処分になる。
が、そんな逆境をものともせず、28歳のときに『フルハウス』で芥川賞候補に上がり、その翌年『家族シネマ』で第116回芥川賞を受賞した。
ちなみに『フルハウス』も『家族シネマ』も、どちらも「崩壊した家族」の姿が描かれている。
柳美里の作品の多くは「家族とは何か」を問うていたり、「帰ることができる場所」を模索していたり、「存在することに不安を抱く者」が登場人物だったりと、彼女の幼少体験が強く表れた作品が多い。
暗くて鬱々とした作品が多いが、その文体は詩的で美しく叙情にあふれていて、読後に深い余韻を残す。
個人的には90年代の中では最もオススメしたい作家だ。
2020年、『JR上野駅公園口』の英訳版『Tokyo Ueno Station』が、TIME誌の「必読書100選」に選ばれ、米国の文学賞である「全米図書賞」(翻訳文学部門)を受賞した。
いま世界から注目を集める柳美里。
過去の作品は絶版になったものも多いが、改めて読み直されるべき作家だと思う。
作品について
文学には「不条理」をテーマにしたものが多い。
実際に、歴代の芥川賞をみてみても「不条理への戸惑い」をテーマにした作品が少なからずある。
それは『家族シネマ』も同様だ。
タイトル通り「家族」を扱った作品なのだが、やはり、この「家族」というのも、人によっては「不条理」の種になってしまうもの。
人は生まれてくる場所を選べない。
- 平和な家庭。
- やさしい両親
- 仲の良い兄弟。
そんな家族のもとに生まれた人は、きっと家族の絆を問うことはない。
家族の絆は、改めて確認するまでもなく、きっと強固なものだからだ。
ところが、
- 争いが絶えない家庭。
- 乱暴な両親。
- わかり合えない兄弟。
そんな家族のもとに生まれた人は、きっとこう思う。
「家族って何?」
「家族の絆って何?」
そして、ここに文学や思想が生まれる。
タイトルの『家族シネマ』・・・・・・この名前に、ドキッとする。
「シネマ」とは「映画」、つまり「フィクション」だ。
「家族なんてフィクションだよ」
そんな作者のシニカルなメッセージが、きっとこのタイトルには込められている。
この話は、
離散して壊れ果てた家族が20年ぶりに結集して「幸せな家族」を演じ映画を撮る、
というもの。
彼らは、カメラが回らないかぎり、必要以上にやりとりもしない。
カメラが回れば、仲良く会話を始めたり、罵倒を始めたりする。
一体何が演技で何が本心なのか分からない。
そんな奇妙な光景が繰り返されていく。
けれど、「じゃあ、ぼくたちの家族って奇妙じゃないの?」
と、その視点を自分自身に向けると、どうだろう。
すくなくとも、家族には「1つの演技」といえる側面がある。
世の中には、「家族の絆は永遠」とか「血のつながりは絶対」みたいな、「家族第一主義」という風潮がある。
- 「家族を一番に優先するべき」
- 「家族なんだから仲良くてあたりまえ」
- 「家族なんだから愛せてあたりまえ」
そういう論理かもしれない。
ただ、世の中には、そうしようにもできない家族というものがある。
頑張って、頑張って、家族を愛そうとしても、それができない人たちがいる。
そう、結局、家族なんて絆を保証されたものなんかではないのだ。
なにも、ぼくはニヒルな態度で、家族を否定しているわけではない。
もちろん、論理的に否定することはたやすい。
だけど、感情がそれをゆるさない。
やっぱり、どんなに論理で「家族ってフィクションでしょ?」と、考え詰めていったとしても、自分の感情が「だけど、お前は家族が大事なんだろ?」と、つよく抵抗をするのだ。
柳美里の作品にも、家族を問うて、「家族なんて虚構だ」といいつつも、やっぱり「家族を捨てられない」そんな主人公たちが登場する。
きっと、作者も、本当は家族というものの大切さを細胞レベルで感じているのだと思う。
スポンサーリンク
『ブエノスアイレス午前零時』(藤沢周)1998年

作者について
新潟県新潟市出身。
法政大学文学部卒業、書評誌『図書新聞』編集者などを経て1993年『ゾーンを左に曲がれ』でデビューした。
1998年に『ブエノスアイレス午前零時』で第 119 回芥川賞受賞。
日本文学協会に所属する研究者で、2004年より母校・法政大学経済学部の教授に就任している。
ちなみに、ぼくは2度ほど藤沢周の講演会を聞いたことがある。
「文学とは何か?」
それを強く説いた藤沢周。
ぼくは彼の文学観にとても共感した。
不遜にも、彼の文学観を要約してみれば、
「文学とは、言語以前の世界に触れることだ」
ということだろう。
じつは、ぼくたちの世界認識は、「ことば」に大きく依存している。
言い換えれば、ぼくたちは「ことば」というフィルターを通した世界しか知らない。
この世界の「実相」について、ぼくたちはほとんど無知だと言っていい。
この世界の「実相」に触れるためには、「ことば」のしがらみを越えなければならないのだ。
じつは、それを実現するためには色んなアプローチがある。
それは、哲学だったり、芸術だったり、宗教だったり、そして、「文学」だったりする。
「この世界はミルフィーユだ」
そういった作家がいた。
世界は何重もの層で覆われているのだという。
その層を一枚一枚 はがしていけば、きっと世界の深奥をのぞき見ることができるのかもしれない。
文学によって「世界の奥の奥をのぞこう」とする作家。
文学によって「言語以前の世界に到達しよう」とする作家。
それが藤沢周なのである。
作品について
藤沢周という作家は「言語の向こうの世界」「言語以前の世界」に対する憧れを強く抱いている作家だと紹介した。
本書『ブエノスアイレス午前零時』は、「言語以前の世界」へ到達しようという、まさにその実践例だと思う。
が、この作品、一筋縄では読み解けない、奥行きの超ふかい作品だ。
- 舞台はアルゼンチンの首都? かと思いきや、雪深い新潟の山間部。
- 主人公は東京からUターンしてきた男
- 自分や生活に対して、物足りなさ、やりきれなさ、鬱屈を抱えている。
- そんな主人公が、ダンスホールで痴呆の老婆とダンスをする。
と、あらすじを説明してみても、この作品の説明をしたことにはならない。
なぜなら、この作品は、「言葉」ではとうてい表現できないものを「言葉」によって表現しようとしているからだ。
藤沢周がつむぎだす言葉の一つ一つ、文の一つ一つ、そして文章の全体、それをじっくりと味わう必要がある。
そういう姿勢を、この作品は、読者に強く求めている。
よって、この作品をオススメしたい人は、次のような人。
- 「分かりやすい作品には、飽き飽きしているんですよ」って人。
- 「言葉による芸術を味わいたいんですよ」って人。
- 「自分の解釈を大切にしたいんですよ」って人。
- 「逃れがたきコトバの呪縛から解放されたいんですよ」って人(←)
こういった人たちは、ぜひ読んで見て欲しい。
ぼくも、この作品をどう評価して良いのか分からずにいるクチだが、読後はなんともいえない、不思議な余韻が残った。
「言葉以前の世界」の片鱗に、指先がちょっとだけ触れたのだと、言えないでもなくもない。
スポンサーリンク
・
『日蝕』(平野啓一郎)1998年

作者について
愛知県に生まれる。
小学生のころは本を読むより、運動をする方が好きだったという。
そんな彼は中学生で三島由紀夫の『金閣寺』と出会い衝撃を受けた。
高校時代は主にトーマス・マンなどの海外文学を読み、「自分も書いてみよう」と創作を始めたのもこの頃だった。
卒業後は京都大学法学部に進学。
「小説家になるなら」と、在学時に漱石も鴎外も芥川も読破し、23歳で作家デビューを果たす。
が、そのデビューは文学界における1つの「事件」だった。
平野啓一郎のデビューが いかにセンセーショナルだったかを教える、一つのキャッチコピーがある。
「三島由紀夫の再来と言うべき神童」
これは、本書『日蝕』の出版時、新潮社によって発信されたものだ。
デビューのいきさつは、こうだ。
当時の平野が新潮社に手紙と作品を送る。
それを読んだ編集長が感動。
すぐに掲載を決め、無名の新人の作品が全文掲載されることになる。
それが『日蝕』だった。
要するに、彼のデビュー作は新人賞を経由せずに「飛び級」よろしく文芸誌に掲載されたのである。
しかも、その作品がそのまま芥川賞を受賞。
選考委員も「近代小説の正統」との評価を与え、その完成度について ほぼすべての選考委員が認めるほど。
芥川賞史上かつてない「事件」に世間の注目も平野啓一郎に集まるワケだが、受賞会見に登場した平野は茶髪にピアスという、まぁ、いわゆる「チャラチャラ」した学生だった。
すると、その風貌と「難解で硬派な作品」とのギャップもまた話題になった。
ちなみに受賞時の平野は23歳。
これは大江健三郎と並ぶ当時の最年少記録であり、大学生の受賞については史上4人目。
以上が、平野が「神童」と言われた所以である。
また、平野啓一郎は、さまざまなジャンルの作品を手がける、変幻自在さも魅力だ。
代表作『マチネの終わりに』は、天才ギタリストの男とジャーナリストの女の悲しい恋愛を描いた傑作だが、『日蝕』と同じ作者とは思えないほど、作風は全然違う。
また、個人ではない「分人」という生き方を唱えた『私とは何か』という評論文もベストセラーになるなど、小説にとどまらない執筆活動を展開している。
作品について
さて、ここでは作品の特徴をとりあげ、「三島由紀夫の再来」と言われた理由についてもう少し詳しく見ていきたい。
「三島の再来」と言われた理由は、大きく次の3つ。
- 凡人離れしたボキャブラリー
- 凡人離れした文体
- 凡人離れした衒学さ
パラパラっと本書を眺めてみると、きっと誰もがこう思う。
ルビ、多ッ!
そう、全体的にルビが多いのだ。
その理由は、重厚な漢語がふんだんに使用されているからだ。
さらに、彼の文体は、天才と呼ばれた日本の文豪たちをほうふつとさせる。
森鴎外や、夏目漱石や、三島由紀夫だ。
- 擬古文体(古文っぽいリズム)は鴎外を。
- 重厚な漢語の多用は漱石を。
- 歴史や神話や哲学への造詣は三島を。
ということで、一言でいって、めちゃくちゃ難しい。
「ここまで難しくする必要あるの?」って感じなのだが、こういう感じのことを「衒学的」とか「ペダンチック」とか言ったりする。
実際、三島由紀夫の作品は、かなりペダンチックだし、そういうのが少なからず、三島の評価を高めていると考えれば、平野啓一郎が「三島由紀夫の再来」と言われて、評価されたというのもうなずける。(とはいえ、「三島の再来だなんて言い過ぎだろ!」と批難する人たちもいた)
ちなみに選考会では
「この作品、最後まで読んだ人ってどれだけいたの?」
という皮肉めいたコメントもあったという。
で、本書のテーマなのだが、一言では片付けられない広がりと深みがある。
中世15世紀のフランスを舞台に、宗教、哲学、芸術、愛、幻想、とにかくあらゆるテーマが縦横無尽に交差していく。
あらすじを紹介することは難しいので、気になる方はぜひ実際に手に取って読んでほしい。
ぼくは、作品のテーマの一つ一つを消化したわけでは、もちろん、ない。
ただ、作者の文章の美しさや、そのほとばしる熱量には、心を動かされた。
なるほだ、確かに衒学的ではある。
だけど、読む人の心を揺さぶる力が、この作品にはある。
余談だが、ぼくはAmazonで『日蝕』の古本を購入したのだが、なんとご本人のサイン入りが届き 軽くテンションが上がったという、どうでもいいエピソードでもって1990年代の紹介を締めくくりたい。
すき間時間で”芥川賞”を聴く

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・
芥川賞をもっと読みたい人はこちら
以下の記事で、さらに作品を紹介している。
「受賞作品をもっと読みたい」と思う人は、ぜひ参考にどうぞ。
【 次の記事を読みたい方はこちら 】
【 芥川賞作品の「テーマ別」記事はこちら 】
芥川賞【テーマ別】おすすめ5選
・【本当におもしろい】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➀-
・【テーマが深い】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➁-
・【ハートウォーミング・日常系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➀-
・【暗い・怖い・ドロドロ】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➁-
・【暴力・アンモラル系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➂-
・【個性的・独自の世界観】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➃-
・【玄人ウケする本格小説】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➀-
・【古典級の名著】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➁-

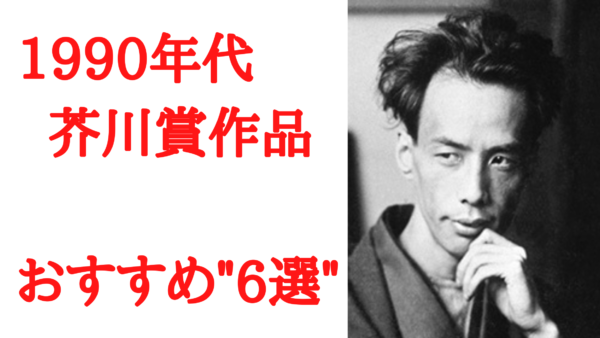




コメント