はじめに

近代文学の作家(文豪)のまとめ記事はこちらから。 【芥川龍之介】……「芥川龍之介」人物・人生・代表作のまとめーぼんやりした不安とはー 【泉鏡花】……「泉鏡花」の人生と人物ーロマン主義・観念小説・幻想文学の名手ー 【尾崎紅葉】……「尾崎紅葉」の人生・人物のまとめ―擬古典主義・硯友社とは何か― 【小林多喜二】……「小林多喜二とプロレタリア文学」―『蟹工船』の内容・代表作家— 【梶井基次郎】……「梶井基次郎」の人生・人物のまとめ―早世した天才のやさぐれエピソード― 【志賀直哉】……「志賀直哉」人物・人生の解説―反自然主義・白樺派とはー 【島崎藤村】……「島崎藤村」人物・人生・代表作の解説 ―自然主義とは何かー 【太宰治】……「太宰治」のまとめ ―人物と「恥の多い生涯」と代表作の解説― 【谷崎潤一郎】……「谷崎潤一郎の人物・人生・文学的特徴」―耽美派の代表作家― 【坪内逍遥】……「坪内逍遥」の写実主義をわかりやすく解説―そもそも日本文学とは何か― 【夏目漱石】……「夏目漱石」のまとめー人物と人生の解説・代表作の紹介ー 【二葉亭四迷】……「二葉亭四迷」の言文一致運動をわかりやすく解説―写実主義を完成させた男― 【森鴎外】……「森鷗外」のまとめ―人物と人生の解説・代表作の紹介― 【横光利一】……「横光利一と新感覚派」を分かりやすく—『蠅』『機械』など代表作も紹介—
志賀直哉といえば、知る人ぞ知る文豪で、文学好きの間でもコアなファンが多く、どちらかといえば「玄人受け」する作家である。
それもそのはずで、実は志賀の生前から、彼の作品や作風を評価するのは、これまた偉大な作家ばかりだったのだ。
ちなみにこんな凄い人たちが、こんな賛辞を与えている。
- 谷崎潤一郎「文章に芸術的な手腕がある」
- 三島由紀夫「自然描写は世界に卓越している」
- 芥川龍之介「あんな文章、私にはかけない」
- 大岡昇平「『暗夜行路』は近代文学の最高峰だ」
- 小林秀雄「『暗夜行路』は確かな知恵で描かれている」
このように志賀直哉を評価する「玄人」たちは多く、文壇のカリスマ的存在ともいえる彼はいつしかこう呼ばれるようになった。
小説の神様
この記事では、そんな志賀直哉の人物像・人生・作品について紹介をしていくが、主に次の点に焦点をあてる。
- 志賀の文学傾向……反自然主義・白樺派とは
- 志賀の作風……無駄のない文体と「心境小説」
- 志賀の生い立ち……祖父の溺愛と、運命の出会い
- 志賀の苦悩……父との不和の原因とは
- 心境の変化……急死に一生の事故
- 「小説の神様」エピソード……太宰治との論争
- 代表作……お手本みたいな小説の数々
それでは1つ1つ見ていくが、その前に志賀直哉の年表を確認しておこう。
志賀直哉の年表
1883年(0歳) …宮城県に生まれる 1885年(2歳) …一家で上京、祖父母の家に住む 1889年(6歳) …学習院初等科に入学 1895年(12歳) …学習院中等科に入学 1900年(17歳) …内村鑑三に出会い、以降7年に渡り師事 1901年(18歳) …足尾銅山問題で父と衝突 1902年(19歳) …武者小路実篤と出会う 1906年(23歳) …東京帝国大学英文学科入学(無試験) 1907年(24歳) …女中との結婚問題で父と衝突 1908年(25歳) …国文科に移る 1910年(27歳) …雑誌「白樺」創刊 …『網走まで』 …東京帝国大学を中退 1912年(29歳) …父との不和悪化により尾道に転居 1913年(30歳) …山手線にはねられ、養生のため城崎へ 1914年(31歳) …武者小路の従妹「サダ」と結婚 1917年(34歳) …父との不和が解ける …『城の崎にて』 …『和解』 1920年(37歳) …『小僧の神様』 1921年(38歳) …『暗夜行路』連載開始 1923年(40歳) …「白樺」廃刊1937年 (54歳) …『暗夜行路』完結(16年越し) 1947年(64歳) …「太宰が嫌い」発言 ※その後 太宰が反発 1949年(66歳) …文化勲章受賞 1971年(88歳) …肺炎と老衰のため死去
スポンサーリンク
志賀の文学傾向
反自然主義とは

文学史を語る際に、よく「〇〇主義」とか「〇〇派」といった言い方をする。
これは基本的に、その作家の「文学に対する考え方」を表している。
では、志賀直哉の主義は何かというと、彼は「反自然主義」の作家である。
ただ、反自然主義と一言でいっても、一般的にそれは更に次の4つに分類される。
- 白樺派
- 耽美派
- 理知派
- 余裕派
志賀はこの中の「白樺派」に位置している。
そもそも「反自然主義」とは、どんな立場なのだろう。
シンプルに言えば、
自然主義に対するアンチ的立場
ということになるのだけど、これじゃ何の説明にもなっていない。
そこでもう少し説明しようと思うのだが、そのためにはまず「自然主義」について紹介しなければならない。
自然主義とはおよそ次のことを理念としている。
- 作家の主観を極力排除する
- 作家の生活をありのままに暴露する
- 主人公や語り手を「私」として描く
- 私小説・告白小説の体裁をとる
志賀が作家として歩み出したころ、文壇を支配していたのがこの「自然主義」だった。
島崎藤村や田山花袋なんかがその重鎮である。
彼らの作品で描かれるのは、作家自身の日常や生活や経験ばかり。
しかも、自分たちが「いかに醜いか」を自虐的に描くことが多かった。
たとえば、島崎藤村は「姪を妊娠させて、パリへ逃亡した」顛末を作品にしたし、田山花袋は「未成年の教え子が好きすぎて、彼女の布団の匂いを嗅いだ」詳細を作品にした。
とにかく、自然主義の連中というのは「自己否定」とか「自己憐憫」の性格が強かったのだ。
若き志賀は、その作風や文学的理念に批判的だった。
「人間ってもっと尊く美しい存在でしょ? 自然主義の連中は自虐的すぎだよ」
ということで、志賀は「人間肯定」と「人間賛美」の理念を掲げ、同じ志をもつ友人達と文学運動を起こしていく。
そんな志賀と友人をひっくるめて「白樺派」と呼ぶ。
白樺派とは

そもそも「白樺」とは、志賀直哉とその友人が1910年に創刊した文芸誌の名前で、そこに参加したのは学習院出身の若者たちだった。
当時の学習院といえば公卿や華族など高級官僚の子どもが通う学校。
白樺に参加したのも、志賀を始め皆が特権階級の若者ばかりだった。
そんな「白樺派」の特徴は上げれば、大きく次の3つになる。
- メンバーの多くが学習院出の特権階級である
- 人間肯定・人間賛美といった「人道主義」を理念としている
- 育ちの良さ故に、西洋に関する教養に富んでいる
「メンバーが学習院出身」について
志賀本人、武者小路実篤、有島武郎、里美弴、柳宗悦など、白樺派の主要なメンバーはみな学習院の出身だ。
学習院というのは、特権階級の若者達が通う学校だった。
だから、身も蓋もないことを言うが、白樺派の主要なメンバーはお金持ちである。
一方で、当時主流だった自然主義の作家の中には、貧しくて生活に苦しむ者さえ少なからずいた。
だから自然主義作家の文学では、
- 人生や生活の苦しさ
- そこで生きる自分の姿
- 隠しきれない内面の醜さ
こういった「苦悩」がどうしても主題として全面に出てきてしまう。
ところが、白樺派の作品にはそういった「苦悩」が描かれていない。
いや、「描くことができない」といった方が正しい。
経済的に恵まれ、豊かな文化資本に囲まれ育った彼らには庶民の「生活苦」を知らないからだ。
「人道主義」について
「白樺派」のメンバーの多くは、人生や人間に対しても肯定的な価値観を持っている。
そんな彼らの価値観にピッタリの作家が、ロシアにいた。
それがあの世界的文豪「トルストイ」である。
代表作は『戦争と平和』
トルストイはそれら作品の中で「人間の幸福とは何か」を問い、「人間愛の尊さ」とか「生きることの喜び」なんかを強く訴えた作家だ。
そんな彼の立場は「人道主義(ヒューマニズム)」と呼ばれている。
要するに「人間万歳」という考え方で、白樺派という文学集団は、トルストイのその「人道主義」にインスパイアされた連中だった。
特に、その思想傾向はリーダー格の武者小路実篤によく見られる。
たとえば武者小路には『友情』という作品があるのだが、これは男女の三角関係という、まぁ文学によくあるテーマを扱った中編小説である。
たとえば自然主義作家の手にかかれば、「痴情のもつれ」とか「恨みつら」とか「妬みひがみ」とか、とにかく「人間の暗部」が描かれることになるわけだが、武者小路の手にかかれば、男女の三角関係だって「めでたしめでたし、大団円のうちに幕」ということになる。
武者小路の人間観は「人道主義(人間万歳)」
だから、彼の作品には「人間の暗部」など、基本的に描かれない。
こんな感じの作風なので、武者小路の作品は自然主義から手ひどく批判された。
彼の代表作「お目出たき人」をもじって、苦悩を知らない「おめでたい文学」などと皮肉られもした。
「西洋の教養」について
白樺派のメンバーには、西洋に関する深い教養がある。
正直、ここが白樺派の一番の強みだといえるだろう。
というのも、この頃の作家の多くは「西洋のホンモノ」に触れることはできなかった。
日本の近代文学にとって、西洋文学は切っても切り離せない。
ゾラ、モーパッサン、フローベール……
文学を志すものであれば、そういった西洋文学に触れることは必要不可欠の時代だった。
そんな中で、貴族出身で「お金持ち」の白樺派は、幼い頃からそういった「ホンモノ」に触れる機会があり、だからこそ、トルストイの思想にも触れ、それを理念に掲げた文学活動を起こすことができたわけだ。
当時の文学シーンにおいて「本当の西洋文学」を理解していたのは、他でもない白樺派だけだったといえる。
白樺派っぽくない2人
と、ここまで白樺派の説明をしてきたが、実は志賀直哉の作品を読んでみると、そこまで「人道主義」っぽさを感じることはない。
実は上記で説明した思想傾向は、主に武者小路実篤のものだ。
だから、自然主義作家らは武者小路実篤を批判こそするが、志賀直哉や有島武郎なんかは高く評価していたりする。
2人は武者小路実篤と本質的に異なる作家なのである。
たとえば志賀直哉は、「自身の性欲」とか「父親との不和」とか自らの暗部をそれなりにだが作品化しているし、有島武郎に至っては「煩悶青年」よろしく強烈に苦悩した挙げ句に自殺をしている。
つまり、彼らは「白樺派」でありながら、自然主義的な傾向を持つ作家だったのだ。
だから、白樺派の人道主義というのは、主に武者小路の思想傾向であり、個人個人を見てみればそこまで「人間万歳」じゃなかったりする。
ちなみに彼らの温度差を整理すると、こんな風になるだろう。
- 武者小路実篤……白樺右翼(自己肯定が強い)
- 有島武郎……白樺左翼(自己肯定に批判的)
- 志賀直哉……2人の中間(ほどほどの自己肯定)
スポンサーリンク
志賀の作風
簡潔で無駄のない文体

志賀直哉は白樺派でありながら「自然主義」的な作家だった。
そういえる最大の理由として、彼の写実(リアリズム)的手法が挙げられるだろう。
写実的手法とは、フィクション要素を徹底的に排除し、作者の経験したことをありのまま書いていく手法で、主に自然主義作家が好んで採用したものだった。
志賀直哉の文体も、その写実的手法が採用されている。
しかも、その文体には全くといい程に無駄がなく、まさに「お手本」のような筆致だった。
たとえば、芥川龍之介と夏目漱石との会話に、こんなものがある。

志賀さんみたいな文章、ぼくにはとても書けないんですけど。どうやったらあんな風に書けるんですか?

あれはね、彼が“思ったまま”を書いているんだよ。私だってあんな風には書けないよ
言うまでもないが、ここでいう「思ったまま」というのは「好き勝手」という意味ではない。
見たまま、聞いたまま、感じたまま、それを「忠実に無駄なく」書いているという意味だ。
後年の芥川は、自身の作品からフィクション性をそぎ落とし、限りなくリアリズム的な小説を書いていくことになるのだが、その他にも志賀みたいな無駄のない文体を目指す作家が沢山いた。
こんな風に、同時代を生きる作家たちからも志賀の文体は一目置かれていたわけだ。
ここが、文壇や世間から「小説の神様」と呼ばれ崇拝された最大の根拠である。
「心境小説」とは
志賀直哉の「中期」~「後期」の小説には、彼が「感じたこと」を冷静に観察し、それを研ぎ澄まされた筆致で描いた作品が現れてくる。
これらの作品は、志賀直哉の「心の姿」が素直にありのまま書かれていることから「心境小説」と呼ばれている。
有名な『城の崎にて』は、そんな「心境小説」の代表作で、それこそ、全くの無駄がなく、事件も発展もなく、自分自身の心境が静かに淡々と描かれている。
たとえて言えば、濁りや雑味が一切なく、それでいて限りなく純度の高い「日本酒純米特別大吟醸」といったところだろうか。
(酒好きなものでスミマセン……)
『暗夜行路』に並んで、志賀直哉の代名詞とも言える作品で、一読して彼の文体の妙を感じることができるはず。
スポンサードリンク
生い立ち~作家デビューまで
祖父からの溺愛

後に志賀は「自分に最も大きな影響を与えた3人」として、次の人物を上げている。
- 祖父の志賀直治
- 師匠の内村鑑三
- 友人の武者小路実篤
この3人との関係を織り交ぜながら、志賀が小説家として歩みだすところまで説明しよう。
志賀は宮城県石巻市の有名な実業家の一族に生まれた。
彼が2歳のころに一家は上京、東京の祖父宅で暮らすことになった。
二歳上の兄が幼い頃に死に、事実上の跡取りとなった志賀を祖父はとても溺愛し、志賀もまた祖父を慕っていた。
幼い志賀を育てたのは両親ではなく祖父母だった。
後述する「志賀と父との不和」の根っこには、父子のコミュニケーション不足があるのだ。
6歳になると学習院初等科へ入学。
学習院時代の志賀は勉強が苦手で、かわりに小説を熱心に読んでいたという。
12歳で学習院中等科に進学すると、いよいよ勉学をおろそかにするようになる。
授業には出ず、親の金でさんざん放蕩を繰り返す志賀に対して、父は
「なぜお前のような男が生まれたんだ」
と罵ったという。
この頃から父子の関係は良好とは言えなかった。
内村鑑三との出会い
志賀は17歳のころに運命の出会いをする。
志賀に影響を与えた2人目の人物、すなわち内村鑑三だ。
内村は明治を代表するキリスト教思想家であり、文学者でもある。
内村に魅せられた志賀は、以降7年間に渡って彼の自宅に通うようになった。
ただ、志賀が惹かれたのは「キリスト教」の教義というよりは、内村の人間そのものだったようだ。
なぜなら、キリスト教には「姦淫してはいけない」という戒律があって、志賀は自分の性欲を否定することができなかったからだ。
ということで、洗礼を受けることはなかった志賀だったが、内村からは、「正義を尊ぶ」とか「不正を憎む」とかいった潔癖な倫理観を受け継ぐこととなった。
これが後の「白樺派」の人道主義に共鳴する種となる。
武者小路実篤との出会い
さて、勉強をおろそかにした志賀は2度の留年を経験するが、それによって2歳年下の生涯の友を得る。
それが武者小路実篤だった。
2人は自分たちの関係に「友だち耽溺」という、ちょっとアレなネーミングをつけ、文学を熱く語っていく。
そして、志賀が23歳の年に2人は東京帝国大学へ進学。
4年後、27歳の年、ついに「白樺」を創刊。
そこに志賀は初期の傑作と言われる『網走まで』を発表すると、いよいよ作家として身を立てようと大学を中退するのだった。
ただ その決断は、父との不和をより深刻なものにしてしまうのだが、それについては次の見出しで詳しく述べる。
スポンサーリンク
父との不和

なぜ志賀と父との間に不和が生じたかと言えば、大きく次の要因や事件がある。
- 志賀が祖父に育てられたこと
- 足尾銅山鉱毒事件
- 女中との結婚騒動
- 国文学科への転科
- 大学を中退し作家になったこと
では以下、1つ1つ説明をしていく。
要因①「祖父からの溺愛」
そもそも祖父から溺愛されて育った志賀には、父との信頼関係が築かれなかった。
父子の不和の根本は間違いなくそこにあるのだが、そこにはある宿命があった。
実は父もまた志賀と同じ経験をしていて、幼い頃に自身の祖父に育てられたのだった。
つまり父は、自分の子との関わり方を知らない。
その事について、志賀は『祖父』という作品で次のように書いている。
父の場合と同じやうに私は父に親しまず(中略)二代同じ事を繰り返したわけである。
この父との関係は、多くの事件をきっかけにどんどん悪化していくことになる。
要因②「足尾銅山事件」
そんな中、父子の関係を決定的に損なう事件が起きる。
足尾銅山鉱毒事件だ。
内村鑑三は、自身の講演会でその不正を糾弾したのだが、それを聞いた志賀もまた、社会の不正を憎み「公共心」と「正義感」のもと、友人らとともに反対運動を起こそうとした。
だが、父はそれに激怒。
実はこの足尾銅山の開発には志賀の祖父も加わっていて、実業家である父もその利害関係のただ中にあったのだ。
不正を憎む志賀と、不正に荷担する父。
こうして父子の関係に大きな軋轢が生まれることとなった。
要因③「女中との結婚騒動」
そんな中で、もう一つの事件が起きる。
それが志賀と女中との結婚騒動だ。
志賀24歳のころ、彼は志賀家で働く女中と深い仲にあった。
そして、結婚を望むようになり父に告白。
だが、父はそれを許さなかった。
志賀は由緒正しき志賀家の跡取りだったので、父は結婚相手に慎重だったのだ。
結婚問題で親子が衝突する例は、近代文学上で割とあるのだが、志賀もまたその一例だったといえるだろう。
スポンサーリンク
・
要因④「国文科への転科」
次の事件は志賀が英文科 → 国文科へと移ったことだった。
当時の東京帝国大学では英文科はエリートが、国文科は堕落者が在籍する学科だった。
たとえば秀才の芥川龍之介や新思潮派の面々は「英文科」に進んだし、すでに作家を志し、勉学なんてクソ食らえの谷崎純一郎は「国文科」に進んだ。
谷崎同様に文学を志し、勉強なんてクソ食らえの志賀もまた、英文科から国文科へと転科した。
それに父は激怒。
勉強もしない、放蕩三昧、そのうえ堕落者が集まる「国文科」へ行く……
まぁ、父が怒るのも理解はできる。
要因⑤「大学中退・作家になる」
ここまでくれば志賀が大学を辞めるのは、もはや時間の問題。
25歳で国文科へ移った志賀は、27歳で「白樺」を創刊・大学を中退。
本格的に作家としての道を歩むことになる。
しかも、父が激怒したのは、志賀がこの期に及んで父に金を無心しにくることだった。
自分の小説を自費出版するのに、父から金を要求する志賀に対して、父は、
「小説を書いて何になる? 小説で食っていけんのか? なめんじゃねえ!」
と憤慨、激怒。
こうして29歳のとき、志賀と父は親子関係を決裂。
志賀は家を出て、尾道へと移っていった。
こうして、志賀は父に対する負の感情を原動力に、多くの中編小説を書いていくことになる。
皮肉なことだが、志賀文学に「父との不和」はなくてはならないものだった。
あっけなく和解
さて、もはや修復不可能に見える2人の関係。
だが、34歳の年に、あっけなく和解。
その顛末は、志賀の私小説『和解』において描かれている。
志賀がたまたま道端で父に出会い、
「ところで、じいちゃんのお見舞いで、実家に帰りたいんだけど」
と尋ねた。すると父は、
「いいよ。あ、おれ、本当は怒ってないから」
と答え、2人は涙を流して喜んだ。
……え、それでいいの?
と、思うのだけど、親子関係なんて、えてしてそんなものなのだろうか。
いずれにしても、父子の和解は成立。
このことは、志賀のその後の作品に大きな影響を与えていくのだが、さらにもう一つ、志賀の心境に大きな変化を与える大事故が起きた。
スポンサーリンク
山手線事故と城崎養生

尾道から帰郷した志賀直哉は、あるとき、同じく白樺派で友人の里美弴と相撲を見に行った。
その帰り道、2人が山手線の線路脇を歩いていたところ、志賀だけが山手線に跳ね飛ばされてしまった。
これがどれだけの事故だったのかはあまり知られていないが、普通だったら死んでもおかしくない大事故だった。
まず、列車に跳ねられた志賀は、4メートル以上ふっとばされた。
そして、背骨をひどく打ち、頭も石に打ちつけ、その切り口はザクロのように口を開き、そこから頭蓋骨が見えるほどだった。
ちなみに、あと少し遠くに吹っ飛ばされていたら鉄橋から転落していたらしく、あと少し飛んだ方向が違えば鉄柵に串刺しになっていたらしい。
文字通り「九死に一生」を得た志賀だったが、だからこそ、この事故は志賀に「死」と「生」をつよく意識させることになった。
医者から、
「もしも背中の傷が脊椎カリエスになれば、あなた死にますよ」
と言われたため、転地療養のために城の崎へ赴くことになる。
その三週間、志賀は自らの「生」と「死」についての思念を深め、それを「ありのまま」に一編の短編を描いた。
それが『城の崎にて』だ。
【 参考記事 解説・考察・あらすじ『城の崎にて』(志賀直哉)―“生と死”の真実に迫る― 】
以降、志賀の作品には達観した「調和的な心境」が描かれるようになっていく。
志賀文学の集大成である長編『暗夜行路』は、志賀の経験を元にした私小説的な作品だが、そこでは「悟り」とでもいえる志賀の思想的な到達点が見て取れる。
志賀も武者小路も「白樺派」といっしょくたにされてしまうが、「小説の神様」と呼ばれた志賀と、「おめでたい坊ちゃん」と呼ばれた武者小路、両者の間には大きな大きな隔たりがあるのだ。
スポンサーリンク
・
「小説の神様」太宰との論争

志賀のエピソードとして有名なのが、太宰治との論争だ。
「論争」とはいっても、両者の間には明らかな温度差があった。
太宰が、
「小説の神様がなんだ。調子に乗るんじゃねえ!」
と語気強めに批判をしていたのに対して、志賀は、
「はいはい太宰くんね。わかったわかった」
くらいのもんで、ほとんど太宰を相手にしなかったという。
それが理由に、後に太宰が自殺をしたあと、志賀直哉はこんな言葉を残している。
私は太宰君が私に反感を持ってゐる事を知ってゐたから、自然、多少は悪意を持った言葉になった。(中略)太宰君が心身共に、それ程衰へてゐる人だといふ事を知ってゐれば、もう少し云いやうがあったと、今は残念に思ってゐる。
(『太宰治の死』より)
「ごめんね、大人げなくちょっと言い過ぎたわ」と、太宰にわびているワケだ。
小説の神様には余裕があったのだ。
では、そもそも なぜ太宰は志賀にかみついたのだろう。
ことの発端は、志賀がある座談会で「最近売れっ子の太宰治をどう思うか」と尋ねられ、次のように答えたことだった。
年の若い人には好いだろうが僕は嫌いだ。とぼけて居るね。あのポーズが好きになれない。
それを聞いた太宰は「売られたケンカは買ったるわ!」の趣で『如是我聞』というエッセイで、その怒りをぶちまけた。
「暗夜行路」
大袈裟な題をつけたものだ。彼は、よくひとの作品を、ハッタリだの何だのと言っているようだが、自分のハッタリを知るがよい。(中略)何処がうまいのだろう。ただ自惚れているだけではないか。
君について、うんざりしていることは、もう一つある。それは芥川の苦悩がまるで解っていないことである。
日蔭者の苦悶。
弱さ。
聖書。
生活の恐怖。
敗者の祈り。
さて、ここで両者の言い分を整理したい。
まず、志賀直哉が嫌った「太宰のポーズ」とは、太宰の作品に見られる「読者へのサービス精神」だった。
ご存知の通り、太宰は私生活においても創作においても「道化」を捨てきれなかった人間だ。
彼の作品には読者へのリップサービスがあり、それは太宰自らも認めるところだった。
「ありのまま」を無駄なく簡潔に書く志賀にとって、その太宰の「ポーズ」が気にくわなかったワケだ。
しかも、太宰や織田作之助といった無頼派の連中というのは、酒とクスリに溺れて自堕落な生活を送る不良少年ばかり。
志賀の潔癖な倫理観とヒューマニズムが、そもそも彼らを毛嫌いしていたのである。
では、一方の太宰は志賀に対してどう思っていたか。
まず、「小説の神様」という立ち位置が気に入らなかった。
このころ志賀はすでに文壇の権威と成り果てていて、周囲は彼を崇めたてまつっている。
しかも書く内容はといえば達観した「調和的心境」で、そこには弱さとか惨めさとか、もっといえば人間的な「苦悩」といったものが、ほとんどなかった。
それは、太宰にとって到底理解できない世界だった。
だからこそ太宰は『如是我聞』で、志賀に対してこういったのだ。
も少し弱くなれ。文学者ならば弱くなれ。
そして、
「お前は解っていない。芥川の苦悩、日陰者の苦悶、弱さ、聖書……」
と続けたのだ
確かに、志賀文学と太宰文学とは真逆の作品で、両者の相性は驚くほどに悪い。
だから両者が反目するのは当然として、それにしても太宰はムキになり過ぎではないだろうか。
ほんとうは、太宰は志賀に憧れていたのだ。
太宰が「芥川賞」に異常なまでに執着したことは有名だが、彼は口では権威を否定しつつも、権威にしがみつくという自家撞着を抱えていた。
「小説の神様」にかみついたのだって、太宰が心の底では志賀への憧れをすてきれなかったからなのだ。
余裕があった志賀と、余裕のなかった太宰。
2人の論戦は、太宰の一方的なイチャモンといえる様相だったわけだが、志賀の「小説の神様」っぷりを世間に改めて知らしめる1つの事件でもあった。
「志賀直哉」を読むなら……
最後に、志賀直哉の代表作品を3つ紹介したい。
『城の崎にて』
志賀直哉といえばこれ。
「心境小説」の傑作と言われ、その文体は「お手本」とか「理想的」とか、とにかく高い評価を得ている。
現代の作家界隈でも、
作家になりたいなら、まずは『城の崎にて』を写しなさい
と言われているらしい。
ただ、凄いの文体だけでなく、志賀の透徹した「死生観」
ここまで「死」の諸相を鋭く分析している小説を、ぼくは他に知らない。
短いけれど、噛めば噛むほど味が出る、優れた短編だと思う。
『和解』
こちらも無駄のない簡潔な文体で、父と子の和解の顛末が描かれている。
前半では、父子の不和が描かれるのだけど、特に印象的な事件は「娘の死」にまつわる父の仕打ちだろう。
ここでの父の言動は到底許せるものではなく、読んでいて胸くそ悪い気持ちになるし、親子の不和はここで決定的なものになったかに見える。
ここからどのように「和解」が実現するのかは、読んで見てのお楽しみ。
『暗夜行路』
とにかく『暗夜行路』を評価する文豪は多い。
- 谷崎潤一郎「文章に芸術的な手腕がある」
- 三島由紀夫「自然描写は世界に卓越している」
- 芥川龍之介「あんな文章、私にはかけない」
- 大岡昇平「『暗夜行路』は近代文学の最高峰だ」
- 小林秀雄「『暗夜行路』は確かな知恵で描かれている」
実際に読んでみると、自然描写と内面描写がとにかく巧いし、物語としてもとても面白い。
志賀直哉の思想的な到達点とも言える本作品。
近代日本文学を語る上で、絶対に外せない1冊だろう。
日本文学を学びたい人へ

この記事にたどり着いた方の多くは、おそらく「日本文学」に興味がある方だと思う。
日本文学の歴史というのは結構複雑で、「〇〇主義」とか「〇〇派」とか、それらの関係をきちんと整理することが難しい。
そこでオススメしたいのが、日本文学者「ドナルド・キーン」の代表作『日本文学の歴史』シリーズだ。
日本文学史の流れはもちろん、各作家の生涯や文学観、代表作などを丁寧に解説してくれる。
解説の端々にドナルド・キーンの日本文学への深い愛情と鋭い洞察が光っていて、「日本文学とは何か」を深く理解することができる。
古代・中世編(全6巻)は奈良時代から安土桃山時代の文学を解説したもので、近世編(全2巻)は江戸時代の文学を解説したもので、近現代編(全9巻)は明治時代から戦後までの文学を解説したものだ。
本書を読めば、間違いなくその辺の文学部の学生よりも日本文学を語ることができるようになるし、文学を学びたい人であれば、ぜひ全巻手元に置いておきたい。
ちなみに、文学部出身の僕も「日本文学をもっと学びたい」と思い、このシリーズを大人買いしたクチだ。
この記事の多くも本書を参考にしていて、今でもドナルド・キーンの書籍からは多くのことを学ばせてもらっている。
「Audible」で近代文学が聴き放題

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、夏目漱石や、谷崎潤一郎、志賀直哉、芥川龍之介、太宰治など 日本近代文学 の代表作品・人気作品が 月額1500円で“聴き放題”。
対象のタイトルは非常に多く、日本近代文学の勘所は 問題なく押さえることができる。
その他にも 現代の純文学、エンタメ小説、海外文学、哲学書、宗教書、新書、ビジネス書などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。
これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。
・
・
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、気軽に試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・




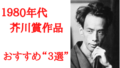

コメント