はじめに

近代文学の作家(文豪)のまとめ記事はこちらから。 【芥川龍之介】……「芥川龍之介」人物・人生・代表作のまとめーぼんやりした不安とはー 【泉鏡花】……「泉鏡花」の人生と人物ーロマン主義・観念小説・幻想文学の名手ー 【尾崎紅葉】……「尾崎紅葉」の人生・人物のまとめ―擬古典主義・硯友社とは何か― 【小林多喜二】……「小林多喜二とプロレタリア文学」―『蟹工船』の内容・代表作家— 【梶井基次郎】……「梶井基次郎」の人生・人物のまとめ―早世した天才のやさぐれエピソード― 【志賀直哉】……「志賀直哉」人物・人生の解説―反自然主義・白樺派とはー 【島崎藤村】……「島崎藤村」人物・人生・代表作の解説 ―自然主義とは何かー 【太宰治】……「太宰治」のまとめ ―人物と「恥の多い生涯」と代表作の解説― 【谷崎潤一郎】……「谷崎潤一郎の人物・人生・文学的特徴」―耽美派の代表作家― 【坪内逍遥】……「坪内逍遥」の写実主義をわかりやすく解説―そもそも日本文学とは何か― 【夏目漱石】……「夏目漱石」のまとめー人物と人生の解説・代表作の紹介ー 【二葉亭四迷】……「二葉亭四迷」の言文一致運動をわかりやすく解説―写実主義を完成させた男― 【森鴎外】……「森鷗外」のまとめ―人物と人生の解説・代表作の紹介― 【横光利一】……「横光利一と新感覚派」を分かりやすく—『蠅』『機械』など代表作も紹介—
芥川龍之介と、聞いて あなたはどんなイメージを持つだろうか。
文豪!
芥川賞!
羅生門!
ってところが、たぶん一般的なイメージか。
もちろん、彼は文豪だし、芥川賞の「芥川」は彼のことだし、高校のころにやった「羅生門」の作者は彼である。
だけど、それだけで彼を語ることは到底できない。
「悲しみに満ちた幼少期を送ったこと」や、
「超天才的な頭脳で小説を書いたこと」や、
「生きづらい世間で身も心もボロボロにしたこと」や、
「35歳という若さで服毒自殺したこと」など、
あなたはそれらのことについて、どれくらい知っているだろうか。
彼には、あまりに有名な言葉がある。
彼の遺書ともいえる『或旧友へ送る手記』の言葉だ。
遺書の冒頭、彼は「自殺者の心理」について触れている。
そして、「自殺の動機」一般例として、以下のものをあげている。
「生活難」
「病苦」
「精神的苦痛」
しかし、彼は「ぼくの経験上、それらは自殺者にとって、動機のすべてではない」と断定する。
そして、あの有名な言葉を残した。
少くとも僕の場合は唯ぼんやりした不安である。何か僕の将来に対する唯ぼんやりした不安である。
ぼくは、この言葉に触れるたびに いつも言いようのない「不安」を感じてしまう。
この「不安」は、いったいどこからくるものなのだろうか。
もしかしたら、芥川の死を思う度に、「死」を近くに感じるからなのかもしれいない。
「死は、おまえにとっても、決して無縁じゃないぞ」
芥川の遺書は、ぼくにそうささやいてくるような気がする。
だって、「ぼんやりとした不安」なら、ぼくにもある。
それによって「虚しさ」や「悲しみ」や「寂しさ」を感じることだってある。
それって程度の差こそあれ、だれだって同じではないだろうか。
とすると、芥川とぼくたちとの間に、いったいどれだけの違いがあるというのか。
無意識のうちに、
「自殺は自分とは無縁の世界だ」
と思っているぼくにとって、1人の人間が「ぼんやりとした不安」なんかで死なれてはこまるのだ。
1人の人間が、35歳の若さで自ら命を絶たなければならなかったこと。
そこには、もっと説得力のある理由があるのではないだろうか。
そう考えたぼくは、「芥川」の人生について調べてみた。
彼の抱えていたという「ぼんやりとした不安」の正体が、少しでもつかめると思ったのだ。
この記事では、そんな文豪「芥川龍之介」の35年の人生についてまとめてみたい。
そこには、彼の「ぼんやりとした不安」について考えるヒントが、沢山潜んでいるだろう。
この記事の最大の目的は、
「ぼんやりとした不安」とは一体何だったのか
これを明らかにすることにある。
そして、芥川の代表作についても紹介をしていこうと思う。
芥川龍之介の年表
1892年(0歳)
…東京都に誕生
…母が病気のため、芥川家に預けられる
1904年(12歳) …芥川家と正式に養子縁組を結ぶ
1905年(13歳) …東京府立第三中学校に入学
1910年(18歳) …第一高等学校に入学
1913年(21歳) …東京帝国大学英文学科に入学
1914年(22歳)
…第三次「新思潮」創刊
1915年(23歳) …『羅生門』 …漱石の「木曜会」に出席
1916年(24歳)
…第四次「新思潮」創刊
…『鼻』を漱石に激賞される
…横須賀海軍機関学校で教鞭をとる
1918年(26歳) …塚本文と結婚 …大阪毎日新聞社社友となる …『地獄変』・『蜘蛛の糸』・『奉教人の死』
1919年(27歳)
…海軍機関学校を辞職し、大阪毎日新聞社に入社
1920年(28歳) …『舞踏会』・『杜子春』
1921年(29歳) …海外視察員として中国へいく
1922年(30歳) …神経衰弱を訴える …『藪の中』・『トロッコ』
1923年(31歳)
…菊池寛が創刊した「文藝春秋」に『侏儒の言葉』を掲載
1925年(33歳)
…『大導寺信輔の半生』
…『芥川龍之介全集』刊行
1926年(34歳) …『点鬼簿』・『鵠沼雑記』 …湯河原で静養
1927年(35歳)…『河童 …睡眠薬で服毒自殺 …遺稿『歯車』・『或阿呆の一生』・『西方の人』
幼少時代「母の喪失体験」

さっそくだが、幼少期こそ芥川の人生を決定づけた時期だったと、ぼくは考えている。
1892年(明治25年)3月1日、東京都に生まれた男の子。
辰年、辰月、辰日、辰の刻に生まれた彼は「龍之介」と名付けられた。
父 新原敏三は43歳。
母 フクは33歳。
両親ともに大厄の年に生まれた子だったため、当時の慣習にならい 龍之介は生まれて間もなく、近所の教会に捨てられてしまう。
龍之介は「捨て子」にされてしまったワケだが、これはあくまでも慣習にのっとった形式的なものだったらしい。
「捨てる日」と「拾う人」をきちんと決めて行うもので、結局のところ、育てるのは実の両親なのだから、一般的にはそこまで深刻なものではなかった。
とはいえ、この「捨て子」という事実は、物心がついた龍之介に深い影を落とした。
そして、この「捨て子」という事実……
まるで、龍之介の将来を暗示していたかのようで、本当に彼は実の親から捨てられることになってしまう。
その経緯はこうだ。
まず、彼が生後8ヶ月のとき、実母フクが精神に障害をきたす。
それが原因で、龍之介はフクの実家である「芥川家」に引き取られることになる。
だから、龍之介は「母」の愛情というものを知らない。
龍之介を育ててくれたのは、母の姉のフキだった。
彼女の教育は、のちの「作家 芥川龍之介の誕生」に大きく影響を与えたと言われている。
フキは、龍之介を外へ連れ出し体を一緒に動かすってことが難しかった。
高齢だったフキにとって、体力的な問題もあったのだろう。
その代わり、フキは龍之介に対して、沢山の本の読み聞かせをしてあげた。
養家の本棚には草双紙(当時の小説類)があふれていて、龍之介は自然と文学への親しみを育てていく。
ぼくは物心ついた頃からこれ等の草双紙を愛してゐた。
後に彼自身そう述べる通り、幼い頃から古今東西の書物に触れていた。
この環境は、とても大きい。
実際に、龍之介の「速読っぷり」はとても有名な話しだ。
「日本文学なら、パラパラめくれば理解できる」であるとか、
「英文学なら、1日に1300ページは楽勝」であるとか、
とにかく、彼は凡人離れしたスピードで、スポンジのように多くの教養を吸収していった。
豊富な「インプット」があればこそ、すぐれた「アウトプット」も可能なのだ。
まちがいなく、作家としての資質は、この頃に培われたといえる。
が、一方で、幼少期の「インドア生活」が龍之介にあたえたものが他にある。
それは、
繊細で傷つきやすい心
である。
後述するが、芥川の人生は「人間のエゴイズム」抜きには考えられない。
もっと言えば「人々の評価」だったり、「人々の思惑」だったり、「人々の悪意」だったり。
世間ってのはそんなもんだ、と割り切れる多くの人にとって、なんてことのないことかもしれない。
だけど、芥川にとって、それらは耐えがたいものだった。
「人間のエゴ」というものが、じわじわと彼の心をむしばんでいくことになるのだが、それについては後述する。
ただ、もし、彼に人並み程度でいいから強い心があれば。
彼は、ひょっとしたら自らの人生を、最後まで生ききることができたのかもしれない。
- 「捨て子」
- 「母の発狂」
- 「内向的な生活」
幼少期に経験したこれらは、たしかに「作家」芥川龍之介にとってプラスに働いたかも知れない。
ただ、「人間」芥川龍之介にとって、果たしてプラスだったのか。
必ずしもそうではないだろう。
スポンサーリンク
小・中校時代「創作への情熱」

小・中校時代の龍之介を一言で語るとすれば、
「まったく手のかからない優等生」
ということになるだろう。
成績は常にトップ。
やはり、幼い頃から親しんだ書物の影響というのが大きい。
小学生の頃には、滝沢馬琴や十返舎一九といった「江戸文学」だけでなく、泉鏡花や尾崎紅葉といった「近代文学」なんかも熱心に読んでいたそうだ。
こんな小学生、当時としても珍しい。
ただ、龍之介が成績優秀の「優等生」だった理由は、それだけではない。
というよりも、こっちの理由のほうが本当で、かつ深刻だ。
龍之介が11歳になるころ、精神を病んでいた母フクが死ぬ。
母の死について、彼は晩年に『点鬼簿』(死者の過去帳の意味)という短編に記している。
それによれば、母は死ぬ直前、一瞬 正気を取り戻し、龍之介をみて涙を流したらしい。
実母の死は、たとえ一緒に過ごした時間が短かったとはいえ、龍之介の心に深い痕跡を残したことが分かる。
こうして、龍之介にとっての肉親は父の新原敏三だけになってしまう。
その心もとなさから、養家では、「絶対に、この人たちから見捨てられちゃダメだ」と思って生活をしていたという。
良い子にしなければ捨てられてしまう
こういった恐怖と不信感が、少年龍之介の心を支配し、彼を「優等生」にしたというわけだ。
龍之介は、養家でとても良い子に振る舞っていたというし、言いたいこともしたいことも幼いながらにグッと我慢をして過ごしていたという。
そんな龍之介の思いを知ってか知らでか、父 新原敏三はすぐに再婚をする。
その相手は、あろうことか前妻フクの妹。
しかも、2人の間には子どもまで生まれている。
こうして父にとって厄介者となった龍之介は、正式に芥川家と養子縁組を結ぶ。
龍之介12歳のこと。
「新原龍之介」が「芥川龍之介」になった瞬間は、同時に龍之介が本格的に「親」を失った瞬間でもあった。
こんなふうに、龍之介の幼少期と小学校時代は、あまりに悲しみに満ちている。
彼は虚構の世界で、悲しみを癒そうとしたのだろう。
じつは、龍之介の「創作」というのは小学校のころから始まる。
彼は、同級生らと作品を持ち寄って本にするという、いわゆる「回覧雑誌」を作り始める。
ちなみに、その当時の作品の中には『目的は死』というものがある。
芥川の晩年を知っているぼくたちからすれば、ドキッとさせられるタイトルである。
中学校に進学しても、芥川の生活は似たようなもので、相変わらず、成績優秀の優等生。
唯一の慰みは、読書と「回覧雑誌」
この頃の作品で目に付く作品として、こんなものがある。
『吾輩も犬である』
言うまでもなくこれは夏目漱石の『吾輩は猫である』を元にした作品なのだが、パロディなのかオマージュなのか、一体どんなスタンスで書いた作品なのだろう、その辺りはよく分からない。
にしても、このタイトル。
控えめにいって、センスがない。
後の文豪芥川龍之介のことを考えると、「ちょっとらしくないなあ」と思ってしまう。
とはいえ、この頃に漱石が登場してくるのは、なにか運命的なものを感じる。
のちに、龍之介は夏目漱石に出会い、彼を師として仰ぐからだ。
漱石が芥川に与えた影響ははかりしれないのだが、それについては後述する。
スポンサーリンク
一高時代「人生を動かす出会い」

18歳になる年、現「東京大学」の前身である、第一高等学校に無試験入学する。
「無試験入学」とは、要するに推薦入学のこと。
小中と優等生だった龍之介を思えば、それも当然のこと。
ちなみに、当時「高等学校」に進学できたのは、同世代のうち1%にも満たなかった。
その入学試験では、広く深い教養が求められたといわれている。
たとえば、当時の国語の問題にこんなものがある。
「西鶴の表現の特徴を答えなさい」
これを真っ白な解答用紙にびっしりと論述しなければいけないのだから、現代の大学入試とは比べものにならないことはすぐに分かる。
さて、第一高等学校では、龍之介にとって人生を動かす3つの「出会い」があった。
1つ目は、のちの同人になる「新思潮」メンバー、すなわち、
- 菊池寛
- 久米正雄
- 松岡譲
- 成瀬成一
との出会いである。
それ以外にも、井川恭とか山本有三とか土屋文明とか、そうそうたる面々もいたのだが、なんといっても「新思潮」メンバーとの出会いは、龍之介が作家としての道を切り開く大きなきっかけとなった。
2つ目は、西洋文学との出会いである。
ツルゲーネフ、イプセン、モーパッサン、ストリンドベリイなどなど。
後に龍之介は、帝国大学の英文学科に進学して、卒業論文ではウイリアム・モリスを扱っている。
そんな西洋への関心は、第一高校時代に強まったといえる。
そして、西洋文学に描かれている厭世観というのも、この頃の龍之介に影響を与えたと思われる。
3つ目は、『聖書』との出会いである。
もっとも、当時の第一高生にとって、『聖書』というのは一つの教養で、多くの学生が手にした1冊だったので、その頃の龍之介にとっても特別なことではなかっただろう。
ただ、これも後述するが、龍之介は後に自身の深い悲しみを通して「聖書」を読み、晩年には「キリスト」を主人公にした作品をいくつか残してもいる。
自殺をした彼の枕元にも、聖書が開かれた状態で置かれていたという。
以上。
- 「同人仲間」
- 「西洋文学」
- 「聖書」
これらとの出会いは、後の龍之介の人生に大きな影響を与えていくことになる。
スポンサードリンク
帝大時代「人間のエゴと失恋」

21歳、東京帝国大学英文科に入学。
この頃の大きなイベントとしては、なんといっても「作家デビュー」である。
その媒体は第三次「新思潮」。
「柳川隆之介」という、なんともムムムなペンネームで、女遊びに溺れる男のわびしい晩年を描いた『老年』という作品を発表した。
これを機に龍之介は本格的に創作活動を開始するようになった。
翌年には、有名な『羅生門』を発表することになる。
そして、その執筆の背景には、決してい無視できない悲しい事件が存在している。
ある女性との恋愛と失恋 である。
そのころ龍之介は、「吉田弥生」という才女と真剣に交際をしていた。
好きな子には、やたらに手紙を書くのというのは、龍之介の気質みたいで、彼のラブレターというのは結構残っている。
手紙はこんな感じ
「これで弥あちゃんへ手紙をあげるのが二度になるのですが、二度とも ある窮屈さを感じてゐるのは事実です」
「眠る前に時々、東京の事や、弥あちゃんのことを思ひ出します」
どうだろう。
およそ、「文豪」らしからぬ、かわいらしい手紙だと思わないだろうか。
龍之介の純粋な恋心や、恋故のもどかしさ、切なさみたいなものが、ほんのりと表れている。
龍之介は弥生を純粋に愛していたのだ。
そして、彼は自然と弥生との結婚を意識していく。
その意思を、養家である「芥川家」に伝えたのは、22歳のことだった。
これまで、「自分の思い」を押し殺して生きてきた龍之介。
養家の親に「自分の本心」を伝えたのは、これが初めてのことだったかもしれない。
ある晩のこと、龍之介は意を決して、弥生との結婚の思いを養家の人々に伝えた。
が、養家の人々は、彼の思いを受け入れなかった。
2人の結婚に強く反対をしたのだ。
その理由は、
- 弥生の「士族」出身でなかったから
- 弥生が婚外子だったから
と、諸説があるのだけれど、いずれにしても、養家の人たちは自分たちの「世間体」を優先したのだといえる。
龍之介は夜通し泣いて、愛する弥生との結婚を認めてもらおうと訴えかけたという。
が、養家の人々は龍之介の思いを拒絶。
結局、龍之介は弥生との結婚を断念することになる。
彼は友人に手紙を送り、その時の心境をこう言葉にした。
エゴイズムのない愛がないとすれば 人の一生ほど苦しいものはない
周囲は醜い、自己も醜い、そしてそれを目のあたりに見て生きるのは苦しい
たしかに、これまで養家の人たちは、親に見捨てられた龍之介を大切に育ててくれた。
そんな彼らであっても、ひとたび利害関係が生じてしまえば、優先するのは「自分たちの保身」だった。
「実の親」だってそうだったではないか。
表面的には自分を愛してくれてるように見えても、その愛情の裏には いつだって身勝手な「自己愛」や「自己保身」といった、「人間のエゴイズム」が隠れている。
こんな人の世を生きていくのが、人生だとしたら、人生とはなんと苦しいものなのだろう。
龍之介はこの「失恋事件」をきっかけに、厭世思考を強めていく。
そして、その悲しみを慰めるように手に取ったのが『聖書』だった。
「愛はすべてエゴイズムだ」という思いを強くした彼だったが、だからこそ、「真実の愛」というものを求めたのかもしれない。
『聖書』には、無償の愛「アガペー」が説かれている。
人間に絶望しつつも、それでも『聖書』に救いを求めようとしたのは、やはり龍之介にとって「誰かから愛される」ということが、必要不可欠なことだったからに違いない。
そんな思いを持て余した彼は、吉原で童貞を捨てると、そのまま官能に溺れていく。
だけど、それじゃダメなことは、龍之介が1番良く分かっていた。
彼の内からは次第に創作のエネルギーが湧いてくる。
有名な『羅生門』とは、このような経緯で生まれた作品なのだ。
【 考察記事 解説・考察『羅生門』―作者が伝えたかったことは何か? 創作秘話も紹介― 】
ここには、徹底的にえぐり出された「人間のエゴイズム」と、「人が主体的に生きるとは、どういうことか」という問いが描かれている。
作品にみなぎる熱量は、それだけ、龍之介の悲しみが強かったという証拠でもある。
『羅生門』に続いて描かれたのが、これも芥川文学の中でも有名な作品。
あの漱石にも絶賛された傑作短編小説、
『鼻』
である。
この頃、芥川は友人らと、夏目漱石の家に出入りをしていた。
いわゆる「木曜会」の一員だったのだ。
漱石を師として仰いだ彼らは、漱石から強く影響を受け、自分たちの創作の場を作りたいと一念発起。
その雑誌は第四次『新思潮』、芥川はそこに『鼻』を掲載する。
それを読んだ漱石は激賞した。
「大変おもしろい」
「材料が非常に新しい」
「文章が整っている」
「敬服した」
そして、漱石はこうもいう。
あゝいふものを是から二三十並べて御覧なさい。文壇で類のない作家になれます。
こうして、作家としての自信を得た芥川。
大学を卒業後、さらに意欲的に創作を続けていく。
ここに、作家 芥川龍之介が誕生したと言えるだろう。
彼にとって悲しい失恋という事件が、作家 芥川龍之介を生み出す大きなきっかけとなった。
芥川は、この時まだ24歳であった。
そして、芥川の代表作についても紹介をしていこうと思う。
スポンサーリンク
新進作家時代「前途洋々な船出」

大学卒業した芥川は、横須賀にある海軍機関学校の嘱託教官となり、英語を教える。
教員と作家、2足のわらじを履く彼だが、そのバイタリティはすさまじく、次々に作品を残していく。
しかし、この頃の芥川の作品は、『羅生門』や『鼻』ほどの傑作を生みだせず、作品はことごとく世間から酷評される。
そこには、たぶんにして「若い売れっ子作家」への妬みや僻みもあったようだ。
それでも、自分の作品がこき下ろされるのは、芥川にとって辛かった。
そんなとき、師である漱石から「作家としての姿勢」について諭す手紙が届く。
むやみにあせってはいけません。ただ牛のように図々しく進んでいくのが大事です。
あせってはいけません。頭をわるくしてはいけません。根気づくでおいでなさい。
漱石は、芥川の空回りを見抜いていたのかもしれない。
尊敬する漱石の言葉は、駆け出し作家の芥川にとって、とても励みになるものだった。
が、そんな漱石も、突如この世を去ってしまう。
その喪失感と悲しみについて、芥川はこう書いている。
僕はまだこんなやりきれなく悲しい目にあったことはありません。今でも思い出すとたまらなくなります。始めて僕の書く物を認めて下すったのが先生なんですから。(塚本文宛ての書簡)
精神的肉体的にも疲労したという何だかぽかんとしてゐる。一体夏目さんは特にオレたちの為に少し早く死にすぎたね。このころ痛切にさう思ふ。(松岡譲宛ての書簡)
とはいえ、悲しんでばかりもいられない。
漱石からもらった言葉を胸に、芥川は「牛のように」創作を続けていく。
ちなみに、この頃( 初期の )芥川の作品は、おもに「古典文学」から題材を得ている。
『羅生門』も『鼻』も『芋粥』も、『今昔物語』という鎌倉時代の説話からインスピレーションを得たものだ。
これは、当時の流行を考えると とても斬新だった。
なぜなら、当時の文壇は「自然主義」という潮流が一般的だったからだ。
「自然主義」とは要するに、
「作家自らの生活を赤裸々に暴露する」といった作品こそが文学だ!
という主張をいう。
ところが、芥川の場合は「古典」を元にした作品を描いている。
そして、彼の明晰な頭脳によって、計算され尽くしたフィクションを作り上げるワケだ。
こういう「自然主義」とは一線を画した態度を 文学史的に、「反自然主義」と呼んでいる。
しかも、芥川は、その明晰な「理知」によって虚構世界を構築していくわけで、反自然主義のなかでも、
「理知派」とか
「新技巧派」なんて呼ばれている。
ただし、『羅生門』の説明でも分かるとおり、たとえ描かれる世界は「虚構」であったとしても、そこにはっきりと芥川自らの姿が投影されている。
だからこそ、作品には一定の説得力と、強烈な訴求力があるわけだ。
次第に芥川の評価も高まっていき、「大阪毎日新聞」から新作執筆のオファーを受ける
そうして誕生したのが、有名な『地獄変』である。
これも『宇治拾遺物語』という鎌倉時代の説話からインスピレーションを受けている。
狂気的な芸術家を描いた作品なのだが、芥川は「芸術こそが最も尊い」と考えていた。
人生は一行のボオドレエルにも若かない
これも晩年の芥川の言葉なのだが、芥川の「芸術至上主義」と「厭世主義」とが現れた言葉だと言われている。
この『地獄変』も、世間から高い評価を受けた。
そして、「大阪毎日新聞」との契約が本格的にきまり、海軍機関学校を退職。
専属作家 として創作を開始していく。
さて、一方のプライベートでは、「塚本文」という女性と結婚している。
ここで彼は、あまりにギャップのある甘ったるい手紙を彼女に送っている。
有名な手紙だが、ここに引用したい。
こんどお母さんがおいでの時 せひ一緒にいらっしゃい。その時、ゆっくり話しませう。2人きりで いつまでもいつまでも話しませう。さうしてKissしてもいいでせう。いやならばよします。この頃ボクは 文ちゃんがお菓子なら頭から食べてしまひたい位 可愛い気がします。嘘ぢゃありません。文ちゃんがボクを愛してくれるよりか 二倍も三倍もボクのほうが愛してゐるやうな気がします。
どうだろう。
先ほど引いた、「弥あちゃん」よりも「文ちゃん」への手紙のほうが、濃厚だと思わないだろうか。
後にも先にも、こんなにデレデレした芥川の姿をみることはできない。
それくらい、このころ、彼は幸せだったのだろう。
創作も評価された。
生活も軌道にのった。
恋愛も結婚も順調だった。
このとき、彼は26歳。
彼の幸せが、このまま続いてくれれば良かったのに、とぼくは思う。
それは芥川本人こそが、つよく望んだことだったに違いない。
だけど、人生はとても残酷なもので、ここから芥川の生活にゆっくりと影が差し込んでいく。
スポンサーリンク
人生のかげり「秀しげ子という女」

きっかけは、「秀しげ子」という女性との出会いだった。
しげ子とは、とある作家連中の集まりで偶然出会った。
はじめは、どこか愁いをまとったなまめかしい彼女に、芥川は惹かれたという。
そして、2人は密通。
ところが、芥川は彼女を「狂人の娘」とか「復讐の神」と呼ぶほどに、嫌悪し、怯えることになる。
しげ子には旺盛な「動物的本能」があったというのだが、要するに、
とんでもない性欲の持ち主 だったわけだ。
しかも、かなりの粘着体質だったようで、その後もストーカーのように彼にまとわりついてきた。
しげ子は次男を出産した際に、芥川に対して、
「この子、あなたに似ていませんか?」
と、媚びるように脅してきたという。
晩年の作品『或阿呆の一生』には、その時のことが書かれているのだが、芥川の心労と苦悩を読み取ることができる。
さて、「秀しげ子」事件もあって、創作活動は停滞していく。
そして、「胃アトニー」と「痔疾」と「神経衰弱」に悩むようになっていく。
この頃に第一子である長男『比呂志』が誕生するのだが、その際に芥川はこう思ったという。
何の為にこいつも生まれて来たのだろう? この娑婆苦の満ち満ちた世界へ
いや、ふざけんな! 作ったんはお前だろ!
と、ここに関しては、ぼくは断固として芥川に抗議したい。
父親のお前がそれを言っちゃ、オシマイではないか、と思うからだ。
とはいえ、だ。
とはいえ、一方で、彼が言わんとすることも分かってしまうのだ。
彼は幼少時代から、父親になるまでの間、その厭世的な価値観を着実に育ててきたわけで、その厭世観が 生まれ落ちて大声で泣き叫ぶ息子の姿に刺激されたのだろう。
「なぜ、ぼくは生まれてきたのだろう」
ときに、ぼくたちはそう問わずにいられない。
そう問うてしまうのは、いつだって、苦しくてたまらないときだ。
長男が誕生したときの芥川は、まさに辛くてたまらない時期だったのだ。
「人生は地獄よりも地獄的である」
これは、この頃に書かれた『侏儒の言葉』の冒頭部分。
これが、芥川の人生観である。
スポンサーリンク
・
作風の変化「自分自身を題材に」

30代になって、芥川の作風に変化が見られる。
そのきっかけの1つは「関東大震災」だったと言われている。
震災で目の当たりにしたのは、世界の不条理と人間の残酷さだった。
災害によって一瞬で崩れ去る生活と、混乱する人々の姿。
朝鮮人に対して暴力を加え、暴徒化する日本人の姿。
芥川は「自警団員」として、そうした現実を目の当たりにしていた。
以降、彼は現実をそのままに書き出す、いわゆる「リアリズム小説」を書き始める。
世界や人間の「ありのまま」を描こうとしたのかもしれない。
しかも、その題材は基本的には自らの身辺に求めた。
「保吉物」とよばれる一連の「私小説」を書くのもこの頃のこと。
さらに、『大導寺信輔の半生』という、自伝的な小説も書いている。
どうもこの辺りの芥川には、自分自身の半生を振り返り、人生を総括しようとしている節がある。
『虚構』を理知によって構築していたこれまでの芥川を思えば、やはりどこか不自然だ。
本人の実感としても、それは「らしく」なかったのだろう。
結局、リアリズム小説も、私小説も、告白小説も、どれも彼自身にはなじまず、創作はどんどん停滞していくことになる。
そうして、鬱々とした思いだけがどんどんと膨らんでいく。
- 胃アトニー
- 痔疾
- 神経衰弱
- 胃けいれん
- 腸カタル
- ピリン疹
- 心悸亢進
これが、この頃の持病なのだが、もう素人には何が何やらさっぱりである。
とはいえ、いよいよ限界が近づいていることは分かるし、大量の薬が必要だったことも想像に難くない。
こうして、芥川は崩壊と破滅へと一歩、また一歩と近づいていくことになる。
スポンサーリンク
晩年と死「芥川を苦しめた事件」

33歳から35歳の2年間は、芥川にとって、最も苦しい1年だったといえるだろう。
このころまでに、心身ともに追い詰められていたことはすでに見てきた。
が、さらに追い打ちをかけるように、2つの事件が彼に降りかかる。
1つ目は、印税問題だ。
彼は3年近くかけて『近代日本文芸読本』全5集を編集してきた。
さまざまな日本作家たちの名作を集めた、文学全集である。
それが刊行されたのは、芥川が33歳のころのこと。
今後の文学教育に期待をして心魂を注いだ、彼にとっては渾身の仕事であった。
が、残念ながら、売れ行きはイマイチ。
実際に、芥川に入ってきた印税収入というのも微々たるものだったという。
と、まぁ、別段、ここまでは問題ない。
頑張ったね、だけど、残念だったね で済む話である。
問題は、芥川が受け取った「印税」についてよからぬ噂が広まったことだった。
実はこの頃、芥川は自宅に書斎を新築していた。
すると、なぜか「印税」を「書斎の新築」にかこつけて、こう非難する人々が現れた。
「芥川は、印税でもうけて、書斎なんか建てていやがる。作家の作品を利用して、1人だけいい思いをしやがって。ゆるせん!」
もちろん、根も葉もない、全くの言いがかりではある。
しかし、この頃の芥川の神経がすでにズタボロであることは、散々確認してきたことだ。
良かれと思ってしたことが、人々の怒りを買い、彼らの悪意は容赦なく自分に向けられる。
彼は、それに耐えることができなかった。
こうして、芥川の繊細な心に、さらなる大きな負担が加わることとなった。
2つ目は、義兄の自殺だ。
芥川にはヒサという姉がいたのだが、その夫が、鉄道自殺をする。
芥川は、その後処理に忙殺されることとなる。
加えて、未亡人となった姉と その子供たちの面倒も、芥川が一手に引き受けることとなった。
すでに、養家の家族を含めて、8人の家族の生活を支えていた芥川にとって、これはあまりにも大きな負担となった。
だけど、彼は、
「オレが頑張らなくちゃ、この人たちが路頭に迷ってしまう」
という使命感から、歯を食いしばって、創作に打ち込むことになる。
だけど、この時期、肌に合わない「リアリズム小説」を書いていた彼にとって、創作は容易なことではない。
そもそも、創作できるような精神状態ではないのだ。
まったくはかどらない創作。
沢山の家族を支えなければならないプレッシャー。
そのはざまで、彼は息もできないほどに、追い詰められていく。
この頃の芥川は不眠症と、うつ状態で、幻聴・幻覚・食欲不振・めまいに悩まされていた。
死んだ母を見と言ったり、犬が振り返って自分を嘲笑したといったり……
とにかく、常軌を逸した精神状態だったという。
すでに存在すること自体が、彼にとって名状しがたい苦しみとなっていた。
その苦しみを薬によってごまかす日々。
睡眠薬もすでに手放せなくなっていた。
この頃に書いた作品に『歯車』がある。
ここには、狂気と死といった、破滅の予感が淡々と描かれている。
ドッペルゲンガーに遭遇したり、レインコートの幽霊を見たり、これらは間違いなく、芥川がこの頃に経験した幻覚や幻聴がもとになっている。
また、タイトルの『歯車』とは、医学的に「閃輝暗点(せんきあんてん)」のことだと言われている。
「閃輝暗点」とは、はげしい片頭痛が訪れる前兆のことで、視界の片隅にチカチカと歯車のようなものが見える症状である。
ちなみに、ぼくは数年前にこの「閃輝暗点」を経験した。
とつぜん、視野狭窄のように、目の前が暗くなりだしたと思ったら、かたすみに白くぼんやりした影がチカチカと回っていたのだった。
その後に強烈な片頭痛がやってきた。
脳外科に急行しMRをとった結果、脳には特に異常がないことが分かった。
ほっと、胸をなでおろすぼくに、
「つよめの片頭痛ですね」
と、医師は診断を下した。
「あの、視界が急に暗くなって、それでチカチカって……」
と、ぼくが当時の状況を話すと、
「ああ、それ、閃輝暗点ですよ」
と教えてくれた。
え? 芥川の歯車っすか?
と、のどまで出かかるほど、奇妙な感動を覚えたのを覚えている。
あのときの片頭痛も強烈だったけど、きっと芥川のはもっともっと強烈だったんだろうな、と思う今日この頃である。
話を戻そう。
この頃の作品として、『河童』も有名だ。
精神病患者が「河童の世界」について語るという短編小説なのだが、まず、この精神病患者は、芥川の分身だと考えられる。
それから、詩人の「トック」という河童も芥川の分身のように登場するのだが、この河童もまた自殺をしてしまう。
要するに、芥川の前途には、「自殺」か「狂気」しか、すでに残されてはいなかったのだろう。
『河童』には印象的なシーンがある。
「わたしもほかの河童のやうにこの国へ生まれて来るかどうか、一応父親に尋ねられてから母親の胎内を離れたのだよ。」
これは河童の言葉なのだが、読んでみてわかるように、河童の世界では生まれ落ちるその前に、
「本当に、お前はこの世界に生まれてきたいのか?」
と、本人の意思を確認できるというのだ。
この場面……
芥川の人生を知っているぼくたちにとって、とても痛切な場面だといえる。
自分の意志と無関係にこの世に産み落とされ、
幼少期に捨て子同然に扱われ、
養家ではいい子になろうと精一杯振る舞い、
好きな女の子とは「家」の都合で別れさせられ、
人々の思惑や悪意にさらされ薬漬けになってしまった芥川。
彼にとって「人生は地獄以上に地獄的」であり、この世界に生きていること自体が、彼にとって苦しくて、不可解で、不条理なことだった。
だから、『河童』という作品には、
「こんな世界なら、ぼくは生まれたくなんてなかった」
という、芥川の悲痛な叫びが表れていると、ぼくは思う。
さて、ここまでくれば「いつ自殺してもおかしくない」と思える精神状態だといえる。
実際に、彼は妻の友人と心中未遂事件を起こすほど、すでに「自死」は彼にとって現実的になっていた。
そして、芥川35歳の7月24日、それは日曜日だった。
夜から降り出した雨の音を聞きながら、彼は書き物をしていたという。
深夜2時。
すでに睡眠薬ヴェロナールとジアールを致死量飲み下した彼は、ゆっくりと立ち上がって、妻たちが寝ている寝室へいく。
床につき、なにやら書物を読んでいると、次第に意識が遠のいていった。
翌朝、布団の中で変わり果てた芥川の姿を最初に目にしたのは、妻の文だったという。
その枕元には、開きっぱなしの『旧約聖書』がそっと置かれ、その後にいくつかの遺書と、書きかけの原稿も見つかった。
死の直前に書いていたのは、『続西方の人』
『西方の人』に続き、キリストについて書いた作品であった。
小穴隆一が書いた芥川のデスマスクは、生前の苦しみがまるで嘘のような、安らかな表情をしている。
キリストは、芥川にとって救いになりえたのだろうか。
それは芥川にしか分からない。
スポンサーリンク
・
終わりに 「現代に受け継がれる芥川の精神」

以上、思った以上に長くなってしまったが、芥川の人生についてまとめてみた。
こうしてみてみると、彼の「ぼんやりした不安」というのが、なんら観念的なものではなく、どこまでも具体的で、とても人間的なものであることが分かると思う。
とかく、芥川の自殺が語られるとき、この「ぼんやりとした不安」ばかりが一人歩きをして、どこか芥川を神格化するような雰囲気を感じることがある。
だけど、こうしてみてみると、彼の死にはなんのカリスマ性もない。
それは、繊細な心を持った1人の人間が、家族の愛をしらずに、自分の本心を偽り、人々の悪意に傷つき、身も心もボロボロになった挙句、「もう死ぬしかない」と大量の睡眠薬を飲んで眠るように逝ったという、そういう血の通った具体的な人生の証なのだ。
もちろん、「ぼんやりとした不安」と書いた彼の思いに、嘘も衒いもないだろう。
芥川自身、なんでこんなに苦しいのか、うまく対象化することが難しかったと思う。
とかく、身も心もボロボロになってしまった人は、精神的な視野狭窄に陥り、自分や周囲を冷静に見ることができなくなってしまうからだ。
それに、彼は作家なのだ。
安易に「病苦」とか「生活苦」といった、ありきたりな言葉を与えることに、大きな抵抗があったのだろう。
作家として言葉や自分の心を大切にしてきた彼だからこそ、最後の最後まで、ふさわしい言葉を探して遺書を書いたのだと思う。
彼は、死の直前まで、作家として生きた 文字通りの文豪だったのだ。
さて、最後に芥川の葬儀の様子について書いて、この記事をしめくくりたい。
弔辞を読んだのは、菊池寛だった。
彼は芥川にとって「新思潮」の同人であり、長年の親友でもあった。
菊池寛はすっと席を立ち、芥川の霊前に立つと、
「芥川龍之介君よ・・・・・・」
と呼びかけた。
だけど、そのまま言葉につまり、慟哭してしまい、用意していた原稿を読み進められなかった。
そんな姿に、列席者たちも涙を流したと言われている。
親友である菊池寛の脳裏に、学生時代の芥川の姿や、幸福だった彼の姿、苦しくてのたうち回った彼の姿、それでも生きようともがいた彼の姿、そういうものが走馬灯のように蘇り、親友の無念を思うと涙をとめられなかったのだろう。
芥川の死から、約10年後。
菊池寛は、親友の生前の業績をたたえ、ある文学賞を創設する。
それが「芥川賞」だ。
日本人の誰もが知っている純文学の新人賞。
受賞者の中には、芥川に魅了され、文学を志したという作家も多い。
そして彼らが描く作品というのは、いまも文学に新しい風を巻き起こし、ぼくたちを魅了し続けている。
日本文学を学びたい人へ

この記事にたどり着いた方の多くは、おそらく「日本文学」に興味がある方だと思う。
日本文学の歴史というのは結構複雑で、「〇〇主義」とか「〇〇派」とか、それらの関係をきちんと整理することが難しい。
そこでオススメしたいのが、日本文学者「ドナルド・キーン」の代表作『日本文学の歴史』シリーズだ。
日本文学史の流れはもちろん、各作家の生涯や文学観、代表作などを丁寧に解説してくれる。
解説の端々にドナルド・キーンの日本文学への深い愛情と鋭い洞察が光っていて、「日本文学とは何か」を深く理解することができる。
古代・中世編(全6巻)は奈良時代から安土桃山時代の文学を解説したもので、近世編(全2巻)は江戸時代の文学を解説したもので、近現代編(全9巻)は明治時代から戦後までの文学を解説したものだ。
本書を読めば、間違いなくその辺の文学部の学生よりも日本文学を語ることができるようになるし、文学を学びたい人であれば、ぜひ全巻手元に置いておきたい。
ちなみに、文学部出身の僕も「日本文学をもっと学びたい」と思い、このシリーズを大人買いしたクチだ。
この記事の多くも本書を参考にしていて、今でもドナルド・キーンの書籍からは多くのことを学ばせてもらっている。
「Audible」で近代文学が聴き放題

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、夏目漱石や、谷崎潤一郎、志賀直哉、芥川龍之介、太宰治など 日本近代文学 の代表作品・人気作品が 月額1500円で“聴き放題”。
対象のタイトルは非常に多く、日本近代文学の勘所は 問題なく押さえることができる。
その他にも 現代の純文学、エンタメ小説、海外文学、哲学書、宗教書、新書、ビジネス書などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。
これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。
・
・
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、気軽に試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・

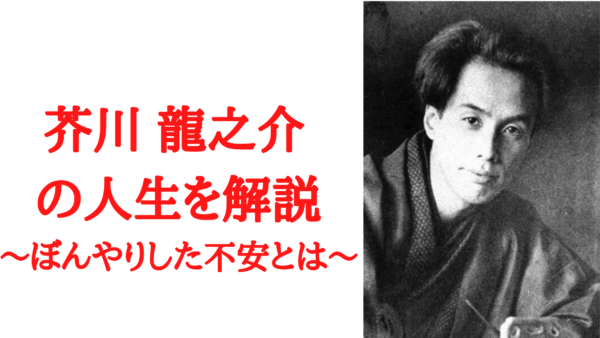



コメント
どういった流れでか、このサイトに辿り着き他の用事を放り出して一気に読み通してしまいました。夏目、芥川、三島、太宰と、彼らが背負わされた人生の荷は壮絶で、もう気の毒と言うほかにありません。その辺のことは、敬愛する吉本隆明氏の書物から学んだことですが、自分も含め「表現とは、欠損を埋め合わせる営為」と理解しています。存在することの異和を何とか了解しようといった衝動でしょうか。
で、何故芥川龍之介に引っかかったのかと言いますと、僕の叔父の再婚相手で当時未亡人だった叔母の元ご主人が、実は芥川の愛人の子でして、そういった背景のある人たちは、常人にはない苦労があって、結局元ご主人も若くして亡くなり、残した息子(一応僕の従弟)は離婚を繰り返し一昨年がんで亡くなった溺愛された母親の葬儀も未だに済ませていないという有様です。ひとって何故こんなにも不平等に生れ落ちるのだろう…自分も含め強く実感する今日この頃です。
長くなりました。僕の尊敬する吉本隆明の言葉で「どんな奴でも10年毎日机に向かって手を動かし書き続ければものになる。嘘じゃない、この素首を賭けてもいい!」というのがあります。粘り強く書き続けて下さい!
因みに僕は45年以上続けている漆工芸家です。http://urushi-art.net
とても面白かったです。
東 日出夫さん
コメントありがとうございます。吉本隆明を敬愛されているということで、東さんの人となりが分かるような気がします。実際、言葉の端々に誠実かつ深い内面が垣間見えるような気がしました。
>自分も含め「表現とは、欠損を埋め合わせる営為」と理解しています。存在することの異和を何とか了解しようといった衝動でしょうか。
僕も激しく同意します。曲がりなりにも、僕も「書く」ことに魅せられた人間なので、吉本隆明の言葉は心にささります。
吉本隆明も芥川にシンパシーを感じていた論客でしたね。確か「芥川の死は思想的なものではなく、文学的なものだった」といったことを言っていたと思いますが、まさにその通りだと思います。芥川と大川に関する論考にも、吉本の芥川に対する思いが表れていて、読んでいて涙が出ました。芥川の人生は、読み手に悲しみや苦悩があるほど、惹きつけるものがありますよね。きっと、東さんも同じなんだろうなと勝手ながら想像しています。芥川との不思議な縁も、興味深く読ませていただきました。人の一生とは、生きるとは、いったい何なのでしょうね。僕も文学や思想を通して、模索し続ける毎日です。
>「どんな奴でも10年毎日机に向かって手を動かし書き続ければものになる。嘘じゃない、この素首を賭けてもいい!」
励まされる言葉です。ブログも小説も、これからずっと書き続けていきたいと思います。
お時間のあるときに、またブログをのぞきに来ていただけると嬉しいです!
こんばんは
昨夜コメントの返事を書いている途中で気絶💦長めのコメントのセキュリティー文字が承認されずすべて消えてしまいました。実は、今日も「時間」とは何かを検索して、またまたこのサイトに行き着きました。で、昨日はなかなか芥川のところに行き着かず迷走していたら「言語にとって美とはなにか」に行き着き、嬉しく拝読。Kenさんは多分お若くて30~40代?なのによく「言語にとってを美とはなにか」をお読みになりましたねぇ。感心しました。
また寄らせてもらいます。おやすみなさい。。
返信が遅れてすみません。
ブログの記事、あれこれ読んでいただいたようでとても嬉しいです。また、『言語にとって美とは何か』の記事も(おそろしく拙稿にもかかわらず)読んでいただいということで、大変恐縮です。
吉本隆明が好きな友人がいまして、彼の薦めで『言語にとって美とは何か』は読みました。いや、「読んだ」というのは適切ではないかもしれませんね。おそろしく難解なあの作品を、どれだけ理解できたかはいまだに疑問です……。時間があれば、共同幻想論なんかも読み直し、考察記事を書きたいなーと思いつつ、なかなか実現ができずにいます。もし、『共同幻想論』の記事を描くことがあったら、その時はぜひ、また遊びに来ていただけると嬉しいです!