永井龍男の「退任事件」

芥川賞受賞作品まとめ ・1950年代「芥川賞」おすすめ9選 ―戦後文学の全盛― ・1960年代「芥川賞」おすすめ7選―女性作家の台頭― ・1970年代「芥川賞」おすすめ6選―文学に吹く新しい風― ・1980年代「芥川賞」おすすすめ3選―空前絶後の❝暗黒時代❞― ・1990年代「芥川賞」おすすめ6選 ―現代女流作家の躍進― ・2000年代「芥川賞」おすすめ10選 ―個性派ぞろいの作家たち― ・2010年代「芥川賞」おすすめ10選 ―バラエティ豊かな傑作たち― ・2020年代「芥川賞」おすすめ7選 -直近全作品を読んだ上で厳選―
1970年代の文学シーンを象徴するできごとを紹介したい。
それは、選考委員の永井龍男の「退任事件」である。
永井は1958年から長年にわたり選考委員をつとめる、言わば「古参」の委員だった。
そんな彼が自ら選考委員を退くきっかけとなった2つの作品がある。それが、
- 村上龍の『限りなく透明に近いブルー』(1976年)
- 池田満寿夫『エーゲ海に捧ぐ』(1977年)
であった。
永井はその2つの作品が受賞することに猛反発を示した。
『限りなく…』については、「受賞を見送り、次作を待つべき」と言い、『エーゲ海に捧ぐ』については「これは文学ではない」とまで言っている。
しかし永井の評価とうらはらに、2作品はその「前衛さ」が評価され、芥川賞を受賞することとなった。
この一連のできごとをうけて永井は、
「自分の委員としての資格について検討されなければならない」
という言葉を残し、約20年務めてきた選考委員を退任したのだった。
これは1970年代の文学シーンを象徴する出来事だと思う。
受賞作を眺めてみると、50年代、60年代の作品と雰囲気の異なるものが少なくない。
村上龍・池田満寿夫・中上健次・宮本輝……
彼らは70年代を代表する作家たちだが、中上や宮本は「戦後生まれ」である。
彼らによる文学は当時の文壇にとって新鮮であり、70年代は「文学に新風が吹いた時代」だったと概括できるだろう。
そんな1970年代の芥川賞作品の中から、「6作品」を厳選して以下で紹介していこうと思う。
『杳子』(古井由吉)1970年

作者について
文学好きの中で古井由吉の熱烈なファンは多い。
お笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹も、古井由吉へのリスペクトをあちこちで語っていたりする。
- 分かりやすい作品
- ありきたりの展開
- 典型的な登場人物
そういうのに飽き飽きしている人に、古井由吉はオススメの作家だ。
東京大学文学部出身の古井は、金沢大学や立教大学の教員を経て、33歳の年に専業作家に転身。
その同年に『杳子』で第64回芥川賞を受賞する。
実はこのとき同時に、古井の他の作品『妻隠』も候補作に上がっていた。
1人の作家が、2作品でノミネートという……
これは、芥川史上かなり稀なケースである。
しかも、その2つの作風は、まるで違っていた。
選考委員の中に「あまりに作風が違うので、別人の筆かと思った」と言うものさえいたくらい。
『杳子』が渾沌として曖昧さを残す作品だとすれば、『妻隠』は明るく分かりやすい作品だ。
その毛色の違う2作品は「どちらも受賞にふさわしい」という評価を得る。
が、「そのどちらを受賞作とするか」の議論になると意見は真っ二つに割れるのだった。
『杳子』を推したのが、丹羽文雄・船橋聖一・大岡昇平・石川淳
『妻隠』を推したのが、中村光夫・永井龍男・井上靖
ちなみに川端康成は、
「そもそも、予選の段階で1つにしぼれないとか、ありえないでしょ」
と強く不満を抱き『杳子』のほうしか読まなかったという( 自由すぎ )。
こんな感じで、選考会で波乱が巻き起こった。
古井由吉、その規格外の才能をうかがい知れるエピソードである。
なお古井は、同世代の黒井千次や小川国夫らとともに「内向の世代」と呼ばれている。
「内向の世代」とは、あくまで日常を描きながら、個人の内面や人間の本質を追究する作家たちに使われた呼称である。
作品について
『杳子』は、読み手に「誠実で根気強い読み」を求める作品である。
それは「ありきたりな作品に飽き飽きしている人にオススメ」といった、さっきの紹介に通じる部分なのだが、表現を変えれば「捉えどころがなく分かりにくい」ということにもなる。
選考委員たちも異口同音に、こんなことを述べている。
「渾沌として、暗く、明晰でない感じが小説の持ち味になっている」
「密度の濃い、面白いややこしさがあるが、筆の妙味にうっとりした」
『杳子』は、その「捉えどころのなさ」と「絶妙な筆致」によって、選考委員たちを魅了したというわけだ。
杳子は深い谷底に一人で坐っていた
作品はこんな書き出しで始まる。
この物語をあえて一言でいうならば、
神経を病む「杳子」と「僕」との恋愛物語
ということになるのだろう。
とはいえ、当然そんな一言で全てかたづけられっこない。
「僕」の心理も「杳子」の心理も、複雑で繊細に描かれている。
彼らの内面に「わかりやすさ」はない。
それなのに、読み進めていく内に、彼らの“孤独”というものがじわじわと伝わってくる。
そして、この小説世界には、言葉で言い表すことの難しい美しさがある。
それは、古井の流麗な文体が効いているからであり、まさしく“言葉の芸術”とでもいえる趣なのだ。
とにかく「ありきたりな作品にうんざり」って人や「ことばの芸術に触れたい」って人は、ぜひ『杳子』を手に取って読んでみてほしい。
ちなみに「新潮文庫」には『妻隠』も収録されているので、2つを比較して読んでみてもおもしろいと思う。
『月山』(森敦)1973年

作者について
森敦が芥川賞を受賞したのは、なんと61歳のことだった。
選考でも
「60歳を超えた新人なんてありえない」
という声もあがったというが、そんな中でも丹羽文雄は、
「私は、この人の名前を30年昔にしっていた」
とした上で、
「ちっとも老人くさくないのは、脅威である」
と絶賛している。
また「森敦が芥川賞を受賞した」というニュースを耳にし、はるか昔に聞いたその名前に驚いた文学ファンも少なからずいたという。
森敦とは、一体なにものなのか。
1912年に生まれた森は、旧制第一高等学校に入学した戦前の秀才文学少年だった。
彼は菊池寛に見いだされ、横光利一に師事し、若い頃は あの太宰治・檀一雄・中原中也の同人として創作に励んだ。
そうそうたるメンバーと肩を並べていた森だったが、ある日から作家として沈黙することになる。
それから40年……
時は流れ、人々が「森敦」を忘れかけた頃、彼は再び文壇に現れたのだった。
選考委員たちは、彼をとても好意的に迎え入れた。
「森敦の登場は、井上靖、大江健三郎の登場を思わせる」
「彼の作品を読んで、久しぶりに小説を読む楽しさを堪能した」
「60代は決して“老い”ではない、むしろ作家として成熟の時期である」
この記事の冒頭、ぼくは「1970年代は、文学に新風が吹いた」と紹介したが、『月山』はそんな中で突如現れた「近代文学」さながらの正統派の小説だったのだ。
なお、61歳の受賞は当時としては最高齢記録だった。
その記録は、2013年に黒田夏子( 『ab さんご』 )が75歳で受賞して更新している。
作品について
『月山』は俗世間から関係を絶った男が、冬の山奥で過ごす物語だ。
「月山」とは庄内平野の裏にある山で、古くから「死者の山」とされてきた。
また、その近くにある「鳥海山」は逆に「生者の山」だという。
2つの山が象徴するように、この作品には「生と死」というテーマがひっそりと流れている。
森敦の筆も仕上がっていて、月山の秀麗な姿と山里の生活が写実的に淡々と描かれていく。
この山里に暮らす人々は、四季とともに生きている。
春の訪れを喜び、冬の訪れに堪えしのぶ……。
作中、なんらの事件も発展もないので盛り上がりには欠けるが、それにより逆に際立つものがある。
それは「村里に流れる時間」である。
その時間とは「都会」に流れる「直線的な時間」とは違い、春夏秋冬を繰り返す「円環的な時間」だといえる。
そしてそれは、生と死を内包する「人間の命」と結びついてる。
井上靖の選評が、おそらく『月山』の魅力をよく伝えている。
「雪深い集落の冬ごもりの生活を、方言をうまく使って、現世とも幽界ともさだかならぬ土俗的な味わいで描き上げた」
静かで美しく、全ての生命を包み込むような、そんな味わい深い作品だ。
スポンサーリンク
『岬』(中上健次)1975年

作者について
和歌山県生まれ。
その生い立ちはあまりに複雑だった。
私生児として生まれた中上健次。
彼の母には前夫との子どもが4人いて、一方の父には別の女との子どもがいた。
そして両親は離婚。
その後も複雑な家族構成に翻弄され、幼い彼の心に深い痕跡を残した。
県立新宮高校に進学。
在学中にサドやジュネに傾倒し、次第に文学を志すようになる。
卒業後に上京すると、今度はジャズや映画にのめり込んだ。
他ジャンルの芸術から得たパワーを吐き出すように創作した中上の作品は“旺盛”とか“エネルギッシュ”という形容がふさわしい。
彼の作品には、都会が舞台で若者が主人公のは話が多い。
だけど「中上らしい」作品というのは、彼の出身地である和歌山県(紀州)を舞台にした作品だ。
第74回芥川賞を受賞した『岬』も、そんな紀州を舞台にした、まさに「中上らしい」作品だといえるだろう。
候補に上がること4度目の受賞で、このとき中上は30歳。
芥川賞史上、初の「戦後生まれ」作家であった。
受賞後はめまぐるしい日々を送った。
海外に奔走したり、文化人・芸能人・学者・評論家など、各界の著名人と対談したり……
純文学畑の彼だが、その枠を軽々と飛び越え、まさしく時代の寵児となっていった。
彼の文学を高く評価する思想家に柄谷行人や蓮實重彦がいる。
また、2021年に『推し、燃ゆ』で芥川賞を受賞した宇佐美りんは、中上健次を尊崇していることを多くのメディアで語っている。
作品について
『岬』で描かれているのは主に次の2つ。
- 複雑で閉塞的な土地
- 逃れられない血縁
である。
これらは、ある意味で文学の「王道テーマ」であり、最近の受賞作だと田中慎弥の『共喰い』が記憶に新しい。
ただこの『岬』の凄いところは、なんといっても作品にみなぎる「エネルギー」である。
ただ、ここで『岬』の欠点について触れなくてはいけない。
それは、
家族関係が複雑すぎること。
である。
主人公には異父兄弟や異母兄弟が多くいて、複雑な家族構成のもとで生活している。
その関係があまりに入り組みすぎているので、
あれ? 誰と誰が親子で、誰と誰が兄弟でしたっけ?
と、人物関係を何度も見失ってしまう。
ただ、それは作中の当人たちもそうで、彼らはそんな「異常な血縁関係」を強いられているわけなのだ。
そんな中で起きる事件は2つ。
- 異父兄の自殺
- 親戚による刺殺事件
それらを主人公は、決して他人事と捉えることができない。
- 呪われた「血縁」
- 閉ざされた「土地」
- そこで起きた「事件」
これらに、読者は言いようもない暗澹たる気持ちをおぼえるだろう。
ただ、繰り返しになるが、難点は「家族関係の複雑さ」で、選考委員でさえ口をそろえてこう言っている。
「家族関係が複雑すぎ、2度読んだ」
「登場人物の親戚関係を飲み込むのに骨がおれた」
「人物がゴチャゴチャして、わけがわからん」
それでもこの作品が受賞したのは、中上が持つ圧倒的なエネルギーによる。
「複雑な家族関係」に戸惑いつつも、選考会ではこう評価された。
「新進気鋭な作家としてのエネルギーが感じられる」
「この作家は、どんな材料でもこなせる力がある」
「若いのに、これほど独自の世界を持つのは、ひとつの才能」
「作者は現実に体当たりしている」
ここまでの熱量で作品を完成させたのは、やはり中上自身も「複雑な生い立ち」を経ているからなのだろう。
『岬』で扱われた「肉親の血の問題」は、さらに深化拡充されて『枯木灘』として結実。
毎日出版文化賞・芸術選奨新人賞を受賞した。
スポンサーリンク
『限りなく透明に近いブルー』(村上龍)1976年

作者について
アメリカ海軍基地の街である長崎県佐世保市に生まれる
その体験をもとに描いた、『限りなく透明に近いブルー』で作家デビュー。
本作はそのまま芥川賞受賞へ。
作品は発表されるや瞬く間にベストセラー(推定130万部)
『限りなく透明に近いブルー』が、これほどまで世間で注目されたのは、「暴力」や「性」を露骨に扱った、そのセンセーショナルな内容にあった。
選考委員の吉行淳之介は、
「いったん読むのをやめた。気を取り直すのに一週間かかった。読了するのに半月かかった」
と、困惑を隠せないでいた。(吉行淳之介といえば「男女の交情」を描く名手なのだが、その彼でさえ拒否反応を示すほど!)
同じく選考委員の丹羽文雄は、その刺激的な内容を指摘しつつも、
「この小説の魅力を強烈に感じた」
「久しぶりに文壇に新鮮な風が吹き込んだ」
「これは20代にしか書けない作品だ」
と、その若い才能を高く評価している。
その一方で、永井龍男のように「前衛性」を最後まで理解できず猛反発した選考委員もいた。(退任事件については後述の通り)
要するに、村上龍は彗星のごとく現れた「新たな文学の旗手」だったのだ。
そんな彼の1番の代表作、『コインロッカー・ベイビーズ』
純文学賞の権威、野間文芸新人賞を受賞、その後も数多くの純文学賞を受賞している。
2000年より、約18年間芥川賞選考委員を務めていたが、第158回を以て退任した。
作品について
- 時は70年代、ヒッピームーブメントの真っ只中。
- 舞台は東京、とある米軍基地の町。
- 主人公はリュウという若者。
- 彼の仲間達は小さなアパートの1室で、乱交パーティを繰り広げる。
とにかく、本書で描かれるのは、酒とドラッグとセックス。
ちなみに、当初の題名は「クリトリスにバターを」だったらしい。
あまりにも露骨すぎ……
だが、仮にその名前だったとしても、それに負けないくらい本書はスゴい。
彼ら若者たちにとって、エクスタシーと肉体的な痛みのみがリアルで、そんな彼等の姿を通して描かれるのは、汚くむき出しにされた強烈な生だといえる。
70年代というのは、高度経済成長真っ只中。
日本がどんどん豊かになっていく時代だ。
そんな時代に突如あらわれた『限りなく透明に近いブルー』
そのセンセーショナルな内容で、当時かなりの反響を生んだ。
じつは、この辺りから、暴力モノ、セックスモノが流行り出す。
たとえば、山田詠美のデビューは80年代。
デビュー作『ベッドタイムアイズ』も、暴力やセックスがふんだんに描かれている。
豊かな時代の中で、「生きるリアリティ」が人々から失われていったからなのだろう。
それをを改めて問うたこれらの作品は、期せずしてその時代を象徴していたともいえる。
じゃあ、現代はどうなのかと言えば、事情はそう変わらない。
性や死はいつの時代だってタブーだし、とくに現代は「死」をとにかく隠蔽し続ける時代だ。
そんな中で、人々の生命感はとても希薄で乏しいものになっている。
だからこそ、本書が描く暴力や傷みは、今でも人々の生命感やリアリティを刺激し続けるのかもしれない。
やはり、時代が文学を生むのだ。
スポンサーリンク
『エーゲ海に捧ぐ』(池田満寿夫)1977年

作者について
池田満寿夫は、もともと文学畑の人ではなく美術家だった。
しかも、かなり名の知れた美術家で、ヴェネティアの大きなコンクールで国際大賞を受賞するほど。
そこからは海外に滞在しながら、徐々に文筆活動も行うようになった。
そんな経歴の持ち主なので、作風もこれまでの文学の型を大きく飛び出すものだった。
43歳のころ『エーゲ海に捧ぐ』で代77回芥川賞を受賞するが、すでに述べた通り、この作品をめぐって永井龍男が選考委員を自ら退任している。
池田満寿夫もまた村上龍と同じく、1970年代にあらわれた前衛的な作家だった。
その活躍は美術や文学に留まらなかった。
『エーゲ海に捧ぐ』は自ら監督も務めて映画化し、カンヌ国際映画祭に出品し話題となった。
ほかにも陶芸にも興味を示したり、執筆・制作・演出・出演といった感じで、多彩な活動を見せた。
いまでこそ芥川賞には、お笑い芸人・アイドル・ミュージシャンなど「異業種」からの受賞が珍しくないが、70年代以前はそういったことはほとんどなかった。
そういった意味でも、70年代は文学に「新たな風」が吹き込まれた時代なのだ。
作品について
この作品には、とにかく性描写が多く、いわば「純文学的官能小説」といった趣だ。
前回の『限りなく透明に近いブルー』に続き、この露骨な作品で選考委員の永井龍男は「とどめ」をさされてしまったのだった。
主人公の「私」は彫刻家で、アメリカに滞在している。
そこから日本にいる妻に電話をかけているのだが、作品に描かれるのはその間の2時間ばかりの出来事だ。
ではその何が「官能的」かと言うと、
まず、受話器を握る「私」の目の前に、浮気相手の陰部がある。
女性はイタリア人の「アニタ」
そこには他に「グロリア」という女性もいて、彼女たちは次第に互いの身体を愛撫し始める。
「私」はそんな光景を見ながら、日本にいる妻と電話をしているわけだ。
そして受話器からは妻の罵声が響いている……
いや、どんな状況?
と、あらすじで早速面食らうと思う。
『岬』は2時間そこらの出来事を書いた小説なのだけど、とにかく性描写のオンパレードだし、しかもメチャクチャ緻密に細部を描くし、タイトルの『エーゲ海』みたいな優雅さは全くない。
それもそのはず。
実は「エーゲ海」とは 「女性の性器」のメタファーなのだ。
この小説には数々のエロティックなメタファーにあふれている。
こんな小説は今までになかった。
遠藤周作、中村光夫、吉行淳之介なんかは高く評価した。
永井龍男は「こんなの文学じゃない」と一蹴した。
「前衛的」と評価するか、「下劣」と評価するか、それは読み手次第。
1970年代を代表する問題作、ぜひ一読してみてはいかがだろう。
スポンサーリンク
・
『螢川』(宮本輝)1977年

作者について
宮本輝は、この記事のラストを飾るのにふさわしい文学界のレジェンドである。
1977年に自らの幼少期をもとに描いた『泥の河』で作家デビュー。
その翌年に、『螢川』で芥川賞を受賞し、作家としての地位を確立。
宮本輝は、細やかな人間心理を、叙情性豊かで美しい文章で描く作家だ。
一文一文が洗練された文章は読んでいて心地よく、読後も感動が潮のように押し寄せてくる。
そんな芸術的に完成度の高い文章表現が高く評価され、芥川賞を受賞したわけなのだが、加えて、読み手の感情を揺さぶる物語も描けるストーリーテラーとしての一面もある。
宮本輝は、吉川英治文学賞を史上最年少で受賞している。
この賞は東野圭吾とか宮部みゆきとかも受賞していて、いわゆるエンタメ小説を対象の文学賞だ。
文章としても美しく、物語としても人の心を動かす、それが宮本輝という作家なのだ
1996年から2020年まで芥川賞選考委員をつとめ、その引退時には『文藝春秋』で特集が組まれたほど。
2010年には紫綬褒章を受勲している。
現代文学を語る上で、絶対に外すことのできない重鎮中の重鎮、レジェンドオブレジェンドである。
作品について
この小説は、たくさんのエピソードが交錯していて、あらすじを紹介するのが難しい。
なので、まずは舞台設定を簡単に。
- 舞台は昭和37年、冬の富山。
- 主人公達夫は14歳。
- 年老いた父、母と貧しい暮らしを送っている。
と、こう書いただけで、作品にただよう息苦しさを感じると思う。
両親は互いに再婚同士で、父親はすでに66歳。
そんな父は、物語の途中で脳溢血により他界する。
それ以外にも、様々なエピソードが展開されていく。
父の死、友人の死、母親の過去、達夫の恋心と嫉妬心。
この作品を読むと、人間の一生とはなんと短く、なんと儚いことかと思わずにはいられない。波乱に満ちた人生を、晩年に振り返ってみれば、きっと一晩の夢のような儚さを感じるのだろう。
そんな「人生のはかなさ」が、『螢川』で巧みに表現されている。
もちろん、読んでいて息苦しく、切なく、苦しいストーリーだ。
だけど、この作品がそれだけで終わらないのは、終盤の「ホタル」のシーンがあるからだ。
そして、このシーンこそ『螢川』の最大の魅力である。
「4月に大雪が降ると、ホタルが大量発生する」ことを聞きつけた達夫は、母たちとホタルを見に行く。
数え切れないホタルが飛び交う幻想的な光景。
これまでずっと描かれてきた、主人公をとりまく重苦しい現実が、無限の蛍の光と美しく重なり合い、強烈な感動が押し寄せてくる。
ここでの宮本輝の文章は神がかっていて、その表現力に圧倒される。
選考でも、
「この世のものと思えないほど美しい」
と、大絶賛。
たった90ページ足らずの作品なのに、読後の感動は長編小説のそれに匹敵する。
宮本輝の作品には素晴らしいものが数多くあるのだが、ぼくはこの『螢川』が最高傑作だと思っている。
ここまで美しい世界を描き出せるのは、宮本輝をおいて他にないだろう。
文学ファンを今でも魅了し続ける名作中の名作……
これは読まなきゃ損である。
スポンサーリンク
・
すき間時間で”芥川賞”を聴く

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・
芥川賞をもっと読みたい人はこちら
以下の記事で、さらに作品を紹介している。
「受賞作品をもっと読みたい」と思う人は、ぜひ参考にどうぞ。
【 次の記事を読みたい方はこちら 】
【 芥川賞作品の「テーマ別」記事はこちら 】
芥川賞【テーマ別】おすすめ5選
・【本当におもしろい】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➀-
・【テーマが深い】おすすめ芥川賞作品5選 -初級編➁-
・【ハートウォーミング・日常系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➀-
・【暗い・怖い・ドロドロ】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➁-
・【暴力・アンモラル系】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➂-
・【個性的・独自の世界観】おすすめ芥川賞作品 5選 -中級編➃-
・【玄人ウケする本格小説】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➀-
・【古典級の名著】おすすめ芥川賞作品 5選 -上級編➁-

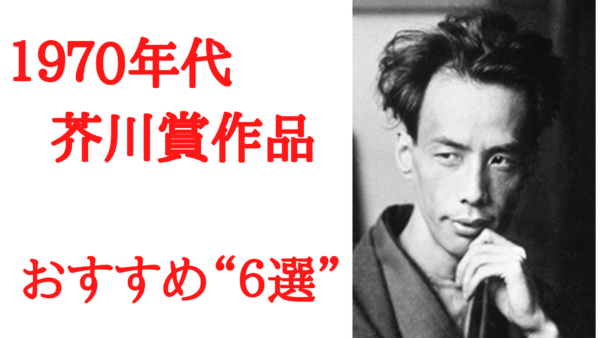

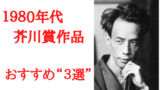

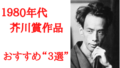
コメント