はじめに

近代文学の作家(文豪)のまとめ記事はこちらから。 【芥川龍之介】……「芥川龍之介」人物・人生・代表作のまとめーぼんやりした不安とはー 【泉鏡花】……「泉鏡花」の人生と人物ーロマン主義・観念小説・幻想文学の名手ー 【尾崎紅葉】……「尾崎紅葉」の人生・人物のまとめ―擬古典主義・硯友社とは何か― 【小林多喜二】……「小林多喜二とプロレタリア文学」―『蟹工船』の内容・代表作家— 【梶井基次郎】……「梶井基次郎」の人生・人物のまとめ―早世した天才のやさぐれエピソード― 【志賀直哉】……「志賀直哉」人物・人生の解説―反自然主義・白樺派とはー 【島崎藤村】……「島崎藤村」人物・人生・代表作の解説 ―自然主義とは何かー 【太宰治】……「太宰治」のまとめ ―人物と「恥の多い生涯」と代表作の解説― 【谷崎潤一郎】……「谷崎潤一郎の人物・人生・文学的特徴」―耽美派の代表作家― 【坪内逍遥】……「坪内逍遥」の写実主義をわかりやすく解説―そもそも日本文学とは何か― 【夏目漱石】……「夏目漱石」のまとめー人物と人生の解説・代表作の紹介ー 【二葉亭四迷】……「二葉亭四迷」の言文一致運動をわかりやすく解説―写実主義を完成させた男― 【森鴎外】……「森鷗外」のまとめ―人物と人生の解説・代表作の紹介― 【横光利一】……「横光利一と新感覚派」を分かりやすく—『蠅』『機械』など代表作も紹介—
日本の近代文学は明治18年、坪内逍遙によって始まったといわれている。
「写実主義」という文学的立場を提唱した彼だったが、しかし残念ながら、その自らの文学論を作品化することはできなかった。
だが、その彼の志を引き継ぎ、日本の「近代文学」の達成を成し遂げたレジェンドがいる。
それが二葉亭四迷だ。
この記事では、そんな彼の「人生と人物」について徹底解説してきたい。
また、彼の一番の業績である「言文一致運動」や代表作『浮雲』についても紹介する。
記事を読み終えれば、「日本文学文学とは何か」が分かり、「日本語」や「創作」の奥深さなんかも感じていただけると思う。
ぜひ、最後までお付き合いください。
「二葉亭四迷」はどんな作家?

ここでは二葉亭四迷という作家について紹介しよう。
まずは、略年表を示し、その上で彼の人生や人物像を具体的に解説する。
略年表
1864年(0歳) …現・東京都市ヶ谷に生まれる 1881年(17歳) …東京外国語学校(現・東京外大)入学 1886年(22歳) …坪内逍遙と出会う …文学論『小説総論』 1887年(23歳) …小説『浮雲』第1編 1888年(24歳) …小説『浮雲』第2編 …ツルゲーネフの翻訳 1889年(25歳) …内閣官報局に入局 1890年(26歳) …小説『浮雲』第3編 ※未完のまま筆を置く …長らく小説執筆から遠ざかる 1899年(35歳) …東京外国語学校の教授になる 1904年(40歳) …大阪朝日新聞に入社 1906年(42歳) …小説『其面影』 1909年(45歳) …肺炎・肺結核により死去
スポンサーリンク
人生と人物像について

後述するが、実は「二葉亭四迷」という名前はペンネームだ。
本名は長谷川辰之助という。
東京の武士の家系に生まれた。
彼は生真面目な性格で、高い理想を持つ上昇志向の若者だった。
目標は「陸軍士官」になること。
当時、北方の脅威となっていたロシアを封じるのが彼の夢だった。
そのためには、まずロシア語を学ばなければいけない。
ということで、17歳のころ、東京外国語学校(東京外大の前身)へ進学する。
ロシア語を学んだのは、そもそも彼の強い正義感からだったのだ。
ただ、当時ロシア語を学ぶ学生というのは少なく、教科書の類いも少なかった。
そこで、四迷がテキストにしたのがロシアの文学作品。
ここが彼の人生のターニングポイントだったと言えるだろう。
ちなみに、この頃のロシア文学はまさに「黄金期」といっていい。
作家のラインナップは次の通りで、それはそうそうたるものだった。
ツルゲーネフ、ゴーゴリィ、トルストイ、ドストエフスキー……
そんな大文豪たちの作品を、四迷は5年間みっちりと読み込んでいった。
当然と言えようか、彼はいつしか「文学」にのめり込んでいく。
そしてある日、彼は、坪内逍遙の『小説神髄』という文学論を知ることになる。
そこには「写実主義」の立場から、「日本の文学とは、こうあるべきだ」という内容が書かれていて、それを読んだ四迷はいたく感動。
すぐに逍遙のもとを訪れ、彼の弟子入りを乞うた。
そして四迷には新たな夢が生まれる。それは、
「日本の文学を、ロシアに負けない文学にすること」
四迷は逍遙のもとへ通い詰め、文学理論を学んだ。
そして、それを進化拡充して『小説総論』という文学論を描き上げた。
これは文学史的にも評価が高い論考で、師である逍遙の文学理論をはるかに凌駕するものだった。
その論考を読んだ逍遙は自らの負けを悟り、四迷の才能を認めた。
実は、このころ逍遙はすでに『当世書生気質』という小説を書き上げていて、そこで「写実主義」の作品化にチャレンジしていた。
が、その試みは失敗に終わる。
「写実主義」の実現は叶わなかったのだ。
逍遙はその半ばとなってしまった夢を、四迷に託すようにこう言った。
「おまえのその文学理論で、小説を書け」
こうして書かれたのが、日本文学史における記念碑的作品『浮雲』である。
この作品がいかに画期的だったかは後ほど詳しく説明するが、とにかく歴史的な意義を一言でいえば「言文一致体」で書かれたことだ。
「言文一致」とは、「話し言葉」で小説を書くこと。
この日本初の試みを彼は見事成功させる。
ただ、作品の成功とは裏腹に、四迷は『浮雲』の執筆を中途でやめてしまう。
以来、彼は長らく小説の執筆から遠ざかる。
そこには、四迷の葛藤や挫折があったのだが、これについても後述する。
いずれにしても、『浮雲』という作品は、実は未完なのだ。
その後の彼は官吏になったり、大学教授になったり、朝日新聞に入社したりと、職を転々とした。
そして、役20年の沈黙を破り再び創作活動に帰ってくる。
40代でリスタートをきった彼だったが、その作家人生は長くはなかった。
朝日新聞社の特派員としてロシアに渡った四迷。
その帰国の途中、船の上で命を落としてしまった。
死因は肺結核。
45歳という若すぎる死だった。
彼の作家人生は短かったが、彼の功績はその後の文学に多大な影響を与えたといっていい。
特に、後に登場する「自然主義」文学にとって、『浮雲』は一つのお手本として迎え入れられた。
そして「自然主義」は、現代の文学にも大きな影響を与えている。
今の「日本文学」があるのは、二葉亭四迷がいたからだといっても過言ではないのだ。
スポンサーリンク
ペンネームの由来

さて、ここでは「二葉亭四迷」のペンネームについて紹介したい。
このペンネームの由来が、
「くたばってしまえ」=「ふたばってしまえ」=「ふたばていしめい」
であることは有名な話だ。
ただ、この「くたばってしまえ」をめぐるエピソードについては2つの説がある。
まつ1つ目は「父親にいわれた」というものだ。
今でこそ「作家」の社会的地位というのは、そこそこ高い( だって〇〇先生って呼ばれるくらいだし )。
文学 = 高尚なもの
と考える人もいないわけでもない。
ところが、明治の日本にあっては
文学 = 低俗なもの
と考えられていた。
二葉亭四迷は、武士の子だ。
しかも明晰な頭脳をもち、当時としては超エリートの大学生でもある。
父や家族からの期待も並々ではなかったわけだが、そんな中、あろうことか四迷は、
「俺はこれから文学をやる」
と、言い放ったわけだ。
それを聞いた父は当然激怒。
「文学なんかで、食っていけるとでも思ってんのか」
そう怒鳴った彼は、我が子に茶碗を投げつけこう言ったという。
「おまえなんて、くたばってしまえ」
ということで、以上が1つ目のエピソードだ。
次に2つ目は「自虐的につぶやいた」というものだ。
四迷は『浮雲』を出版する際に、あることに悩んでいた。
それは、
「こんな無名のオレが出した本なんて、だれも読んでくれないんじゃないか」
という悩みだった。
そこで師である逍遙に相談したところ、
「じゃあ、オレの名前を使って出せば?」
ということになった。
だから、実は『浮雲』は、逍遙の本名である「坪内雄蔵」名義で出版されている。
その冒頭の端書きのところ。
申し訳程度に記されたペンネーム。
それが「二葉亭四迷」だった。
「オレは師匠の名前を借りなきゃ、本も出版できない男なのか」
そんな風に卑屈になった彼は、自らをあざけるようにこう言った。
「オレみたいなやつ、くたばってしまえ」
ということで、以上が2つ目のエピソードだ。
どちらも、いかにも本当らしいエピソードなので、案外どちらも事実なのかもしれない。
いずれにしても、明治時代の日本では「作家」の社会的地位がおどろくほど低かったことを教えてくれる興味深いエピソードである。
スポンサードリンク
「写実主義」を完成

二葉亭四迷の成し遂げた大きな業績の1つに「写実主義」を完成させたことがあげられる。
そもそも「写実主義」ってなに?
っていう話は、こちらの記事【 坪内逍遥の写実主義をわかりやすく解説―そもそも日本文学とは何か― 】で詳しく解説しているので、参考にしていただければと思う。
簡単にいえば、「写実主義」とは、坪内逍遙によって提唱された日本最初の「文学観」で、
小説は 主観を排除して世界のありのままを書くべきだ
という立場のことだ。
二葉亭四迷は、その文学観に感銘を受け、坪内逍遙のもとを通うことになる。
ただ、逍遙の文学論について、四迷にはどうしても納得できないところがあった。
それを一言でいえば、
「ありのまま」さえ書けば それでいいの?
ということになる。
四迷が本格的なロシア文学を学んできたことは、この記事ですでに述べた。
そんな目の肥えた彼にとって、逍遙の文学観はどうにも不完全に映ってしまったのだ。
逍遙が『小説神髄』で「写実主義」を提唱したのは、若干24歳。
その若さで日本文学の礎を築いたこと自体すごすぎることなのだが、やはり彼の文学論には欠点や粗さがあったのもまた事実(こればっかりは仕方ないと思うけど)。
かたや、四迷はといえばロシア文学の専門家。
つまり、彼はトルストイの『戦争と平和』とか、ドストエフスキーの『罪と罰』とかを知っているわけだ。
師匠の『小説神髄』を読んで、
こんな文学論じゃ、日本はロシアに到底およばない。
そう思った彼は、自らの疑問を逍遙にぶつけてみた。
すると逍遙は、
「おまえのその疑問をほりさげて、文学論を書いてみろ」
と促した。
師匠の言葉を受けて、四迷は一冊の文学論を書き上げる。
それが『小説総論』という作品だった( このとき四迷はなんと22歳! )。
そこではまず、逍遙の「心情・風俗をありのままに書け」という立場が次のように批判されいている。
心情・風俗は、あくまでも現象にすぎない
そして、さらに次のような文学観を提唱する。
心情・風俗をありのままに書くことで、その背後にあるものの本質を描くのが文学だ
「人間の本質」
「社会の矛盾」
「この世界の真理」
そういったものは、わかりやすく目の前にあるわけではない。
人々はそれらを見失ってしまっているのではないか。
それらを明らかにし、小説に落とし込み、読者に提示しなければならない。
四迷にとって、「文学」とは「人々が見失ってしまっている物事の本質」を描いたものでなければならなかったわけだ
四迷はこうした理念のもと、逍遙の文学理論を進化拡充させていった。
これを読んだ逍遙は、その文学論の真っ当さと、四迷の文学的センス・教養をみとめ、次のように言った。
「おまえは文学をやれ」
そこで四迷はまず、ロシア文学の翻訳から入った。
すると、その完成度の高さに逍遙は作品を激賞
「翻訳だけじゃもったいない、お前は小説を書きなさい」
こうして結実した作品が『浮雲』という日本文学史における記念碑的な大作だった。
こうして改めて見てみると、二葉亭四迷の文学的センスと教養がいかに卓越していたかがよく分かる。
だけど、それよりも僕は、四迷の才能を認め正しい道標を示してやった坪内逍遙の師としての偉大さを感じずにはいられない。
確かに逍遙は四迷に比べ、文学的センスも教養も劣っていかもしれない。
ただ、そのことを素直に認め、弟子の育成に誠実に取り組んだ逍遙こそ『浮雲』完成の立役者だといっていい。
では、その『浮雲』の何がそんなにすごかったというのだろうか。
それはなんといっても「言文一致体」という、当時の日本において画期的な文体を採用した点である。
スポンサーリンク
「言文一致運動」とは
「口語・文語」は区別されていた

明治時代に起きた一大ムーブメントが「言文一致運動」である。
そもそも「言文一致」とは何かというと、
「話し言葉(言)」と「書き言葉(文)」とを一致させること
である。
それはもっと言えば、
「話し言葉(口語)」で小説を書く
ということになる。
イメージするのが難しい思うので、試しにあなたが今読んでいる、この記事の文章を意識してみて欲しい。
仮にこの文章を僕が「音読」であなたに聞かせたとしても、(ちょっと偉そうなこと以外)大きな違和感はないと思う。
なぜなら、現代においては「話し言葉」と「書き言葉」というのを、( 基本的に )区別して使い分けることはないからだ。
「スピーチ原稿」とか「講演録」なるものが成立するのも、こうした事情があるからに他ならない。
現代の日本語において「言文一致」というのは(おおむね)達成されているわけだ。
こういう状況があたりまえになった今、「言文一致」なんて言葉を聞くと、
――え、じゃあ、昔は別々だったってこと?
と多くの人が驚くかも知れないが、まずは、ここの大前提を理解していただきたい。
さて、日本語の歴史を見てみれば、
・話し言葉 は「口語」 ・書き言葉 は「文語」
と呼ばれ、それぞれ状況ごとに使い分けられてきた。
これは主に、中世(鎌倉時代) ~ 近世(江戸時代)にかけて続いてきたわけだが、そうなると当然こういう疑問がわいてくるだろう。
――そもそも、なんでそんな区別が必要なの?
その答えは割とシンプルで、要するに、
「生活言語」は簡単な言葉でいいけど、「学問言語」は難解な言葉じゃないとダメ
という考えが昔からあったからだ。
この考えは程度の差こそあるものの、今も名残として現代にある考えだ。
たとえば、小説の文体は「やさしい言葉」であるのに対して、評論の文体は「難解な言葉」である傾向が強い。
これも「生活言語は簡単な言葉でいいけど、学問言語は難解な言葉じゃないとダメ」という価値観の表れといえる。
ただ、この区別はとっても自然なことなのだ。
普段の何気ないコミュニケーションにおいて、「実存」やら「現象」やら「疎外」やら「弁償」やらの哲学的な言語は必要ないし、第一その場にふさわしくない。
逆に、抽象的な議論が交わされる思想や哲学の場において、「かわいい」とか「たのしい」とか「うれしい」とか「おいしい」とかの日常語は必要ない、というか議論において全くの無力だ。
この事情は「やまとことば」と「唐言葉」という、かつての日本語にもあてはまる。
・「やまとことば」=「話し言葉」的 ・「唐言葉」=「書き言葉」的
そして繰り返しになるが、「言」と「文」はこんな風に整理できる。
・「言」=「話し言葉」=「やさしい言葉」 ・「文」=「書き言葉」=「難解な言葉」
もちろん、こんな風にシンプルにまとめることは出来ないけれど、基本的な方向性は同じと考えていい。
こうした言語使用の伝統が、二葉亭四迷の時代まで脈々と続いていたわけだ。
スポンサーリンク
・
「言文一致」が なぜ必要だったか

では今度は逆に、そもそも なぜ「言」と「文」を一致させる必要があったのだろうか。
ここまで読んでくれたあなたは、「言文一致」の必要性についてなんとなく勘づいているかもしれない。
結論を言うと、
小説を書くのに、「難解な言葉」はふさわしくないから
ということになる。
思い出してみてほしい。
そもそも坪内逍遙と二葉亭四迷が目指したのは、
「人情・風俗をありのまま描写すること」
である。
それらは言うまでもなく、日本人の、もっといえば自分自身の「日常」の風景を描くことにほかならない。
それを「ありのまま」表現するためには、難解な概念は不必要であるどころか、それを用いることはかえって逆効果となってしまう。
抽象概念では、具体的な「人間の姿」など描くことはできないからだ。
人間なんてのは矛盾していて、不可解で、つかみ所がない存在だろう。
そんな人間を、明晰な言語でもってスパっスパっスパっと割り切ったような小説に、果たして「人間の本質」が宿るだろうか。
その答えは明確だ。
だからこそ、「写実主義」の小説には、日常言語であるところの「話し言葉」の使用がどうしても必要だったわけだ。
これを読んでいるあなたにも、ゴリゴリの抽象概念を多用した小説を読んで、
――うげー、なんか勉強みたいで取っつきにくいなあ。
と、抵抗感を感じたという経験があるのではないだろうか。( なければ、ためしに埴谷雄高の『死霊』でも読んでみればいい )
こういう小説に共感したり、感情移入したりすることは、きっと難しい。
ということで「言文一致運動」とは、「小説」という世界観にぴったりな言語を採用した点で、文学史的に重要な事件だった。
その記念碑としての『浮雲』にも、文学史的な価値がある。
スポンサーリンク
・
「言文一致」を試みた作家たち

かくして『浮雲』は「言文一致」で書かれたワケだが、では実際に読んでみて「分かりやすいか?」と言われると、実は結構分かりにくい。
たとえば冒頭はこんな感じだ。
千早振る神無月ももはや跡二日の余波となッた二十八日の午後三時頃に、神田見附の内より、塗渡る蟻、散る蜘蛛の子とうようよぞよぞよ沸出でて来るのは、孰れも顋を気にし給う方々。しかし熟々見て篤と点検すると、これにも種々種類のあるもので……
『浮雲』より
とまあ、こんな調子で続いていくわけだが、これが「話し言葉」であることはなんとか理解していただけると思う。
地の文章を「話し言葉」にするなんて、初めての試みだったわけだから、多少のぎこちなさはご愛敬だ。
それに、このぎこちなさは最初の2、3章だけであり、読み進めるうちにドンドン滑らかな文体になっていくので、現代の僕たちでもストレスなく読むことができる(はず)。
ちなみに会話文はこんな感じで、わかりやすい。
お勢が溢れるばかりに水を盛ッた「コップ」を盆に載せて持ッて参ッた。
「ハイ本田さん」
「これはお待遠うさま」
「何ですと」
「エ」
「アノとぼけた顔」
「アハハハハ、シカシ余り遅かッたじゃないか」
「だッて用が有ッたんですもの」
「浮気でもしていやアしなかッたか」
「貴君じゃ有るまいシ」
『浮雲』より
とまあ、表記こそ独特だが、こっちは現代の小説とそう大差ない。
さて、「言文一致」で小説を書いたのは、なにも二葉亭四迷だけではない。
師匠の坪内逍遙だって頑張ったわけだし、それ以外にも実験的な文体を採用した作家たちはいる
それが「硯友社」と呼ばれる文学結社の連中だ。
硯友社は、『金色夜叉』で有名な「尾崎紅葉」を中心とした結社で、その頃「写実主義」の逆サイドで勢力を拡大してきていた。
彼らは「擬古典主義」(古典に回帰しよう)という文学理念を掲げて、文学活動をしていたのだが、文体は逍遙らの「写実」を採用していた。
その硯友社の中から、「言文一致」を試みた代表的な作家と作品に、
- 尾崎紅葉 『多情多恨』
- 山田美妙 『夏木立』
あたりが挙げられる。
しかも、彼らは二葉亭四迷が採用した文体とは異なる文体で実験的な創作に挑んだ。
その辺をまとめると、次のようになる。
・二葉亭四迷…「~だ調」を採用 ・山田美妙…「~です調」を採用 ・尾崎紅葉…「~である調」を採用
ここで出そろった3つで、現代の文体の原型が生まれたといっていい。
こうして二葉亭四迷が挑んだ「言文一致」は、時代的な一大ムーブメントとして広がり、以降の作家や作品に大きな影響を与えていった。
スポンサーリンク
小説『浮雲』について
あらすじ
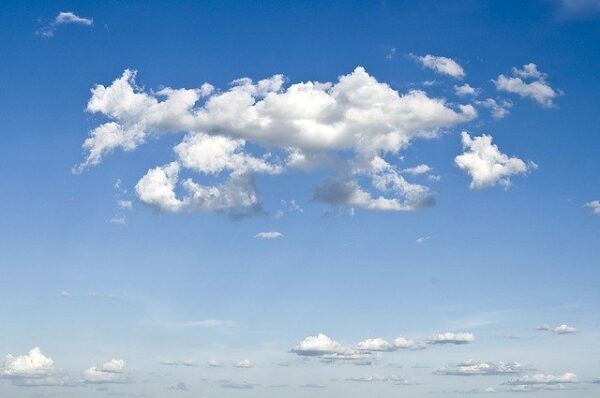
最後に代表作『浮雲』について紹介したい。
あらすじを簡単にまとめると、こんな感じだ。
・主人公「内海文三」は大学を卒業し、官吏の職を得る。 ・文三には思いを寄せる女性がいた。 ・彼女の名前は「お勢」 ・文三の家族も、2人を結婚させようと思っていた。 ・だが、あるとき文三は上司に逆らったことで失職してしまう。 ・当然、2人の結婚にはストップがかかる。 ・そこに表れた「本田」という恋のライバル。 ・彼は文三の同僚だったが、要領も給料も文三よりも上。 ・そんな本田とお勢が、次第に親しくなっていく。 ・やがて文三と本田は絶交。 ・だけど、お勢は本田と距離を取るようになる。 ・それはなぜか? ・文三とお勢の本心は? ・本田とは一体何者なのか? ・この三角関係、一体どうなっていくのか?
……と、いうところで四迷は筆を置き『浮雲』は未完のまま終わる。
「未完」となった3つの理由

さぁ物語はいよいよ佳境に! というこの絶妙なタイミングで、なぜ四迷は『浮雲』を投げ出してしまったのだろうか。
その原因を四迷は語らなかったので、結局のところ彼本人にしか分からない。
ただ、『浮雲』を完成させなかった理由について、多くの評論家が議論を展開している。
その辺りを整理すると、およそ次の3つになる。
- 経済的な理由で執筆を諦めた
- 自分の才能のなさに絶望した
- 存在論的に執筆が苦しくなった
まず1つ目「経済的な理由で執筆を諦めた」について。
これはシンプルで分かりやすい。
作家の社会的地位の低さについては、「くたばってしまえ」の件ですでに紹介した。
実際、『浮雲』だけでは食っていけなかった四迷。
筆を絶ってからは職を転々として、食いぶちをつないでいることからも、経済的な理由は少なからずあったと思われる。
次に2つ目「自分の才能のなさに絶望した」について。
厳密に言い直せば、
どんなにがんばっても、ロシア文学は越えられないことを悟った
ということになる。
そもそも彼が文学の道に入ったのがトルストイやドストエフスキーなどの「ロシア文学」に魅せられたからだった。
しかし、それらの作品に比肩できる作家は、日本文学史上に何人いるのだろうか。
まぁ、目指すハードルが高すぎるといってしまえばそれまでなのだが、とにかく彼の夢は「ロシア文学」を凌駕することだったのだ。
結局彼は、創作の途中で自信を喪失。
『浮雲』では、ロシア文学を越えられない
そうした思いから、筆を絶ったというワケだ。
確かにもともと「生真面目」で「理想が高い」四迷のことなので、これも説としては妥当と思われる。
最後に3つ目「存在論的に執筆が苦しくなった」
個人的には、僕はこの説が好きだ。
この理由は「言文一致」の“さだめ”とも言える。
改めて確認すると、「言文一致体」とは、作者の「内面」を的確に描くことできる文体だった。
それだけに、「言文一致体」で執筆をすることで、作者自身も「作品」にのめりこんでいくことになる。
もっといえば、作者は登場人物と「同一化」していくことになるのだ。
『浮雲』で書かれているのは「文三」の自己矛盾であり 苦悩であり 孤独である。
いつしか、四迷は文三に自分自身を投影していき、文三の諸問題を自らの問題として重く引き受けていってしまったのだろう。
実際に『浮雲』の第1編~2編では、ところどころにユーモアが差し挟まれていて、作品の雰囲気もいくぶんか明るい。
ところが、第3編になるとそういった明るさは急に失われ、作品はどんどん深刻になっていく。
この変化は、作者である四迷の精神的な変化だと思われる。
彼は『浮雲』を書き進めることで、どんどん苦悩し、どんどん孤独になっていったと思われる。
これは現代にも通用する「作家あるある」だと思うのだが、小説を書いていると登場人物と同一化してしまい、苦しくなってしまうというのはよくあること。
また、思想家の「柄谷行人」は、名著『日本近代文学の起源』において、
「言文一致によって、作者は内面を新たに発見していく」
という、とても興味深い論考を残している。
『浮雲』執筆は、まさに四迷にとって存在論的な苦しみを生む営みとなっていったのだろう。
書けば書くほど苦しくなり、苦しめば苦しむほど「文三」は追い詰められていき、「文三」が追い詰められれば追い詰められるほど、作者の苦悩は深くなる。
この負のスパイラルから解放されるために、四迷は『浮雲』から距離を取らなければならなかった。
これは「近代文学」一般の宿命と言って良いかもしれない。
日本の近代文学史を見渡せば、多くの作家の苦悩を見て取ることができる。
あるものは精神を損ない、あるものは酒や薬に溺れ、あるものは自死をしていった。
これは江戸以前にはほとんど見られない現象だ。
もし、「作家の苦悩」というものがあるとすれば、その1つに「言文一致」に由来する苦悩があるのかもしれない。
日本文学史に残る沢山の「傑作」の背景に、「創作」に伴う苦しみがあるとすれば、そこには「言文一致」にともなう「自己同一化」があるのかもしれない。
とするならば、二葉亭四迷とはある意味「因果」な作家だということができるだろう。
日本文学を学びたい人へ

この記事にたどり着いた方の多くは、おそらく「日本文学」に興味がある方だと思う。
日本文学の歴史というのは結構複雑で、「〇〇主義」とか「〇〇派」とか、それらの関係をきちんと整理することが難しい。
そこでオススメしたいのが、日本文学者「ドナルド・キーン」の代表作『日本文学の歴史』シリーズだ。
日本文学史の流れはもちろん、各作家の生涯や文学観、代表作などを丁寧に解説してくれる。
解説の端々にドナルド・キーンの日本文学への深い愛情と鋭い洞察が光っていて、「日本文学とは何か」を深く理解することができる。
古代・中世編(全6巻)は奈良時代から安土桃山時代の文学を解説したもので、近世編(全2巻)は江戸時代の文学を解説したもので、近現代編(全9巻)は明治時代から戦後までの文学を解説したものだ。
本書を読めば、間違いなくその辺の文学部の学生よりも日本文学を語ることができるようになるし、文学を学びたい人であれば、ぜひ全巻手元に置いておきたい。
ちなみに、文学部出身の僕も「日本文学をもっと学びたい」と思い、このシリーズを大人買いしたクチだ。
この記事の多くも本書を参考にしていて、今でもドナルド・キーンの書籍からは多くのことを学ばせてもらっている。
「Audible」で近代文学が聴き放題

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、夏目漱石や、谷崎潤一郎、志賀直哉、芥川龍之介、太宰治など 日本近代文学 の代表作品・人気作品が 月額1500円で“聴き放題”。
対象のタイトルは非常に多く、日本近代文学の勘所は 問題なく押さえることができる。
その他にも 現代の純文学、エンタメ小説、海外文学、哲学書、宗教書、新書、ビジネス書などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。
これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。
・
・
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、気軽に試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・




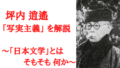

コメント