はじめに「真理は絶対ある」

西洋哲学の歴史を解説するこのシリーズ。
今回は「ソクラテスの哲学」について解説をしたい。
ソクラテスの登場が「哲学史」に与えた影響は大きい。
「真理なんて人それぞれ」といった「相対主義」が世に広まる中で「真理や普遍的な価値は必ずあるんだ!」と、彼は自らの哲学を貫き、そして自らの運命を受け入れた。
この記事では、そんな「ソクラテスの哲学」ついて分かりやすく解説をしていきたい。
お時間のあるかたは、ぜひ最後までお付き合いください。
ソフィストの時代
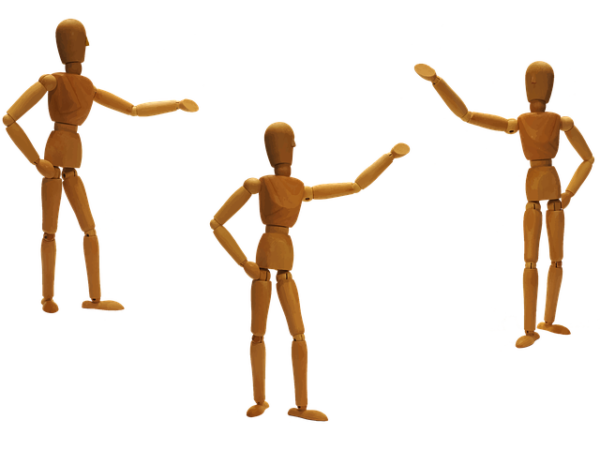
ソクラテスが活躍したのは、紀元前5世紀頃。
場所は「アテネ」という都市国家。
当時のアテネでは、幅を利かせている連中がいた。
それは「ソフィスト」と呼ばれる知識人たちだった。
ソフィストが「哲学界」にどんな影響を与えたのかについては、こちらの記事【 解説【プロタゴラスとゴルギアスの哲学」を分かりやすくーソフィストの功罪とはー 】を参照してほしいのだが、それを一言でいうならば「思想の堕落」である。
ソフィストたちが共通して持っていた考えは、
「結局、価値観なんて人それぞれ。真理なんてこの世に存在しないよね」
というものだった。
これを「相対主義」と呼ぶのだが、これによって人々の哲学的な情熱は急速に失われ、彼らの関心は「真理の探究」から離れていってしまった。
じゃあ、その関心がどこに向かったのかというと「自分の考えをいかにして“真理っぽく”見せるか」である。
“真理”なんてものが存在しないのであれば、その考えが正しいかどうかは「議論での勝敗」に委ねなれてしまう。
議論で勝ちさえすれば、世間から「あの人が正しい!」「あの人こそ知者だ!」と認められるというワケだ。
だから、人々は「真理の探究」なんてそっちのけで、「弁論術」や「修辞法(レトリック)」など「自分の主張を、いかに真理っぽく見せるか」の技術の習得にやっきになっていった。
――思想の堕落――
ソクラテスは、そんな時代に生まれた。
スポンサーリンク
デルフォイの神託

石工の父と助産師の母との間に生まれたソクラテス。
3度の戦役で従軍をしたほかは、もっぱら人々との「対話」を繰り返していた。
「申し分もなく変わった人間」と言われていた彼。
その理由の一つは、彼が老若男女問わず、あらゆる人との対話に執着していたからに他ならない。
対話の場となったのは、「アゴラ」と呼ばれる公共の広場。
そこは、年齢、国籍、身分、なにもかもバラバラな人々が集まる場所だ。
ソクラテスは頻繁にアゴラを訪れるや、とにかく沢山の人と対話を交わした。
それは、ソクラテスには、
「俺にはなんにも分からない」
という確たる思いがあって、
「とにかく本当のことが知りたい!」
という強い情熱があったからだった。
当時のアテネには「人気さえ取れれば良い」と「弁論術」ばかりを学ぶ若者たちがあふれ、また、そうした若者たちを食い物にするように、高額で「弁論術」を教える「ソフィスト」がはびこっていた。
そんな彼らをしり目に、ソクラテスは「真理が知りたい!」という一心で、人々との対話にいそしんだ。
始めは、「いちソフィスト」くらいにみなされていたソクラテスだったが、やがて、アテネにはこんな噂が広がる。
――ソクラテスこそが、本当の知者だ――
もちろん、ソクラテスは「僕はなんでも知ってますよ」とか「僕は真理を発見しましたよ」とか、そんなことを吹聴していたわけではない。
そんなこと、口が裂けたって、彼は言うはずがないのだ。
むしろその逆で、彼は「僕はなんにも知らないんですよ」と繰り返しながら、多くの人々と対話をしていたのだった。
そんなソクラテスの「知的に謙虚な態度」に触れた人々は、次第にこう思うようになる。
「その辺の知ったかソフィストなんかよりも、ソクラテスのほうがずっと偉大だぞ」
こうしてソクラテスに対する評価や信頼はグングンと高まっていった。
そんなある日、ソクラテスは友人で弟子の「カイレポン」から、こんなことを言われる。
「あのさ、こないだ、デルフォイに行ったんだけど……」
“デルフォイ”というのは、古代ギリシアで「世界のへそ」と言われた聖域である。
そこには太陽神を祭る「アポロン神殿」があって、人々はそこで神の言葉(神託)を得ていた。
神託は、結婚、病気、商売など「個人的な問題」にとどまらず、祭儀、戦争、政治など「公的な問題」など多岐に渡っており、人々はそれら神託を重く捉えていた。
「そのデルフォイで、おれ、神託を受けたんだけど……」
カイレポンが受けた神託、それがあの、
――ソクラテス以上に賢い者はいない――
というものだった。
いやいやいやいやいやー、そんなはずありませんから!
ソクラテスは、率直にそう思った。
だって、彼の胸には、
「俺にはなにも分からない」
という思いが強くあるのだから。
スポンサーリンク
問答法(産婆術)

“デルフォイの神託”すなわち、
――ソクラテス以上に賢い者はいない――
という言葉は、ソクラテスにとって到底信じられるものではなかった。
「俺ほど知に疎く、賢者から遠い者はいないはずなのに……」
自問自答を繰り返すソクラテス。
「やっぱ、解せねえ……」
だがそのとき、ふと、ある言葉を思い出す。
――汝自身を知れ――
これも、あのデルフォイのアポロン神殿の入り口に掲げられた言葉だった。
「俺は俺自身を知らない……ならば、ちょっと試してみようか」
そう思いついたソクラテスは、再び、あのアゴラに出かける。
そこで彼が行ったのが、世の中で「知者」と呼ばれている、あの「ソフィスト」との対話だった。
ソフィストとの対話の中で、“デルフォイの神託”の真相が分かるかもしれない。
「あの……」
1人のソフィストに声をかけるソクラテス。
「なんだ?」
ソクラテスは、自分自身にとって最大の謎を相手にぶつけた。
「“正義”って何ですか?」
すると、ソフィストは間髪入れず、こう答えた。
「国家にとって“善い行い”をすることだ」
「あの、全然分からないんですけど。“善い行い”って何ですか?」
ソフィストは、不愉快げに眉間にシワを寄せる。
「善いってのは……そりゃ、人々の“幸せ”を実現することだろ」
「いやいや、全然分かりません。その“幸せ”って何なんですか?」
返事に窮してしまうソフィスト。
そんな彼にソクラテスは言う。
「結局のところ、あなたは“幸せ”も“善い”も“正義”も、何一つ分からないのですね。それなのに、ソフィスト(知者)を自称している。まずは、その傲慢さを理解しなければいけないようですね」
こうしてソクラテスは、公衆の面前で、そのソフィストを完膚なきまでにやり込めてしまった。
その後もソクラテスは「知識人」と呼ばれる人々と、数々の議論を繰り返した。
彼の相手は「ソフィスト」だけに限らない。
たとえば「政治家」
たとえば「詩人」
政治家は「正義」について、詩人は「美」について、それぞれ何一つ知らないくせに「物知り顔」で講釈を垂れている。
ソクラテスは、そうした連中の「無知」を「問答」を通じて次々と暴いていった。
これが、ソクラテスの有名な「問答法」である。
問答法とは、質問を重ねることで 各個人が抱いている主張や意見の根底にある「無知」や「矛盾」をあぶり出す方法のこと。
だけど、ここで急いで強調したいことがある。
ソクラテスは「問答法」を通じて、相手を論破したかった訳ではない。
議論に勝って、満足感や優越感に浸りたかった訳ではない。
ソクラテスは、ただただ「真理」が知りたかったのだ。
多くの人に“自らの無知”を自覚してもらい、そこから共に「真理」を探究していきたかったのだ。
だからこそ、この「問答法」を、ソクラテス自身は「産婆術」と呼んだ。
このネーミングはソクラテスの母が「助産師」であったことに因んでもいるが、ソクラテスの次のような意識が表れているといっていい。
「俺は相手の内から“真理への探究心”を取り上げる“産婆”のような存在だ」
「俺が人々に“真理”を教えるんじゃない。“真理”は1人1人が自ら目覚めるものなんだ」
繰り返すが、ソクラテスは相手を負かしたかったのではなく、ただただ人々と「真理」について探求したかったのだ。
「問答法」には「ソクラテス的アイロニー」という別名がある。
直訳すると「ソクラテスの皮肉」となるこのネーミング。
まるでソクラテスに“悪意”があるかのような言い方なので、僕は「問答法」の本質からズレた不適切な表現だと思っている。
とはいえ、事実ソクラテスの「問答」を“悪意”と捉えた人々は多かった。
「公衆の面前で、恥をかかせやがって」
そう思った人々の悪意や怨恨が、結果的にソクラテスを死に追い込むのだが、それについては後述する。
スポンサードリンク
無知の自覚

人というのは「自分は不完全だ」と思うからこそ、その欠落を埋めるため「知恵」を求めるもの。
なぜソクラテスが「問答」や「対話」を続けたのかといえば、彼が「俺は無知だ」という強烈な“欠落感”を抱いていたからである。
だけど、人々との「問答」や「対話」を繰り返す中で、ソクラテスはあることを思い始めていた。
それは、
「俺は“自分が無知である”と思っている。一方で、他の人々は“自分は無知でない”と思っている。この差はとてつもなく大きいのでは?」
いつものようにソフィストと対話をした帰り道、ソクラテスは次のように考えた。
私のほうが、この男より知恵がある。この男も私も、おそらく善美のことがらは何も知らないらしいけれど、この男は知らないのになにか知っているように思っている。私は知らないので、そのとおり知らないと思っている。だから、つまり、このちょっとしたことで、私のほうが知恵があることになるらしい。つまり、わたしは知らないことは知らないと思う。ただそれだけのことで、まさっているらしいのです。
『弁明』より
このソクラテスの態度は、一般的に「無知の知」として知られるものだ。
が、「無知の知」という表現は実は誤りで、本来は「無知の自覚」とすべきなのだ。
というのも、上記をよく見てみると、
「わたしは知らないと思っている」とか、
「わたしのほうが知恵があることになるらしい」とか、
「わたしのほうがまさっているらしい」とか、
こんな風にソクラテスは「思う」とか「らしい」とか繰り返し、「俺は無知だ」ということすら保留していることが分かるからだ。
たとえば「おれは自分が無知であることを知っている」そう言ってしまったとしたら、その瞬間、彼は「無知」ではなくなってしまう。
なぜなら、無知であることを「知っている」からだ。
これは別に言葉遊びなんかじゃない。
これは、ソクラテスの徹底した知的謙虚さの表れなのである。
もしもソクラテスが「俺は無知だと知っている」と確信した場合、それはそのまま「俺は他の連中よりも、知者である」という確信につながってしまう。
その瞬間、きっと彼の「真理の探究」の歩みは止まってしまうだろう。
だって「自分は無知である」という1つの“真理”を“悟った”ことになるのだから。
だから「無知の知」は、ソクラテスの知的謙虚さを損なう間違った訳語であって、本当は「無知の自覚」というべきなのである。
ソクラテスはあくまで「自分は無知だ」と思っているのだ。
そんな彼の思いを代弁するなら、
「みんな平気で知ったかぶりしてるけど、それが俺には信じられない。俺はそんなこと絶対にできっこない。その点が、俺とみんなとの違いなんだろうな、きっと」
と、こんなところなのだろう。
だけど、その「思い」や「自覚」があるからこそ、彼は飽くまで「真理とは何か」を追い求め続ける。
「無知の自覚」こそ、彼の哲学の原動力なのである。
スポンサーリンク
ソクラテスの凄さ

改めていうまでもなく「ソクラテス」は、古代ギリシアを代表する哲学者である。
だけどそもそも、ソクラテスは「ソフィスト」や「かつての哲学者たち」と一体何が違ったのだろう。
まず1点目は、あくなき「真理への探究心」があった点である。
「哲学」はギリシア語で「フィロソフィア」という。
フィロは「愛する」、ソフィアは「知」という意味だ。
世間で幅を利かせていた「ソフィスト」
日本語で「知者」の意を持つ彼らは「俺は何でも知っている」といってはばからなかった。
しかも、彼らは「相対主義」をとなえ、「真理なんて人それぞれ」という立場から、思想の堕落を招きもした。
そんな彼らに対して、ソクラテスはこう反発する。
「“真理”は必ずある。普遍的な“善”や“美”というものを、明らかにするべきだ」
こんなふうに、ソクラテスは「知」を「愛した」人間だった。
「フィロソフィスト」とは「愛知者」の意であり、「俺は何も知らない」と知的謙虚な姿勢でもって、真理を探究し続ける人間を指す。
「愛知」の別名が「哲学」であるとすれば、ソクラテスという男こそ「哲学者」だということになる。
ここに、ソフィストとソクラテスとの決定的な違いがある。
次に2点目は、自らの関心が「世界の根本原理(アルケー)」にではなく、「人間の生き方」にあった点だ。
ソクラテス以前の哲学といえば、タレスとかヘラクレイトスに代表される、いわゆる「イオニア自然学派」が大きな勢力を誇っていた。
【 参考記事➀ 解説・考察【ミレトス学派とピタゴラスの哲学 】
【 参考記事➁ 解説・考察【ヘラクレイトスとパルメニデスの哲学 】
彼らの主な関心は「この世界は何でできているの?」というもの、つまりアルケー(世界の根本原理)である。
それに対して、ソクラテスの関心は、
- 正義とは何か
- 善とは何か
- 幸福とは何か
といったものであり、要するにそれらは、
「人間は、いかにして生きるべきか」
という問いに集約される。
つまり、ソクラテス以前の哲学が「自然」や「世界」に関心を向けていたのに対して、ソクラテスは初めて「人間」に関心を向けたと言うことができる。
ソクラテスの登場によって、哲学は「存在論」に加えて「倫理学」という領域を獲得したことになる。
これは、哲学史における大きなターニングポイントだといっていい。
以上、ソクラテスの凄さは、
- 「真理」への飽くなき探究心があったこと
- 哲学の射程を「人間」にまで広げたこと
この2点にまとめることができる。
スポンサーリンク
・
ソクラテスの哲学

ここまで、「ソクラテスの哲学への姿勢」や「ソクラテスが登場した哲学史的な意義」について確認をしてきた。
ここではいよいよ、ソクラテスの「思想」や「哲学」について、具体的に見ていきたい。
魂(プシュケー)の世話
「人間はいかにいきるべきか」
ソクラテスはその生涯をかけて、この問いに応え続けた。
多くの人々は言う、
「人間は、富とか、健康とか、名誉があれば幸せだ」
だが、ソクラテスはそうは考えなかった。
「たしかに、それらは人間を幸せにする可能性がある。だけど、それは“正しく”使われたときだけだ」
ソクラテスは次のように言う。
人々は、富、健康、名誉を求めて躍起になっている。
だけど、彼らは大切なモノを蔑ろにしている。
それは自分自身の「魂」である。
「よい魂」とは、富や健康、名誉などを正しく使い、幸せになるための大前提だ。
まず、人間がもっとも優先すべきは、自らの“魂”を磨くことなのだ、と。
これをソクラテスは「魂(プシュケー)の世話」と呼び、人間が正しく生きるために最も必要なことと考えた。
知徳合一(徳とは知恵を得ること)
では、いかにして人間は「魂の世話」ができるのか。
ソクラテスによれば「知恵を探求することで、魂は磨かれる」という。
それでは「知恵」とは具体的に何なのか。
それは、「真理」であり「善」であり「美」である
いわゆる「真・善・美」
これこそ、ソクラテスが最も大切にしたものであり、それを体得することが人間の「徳」であるとソクラテスは考えた。
以上をまとめると、
「真・善・美」=「知恵」=「徳」
ということになる。
これを「知徳合一」(知恵の体得は徳の体得である)と呼ぶ。
知行合一(知恵をえれば行動できる)
ただ、一口に「知恵を得る」といっても、そこには大きな問題がはらんでいる。
たとえば、あなたは「嘘をつくことは悪い」という知識を持っている。
あるときあなたは、親の大切な花瓶を割ったことをとがめられ、自己保身からとっさに嘘をついてしまった。
このとき、あなたの「嘘をつくことは悪い」という知識は、ソクラテスに言わせれば「偽物」ということになる。
要するに「頭で知ったような気になっているだけ」というわけだ。
ソクラテスによれば、「本当の知識」は必ず「行動」に結びつくという。
「嘘は悪いこと」と考えつつ、「嘘をつく」あなたは、知識を体得してはいないのだ。
もしも「正義」や「善い」という知識を得たとしたら、あなたはどんな状況下であっても、正しい行動ができるというわけだ。
「知識」=「行動」
これを「知行合一」(知識は必ず行動につながる)と呼ぶ。
福徳一致(幸福はつまり徳の体得だ)
ここまで読むと、ソクラテスが「真理とは何か」「善とは何か」「美とは何か」といった、「知恵」を最も重く見ていたことが分かる。
こうした「知」を哲学の根本に置く立場を、主知主義と呼ぶ。
その「知恵」を得ることこそ人間の「徳」であるという考えを、先ほど「知徳合一」として説明した。
さらに「知恵」を得た人間は、必ずその通りに「行動」できるという考えを、「知行合一」として説明した。
その2つを踏まえて、ソクラテスは次のように考える。
「知」を手に入れ「徳」を実現できたとき、人間は「幸福」を感じることができる。
つまり、
「知の体得」=「徳」=「幸福」
ということにある。
これを「福徳一致」(幸福とはつまり徳の体得だ)と呼ぶ。
まとめ
以上が、ソクラテスの哲学である。
まとめると、以下の通り。
1、人間は「魂(プシュケー)の世話」をしなければならない。 2、「魂の世話」とは、真・善・美についての「知識」を体得することである。 3、「知識」の体得は、「行動」につながる。(知行合一) 4、「知識」の体得は、「徳」につながる。(知徳合一) 5、「徳」の体得は、「幸福」につながる。(福徳一致)
スポンサーリンク
ソクラテスの最期

ソクラテスの死については、プラトン著『ソクラテスの弁明』に詳しい。
ソクラテスの人生の結末、それは、
「不当な裁判にかけられ、死刑を執行された」
というものである。
そもそも、なぜソクラテスは裁判にかけられたのか。
『ソクラテスの弁明』によれば、その理由は大きく次の2つ。
- 独自の神を信仰したこと。
- 若者を堕落させたこと。
まず1「独自の神を信仰したこと」について。
確かにソクラテスは「内なる声」として、しばしば「ダイモン」という神の声を聴くことがあり、実際にそれを重く受け止めていた。
当時のアテネでは、ギリシア神話にも登場する「オリンポスの神々」が信仰されていた。
そんな中にあって、ソクラテスはたびたび「ダイモン」の声を聞き、それに従って行動をしていた。
それに対して、人々は、
「ソクラテスは我々と異なる、奇怪な神を信仰している!」
と糾弾した。
つまり、ソクラテスは“宗教的犯罪者”として訴えられたのだった。
次に2「若者を堕落させたこと」について。
確かに、ソクラテスの人気は爆発的に広がり、多くの若者たちに影響を与えた。
ソクラテスに感化された若者たちは、彼同様に「対話」や「議論」を繰り返し、真理を熱心に探究した。
そんな中、アテネは「ペロポネソス戦争」で敗戦する。
その戦争で敵国に情報を漏洩させた若者がいたのだが、それが、ソクラテスの弟子だった。
また、衆愚政治や恐怖政治の筆頭となった政治家にも、ソクラテスの弟子がいた。
人々は、
「戦争に負けたのも、政治が腐敗したのも、ソクラテスが若者を堕落させたからだ!」
と、ソクラテスを糾弾した。
つまり、ソクラテスは“政治的犯罪者”として訴えられたのだった。
以上2つが、ソクラテスが裁判にかけられた大まかな理由だ。
ただ、それらは「表向き」の理由というべきものであって、彼が裁判にかけられた最大の理由は彼が「政治家たちの恨みを買ったから」だといっていい。
ソクラテスが「問答法」によって、多くの政治家たちの「無知」を暴いたことはすでに見た。
「問答」は常にアゴラなどの「公衆の面前」で行われたため、「人前で赤っ恥をかかせやがって」と逆恨みする連中は多かったという。
とはいえ、さすがに「ソクラテスが気にくわないから」なんて露骨な理由で、裁判にかけるわけにいかない。
そんな中、ソクラテスが「ダイモン」なる単一の神を信じていることや、弟子たちによる「敗戦」や「政治の腐敗」が口実として利用されたというわけだ。
ただ、ソクラテスもソクラテスだった。
裁判の中でそうした「不当さ」を主張したり、命乞いをしたりしたって良さそうなところ、そんな態度を一切見せず、あろうことか陪審員を挑発するような言動を繰り返したのだった。
陪審員を敵に回してしまったソクラテスには、当然のごとく死刑判決が下る。
ことの成り行きを見守っていた弟子や友人たちは、裁判の不正を憎み、ソクラテスの運命を嘆き悲しんだ。
友人の「クリトン」なんかは
「今ならまだ間に合う。金を積むなり脱獄するなりすれば、なんとか生き延びられるはずだ。頼むから命を粗末にしないでくれ」
と、ソクラテスを説得した。
ところが、ソクラテスは、
「不正に不正で答えてどうする。俺は判決に従う。悪法もまた法じゃないか。それに俺は、最期まで俺の正義に従いたいんだ。大切なのはただ生きることじゃない。善く生きることだ」
そう言って、彼は自分自身の「正義」を貫くのだった。(まさに知行合一!)
「それに・・・・・・」
ソクラテスはさらに続けた。
「確かに死は肉体の終わりなのかも知れない。だけど、それは魂の終わりを意味するわけじゃない。魂は不滅だ。決して死んだりはしない。俺は死など恐れない」
ソクラテスにとって、「死」とは悲観すべきものではなかったのだ。
むしろ、「死」は、肉体という牢獄からの解放であり、「魂の新生」ですらあった。
こうして周囲の説得をことごとく拒絶し、従容と毒杯をあおったソクラテス。
その直前の様子を伝える「ソクラテスの死」という名画がある

嘆き、悲しみ、うつむく弟子や友人たち。
それと対照的に、決然と天を指さし、毒杯を受け取るソクラテス。
「俺は死など恐れない」
そんなソクラテスの力強い声が聞こえてきそうな作品である。
スポンサーリンク
おわりに「プラトンという弟子」

以上、ソクラテスの哲学について解説を行ってきた。
ソフィストの登場により、堕落した思想界……
「真理なんて人それぞれ」
「普遍的価値なんて幻想にすぎない」
「大事なのは、真理っぽくみせること」
そんな空気が蔓延する中、彗星のごとく現れ、迷妄な文化人たちをバッタバッタと論破して、
「真理や普遍的な価値は必ずあるんだ!」
と、“哲学的情熱”を呼び込んだのが、まさにソクラテスその人だった。
西洋世界で一度消えかけた「思想の火」は、彼によってふたたび大きく灯されたことになる。
その「思想の火」に大量の燃料を注ぎ、西洋哲学の伝統を確立させた哲学史における「レジェンド」
それが、あのプラトンである。
――プラトンがいなければ、今の哲学も西洋世界も存在しない――
そういってたとしても、過言ではない。
ソクラテスの思想を受け継いだプラトンという弟子により、これ以降の哲学はいよいよ盛り上がりを見せていく。
【 詳しくはこちら 解説・考察【プラトンのイデア論】—魂の三文説、哲人王思想も分かりやすく説明— 】
以上で、記事はおしまいです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
【 哲学史の一覧はこちら 】 1、【ミレトス学派とピタゴラスの哲学】 2、【ヘラクレイトスとパルメニデス】 3、【デモクリトスの原子論】 4、【プロタゴラスとゴルギアスの哲学】 5、【ソクラテスの哲学・思想】 6、【プラトンのイデア論】
オススメ!ー”哲学”をするならー
初心者にオススメの本
「哲学を学んでみたいけど、1人ではむずかしい」
そんな悩みを持つ方に、超おすすめの本がこちら。
本書は西洋哲学について「古代」から「現代」まで網羅している。
それぞれの哲学の要点を分かりやすく、そして簡潔に、さらに可愛くまとめていて、初心者には自信をもってお勧めできる1冊だ。
とても人気のある本なので続編も出ている。
こちらは主に「日本の哲学」「中国思想」、そして現代哲学の主流である「分析哲学」が紹介されている。
これを読み切れば、東洋思想はもちろん、現代の西洋哲学における議論の要点をほぼ全て押さえることができるはず。
付録で「シリーズ1作目」の内容を簡単に紹介してくれるのもとても嬉しい。
哲学を学び始めるなら、この2冊はぜひ手元に置いておきたい。
“耳読書”「Audible」がオススメ

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、哲学書・思想書・宗教書が月額1500円で“聴き放題”。
例えば、以下のような「解説書」も聴き放題の対象だし……

・
以下のような「原著」も聴き放題の対象となっている。

・
それ以外にも純文学、エンタメ小説、海外文学、新書、ビジネス書、などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。
これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。
・
・
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、軽い気持ちで試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
.
・





コメント