はじめに
第165回芥川賞が、2021年7月14に発表された。
受賞作は2作品、そのうちの1つがこれ。
『貝に続く場所にて』(石沢麻依)
この記事では本書の「あらすじ」と「登場人物」をまとめ、「テーマ」について考察したい。
あらすじ

- 舞台は、震災から9年後、「コロナ禍」のドイツ。
- ある日、主人公「私」のもとに知人からメールが届く。
- メールによれば、「野宮がゲッティンゲンにくる」という。
- 実際に「私」がゲッティンゲン駅にいくと、そこには野宮がいた。
- ただ、野宮は9年前の東日本大震災に遭い、そのまま「行方不明」になっていたはず。
- 目の前の野宮は「死者」なのか「生者」なのか「幽霊」なのか
- 野宮の突然の登場により、「私」は9年前の震災の光景や死者について想う。
登場人物の紹介

小峰里美(私) 語り手。ドイツのゲッティンゲンに留学中。大学で西洋美術史を専攻している。東日本大震災を経験。
野宮 東日本大震災で行方不明になったきり、見つかっていない。ゲッディンゲンに住む「私」のもとに現れる。
澤田 野宮の大学時代の同期。「野宮がゲッティンゲンにくる」ことを「私」に知らせる。東日本大震災を経験。
晶紀子 「私」の大学時代の同期。現在はベルギーに住んでいる。東日本大震災を経験。
アガータ 「私」の同居人。現在情報学を学んでいる。母を自殺でなくしている。
ウルスラ ドイツ語と文学の元教師。「木曜」になると、多くの人が彼女を訪れる。
アグネス 12歳の少女。ウルスラのもとを訪ねる1人。
バルバラ アグネスの母。
カタリナ 修士学生。専攻は哲学。
ルチア ウルスラのもとを訪ねる1人。
寺田 物理学者。野宮と知り合う。
作品の特徴

作者 石沢麻依は、トントン拍子に、芥川賞を受賞した。
- 2021年5月「群像新人文学賞」を受賞しデビュー。
- 2021年6月「芥川賞」ノミネート
- 2021年7月「芥川賞」受賞。
ってな感じ。
文字通り、「トン・トン・トン」である。
それは、この作品が文壇において、きわめて高く評価されたということでもある。
実際に、選考会では、『貝に続く場所にて』への評価は高く、ほとんど揺らぐこともなかったという。
「デビュー作にして、芥川賞受賞」というのは、けっこう久しぶりではないだろうか。
調べてみると、若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』以来の、約4年ぶりということになる。
さて、そんな、期待が高まる『貝に続く場所にて』……
誤解を恐れず、まず、はっきりいってしまおう。
かなり、とっつきにくい作品だと思う。
芥川賞は人並み以上には読んできたぼくだけど、そんなぼくにとっても、近年まれに見るくらいに読みづらく、難解な作品だった。
「あー、わかりました、じゃあもういいです」
と、記事を閉じかけた人は、ちょっと待って。
話しはここからなので、どうか、もう少しお付き合いを願いたい。
この作品は、確かにとっつきにくい作品ではある。
だけど、現代を生きるぼくたちに、強烈な問題提起をしている作品でもある。
それについて、この記事ではきちんと書いていこうと思う。
だから、もうちょっと我慢して読んでほしい。
とはいえ、「とっつきにくい点」に関して、まず以下に簡単にまとめてみる。
- 文章がギュウギュウに詰まっている点
- 比喩的・暗示的な文体が採用されている点
- 西洋美術の教養がふんだんに盛り込まれている点
- 「テーマ」がシンボリックに語られる点
簡単に説明しよう。
まず、1について
本を手に取ってパラパラめくってみればすぐに分かる。
ページは151ページと、長くはないのだけど、ほとんど改行がない。
活字がギッシリなのだ。
読書になじみのない人であれば、たぶん10ページくらいで本を閉じてしまうかもしれない。
続いて、2について
作品の冒頭を引用することで説明に代えたい。
以下は、「私」が、ゲッティンゲンの街で、9年前に行方不明になったはずの「野宮」を待っているシーンだ。
人気のない駅舎の陰に立って、私は半ば顔の消えた来訪者を待ち続けていた。記憶をさらって顔の像を何とか結び合わせても、それはすぐに水のようにくずれてゆく。それでも、断片を集めて輪郭の内側に押し込んで、つぎはぎの肖像を作り出す。その反復は、疼く歯を舌で探る行為と似た臆病な感覚に満ちていた。
と、こんな感じだ。
これが、ほとんど改行なく、151ページにわたって続いていくことになる。
とはいえ、選考会では、この文体が高く評価された。
ぼくも、この文体に好感を持った1人だ。
とはいえ、万人受けする文体ではない。
続いて、3について
個人的には、ぼくはこれがきつかった。
少なからず文学作品には、その作者の専門性とか教養とかが語られるものだ。
だけど、この作品は、それがさすがに多すぎる。
ではその「教養」とは何かというと、「西洋美術」にまつわるあれこれである。
ぼくは西洋美術に興味がない(断言)。
だから、そんなぼくなので、正直、カナリきつかった。
もちろんこれは、ぼくの「絵画」や「彫刻」に関する造詣の浅さを棚上げした意見だ。
ただ、ほとんどの人が、この世界観についていくのは、厳しいんじゃないかと思う。
ちなみに、こういうペダンチックな作品が受賞した例は過去にも結構ある。
有名どころだと、平野啓一郎の『日蝕』があげられる。
あの時も、ペダンチックな内容が、読者の間で賛否を生んだ。
あの作品も 結構キツかったけど、この作品も 結構キツイ。
とはいえ、群像新人文学賞の選考委員の島田雅彦は、
人文的教養溢れる大人の傑作
と、絶賛しているので、分かる人には分かるのだろう(だから、ぼくが悪いんだと思う)。
最後に4つ目
この点に関しては、以下、詳しく考察していきたい。
テーマに関しては、正直言って言って、ぼんやり読んでいたのでは掴むことはできないだろう。
それくらい暗示的、象徴的に書かれている。
だけど、一方で、ここが作品の魅力でもあると、ぼくは考えている。
この作品はテーマをストレートに語るのではなく、象徴的・暗示的に語ることで、芸術性や文学性を高めている。
では、そのテーマとは一体なにか。
この作品をつらぬく大きなテーマは、いうまでもなく「東日本大震災」である。
だけど、「震災の悲惨さ」とか「震災のむごたらしさ」とか、もっといえば「感動的なヒューマンドラマ」なんかは、全く語られてはいない。
では、「震災」について、何が語られているのだろうか。
それは、
- 時間とともに風化していく記憶
- 記憶を呼び覚ます「物」
- 生者と死者のつながり
である。
そして これらを、
「震災後10年」
「コロナ禍」
という文脈で、もう一度見つめてみると、この作品が、ぼくたちに向けて、強烈な問題提起をしていることが少しずつ見えてくるのだ。

考察① 風化していく記憶

この作品のキーマンは、なんといっても野宮だ。
彼は東日本大震災で死んでいる(厳密には行方不明)。
そんな彼が、震災を経験し今も生き延びている「私」の目の前に現れた。
これは、いったい、何を暗示しているのか。
「私と野宮が出会うこと」これは、
「生者と死者が出会うと」と言い換えられる。
なにを、当たり前のことを、
と感じる人も多いとは思うが、あえて、もう少し続けさせてほしい。
「私と野宮が対話すること」これは、
「生者と死者が対話すること」である。
「私が野宮の声を聴くこと」これは、
「生者が死者の声を聴くこと」である。
「私が野宮について考えること」これは、
「生者が死者について考えること」である。
さすがに しつこいので この辺りでやめるが、「じゃあ、実際、ぼくたちはどうだろう」と考えてみてほしい。
震災後10年(作中では9年)が経過した今、
コロナ禍で、毎日人々がなくなっていく今、
あなたは死者と出会っているだろうか。
あなたは死者と対話しているだろうか。
あなたは死者の声を聴いているだろうか。
あなたは死者について考えているだろうか。
そう問われて、自信をもって「はい」と答えられる人は、きっと多くはない。
作中で、「メメント・モリ」という言葉が使われている。
増え続けるコロナ禍の死や、9年前に震災で海に消えた野宮など、いくつもの死の印象や記憶が頭の中を過る。メメント・モリ。死を忘れることなかれ。(P63より)
「メメント・モリ」とは、ラテン語で「死を忘れるな」という。
芸術や、文学、哲学など、あらゆる分野のモチーフとして使われる言葉だ。
とはいえ、「死を忘れるな」といわれても、それはとてつもなく難しいことだ。
なぜなら、「死と向き合うこと」には、必ず「痛み」が伴うからだ。
そんな「痛み」は、作中で「歯」というシンボルで描かれている。
ある朝、目が覚めると、背中に歯が生えていることに気づいた。(P105)
え? 背中に? 歯が? 急に?
といった印象を受けるシーン。
まあ、この作品は 「死者が現れる」話なので、そもそもが幻想文学っぽくはあるのだけど、それでもこのシーンは唐突なので、非常に印象的に映る。
「私」は、すぐにこの「歯」を抜くのだけど、その跡にはズキズキと痛みが残る。
この「歯」とは、一体何か。
災害時「歯」は、「個人特定の材料」になる(と作中で紹介されている)。
そこで、「私」もとっさに、「これは野宮の歯なのだろうか」と考える。
さらに、抜かれた「歯」について、「私」はこう考える。
記憶の歯 (P108より)
つまり、「歯」とは「死者にまつわる記憶」を象徴していると思われる。
そして、生えてきた「歯」には、痛みがともなう。
同様に、「死者」である野宮と向き合うことにも、痛みがともなう。
作中における「歯」とは、「生者と死者のつながり」について、そこから生まれる「精神的な痛み」について、シンボリックに語るものなのだと思われる。
野宮と連絡をとることはなかった。会わずにすむ理由を、いくつも数え上げるばかりだった。彼が来たのが別の街ならば、と恨みがましく思う度に、罪悪感にかられ、少しずつ感情の表面が削られていく。(P62)より
「私」は、野宮に遭うことを、野宮と対話することを、意識的に避けていた。
そんな「私」に「野宮の歯」が生えてきたのは、決して偶然ではない。
メメント・モリ ――死を忘れるな。
野宮は、「私」にそう伝えたかったのかもしれない。
スポンサーリンク
考察② 記憶を回復させる物

では、死者と向き合い、死者と対話するのは、どうやって可能なのだろうか。
もちろん、頭の中で死者について繰り返し考えることも可能だ。
だけど、それは、あくまでも観念的、抽象的な営みであって、生々しい「死者」を取り戻すことにはならない。
作中にもこうある。
言葉と感覚の距離感は、私の中でも渦巻いている。「戦争」「空襲」「噴火」などの言葉に対して、私は感覚を伴うイメージがあるわけではない。「津波」にしても私は感情的にこの言葉と結びついている気がするだけで、実際のところ画面越しか見ていない。(P41より)
「私」もそう考えるように、「言葉」や「思考」による想起には、ありありとした具体性や実在性が欠けている。
では、「死者」と向き合うために、どうすればいいというのか。
その可能性は「災害の跡(風景)」や「遺留品(物)」にある。
戦後活躍した「第三の新人」遠藤周作が似たようなことを言っていた。
彼はアウシュビッツを訪れたとき、その跡地や遺留品の数々を見て、強烈なめまいを感じたという。
囚人を運んだトロッコ、ガス室、死体焼却炉、囚人たちの義足、眼鏡、おもちゃ、靴……
それらが、強烈に遠藤周作を襲い、彼をとらえて離さなかった。
その日、ホテルに戻った遠藤周作は、自らの「靴」を捨てたという。
アウシュビッツを歩いた靴に、彼ら囚人たちの「記憶」をありありと感じたからだった。
ぼくも、囚人たちのおびただしい「靴」の画像を見たことがる。
画面越しであっても、その「靴」たちには、強烈に訴えかけてくるものがあった。
もし、実際にアウシュビッツに足を運び、ガス室や、死体焼却所や、おびただしい靴を目にしたとき、遠藤周作ほどじゃないにしても、ぼくだってめまいの1つを感じてしまうだろう。
ぼくは、先日、ニュースで「孤独死」をした男性について目にした。
テレビ画面には、彼の「死に場所」となったアパートの一室が映し出されていた。
そこにあふれる遺留品の数々。
ダイニングテーブルの上に散らばった沢山の食器。
一か所にグシャグシャに集められている衣類と、空きっぱなしのタンス。
シーツがしわくちゃになった敷布団と、黄ばんだ枕や掛布団。
そういう、沢山の「物」1つ1つには、その男性の「存在」の残滓といおうか、見ている人のむねに訴えてくる何かが湛えられていた。
それは死者の「声なき声」といえるかもしれない。
画面越しでもそうなのだ。
もし、現場へいって、その1つ1つと対峙した時、その「声なき声」は、よりいっそう強く感じられるのだろう。
作中において、「聖遺物容器」というものが取り上げられている。
聖遺物とは、キリストや聖母、聖人の遺骸や遺品を表す。身体の一部のほかに、身体に触れたものには聖性が宿るとみなされ、カトリックの信仰の中に組み込まれている。(P78より)
それらを収めるのが、聖遺物容器であるという。
そこには骨や歯の欠片、髪や衣服の切れ端などが入れられている。
その1つ1つに「聖性」が宿るという。
この「聖性」も「死者の声」と考えていい。
そして、そういう「死者の声」を持つ「物」の集積が、「被災地」である。
登場人物達は、被災地跡を訪れ、死者の記憶、物、風景について考える。
形をとどめなくなった物が堆積する場所を歩きながら、人の生きる場所にどれほどの物が組み合わさって形をなしていたか、そして人の生や時間がどれほど複雑に映し出されていたのか・・・・・・(P68より)
「被災地」というのは、「死者の声」を持つ「風景」だといえる。
そこは、ある「現実」を、人々に伝えてくる場でもある。
その「現実」というのは、「匿名の現実」ではない。
つまり、「死者〇〇人、行方不明者〇〇人、重軽傷者〇〇人」といった、「数」に還元できるような「現実」ではない。
作中において、その「現実の風景」は、
「顔」
と表現されている。
仙台東部道路をはさんだ土地の写真を見たとき、私の目の中にはこの二面の顔が重ね合わせられた。海に飲み込まれた場所と、津波が届くことのなかった場所、この2つは時間が経っても完全に戻ることはない。仮に建物や街が元通りに再建されたとしても、その下には2つに分け隔てられた顔が残り続けるのだ。
(中略)
匿名の報告や写真、影像にこめられた眼差しを表面的になぞっても、それは記憶ではなく印象を作り上げることしかできない。(P117より)
「顔」とは、唯一無二で、極めて具体的なものだ。
被災地というのも、そういう唯一性、具体性をそなえた場所だということなのだろう。
その背景にあるのは、言うまでもなく1人1人の「死者」の存在だ。
かつて、具体的な生活を送り、具体的な感情を持ち、具体的な物語を生きた、そういう「死者」たち。
「風景」の前に立ち、そんな1人の「死者の声」に耳を傾ける。
そうすることによって、生き残ったものたちは「死者」とのつながりを回復し、記憶の風化を防ぐことができるはず。
『貝に続く場所にて』は、ぼくたちに、そう訴えているのかもしれない。
スポンサーリンク
考察③ 生者と死者のつながり

これまで、確認してきたことは、
「風景」の前に立ち、「死者の声」に耳を傾けることで、「生者と死者とのつながり」を回復できるのではないか、
そういうことだった。
とはいえ、それはぼくたちにとって、とても難しい。
「死者の声」なんて、聞こえてこないよ!
身もふたもなくいえば、そんなところだろうか。
「死者」のことなんて、想像しても、想像しきれないよ!
こんなふうにも言えるだろうか。
その、難しさについては、作中でも語られる。
被災地を歩く「澤田」は、死者の「記憶」を持つ様々な遺留品を目にする。
しかし、彼には、それらの「具体性」を「死者」たちと共有することができない。
人形や靴、車や鞄、服や本、机に箪笥。それは単純な名詞ではなかった。そこにあるのは、時間からもぎ取られた人の過去の断片だった。澤田はそこに人を見ていた。
(中略)
しかし、その誰かでありながらも、彼には見知らぬ人たちの声の一部を目にしても、その記憶を共有することはできない。海水に濡れ泥にまみれた物、壊れてわずかに形を留めている物まで、見えない声として視覚的に捉えて、やがて彼の中で反響するが、それを聞き取って理解することはできない。耳を傾け続けても、そこから人の姿をおぼろにしか思い描けない。(P67より)
たとえ、風景に触れて、そこから「死者の声」に耳を傾けてみても、それを聴き取ることも、理解することもできない。
なぜなら、死者は、どこまでいっても自分にとって「他者」だからだ。
彼らの苦しみや悲しみを、自分が経験的に感覚的に、もっといえば「自分のものとして」理解することは、そもそも原理的にできっこない。
だけど、それは逆に、「死者との対話」には、終わりがないということでもある。
「死者」を100%理解できないが故に、「死者との対話」に終わりはない、
それは不断に続く営みであり、生き残った者は「死者」に思いを馳せ続けなければならないというのだ。
これは、実際、かなり厳しい指摘ではある。
ぼくが敬愛する批評家で詩人に、若松英輔という人がいる。
彼は多くの本で、「死者」について語っている。
彼はこう言っている。
死者は実在している。
以下で、そんな彼の言葉を紹介したい。
見えないことと、ないこととは違う。見えないが存在する、そうしたものが、わたしたちの人生をそこから支えているらしい。
『悲しみの秘義』より
すでに逝き、もう二度とその姿を認識することができないと思っていた人の存在を、悲しみの中に見いだしたとき、感じた。
姿は見えず、ふれることも、互いに言葉で語り合うこともできない。しかし、確かに実在する。悲しみのなかに生きている。
『悲しみの秘義』より
若松英輔によれば、「死者」も「死者の声」も、見えないからこそ、聞こえないからこそ、それは確かに実在するのだという。
「見えないからといって、死者が実在しないとは限らない」
「死者はこれまでと違った仕方で、実在している」
これらは、若松が繰り返し語る言葉だ。
そして、死者の声というのもまた、このようにな「声なき声」なのだろう。
たしかに、死者は見えない、その声もまた聞こえない。
だからといって、死者は実在しないと言い切ることはできない。
たとえば「物」を通して、たとえば「風景」を通して、
彼らは、生き残った者たちに、今もなお語りかけているのかもしれない。
その声に耳を傾け続けること、彼らの「断絶された記憶」に思いをはせ続けること。
それこそが、死者とのつながりを回復させることなのだと、ぼくはこの作品を読んで改めて感じた。
「死者の声」を聴くことは、それは「祈り」でもある。
「祈り」とは、いつだって「静寂」の中でなされるものだ。
だけど、それはただの「静寂」ではない。
そこにはか必ず「声なき声」があるはずだ。
さきに紹介した遠藤周作は、代表作『沈黙』においても、「祈り」と「声なき声」の関係に触れている。
この『貝に続く場所にて』もまた、「祈り」と「死者の声なき声」をテーマにしている。
東日本大震災から10年の今、
「コロナ」で日々、命が失われている今、
改めて、ぼくたちは「死者の声」に耳を傾けなければならない。
スポンサードリンク
考察④ 『貝に続く場所』が意味するもの

最後に、タイトルの「貝に続く場所にて」が意味するところを考察して、記事を終わりにしようと思う。
「貝」については、作中でこう紹介されている。
帆立貝は、野宮にとって彼の場所に続く道標なのかもしれない。
(中略)
漁港の賑わいや色鮮やかな生活の色、香ばしく焼ける匂い、彼の家族の声、そして海。
「貝」とは、野宮の場所に続く道標だという。
そして、野宮とは「死者」の象徴的存在だ。
つまり「貝に続く場所」というのは、「死者たち」との繋がりを回復できる場所ということなのだろう。
繰り返すが、そこは「死者の声なき声」が聞こえる場所だ。
つまり、本書のタイトルは、「生き残った者」の「祈り」を表現していると思われる。
ちなみに、本書の帯にはこうある。
静謐な「祈り」をこめて描く「鎮魂の物語」
「祈り」は分かる。
ただ、この「鎮魂」という言葉は、どうだろう・・・・・・
ぼくは、この作品にとって、「鎮魂」はもっともふさわしくない言葉だと感じた。
そもそも、死者の魂を鎮める「鎮魂」という言葉に、ぼくはあまり良い印象を持っていない。
なぜなら、「鎮魂」は、死者との対話に終止符をうつことだと、ぼくは思うからだ。
生きている者が感じる「居心地の悪さ」や、「わり切れなさ」や、「罪悪感」とか、そういう精神的な重荷を下ろすのが、「鎮魂」という発想だと思う。
そして、本書が人々に戒めていたもの、それこそが、「鎮魂」だとぼくは思う。
破壊された顔は、3月が訪れる度に、再生や復興という言葉で化粧が施されようとする。そのたびに、失われた顔は幽霊のように浮かび上がる。(P117より)
芥川賞の受賞会見で、作者は「復興」という言葉への違和感を語っていた。
そういう意味では、「鎮魂」もまた、大いに違和感がある言葉だといえる。
「鎮魂」とは、記憶の隠蔽であり、記憶の風化につながるものとさえ言える。
「鎮魂」でカタルシスを得るのは死者じゃない。
いつだって、生き残った者のほうだ。
ぼくたちは、死者を「鎮魂」して「死者の声」を封じてはいけない。
死者と向き合うこと、
そこには、もちろん、傷みはある。
だけど、死者は実在するのだから。
耳をすませば、死者の声がするのだから。
それを隠蔽してはいけない。
生き残った者の使命は、「死者」とともに生きることなのだろう。
オススメの本
『彼岸花が咲く島』(李琴峰)
『貝に続く場所にて』と同時受賞した作品。
こちらは比較的読みやすく、ミステリー仕立ての展開も読んでいて面白い。
また、「日本語」や「言語」についての問題意識も作品に表れている興味深い作品だ。
『彼岸花が咲く島』についてはこちらの記事で考察をしているので、よろしければ参考にしていただきたい。

”耳読書”「Audible」がおすすめ

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・

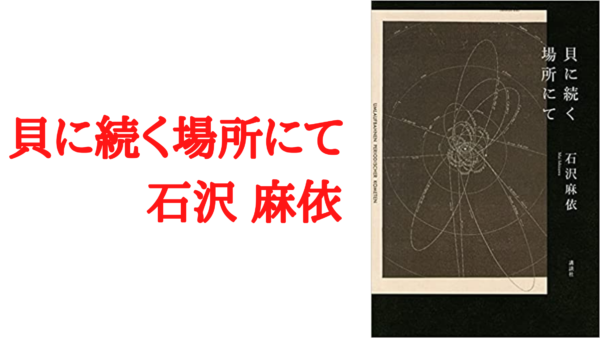



コメント