はじめに

芥川龍之介賞(通称「芥川賞」)は、日本でもっとも有名な文学賞といっても過言ではない。
1935年に芥川龍之介の友人である「菊池寛」によって創設された本賞は、これまでに多くの偉大な作家を輩出してきた。
あの太宰治が欲しくてほしくて仕方なかった本賞だが、小説を書く人であれば、誰しもが受賞を夢見る賞であることは間違いない。
この記事では、そんな芥川賞にまつわるおもしろエピソードや裏話なんかを紹介したい。
- マスコミが注目するようになったきっかけって?
- 選考委員が辞任するほどの過激作品って?
- 今でも語り継がれる芥川賞の黒歴史って?
こんな感じのエピソードを一挙に紹介していく。
この記事を最後まで読めば、きっと芥川賞への興味もいっそう増すはず。
お時間のある方はぜひ最後までお付き合いください。
“マスコミ”が注目したきっかけ

芥川賞ほどマスコミに取り上げられる文学賞は他にない。
候補作が出ればすぐに報じられるし、受賞会見はネットでライブ配信されるし、翌日のワイドショーで受賞が大きく取り上げられる。
お笑い芸人の又吉が受賞したときなど、様々なメディアが切り口を変えて様々な番組で取り上げていた。
では、そもそも芥川賞がマスコミに大体的に取り上げられるようになったのはいつからなのだろう。
結論を言えば、1955年の『太陽の季節』(石原慎太郎)の受賞からである。
石原慎太郎といえば、「元東京都知事」のイメージが強すぎるのだが、彼は芥川賞の選考で井上靖・川端康成に評価された、実力派の作家である。
第34回芥川賞を受賞した石原は一橋大学の学生で、まだあどけなさの残る可愛らしい青年だった。
だが、それとは打って変わり、作品はあまりにセンセーショナルだった。
『太陽の季節』を一言で言えば、「とにかくアンモラルな作品」である。
クラブ、ナンパに始まり、妊娠、中絶、死などはもちろん、果ては人身売買のような場面もありで、これまでの文学とは明らかに異質だった。
選考委員の間でも作品に対する評価は真っ二つに分かれ、強い嫌悪を示す選考委員もいた。
実際に、選考委員の佐藤春夫は作品の「反倫理的」な点を上げて、
「作者の美的節度の欠如に、嫌悪感を禁じ得なかった」
と痛烈に批判している。
「作者のイメージ」と「作品とのギャップ」
こうした事情が世間の興味を引き、マスコミも「芥川賞」を大々的に取り上げた。
そして出版されるや、『太陽の季節』は30万部の大ヒットを記録。
「太陽族」という流行語が生まれ、「慎太郎刈り」なるヘアスタイルが流行。
『太陽の季節』は映画化され、弟の石原裕次郎はそこで映画デビュー。
芥川賞史上において、ここまでセンセーショナルなデビューを飾った作家はいなかった。
そして、ここまで世間に「芥川賞」を知らしめた作家もいなかった。
そういう意味で、現代の「芥川賞」の知名度の高さには、間違いなく石原の功績がある。
史上№1の“天才”はだれか
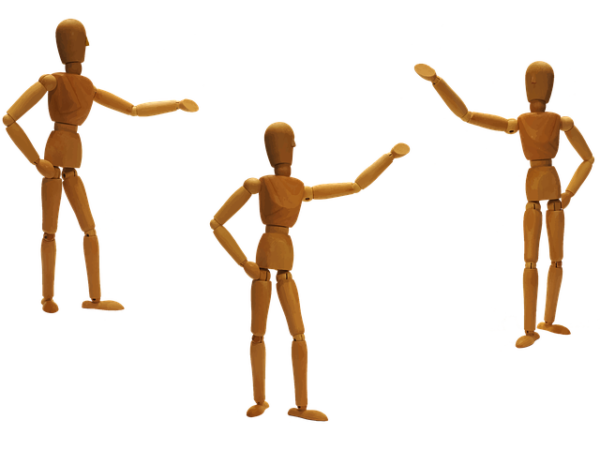
まず3人に厳選
芥川賞は「新人作家による優れた純文学を作品」を対象に与えられる賞なので、受賞する時点でその作家に才能があるのは間違いない。
では、芥川史上、もっとも才能のある、いわゆる「天才」作家とはだれなのだろう。
僕は次の3人を上げたいと思う。(文学好きであれば異論はないと思う)
- 阿部公房
- 古井由吉
- 大江健三郎
この甲乙つけがたい「神様レベル」の作家たちだが、あえて№1を決めるとすれば、ノーベル文学賞をとった大江健三郎ということになるだろう。
阿部公房と古井由吉は順番をつけがたいが、芥川賞受賞時のエピソードを踏まえて、僕は古井由吉を2番手にあげたいと思う。
したがって順位は次の通り。
- 3位 阿部公房
- 2位 古井由吉
- 1位 大江健三郎
それでは、順番に紹介しよう。
3位 阿部公房(1951年)
「東京大学医学部卒業」という学歴は、正真正銘、芥川賞史上№1
だが、卒業後、安部は国家試験を受けることなく、文学の道を志す。
そんな若き安部公房を発掘したのは、戦後文学を牽引した埴谷雄高だった。
彼の主催する『近代文学』で、安部は作品を発表し始める。
そして『壁』で、第25回芥川賞受賞。
ちなみに、この時の候補者には安岡章太郎、堀田前衛など、とてつもないライバルたちがいた。
安部公房の作品といえば、とにかく読み手の現実感を奪っていく不思議な力があり、その作風は「シュールレアリズム(超現実主義)」と呼ばれている。
シュールレアリズムとは、1920年代ころから戦後にかけて、主にフランスやドイツで流行した文学のことだが、阿部公房はそれを若くして日本で本格的に実践した初の作家だといっていい。
たとえば、カフカの『変身』とか、カミュの『異邦人』なんかもそうだけれど、突然 自分の身に訪れた「不条理」を描く作品というのは、これまでにもあった。
安部公房の受賞作『壁』もまた「不条理」を描く点では同じなのだが、これまでの既存の枠をさらに突き抜けた奇抜さがあり、まさしく現代版の「不条理文学」といえる。
そして、そんな阿部公房の作品はまたたくまに世界でも高く評価される。
実は阿部公房も当時から「ノーベル文学賞に近い作家」と言われていて、その評価は大江健三郎に決して劣ってはいなかった。
ちなみに、阿部公房が芥川賞を受賞した50年代というのは、間違いなく日本の現代文学の黄金期で、他の芥川賞受賞作品には、
- 『悪い仲間』安岡章太郎)1953年
- 『驟雨』(吉行淳之介)1954年
- 『アメリカン・スクール』(小島信夫)1954年
- 『プールサイド小景』(庄野潤三)1954年
- 『白い人』(遠藤周作)1955年
- 『太陽の季節』(石原慎太郎)1955年
- 『裸の王様』(開高健)1957年
- 『飼育』(大江健三郎)1958年上
といったそうそうたるタイトルが並んでいる。
2位 古井由吉(1970年)
純文学に馴染みのない人にとっては
「古井由吉って誰?」
といった感じだと思うのだが、彼もまた戦後に登場した天才的作家の一人である。
東京大学文学部出身の古井は、金沢大学や立教大学の教員を経て、33歳の年に専業作家に転身。
その同年に『杳子』で第64回芥川賞を受賞するワケだが、何がスゴいって他の作品でも同時にノミネートされている点である。
実はこのとき同時に、古井の他の作品『妻隠』も候補作に上がっていた。
1人の作家が、2作品でノミネートという……
これは、芥川史上かなり稀なケースである。
しかも、その2つの作風は、まるで違っていた。
選考委員の中に「あまりに作風が違うので、別人の筆かと思った」と言うものさえいたくらい。
『杳子』が渾沌として曖昧さを残す作品だとすれば、『妻隠』は明るく分かりやすい作品だ。
その毛色の違う2作品は「どちらも受賞にふさわしい」という評価を得る。
が、「そのどちらを受賞作とするか」の議論になると意見は真っ二つに割れるのだった。
『杳子』を推したのが、丹羽文雄・船橋聖一・大岡昇平・石川淳
『妻隠』を推したのが、中村光夫・永井龍男・井上靖
ちなみに川端康成は、
「そもそも、予選の段階で1つにしぼれないとか、ありえないでしょ」
と強く不満を抱き『杳子』のほうしか読まなかったという( 自由すぎ )。
こんな感じで、選考会で波乱が巻き起こったわけだが、こんなことは芥川賞史において、後にも先にも古井由吉だけである。
その規格外の才能をうかがい知れるエピソードだといっていい。
なお古井は、同世代の黒井千次や小川国夫らとともに「内向の世代」と呼ばれている。
「内向の世代」とは、あくまで日常を描きながら、個人の内面や人間の本質を追究する作家たちに使われた呼称である。
1位 大江健三郎(1958年)
大江健三郎は、東京大学ではフランス文学を学び、サルトルに傾倒。
卒論もまた「サルトルの小説のイメージについて」であった。
在学中に発表した『奇妙な仕事』で注目され、『死者の奢り』で芥川賞候補となる。
選考委員の川端康成が大江をプッシュしたものの、この時は開高健の『裸の王様』が受賞した。
だが、これをきっかけとして、大江は一挙に注目され、流行作家へとのし上がる。
そして、翌年に『飼育』で再び芥川賞の候補になる。
しかし、選考委員たちは『飼育』を推すことにためらうのだった。
彼らが口をそろえて言うのは、
「大江健三郎は、すでに新人ではないんじゃないか」
ということだった。
つまり大江は、デビュー後たった1年で「もはや新人ではない」と文壇から評価されてしまったわけだ。
改めていうまでもないが、芥川賞とは「新人賞」である。
中村光夫は、
「候補作の中では、抜群の出来だ」
と前置きをした上で、
「大江氏のようにすでに流行児といって良い作家に、この賞を改めて受賞するのは適切なのか」
という逡巡を述べている。
このことも、作家としての大江が異次元レベルの早熟であったことを意味している。
しかし結局、その圧倒的な作品によって、ほぼ満場一致での受賞となった。
23歳の受賞は当時としての最年少記録であり、石原慎太郎、開高健らに次ぐ新世代の作家として注目を集めた。
大江の作品は、やはりサルトルの「実存主義」の影響が強い。
特に、初期の作品には、閉塞した環境で生きる人間の姿を描いたものが多い。
『死者の奢り』や『飼育』は、まさしくその好例だろう。
作風に変化が訪れるのは、大江に長男「光」が誕生してからだと言われている。
長男は知的障害をもっていた。
一度は息子の死を願いながらも、大江は息子を受け入れていく。
そして、そんな光との共生について、たびたび小説に書いた。
その代表作といえるのが『新しい人よ眼ざめよ』である。
その一方では『ヒロシマ・ノート』など、戦争の悲惨さを訴える作品も残している。
さらに、代表作『万延元年のフットボール』は、戦後文学の最高傑作としての呼び声が高い。
1994年、大江59歳の時にノーベル文学賞を受賞。
日本人の受賞は川端康成に次ぐ2人目。
芥川賞の選考を思い返せば川端が大江を強く推していたわけだが、おそらくそれも偶然ではないのだろう。
なお、ノーベル賞受賞の理由はこうだった。
「詩的な言語を使って、現実と神話の入り交じる世界を創造し、窮地にある現代人の姿を、見るものを当惑させるような絵図に描いた」
“最年少記録”をWで更新

2003年の芥川賞は、マスコミで大きく取り上げられた。
実に37年ぶりに最年少記録が更新されたからだった。
しかも、2人同時に。
それまでの最年少記録は丸山健二の23歳。
それを更新したのは、20歳の金原ひとみ(『蛇にピアス』)と、19歳の綿矢りさ(『蹴りたい背中』)である。
金髪にミニスカートで現れた金原ひとみは、いわゆる当時で言うところの「ギャル」を地で行くような風貌で、一方の綿矢りさは現役の大学生で、どちらかといえば清楚系の服装に身を包み可愛らしい雰囲気。
そうした両者の外見も、間違いなくマスコミが好んだ要素だといえる。
ただ、ここで勘違いしてはいけないのは、作者の見た目は作品の評価とは全く無縁であるということだ。
金原ひとみの『蛇にピアス』は、生きることのリアリティを“痛み”に求める少女の破滅的世界観を描いていたし、綿矢りさの『蹴りたい背中』は、スクールカーストで孤独を感じる少女の「抑えがたい衝動・欲求」を描いていた。
つまり、どちらも本格的な純文学作品なのだ。
ということで、『蛇にピアス』と『蹴りたい背中』が掲載された『文藝春秋』はミリオンセラーを達成。
単行本については『蛇にピアス』は50万部越えのベストセラーを、『蹴りたい背中』に至っては127万部越えのミリオンセラーを達成した。
スポンサーリンク
帰ってきた“大型新人”の登場

芥川賞では60代や70代での受賞というのが少なからずある。
そして、あくまで芥川賞が「新人賞」であることを踏まえると、彼らは60代・70代という“超遅咲きの新人”ということになるだろう。
中でも、芥川賞の歴史において、選考委員にもよく知られた「帰ってきた新人」による受賞例がある。
それが1973年の森敦『月山』である。
まず、森敦が芥川賞を受賞したのは61歳のこと。
選考でも
「60歳を超えた新人なんてありえない」
という声もあがったというが、そんな中でも丹羽文雄は、
「私は、この人の名前を30年昔に知っていた」
とした上で、
「ちっとも老人くさくないのは、脅威である」
と絶賛している。
また「森敦が芥川賞を受賞した」というニュースを耳にし、はるか昔に聞いたその名前に驚いた文学ファンも少なからずいたという。
森敦とは、一体なにものなのか。
1912年に生まれた森は、旧制第一高等学校に入学した戦前の秀才文学少年だった。
彼は菊池寛に見いだされ、横光利一に師事し、若い頃は あの太宰治・檀一雄・中原中也の同人として創作に励んだ。
そうそうたるメンバーと肩を並べていた森だったが、ある日から作家として沈黙することになる。
それから40年……
時は流れ、人々が「森敦」を忘れかけた頃、彼は再び文壇に現れたのだった。
選考委員たちは、彼をとても好意的に迎え入れた。
「森敦の登場は、井上靖、大江健三郎の登場を思わせる」
「彼の作品を読んで、久しぶりに小説を読む楽しさを堪能した」
「60代は決して“老い”ではない、むしろ作家として成熟の時期である」
こんな風に、「帰ってきた新人」による、超正統派純文学は、文学玄人たちに好意をもって向かい入れられたのだった。
なお、61歳の受賞は当時の最高齢記録。
その記録は、2013年に黒田夏子( 『ab さんご』 )が75歳で受賞して更新している。
お茶の間を楽しませた“記者会見”

芥川賞の隠れた魅力の一つに、受賞後の記者会見がある。
「作品は作品! 作者は作者!」とする文学フリークの方も多いとは思うが、それでも「こんな作品を書く作者ってどんな人なんだろう」と、興味を持つ人もいるのもまた事実。
会見は、そうした作者のパーソナリティを垣間見える貴重な瞬間なのだが、そんな会見の中で個性的な返答をする作家も珍しくない。
その代表格は、なんといっても2010年受賞の西村賢太(『苦役列車』)である。
その日も記者たちによる、テンプレ通りの質問が飛び交っていた。
決して清潔感があるとはいえない出で立ちで登場した西村賢太は、なんとも言えないアンニュイな態度で、その質問の一つ一つに答えていた。
「受賞を聞いたとき、何をしていましたか?」
その質問に対して、西村賢太は臆面もなく、次のように言い放った。
「そろそろ、風俗に行こうかなっておもってました」
もう、なんというか、いろいろと吹っ切れている作家なのがお分かりいただけるだろう。
そして、受賞作『苦役列車』は、そんな西村賢太の私小説なのだ。
なんというか、作品を一言で表すならば、
孤独な童貞が社会に吐き出す”ゲロ”
といった趣なので、受賞会見も“さもありなん”である。
そんなぶっ飛び記者会見の記憶もまだ新しい翌年のこと。
2年連続で、お茶の間を楽しませたぶっ飛び会見が生まれた。
それが2011年受賞の田中慎弥(『共喰い』)の記者会見である。
会場に現れたのは、猫背気味の中年男。
席につくや、ふてぶてしく不機嫌な態度で辺りを一瞥。
「今のお気持ちをお聞かせください」
といった質問に対する彼の、最初の返事はというと、
「(芥川賞は)自分がもらってあたりまえ」
続いて、
「(しょうがないから、芥川賞を)もらっといてやる」
と言い放つ。
挙げ句に、
「(こんな会見)とっとと終わりにしましょうよ」
である。
芥川賞史上、間違いなく№1で無礼な男である。
その後も終止不機嫌に辺りをねめつける田中慎弥に対して多くの批判の声が上がった。
とはいえ、受賞作『共喰い』をすでに読んでいた当時の僕は
「この作品の作者らしいなあ」
と率直に感じた。
というのも、『共喰い』という作品も一言で言えば、めちゃくちゃ不快な作品だからである(もちろん誉め言葉)。
他にも、2004年モブノリオの第一声、
「どうも、舞城王太郎です」
と、ライバル候補者である覆面作家の名を語ったものも面白かったし、2015年又吉直樹の「又吉さんの受賞を芥川龍之介が聞いたら、どんな言葉をかけてくれると思いますか?」という質問に対する、
「芥川は、こんなベートーベンみたいな髪型のヤツ、嫌いやと思います」
といった返答も面白かった。
こんなふうに、受賞会見も芥川賞の隠れた魅力といっていい。
余談だが、僕がいちばん好きな受賞会見は2016年の「三島由紀夫賞」の受賞会見。
記者からのあらゆる質問に対して、
「受賞は不愉快です。はた迷惑です。質問にも答えられません」
と答え続けた蓮實重彦のものである。
選考委員の“退任事件“

1970年代の文学シーンを象徴するできごとを紹介したい。
それは、選考委員の永井龍男の「退任事件」である。
永井は1958年から長年にわたり選考委員をつとめる、言わば「古参」の委員だった。
そんな彼が自ら選考委員を退くきっかけとなった2つの作品がある。それが、
- 村上龍の『限りなく透明に近いブルー』(1976年)
- 池田満寿夫『エーゲ海に捧ぐ』(1977年)
であった。
永井はその2つの作品が受賞することに猛反発を示した。
まず、『限りなく透明に近いブルー』はといえば、むき出しの性と暴力を描いた問題作。
当初のタイトルは『クリ〇リスにバター』というものだっという裏話は、作品のインパクトを教えてくれる。
次に『エーゲ海に捧ぐ』も とにかく性にスポットを当てまくった作品で、当時「純文学的官能小説」と呼ばれていた。
そもそもタイトルの「エーゲ海」は女性の陰部のメタファーであり、そうしたエロメタファーが随所にちりばめられている。
さて、こうした2作品に対する永井の評価なのだが、『限りなく…』については「受賞を見送り、次作を待つべき」と言い、『エーゲ海に捧ぐ』については「これは文学ではない」とまで言っている。
しかし永井の評価とうらはらに、2作品はその「前衛さ」が評価され、芥川賞を受賞することとなった。
この一連のできごとをうけて永井は、
「自分の委員としての資格について検討されなければならない」
という言葉を残し、約20年務めてきた選考委員を退任したのだった。
これは1970年代の文学シーンを象徴する出来事だと思う。
受賞作を眺めてみると、50年代、60年代の作品と雰囲気の異なるものが少なくない。
村上龍・池田満寿夫・中上健次・宮本輝……
彼らは70年代を代表する作家たちだが、中上や宮本は「戦後生まれ」である。
彼らによる文学は当時の文壇にとって新鮮であり、70年代は「文学に新風が吹いた時代」だったと概括できるだろう。
芥川賞最大の“黒歴史”

芥川賞を取れなかった村上春樹
ここでは、あえて“黒歴史”というネガティブな言葉で紹介したいことがある。
それは、村上春樹が芥川賞を取れなかったことだ。
村上は過去に2度芥川賞候補にノミネートされ、受賞を逃している。
- 1979年『風の歌を聴け』落選 → 重兼芳子・青野聰が受賞
- 1980年『一九七三年のピンボール』落選 → 受賞作なし
1980年にいたっては、「受賞作なし」という結末。
これこそ芥川賞における“黒歴史”であり、いまでも文壇の汚点の1つとして認識されている。
村上春樹といえば、あらためて紹介するまでもないが、世界規模で活躍する日本の現代作家である。
認知度・実績で彼に並ぶ現代作家はおらず、今もっともノーベル文学賞に近い日本人作家とも言われている。
そんな村上春樹の作家デビューは1979年『風の歌を聴け』で群像文学新人賞を受賞してのことだった。
選考会では満場一致。
このとき、選考委員の丸山才一は作品のアメリカ文学からの影響を指摘し、
「この新人の登場は一つの事件」
と激賞した。
『風の歌を聴け』といえば、いまや10カ国以上で翻訳されている村上文学の代表作で、世界からも高く評価されている作品だ。
しかし、同作は1979年の芥川賞候補にノミネートしたものの落選。
翌年は『一九七三年のピンボール』で候補に上がるも、こちらも落選。
ちなみに、このときの選考委員は以下の通り。(※一部欠席者あり)
- 井上 靖
- 遠藤 周作
- 大江 健三郎
- 瀧井 孝作
- 中村 光夫
- 丹羽 文雄
- 丸谷 才一
- 安岡 章太郎
- 吉行 淳之介
こうしてみてみると、その顔ぶれがいかに豪華であるかが分かるだろう。
なぜ受賞できなかったのか
では、主に選考委員たちの評価はどういうものだったのか。
丸山才一が激賞したのは先に見たが、選考では多くの選考員が「アメリカ文学の模倣」として批判した。
芥川賞というのは新人をもみくちゃにする賞で、それでもかまわないと送り出してもよいだけの力は、この作品にはない。(吉行淳之介)
憎いほど計算した小説である。しかし、・・・(中略)・・・手法がうまければうまいほど私には「本当にそんなに簡単に意味をとっていいのか」という気持にならざるをえなかった。(遠藤周作)
外国の翻訳小説の読み過ぎで書いたような、ハイカラなバタくさい作だ(瀧井孝作)
今日のアメリカ小説をたくみに模倣した作品もあった・・・(中略)・・・作者自身にも読み手にも無益な試みのように感じられた(大江健三郎)
要するに、批判された点は大きく次の2点、
- 計算され尽くされた小説世界
- アメリカ文学からの影響
これらは、1979年当時にあって前衛的な性格だったといっていい。
こうして、村上春樹に芥川賞を与えなかった文壇だったが、その後すくに、その過ちに気づくことになる。
1985年に「谷崎潤一郎賞」(実力のあるベテラン作家に与えられる権威ある賞)を(慌てたように)授賞している。
翌年1986年は『ノルウェイの森』が刊行され、上下430万部を売る大ベストセラーとなる。2年後の1988年には『羊をめぐる冒険』の続編『ダンス・ダンス・ダンス』が発表され、1989年には『羊をめぐる冒険』の英訳版『Wild Sheep Chase』が出版された。
芥川賞に落選後の10年足らずで、村上春樹は日本を代表する世界的な作家へとのし上がっていったわけだ。
では、なぜ、村上春樹は芥川賞を受賞できなかったのだろう。
『芥川賞はなぜ村上春樹に与えられなかったか』(幻冬舎新書)という、なんとも露骨なネーミングの書があるが、そこで詳しく考察をされている。
内容を要約すれば、
選考委員が村上春樹の「前衛性」を理解できなかった、
ということになる。
実際、選考員の大江健三郎は後年になって次のように語っている。
「私は(中略)表層的なものの奥の村上さんの実力を見ぬく力を持った批評家ではありませんでした」(『大江健三郎 作家自身を語る』より)
では、とうの本人、村上春樹は芥川賞をとれなかったことについて、なんと言っているのだろう。
正直に申しまして、僕としては(できればそのまますんなり信じていただきたいのですが、)とってもとらなくてもどちらでもいいと考えていました。『職業としての小説家』より
村上がそう考える理由は二つ。
- 作品発表の場があるだけで十分だから
- 2作品の出来に納得いっていないから
さらに、村上に芥川賞を与え損ねた文壇の中で「今さら村上春樹に芥川賞やれないよね」というコンセンサスが生まれていったのだという。
そのとき村上はこう感じたという。
かえってすっきりしたというか、芥川賞についてもうこれ以上考える必要がなくなった、という安堵感の方が強かったように思います。『職業としての小説家』より
なんでも、選考会が近づくたびに、自分よりも周囲の人たちがそわそわして、それが煩わしかったんだとか。
きっと村上は、毎年のように外野が大騒ぎする「ノーベル文学賞」に対しても同じことを思っているのだろう。
おわりに

以上、芥川賞にまつわる裏話やおもしろエピソードなどを紹介してきた。
こうしたエピソードがあるのも、芥川賞が歴史もあり、多くの注目を集め、日本を代表する文学賞だからに他ならない。
この記事で紹介したエピソードを踏まえれば、きっと芥川賞を違った角度から楽しめると思う。
ぜひ、多くの作品を手に取って、芥川賞の歴史を楽しんでいただけると嬉しく思う。
ちなみに、芥川賞についてもっと知りたいという方は以下の記事も参考にしてほしい。
【 参考記事 解説【芥川賞を取るには】—どうやってノミネートされ、どうやって選ばれるのか— 】
【 参考記事 解説「芥川賞とはどんな賞?」—受賞作の傾向・過去のデータを徹底分析!— 】
最後に、以下で「芥川賞を効率よく読むサービス」や「格安で出版する方法」なども紹介しているので、興味のある方はぜひ参考にどうぞ。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
すき間時間で”芥川賞”を聴く

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・
格安で自費出版したい人へ

「自分の作品を形にしたい!」
「自分の作品を多くの人に届けたい!」
そんな思いを持つ人は、Kindle出版 がオススメ。
近年、その需要を急激に伸ばしているKindleだが、そのkindleでの出版なら格安で高品質な電子書籍を出版できる。
もしも自費出版にすこしでも興味があるなら、”手ごろな価格設定” と ”手厚いフォロー”が魅力的な 「パブフル」のサービスをチェックしてみてほしい。
無料で相談ができ、支払いも完全後払いなので、安心して自費出版を検討できる。
・
・
※「おすすめの代行業者」について知りたい方はこちらから
・
※「そもそもkindle出版って何?」という方はこちらから







コメント
知らないエピソードも沢山あって、大変面白かったです。
芥川賞作家ともなるとやはり変な人が多いんですね。
先日亡くなってしまった大江健三郎さんは、常に戦後文学の最前線に立たれ、新たなことに挑戦し続ける作家でした。新人の時から「すでに新人ではない」という嬉しい褒め言葉(?)でデビューした大江が、常に日本の小説界に新しい風をもたらしたところに、この作家の特異性があるのでしょう。
考人さん
コメントありがとうございます。やはり、文学者には独特な価値観を持っている人がいて、それは今も昔も変わらないのでしょうね。
考人さんもおっしゃる通り、大江健三郎の早熟っぷりは目を瞠るものがありますね。個人的には、中・後期の作風はあまり好みではないのですが、文壇に登場したての大江の作品が好きですね。文章の端々から、若き大江の気概のようなものが伝わってきます。