はじめに「批評性ある作品」

『東京都同情塔』は、第170回芥川賞受賞作で、多くのテーマを扱った批評性やメッセージ性にあふれる作品だ。
とはいえ、僕個人としては、ややテーマにまとまりを感じられず、作者は何が言いたいのか、作品が伝えようとしていることは何なのか、正直あまり見えてこなかった。
だけど、なんとか文章にしがみつき、全体を俯瞰したり、細部についてじっくりと考えたりする中で、次第に見えてくるものがあった。
そうした僕自身の気づきや解釈をもとに、この記事では『東京都同情塔』について解説と考察をしていきたい。
お時間のある方は、ぜひ最後までお付き合いください。
作品のテーマ

本作『東京都同情塔』は、非常に批評性に富んだ作品で、読み手一人一人が様々なアプローチで解釈することができる作品だと思う。
実際に、本作が扱うテーマについて、思いつくだけでもザっと以下のものが挙げられる。
率直にいって、150頁たらずの中編小説で、これだけのテーマを扱うのはとても難しい。
実際に、僕は本作を読んで、上記の内の多くは「背景」になってしまっていると感じたし、読後の消化不良感が否めなかった。
とはいえ、芥川賞選考委員の吉田修一は、
「完成度が高く、欠点を探すことが難しい」
という高い評価を与えているので、僕自身、まだまだ読みが浅いんだなと感じている。
さて、本作には強い批評性やメッセージ性があることは間違いないのだが、では、それは一体何だろう。
それは「言語とコミュニケーションの問題」であると僕は考えている。
実際に、作者の九段理江は芥川賞の受賞会見で、次のように語っている。
「言語やコミュニケーションといったテーマは、デビュー前の作品から一貫して持ち続けているテーマです」
芥川賞受賞会見より
本作『東京都同情塔』もその例外ではなく、「言語とコミュニケーションの問題」が最も強いメッセージ性を持って描かれている。
スポンサーリンク
「東京都同情塔」が象徴するもの

では、その「言語とコミュニケーションの問題」は、本作でどのように描かれているのか。
それがもっとも現れた箇所は、作品冒頭。
「東京都同情塔」について語られる箇所である。
バベルの塔の再来。シンパシータワートーキョーの建設は、やがて我々の言葉を乱し、世界をばらばらにする。(単行本P3より)
ここで象徴的なのが、「シンパシータワートーキョー」(以下、東京都同情塔)が「バベルの塔」になぞらえられている点だ。
バベルの塔は、旧約聖書にある有名なお話で、超シンプルにまとめるとこんな内容になる。
こうしてみてみると、本作で重要なモチーフとなっている「東京都同情塔」に、どんな意味が託されているかが見えてくる。
結論を言うとこうだ。
ここで、もう一度「バベルの塔」との関連を踏まえて、「東京都同情塔」について記述をすると次のようなものになる。
「東京都同情塔」は、人間の傲慢さによって建築され、その結果、人々の言葉は乱れ、人々はコミュニケーションが取れなくなってしまった。
こう説明されても、まだまだチンプンカンプンである。
そこで以下では、
- 人間の言葉の乱れ
- 人間のディスコミュニケーション
- 人間の傲慢さ
この3つの点について、さらに詳しく考察をしてみたい。
スポンサーリンク
人々の言葉の乱れ
“無色透明”な言葉

東京都同情塔が建築されたため、人々の言葉は乱れていく……
このことについて、作品冒頭で主人公「牧名沙羅」は次のように説明している。
この混乱は、建築技術の進歩によって傲慢になった人間が天に近づこうとして、神の怒りに触れたせいじゃない。各々の勝手な感性で言葉を乱用し、捏造し、拡大し、排除した、その当然の帰結として、お互いの言っていることがわからなくなる。喋った先から言葉はすべて、他人には理解不能な独り言になる。独り言が世界を席巻する。大独り言時代の到来。(P3より)
つまり、沙羅によれば、人々の言葉が混乱してしまった原因は、神の怒りではなく、他でもなく「人間自身」にあるのだという。
「人々が身勝手に言葉を運用してきたから、言葉が乱れてしまったのだ」と。
では「身勝手な言葉の運用」とは、一体なんなのだろう。
結論を言えば、度が過ぎる“適切な言葉選び”だと言っていいだろう。
これは特にSNSが人々のコミュニケーションの場である昨今、誰もが実感できることではないだろうか。
誰かを不快にしないだろうか
コンプラ的に問題ないだろうか
炎上したり叩かれたりしないだろうか
そんな風にして、人々は慎重に自らの言葉を検閲し、政治的・思想的に中立的で、公平公正な表現を積み上げていく。
そこには、人間的なクセ、エグみ、曇り、汚れといった夾雑物は一切ない。
いわば“無味無臭”で“無色透明”な言葉である。
そうした言葉は、もはやAIによって生成される文章と何ら変わるものではない。
スポンサードリンク
生成AIのような言葉

本書では頻繁に生成AIによる文章が挿入されている。
そのどれもが、先ほど説明したように無色透明、無味無臭で、絶対に誰も不快にしない言葉である。
別にそれ自体、批難されるべきものではないだろう。
だけど、もしも人々が皆、そうしたAIのような言葉を使うようになったとしたらどうだろう。
何かいいようのない違和感や不安感を覚えないだろうか。
作中で、そうしたAIのような言葉を喋る人物として描かれているのは、他でもない主人公「牧名沙羅」である。
沙羅の中にもまた“検閲官”が存在していて、彼女はいつも「この言葉選びは、果たして適切だろうか」ということを病的なまでに突き詰めている。
彼女の言葉には様々な特徴がある。
たとえば、「選び抜かれな言葉」というものがソレである。
超がつくほどの合理主義である沙羅には「現実にふさわしい言葉」を選ばなければならないという信念(もはや脅迫観念)があり、彼女の“適切な言葉”への執着というのは並大抵のものではない。
実際に、登場人物の一人「拓人」とのやり取りの中でも“検閲者”は頻繁に登場し、沙羅は自らの言葉選びに苦慮している。
ただし、そうやって選び抜かれた言葉というのはやはり不自然で、対話相手の拓人をいつも困惑させる。
たとえば、沙羅の「東京都同情塔」についての語りを聞いた拓人は、率直に次のように感じる。
それが牧名沙羅由来の言葉であるとは全然思わなかった。彼女の積み上げる言葉が何かに似ているような気がして記憶を辿ると、それがAIの構築する文章であることに思いいたった。(P85より)
このとき拓人は、このAIのような言葉は「沙羅由来の言葉」ではないと直感している。
つまり、沙羅が積み上げる言葉からは、沙羅の個性、人間性、内面、心、そういった彼女の根幹が、全く感じられないのである。
スポンサーリンク
沙羅の言葉の特徴

沙羅の言葉はまるで生成AIのようで、そこに「牧名沙羅」の存在を感じさせるようなモノは何もない。
彼女の言葉の特徴はそれだけではない。
たとえば、話しながらトピックが急に変化するし、一方的に早口で喋ったりする。
それ以外にも「~するべき」とか「~しなければならない」という義務や否定表現が多いという特徴がある。
つまり、沙羅の言葉はどこまでも自己完結的なのだ。
繰り返しになるが、そこには沙羅の「現実にふさわしい言葉を選ばなければならない」という信念(強迫観念)がある。
沙羅にそれを植え付けたのは、おそらく少女時代の辛い体験だろう。
信じた男性に裏切られ、乱暴された過去。
だけど、その時の沙羅には自分に起こった現実を言葉にすることができなかった。
結果、彼女の苦しみは誰からも理解されることなく、彼女の苦しみはそのまま闇へと葬り去られてしまった。
――現実を正しく言葉にしなければならない。
沙羅がそう痛感するのはもっともなことだ。
だけど、その切実な思いは強迫観念へと姿を変え、「~するべき」、「~しなければならない」と独り言のように繰り返し、いつしか沙羅は「現実にふさわしい言葉」だけを病的に求めるようになってしまう。
では、それは沙羅にどのような結果をもたらしたか。
結論を言えば、沙羅にある種の「アイデンティティクライシス」をもたらした。
要するに「自分が自分である」という感覚を、沙羅から奪ってしまったというワケだ。
そのことを暗示させるのが、沙羅が頻繁に使うこの言葉だ。
「とかなんとか言っている建築家の女がここにいるとして、君ならどう思う?」(P54より)
作中で繰り返される、この不自然な「こういう女がここにいるとして」という言葉。
この言葉を繰り返す沙羅に対して、拓人はつぎのように言う。
「いるとして、なんていちいち仮定法を使わないでも建築家の牧名沙羅ならここにいるよ。僕が見てる、聞いてるよ」(P78より)
そう説得をする拓人の言葉に、しかし、沙羅はこうつぶやく。
いるんだ。彼女は初めてその事実を知ったみたいにつぶやく。(P78より)
ここに、沙羅の「存在の不確かさ」が表れている。
つまり、「現実にふさわしい言葉」ばかりにこだわり、AIのような言葉ばかりを積み上げ、結果的に自らの内面にフタをし続けてきた沙羅は、いつしか自らの存在を実感できなくなってしまったのである。
沙羅の言葉の特徴には、彼女の悲しい過去があるワケだが、結果的に彼女に「存在の不確かさ」を与えている真犯人は「言葉」であるといっていい。
人を不快にしないように、あるいは、現実にふさわしいようにして選ばれた言葉は、無味無臭で無色透明のAIさながらの言葉となる。
そして、そうした言葉の運用は、人々からアイデンティティを奪い取り、人格や存在に大きな影響をもたらすのだ。
スポンサーリンク
・
人々のディスコミュニケーション
「内実」のない言葉の応酬
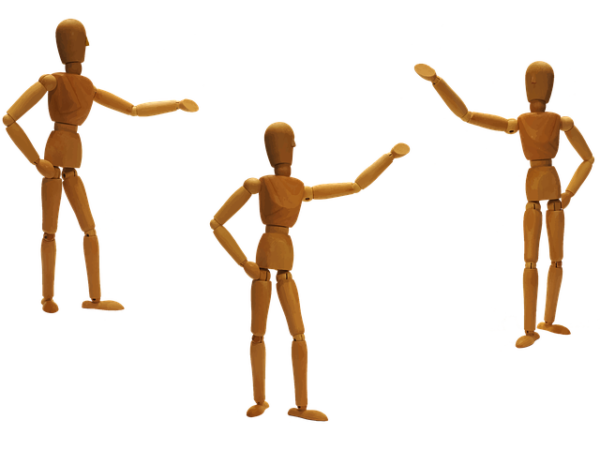
ここからは「東京都同情塔」が暗示する二つ目の問題、「人々のディスコミュニケーション」について触れよう。
無味無臭で無色透明な言葉。
そうした言葉が浸透し、人々から「存在」に根差した言葉が奪われていく。
語られるのは、すべて内なる“検閲者”によって精査された「適切な言葉」ばかり。
「不適切な言葉」はグッと飲み込み、自らの本心や本音を心の底に抑圧する。
ここで、問題になってくるのが「人々のディスコミュニケーション」である。
つまり、
そんな上辺だけの言葉で、本当にコミュニケーションは成り立つのか?
という問題である。
確かに、選び抜かれたスマートでポライトな言葉は、人を傷つけることはない。
その発言でもって、誰かに叩かれることも、炎上することもないだろう。
だけど、そうした言葉の中に、「自分の心」とか「自分の根幹」が、いったいどれだけ表れているのか。
選び抜かれた「適切な言葉」の中に、いったいどれだけ「内容」や「内実」が含まれているのか。
そして、そうした言葉の応酬が、果たして真の意味での「コミュニケーション」であると言えるのだろうか。
本書『東京都同情塔』で問われているのは、まさにこの問題である。
スポンサーリンク
「独り言」が世界を覆う

ここで改めて、作品冒頭を引用してみよう。
バベルの塔の再来。シンパシータワートーキョーの建設は、やがて我々の言葉を乱し、世界をばらばらにする。(単行本P3より)
この「世界をばらばらにする」というのが、「人々のディスコミュニケーション」を指しているのだが、上記の引用箇所は次のように続く。
各々の勝手な感性で言葉を乱用し、捏造し、拡大し、排除した、その当然の帰結として、お互いの言っていることがわからなくなる。喋った先から言葉はすべて、他人には理解不能な独り言になる。独り言が世界を席巻する。大独り言時代の到来。(P3より)
ここで注目したいのが「独り言」というワードだ。
「独り言」とは、つまり、「他者不在」で成り立つ言葉である。
実は、沙羅自信、この「独り言」をしゃべる癖を持っている。
沙羅が「現実にふさわしい言葉」に病的なまで囚われていることはすでに述べた。
その状況を、登場人物の拓人は「言葉の牢獄」と表現している。
彼女が住んでいるのは言葉で出来た家なんかじゃなく、牢獄なんだ。窓もついていない、寒気もできないような不衛生な刑務所。看守が常に彼女の話す言葉を見張っている、監獄。(P67)
沙羅の言葉は誰にも届かない。
病的なまでに追い求めた言葉の数々に、彼女の存在は宿ってはいない。
発せられた言葉は、ただただ虚しく響くばかり。
本当の沙羅は「言葉の牢獄」に閉じ込められるように、いつだって一人である。
そのことを暗示するかのように、沙羅は拓人の前でも、独り言を繰り返す。
だからこそ、沙羅の言葉を聞けば聞くほど、拓人は彼女との間に深い断絶を感じてしまう。
僕たちは同じ人間でありながら本当は違う人間なんだと、あらためて断絶を感じざるを得ない。(中略)今までどうやって会話を成立させてきたのか不思議なくらいだし、そもそも成立させてきたと思っているのは僕だけなのかもしれない。(P62より)
繕われた「適切な言葉」から、語り手の「存在」を感じることは不可能だ。
そして、言葉の牢獄に閉ざされた者の「独り言」の先には、コミュニケートすべき他者は存在していない。
こうした時代を象徴するのが、まさにシンパシータワートーキョー、東京同情塔なのである。
この塔が屹立する世界にあって、人々は誰もが「言葉の牢獄」に閉じ込められ、他者不在の虚しい言葉を生成AIよろしく積み上げていくしかない。
まさに「大独り言時代」——人々から本質的なコミュニケーションが奪われた時代の到来である。
スポンサーリンク
・
人間の傲慢さ
世界は正しく記述できない

最後に「東京都同情塔」が暗示する三つ目の問題、「人間の傲慢さ」について触れよう。
旧約聖書における「バベルの塔」、そこでは人間の「神に対する傲慢さ」が指摘されている。
それに対して、本書『東京都同情塔』では、人間の「言葉に対する傲慢さ」が指摘されていると言っていい。
その「言葉に対する傲慢さ」が最もよく表れているのは、沙羅の言葉に対する信念だろう。
以下で引用するのは、拓人による沙羅についての説明だ。
自分の住む家の素材はみんな言葉で出来ていて、自分自身のことは何でも言語的に説明可能だと信じ切っているみたいに喋りまくる。言葉を言葉以前にとどめておくというホコリっぽい選択肢を、強い意志のもとであらかじめ排除してから、家じゅうにワックスをかけているみたいだ。(P54より)
つまり、沙羅には「自分のことなら何でも言語化することは可能だ」という信念がある。
言葉を正しく、適切に選ぶことができれば、世界を正確に記述することは可能だ、と彼女は信じているのである。
だけど、僕ははっきり言いたい。
人間の言葉で、この世界を正確に記述することなど不可能だ、と。
たとえば、言語学者のサピアやウォーフが明らかにしたように、僕たちの世界認識はそれぞれの母語によって異なっている。
【 参考記事 【サピア=ウォーフ仮説】分かりやすく解説―弱い仮説と強い仮説…正しいのは?― 】
日本語話者には日本語話者の世界認識があり、英語話者には英語話者の世界認識があり、フランス語話者にはフランス語話者の世界認識がある。
つまり言語ごとに世界の記述方法は全く異なるのだ。
そして、それぞれにはそれぞれの合理性があって、どれが正しいとか、どれが間違っているとか、それを決めることは原理的にできない。
「人間に正確な世界認識は不可能である」
こうしたことは、これまで古今東西、多くの哲学者、言語学者が口をそろえて言ってきたことであり、これ以上、ここで僕がもっともらしく語る必要はないだろう。
とにかく、強調しておきたいのは「世界を正しく記述できる」なんて考え方は、人間の傲慢以外の何物でもないということだ。
スポンサーリンク
東京都同情塔の傲慢さ

「世界を正しく記述できる」
こうした考え方は、人間の傲慢である。
もう少し言い換えれば、
「この言葉はこう言い換えるべきだ」とか
「この言葉はこう表現しなければならない」とか
そうやって誰かの言葉を一方的、あるいは暴力的に正そうとすることは、言語的に不遜な態度である。
だけど「東京都同情塔」は、そうした発想のもと建築された。
この塔の理念には、犯罪者への同情的なまなざしがある。
「犯罪者」
そう一口に片付けてしまう時、間違いなくその言葉からこぼれ落ちてしまう、複雑な背景というのがきっとある。
そこで生まれたのが「ホモ・ミゼラビリス」という概念だという。
「世間で“犯罪者”と呼ばれる人たちは、不遇な環境の下、そうせざるを得なかった同情すべき人たちだ」
というわけだ。
うん、確かに、そういう側面もあるだろう。
だけど、今度はその言葉によってこぼれ落ちてしまう、複雑な背景というのもきっとある。
つまり、どちらが正しくて、どちらが間違いだと言うことはできないのだ。
あっちが立てばこっちが立たない。
世界というのは、どのような切り口で切り取ってみても、その実態を100%正しく切り取ることはできないのである。
それなのに、「物事には適切な表現がある」と、まるで世界の実相を知っているかのような態度で、ある一つの言葉を糾弾し、「各々の勝手な感性で言葉を乱用し、捏造し、拡大し、排除」するのは人間の傲慢以外の何物でもない。
スポンサーリンク
・
伝えたいこと・ラストの意味

以上、『東京都同情塔』のテーマについて解説・考察を行ってきた。
改めて、この記事で取り上げたテーマは次の3つだった。
- 人間の言葉の乱れ
- 人間のディスコミュニケーション
- 人間の傲慢さ
ここで改めて、ここまでの内容をまとめつつ、作品が伝えたかったことを記したい。
『東京都同情塔』は、あくまでもSF小説で、僕たちの社会とイコールではない。
だけど、ここで書かれている世界は、僕たちがたどろうとしている未来なのかもしれない。
だとすれば、僕たちはもう一度、言葉に対する態度を見直す必要があるのだろう。
言葉によるコミュニケーションが困難だからこそ、僕たちは改めて言葉への信頼と謙虚さを取り戻さなければならないのだ。
当たり前だけど、僕たちはエスパーじゃない。
相手の気持ちを100%理解することもできなければ、自分の気持ちを100%伝えることもできない。
小説には、こんな箇所がある。
「もし私たちの鼻が交換できたら、いくつかの問題が同時に簡単に解決するのに」(P133より)
相手の鼻と自分の鼻を交換して、
「ああ、君にはこんな風に臭っていたんだね。うん、確かにきついね、僕の体臭……」
なんてことは、僕たちにはできない。
相手の心の中身を取り出して、それを自分の心に入れてみて、
「なるほど、君はこんなに心を痛めていたんだね。今まで気づかなくてごめんね……」
なんてことも、僕たちにはできない。
そうである以上、僕たちが相手を理解するためにできるのは、やはり言葉によるコミュニケーションしかないのである。
だからこそ、言葉への信頼を失くしちゃいけないし、言葉への謙虚さを忘れちゃいけない。
作者の九段理江は、芥川賞の受賞会見で、次のようなことを言っている。
「この作品は、言葉で何かを解決しようとか、言葉で対話することを諦めたくない人のために書いた作品です」
芥川賞受賞会見より
この言葉に僕は深く共感した。
他者を失わないために、言葉を捨ててはいけないのだ、僕たちは。
考えるしかない。言葉って何? ということを。
コミュニケーションって何? ということを。
きっと小説のラストは、そのことを暗示している。
もしも彼らの独り言に返事をしたくなったら、どうすればいいのだろう?
(中略)
考え続けなくてはいけないのだ。いつまで? 実際にこの体が支えきれなくなるまでた。すべての言葉を詰め込んだ頭を地面に打ちつけ、天と地が逆さになるのを見るまでだ。(P143より)
たとえ、言葉でのコミュニケーションに限界があったとしても、言葉によるコミュニケーションを諦めてはいけないのだ。
そのためには、一度、自らが溜め込んだ言葉や、言葉に対する向き合い方を再点検しなければならない。
きっと、そういうことを、小説のラストは語っているのだろう。
以上、『東京都同情塔』の解説と考察を終わります。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
芥川賞作品を読むなら”Audible”

今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、人気の芥川賞作品が月額1500円で“聴き放題”となる。
たとえば以下のような作品が、”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの純文学作品や、伊坂幸太郎や森見登美彦などのエンタメ小説の品揃えも充実している。

その他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は12万冊以上と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・





コメント