はじめに

「宗教」=「あやしい」
そんな思いを抱く人は、僕の周りに結構おおい。
「哲学」=「むずかしい」
そんな思いを抱く人も、僕の周りに結構おおい。
だけど、みなさん、なぜか「哲学」に関しては「あやしい」とあまり思わないようだ。
もし「哲学」が怪しくないのなら、「宗教」だってちっとも怪しくないぞ、と僕は言いたい。
では「宗教」とは、いったい何なのか。
超シンプルに言えば、次の2つになる。
- 宗教は、「自我」と「言葉」の限界を示すもの
- 宗教は、「自我」と「世界」のつながりを取り戻すもの
次に「宗教」と「哲学」の共通点とは何なのか。
これも超シンプルに言えば、次の通りだ。
- “言語以前”の真理を志向すること
最後に「宗教」と「哲学」の違いとは何なのか。
またまたシンプルに言えば、次の通り。
- 哲学は「真実の世界」を“認識する”こと。
- 宗教は「真実の世界」を“体験する”こと。
さて、いきなりこんな結論だけ聞かされたところで、多くの人は間違いなくチンプンカンプンだと思う。

なんだ、「宗教」どころか、「哲学」だって怪しいんじゃないか
そう思われてしまうのは、僕の望むところではない。
そこで、以下、「宗教とは何か」を中心に「哲学とは何か」についても、詳しく解説をしていきたい。
ていねいな解説を心掛けた結果、分量がとても多くなってしまった。
ただ、その分だけ、内容は分かりやすくなっていると思う。
この記事を最後まで読み終えることができれば、「宗教とは何か」その勘所をきちんと理解できるはず。
参考本『宗教とは何か』(八木誠一)

改めて、この記事の一番の目的は何かといえば、「宗教とは何か」を明らかにすることである。
その中で「宗教」と「哲学」との“違い”や“共通点”についても明らかにしてみたい。
そのために、とても参考になるテキストを紹介しよう。
八木誠一 著『宗教とは何か』(法蔵館文庫)である。
――宗教とは何か――
その問いに対する解答を先ほど示した。
実はこれ、本書『宗教とは何か』における結論と(ほぼ)同じものだ。
それを示すと、次の2つになる。
- 宗教は、「自我」と「言葉」の限界を示すもの
- 宗教は、「自我」と「世界」のつながりを取り戻すもの
である。
それを論究するうえで、本書『宗教とは何か』は全5章からなっている。
その内訳は以下の通り。※( )内は僕の補筆。
- 第1章「現代思想の観点から」(問題の設定)
- 第2章「倫理の観点から」(問題の設定)
- 第3章「宗教とは何か」(本論①)
- 第4章「宗教の言語」(本論②)
- 第5章「例証―イエスの言葉に即して―」(本論の実践)
個人的に、本書の「主旨」を理解するうえで特に重要な章は、「第1章」と「第3章」と「第4章」だと考えている。
以下、その3つの章を中心に、できるだけ分かりやすく、かみ砕いて説明をしてみよう。
スポンサーリンク
宗教と哲学の“共通点”と“違い”
「現代思想」による問題提起

本書の第1章では「現代思想が指摘していること」がまとめられている。
「現代思想」と一口にいっても、そのジャンルは様々。
本書で扱われているのは、主に「大陸哲学」(ドイツとかフランス)と「英米哲学」(イギリスとかアメリカ)である。
そこに加えて「心理学」とか、日本の「京都学派」の哲学も扱われている。
これらを整理すると次の通り。
「大陸哲学」 …キルケゴールとかの“実存主義哲学” …ニーチェにおける“生の哲学” …ソシュールとかの“構造主義” …フッサールの“現象学”
「英米哲学」 …ウィトゲンシュタインとかの“分析哲学”
「心理学」 …フロイトやユングの“精神分析学”
「京都学派の哲学」 …西田幾多郎の“主格未分”や“直接経験”の概念など
ごらんのとおり、本書の射程はは驚くほどに広い。
が、これらの「思想」から、八木はある「共通点」を取り出して見せる。
その「共通点」とは、
「自我」と「言語」の“限界”を示している点
である。
多くの「現代思想」が、次のような指摘をている。
「“自我”とか“言葉”があるから、人間はこの世界を正しく認識できないのだ」
こう聞くと、

いや、自我とか言葉って、どっちも人間の“本質”じゃん!

自我とか言葉があるから、人間は他の生き物と区別されるんでしょ?
と、反発や疑問を抱くかもしれない。
うん、確かにその通り。
まず、第一、僕にもあなたにも“自我”はあるからだ。
“自我”とは分かりやすく言えば、
「僕はあなたではない。そこにいる鈴木さんでも佐藤さんでも高橋さんでもない。僕は他でもない僕である」という実感のことだ。
次に、第二、僕もあなたも日常的に“言葉”を使用しているからだ。
目の前にいる「他者」とコミュニケーションをとれるのも“言葉”があるからに他ならない。
たとえば、
「ほら、あの夕日を見てごらん。キレイだろ。僕は夕日が大好きなんだ」
と、こんな風に、自分が見た世界について説明するし、自分の心のありようを語るし、それを他者と共有したりする。
「僕」がいて「あなた」がいる。
2人は「言葉」によってつながれる。
こんな風に僕たちは“自我”とか“言語”とかを、どちらも自明のものとして考えている。
しかも、それらの「利便性」とか「有用性」とかについて、ほとんどの人が疑問にすら思わない。
ただ繰り返すが、「現代思想」においては、まさしくその「自我と言語」が問題視されているのだ。
いや、「自我と言語」という言い方で両者を同列に扱うべきではないだろう。
なぜなら、「自我」を生み出している、その張本人は「言葉」だらだ。
別に犯人捜しをするわけではないが、僕たちが「世界を正しく認識できない」のだとすれば、その最大の原因は「言葉」にあるのだ。
ここについては、後の「京都学派の哲学」で説明したい。
スポンサードリンク
「大陸哲学」の思想内容

ではここからは「現代思想」が「自我」や「言語」についてどのようにとらえているかを簡単に説明したい。
まず「実存主義哲学」
この思想を超シンプルにまとめると、
「他ならぬ“私”にとっての“真理”を追究するべき」
という思想である。
キルケゴールも、ヤスパースも、サルトルも、ハイデガーも、結局のところこの「唯一無二の“私”(実存)にとっての真理とは何か」を問うた哲学者だといえる。
その「真理」へのアプローチは、各思想それぞれ違うわけだけれど、彼らに共通してみられるのは、
- 「真理は“客観的”には語りえない」
- 「本当に必要なのは“私”にとっての真理である」
という謙虚かつ切実な姿勢であるといっていい。
実存主義哲学の画期的な点は、まさしくこの「真理は“客観的な言語”では語れない」ことを指摘した点にあった。
実はこの点において「心理学」も「現象学」も、同じような主張をしている。
たとえば「精神分析学」のフロイトやユングなんかは、人間の思考や行動の背後で「無意識」という領域が大きく影響をしていることを説き、
「人間の“理性”なんてあてにならないよね」
と言い放った。
これは、これまでの西洋では常識だった「人間は、理性によって真理に到達できます」という哲学観に対して、
「それって、人間を買いかぶりすぎじゃないですか?」
と批判をしたものだといえる。
それから「現象学」のフッサールだって似たようなことを言っている。
彼もまた、かつての西洋における「人間は世界を正しく知覚できます」という楽観的な人間観に対して、
「それって、ちょっと短絡的じゃないですか?」
と批判を加えた思想家である。
えてして僕たちは、自分たちの「知覚の正しさ」について疑おうとしない。
たとえば、あなたの目の前に「赤いリンゴ」が見えているとする。
あなたはそれを見て、「赤いリンゴ」の“実在”を信じて疑わないだろう。
多くの人たちは、この世界は「見たまま」「聞いたまま」「感じたまま」に存在していると、そんな確信を持っている。
ところが、フッサールは次のようにいう。
「見えるものは“見える通り”に実在しているとは限らないよ」
それは、言い換えれば、
「客観的な世界」が実在しているかなんて、人間には証明できない
ということになる。
だからこそ、フッサールは「客観的世界」の存在を信じて疑わない僕たちに対して、
「ちょっといったん落ち着こうよ」
ということで、こんな提案をしてくるわけだ。
「世界が実在している”だなんて判断、とりあえず止めてみませんか?」
こうしてフッサールは、人々から「楽観的な世界認識」を捨てさせ、(これを“エポケー”という)「現象そのものへ」のモットーを掲げ「現象学」という哲学を確立した
それから「構造主義」なんて、もう、完膚なきまでに「人間」とか「自我」というものを解体してしまう。
特にソシュールが凄すぎる。
彼は、「あなたが認識しているその世界は、すべて“言葉”が生み出したものに過ぎませんよ」と説明する。
それからレヴィストロースとかバルトとかフーコーも、
「あなたの行動や思考や感情は全て(主に社会の)システムによって選び取らされたものにすぎませんよ」
と説明する。
要するに、「構造主義」が明らかにしたことは、
「人間は意識の深層にある“構造”によって支配されており、人間の“主体性”など幻想である」
ということなのだ。
「構造主義」ほど、人々が持っている「人間への信頼」を打ち砕いた思想はないだろう。
フーコーの有名な言葉に「人間の終焉」というものがある。
これはつまり“人間なんてあてにならない”ということだ。
もはや人類は「構造主義」によって「人間終了のお知らせ」を告げられている状況にある。
ということで、結論。
人間は“真理”に到達できないし、この世界を正しく認識できない。
スポンサーリンク
「分析哲学」の思想内容

さて「人間終了のお知らせ」を発表した構造主義。
それは大体1960年代くらいの話だが、それとほぼ同時期に勢力を拡大してきた哲学がある。
それが英米系の「分析哲学」だ(ちなみに、今はこの分析哲学が主流となっている)。
「分析哲学」ってのは、かなりリアリスティックな思想で、良く言えば謙虚、悪く言えば冷淡な思想である。
「“真理”なんて人間には分かりっこないんだから、せめて人間が“言語化できるもの”だけに関心を向けようよ」
これが「分析哲学」の基本方針である。
大風呂敷を広げずに、言語化できる限りで、地道にコツコツと思想を積み重ねようというわけだ。
語りえないものは、沈黙するしかない
これはウィトゲンシュタインの有名な言葉だが、これは要するに、
“論理”によってきちんと言語化できるものしか認めません
というある種の「割り切り」宣言である。
こういう立場を「論理実証主義」と呼んでいる。
論理実証主義は、
「これは語ることができる。これは語ることができない」
といった感じで「人間の守備範囲」を規定し、守備範囲“外”のものはバサバサと切り捨てていった。
では、その守備範囲外のものとは何か。
それが、
精神、心、神、宗教
というものだったのだ。
- 認識できないもの
- 実体のないもの
- 非物質的なもの
それらは「僕たちの守備範囲を超えちゃってます」と、無情にも切り捨てられてしまったわけだ。
以上が西欧を中心とした「現代思想」の概要である。
「大陸哲学」しかり「英米哲学」しかり。
とにかく「現代思想」が明らかにしたのは「人間」のある種の「無力さ」であった。
さあ。
たぶん、多くの人がこの記事の目的を忘れてしまっているので改めて言っておくが、僕たちの目的は「宗教とは何か」を明らかにすることだった。
それはつまり、著者「八木誠一」の主張を解説することなので、ここでもう一度、彼の主張を提示したい。
- 宗教とは、「自我」と「言葉」の限界を示すもの、である。
- 宗教とは、「自我」と「世界」のつながりを取り戻すもの、である。
どうだろう。
一つ目の「自我と言葉の限界を示す」という部分に関しては、すでに概ね理解できるのではないだろうか。
実は「宗教」の世界観というのも、「現代思想」の世界観と、ほとんど同じなのだ。
両者はともに、
そもそも「人間」には限界がある
ということを主張しているわけだ。
このことを、本書『宗教とは何か』の文脈に即せば、
「自我」と「言葉」には限界がある
と言い換えることができる。
スポンサーリンク
・
「京都学派哲学」の重要さ

では、なぜ「人間」は“世界”を正しく認識できないのだろう。
なぜ「人間」は“真理”を明らかにすることができないのだろう。
その答えは、
人間が「言葉」という桎梏にとらわれてしまっているからだ。
分かりやすく言えば、
人間が「言葉」という“色眼鏡”を通して世界を認識してしまっているからだ。
これは、逆に言うと、
人間が「言葉」の桎梏から解き放たれるとき、“真理”に出会うことができる
ということになる。
この点は大事なのでもう一度いう。
「言葉」の支配から抜け出せたとき、僕たちは“真実の世界”を知ることができる。
そしてこのことは、「京都学派」の哲学者たちが鋭く指摘していることなのだ。
「宗教とは何か」という問いに答える上で、八木は「京都学派」の重要性を認めている。
我々にとって特に重要なのは京都学派の立場である。重要だというのは、言語化以前の現実の現前を立場としているからで、したがってここでは言語を語る自我が相対化されるとともに、言語化する自我たちの、言語化された世界も相対化される。(文庫版P74より)
やや表現が難しいので、かみ砕いて説明してみる。
そもそも、僕たちが世界を認識できるのは“言葉”があるからに他ならない。
たとえば、今あなたの周囲をざっと見渡してほしい。
椅子、テーブル、お皿、リンゴ、コップ、テレビ、パソコン、スマホ……
あなたの世界はあらゆるモノで溢れていて、あなたはその1つ1つを認識している。
だけどそれは、あなたが“言葉”を持っているから可能なのであり、あなたがそれぞれの「名前」を知っているから可能なのだ。
この辺りはソシュールの言語観を理解すれば、ストンと腑に落ちるところなので、詳しくはこちらを参照していただきたい。【 参考記事 分かりやすく解説『言葉とは何か』(丸山圭三郎)ーソシュールの言語観ー 】
要するに、あなたの世界は“言葉”が生み出しているのだと言って良い。
とすれば、たとえば「こころ」とか、「死」とか、そういう実体のないものを信じて疑わないのも、実は“言葉”があるからに他ならない。
そして、もっとラディカルなことを言ってしまえば、「私」というアイデンティティだって “言葉”があるからこそ存在するものなのだ。
想像してみてほしい。
たとえば、あなたが無人島に一人産み落とされ、他者もなく“言葉”を獲得することもなく、今のあなたの年齢まで成長したとする。
その時はたして、あなたは「私」という一人称を使うことができるだろうか。
「私」という「自我」を、あなたは“実感”することができるだろうか。
応えは「否」だ。
“私”という言葉がなければ、あなたは原理的に「私」を感じることはできないのだ。
僕がここで何が言いたいのかといえば、
「自我」とか「世界」を生み出している張本人は、何を隠そう“言葉”である
ということなのだ。

じゃあ、やっぱり、“言葉”って重要なんだね
そう思ったあなた。
ここで「現代思想」が明らかにしたことを、もう一度思い出してほしい。
「真理」は「言語」によって語りえない
多くの思想家、哲学者たちは、口をそろえてそう言いっていたではないか。
つまり、あなたが“言語”を通して知覚・認識している世界は、本当の世界ではない。
もっと過激なことを言ってしまえば、
あなたが見ているその世界は、言語が生み出したフィクションなのだ。
であれば、「真理」とか「本当の世界」に到達するために必要なことは、たった一つ。
「言葉の支配」から脱出することだ。
もう一度、京都学派の重要性について、八木の言葉を引用する。
我々にとって特に重要なのは京都学派の立場である。重要だというのは、言語化以前の現実の現前を立場としているからで、したがってここでは言語を語る自我が相対化されるとともに、言語化する自我たちの、言語化された世界も相対化される。(文庫版P74より)
京都学派の哲学者たちが目指したもの。
それがまさしく
「言語化以前」の世界の現前、というわけだ。
スポンサーリンク
西田哲学「直接経験」とは

「京都学派」の哲学の中から紹介したい概念が、西田幾多郎の「直接経験」という概念だ。
「直接経験」とは何か、それを乱暴に一言で言ってしまえば、
“私”と“世界” が一体化した経験
ということになる。
それはつまり、
「言語化以前の世界」を取り戻すこと
と言い直すことができる。
たとえば、美しい風景を見たときに、僕たちは「言葉を奪われる」ほどに感動する。
あるいは、あまりに素晴らしい芸術作品に出会って、「我を忘れる」ほどに集中することが、まれにある。
茫然「自失」することもあるし、「放心」状態になることもある。
そんなとき、“僕”や“私”という意識は実は存在していない。
「ねえ、ちょっと! 話し聞いてるの!?」
と、声を掛けられて、ようやく冷静な“思考”つまり“言葉”が戻ってきたときに、
「あ、ごめん、ちょっとぼーっとしてたわ。で、なんだったっけ?」
と、「自分」と「他者(世界)」を取り戻す。
この「すべてが一体化して、ただ“経験”があるだけの状態」こそが、西田のいう「直接経験」で、それこそが「真理」の体験なのである。
直接経験には、大きく3つのタイプが存在している。
- 主―客直接経験
- 我―汝直接経験
- 自我―自己直接経験
西田はこれらの「直接経験」について、こんな風に説明している。
毫も思慮分別を加えない、真に経験そのままのの状態、たとえば、色を見、音を聞く刹那、いまだこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じているというような考えのみならず、この色、この音はなんであるという判断すら加わらない前をいうのである。『善の研究』より
要するに、西田のいう「直接経験」とは、
「”私“が消滅して、ただ”世界“と”経験“だけがある」という状態、をいうのだ。
「“私”と“世界”の一体化」と言い換えてもいい。
これを西田は「主客未分」と呼んでいるのだが、「直接経験」とほぼ同義と考えてもらってかまわない。
これは、「“私”がいて、目の前の“世界“を認識している」という、僕たちの常識的世界観に反している。
さて、以上の「直接経験」について、八木はおおむね次のように解釈している。
- 主―客直接経験 = 私と事物が一体となる経験
- 我―汝直接経験 = 私とあなたが一体となる経験
- 自我―自己直接経験 = 私と“超越”が一体となる経験

いや“超越”って何?
と、思うだろうが、この辺りのことは次章で説明するするので、慌てないでほしい。
「直接経験」それぞれ次のように呼ばれている。
- 直接経験タイプA
- 直接経験タイプB
- 直接経験タイプC
この分類は便宜的なものなのだが、かるく覚えておいてもらえると嬉しい。
この章の“まとめ”

さて、以上が「現代思想」についての解説だ。
八木が言いたいことは、
「現代思想」の世界観も「宗教」の世界観も、つまるところは同じだよ
ということである。
両者はともに、
「人間は真実の世界に到達していない」
ということを前提にしつつも、
「人間と世界が一体化した状態がある」
ということを主張しているのだ。
ちなみに八木は、「宗教」に関して次のように言っている。
宗教――すくなくともキリスト教と仏教――は、直接経験を知り、経験自体と、この経験の現場で見えてくるものを伝えてきた。
宗教が伝えてきたものは「直接経験」である、と言っているワケだ。
じゃあ「宗教」と「哲学」って、全く同じものなの?
そう問われれば、「否」と答えたい。
両者の違いはこうだ。
- 哲学は「真実の世界」を“認識する”こと。
- 宗教は「真実の世界」を“体験する”こと。
まさにこの点において「宗教」の本質が見えてくるのであり、「宗教とは何か」の問いに答えるための糸口がある。
スポンサーリンク
・
「宗教」とは何か
「直接経験」≠「宗教」

ここまで読んだ読者の中には、ひょっとして、

分かった! とにかく「宗教」=「直接経験」なんだね
と、理解している方もいるかもしれないので、早い内に誤解を解いておかなくちゃいけない。
「直接経験」(自我と世界の一体化した世界)というのは、基本的に「哲学」の次元を出るものではない。
- 事物との一体化
- 他者との一体化
それはあくまでも「認識」であって、それを「宗教」と呼ぶことはできない。
ただし「直接経験」のうち、「宗教」の本質と類似、あるいは同等の概念がある。
ここでもう一度、直接経験の3つのタイプを思い出して欲しい。
直接体験タイプA …主―客直接経験 = 私と事物が一体となる経験
直接体験タイプB …我―汝直接経験 = 私とあなたが一体となる経験
直接体験タイプC …自我―自己直接経験 = 私と“超越”が一体となる経験
唐突だけど、まずは結論を言う。
「直接経験タイプC」こそ「宗教」の本質であり「宗教」の始まりである。
八木はこんなふうに説明をしている。
直接経験Cの立場は宗教となりうるけれども、直接経験AあるいはBだけでは哲学の立場となりえても、宗教とは言い難いだろう。(P197より)
つまり、
- “私”と“事物”の一体 = あくまで哲学
- “私”と“あなた”の一体 = あくまで哲学
- “私”と“超越”の一体 = もはや宗教
と、八木は言っている。
AとBが宗教になり得るためには、必ずCと結びつけなければならない、と八木は続ける。
「宗教」の根幹には、必ず「自我―自己の直接体験」が必要というわけだ。

っていうか “自我”って何? “自己”って何? “超越”って何? さっぱり分からないよ
そんな読者の声が聞こえてきそうなので、いそいで次の説明にうつる。
スポンサーリンク
「自己」=「神」

直接経験C(“私”と“超越”の一体化体験)の説明のとっかかりとして、まず八木の次の言葉を引用したい。
(直接体験)Cが宗教たりうるというのは、そこで超越的―内在的な働きが自覚され、神秘として経験されるからであり、そこから、その働きに自分をうち任せつつ、自覚を深めてゆく信仰的認識の立場が開けてゆくからである。
うん、なんだか難しいぞ。
難しいのだけれど、この部分を理解しなければ「宗教とは何か」を理解することはできないので、ぜひ頑張ってついてきてほしい。
まず、直接体験Cとは「自我」と「自己」が一体化することだった。
この「自己」というのが、本書における超重要ワードである。
そして、本書において色んな言葉で言い換えられている。
たとえば、超越、神秘、法、如来、そして神……
こう書けば分かると思うが、「自己」というのは、「宗教」の基礎といおうか、勘所と言おうか、とにかく絶対に外すことのできない本質的な部分なのである。
純粋経験Cというのは、「自我」と「自己」が一体化する経験のこと、つまり、
“私”が“超越”と一体化すること、を表している。
この“超越”は仏教の文脈で言えば「法」とか「如来」と言い換えられるだろうし、イスラム教の文脈で言えば「アッラー」ということになるだろうし、ヒンズー教の文脈で言えば「ブラフマン」ということになるだろうし、そしてキリスト教の文脈で言えば「神」ということになる。
ほら、段々見えてきた。
つまり、宗教とは「自我」と「自己」の一体化を目指す営みなのである。
そして、仮に「キリスト教」という宗教を説明するならば、それは、
「私」と「神」の一体化を目指す営み
ということができるのだ。
そして、その一体化を目指すためには「言語の支配」から解放される必要がある。
ここでもう一度、先ほどの八木の言葉を引用したい。
(直接体験)Cが宗教たりうるというのは、そこで超越的―内在的な働きが自覚され、神秘として経験されるからであり、そこから、その働きに自分をうち任せつつ、自覚を深めてゆく信仰的認識の立場が開けてゆくからである。
ここを注意深く読んでみると、「超越的―内在的な働きが自覚され」という表現が目に付く。
これはつまり、
超越(神)は、自らの内に存在している
ということに他ならない。
神とは“私”(つまり自我)の中にある。
神は「私」の“外”に存在しているのではない。
神は「私」の“内”に存在しているのだ。
その“私”の中に宿っている“神”の働きに気がつくこと、自覚すること、もっといえば“体験”すること。
そこに「宗教」の本質が宿っている。
スポンサーリンク
・
「私」という幻想

ここで、少し「哲学的」な話題に立ち返り「私」という概念の不確かさについて共感してもらいたい。
早速 いまここで試して欲しいことがある。
目を閉じても、開いていても構わない(まぁ、閉じた方がやりやすいかも)。
あなたの「意識」の隅々を探ってみて「私」がどこに“ある”のか、探してみてほしい。
「私」の正体を突き止めてみて欲しい。
念のため確認しておくが、僕がいう「私」というのは、あなたの「名前」でもないし、あなたの「思い出」でもないし、あなたの「思考」でもない。
あなたが「私」と呼ぶところの対象といおうか、実体というおうか。
とにかく「あった! これが“私”だ!」と確信できるまで、あなたの隅々を探してみて欲しいのだ。
さあ。
それでは目を閉じて、。
はい、どうぞ。
…
……
………
…………どうだろう。
うまくいっただろうか。
どうか認めて欲しい。
間違いなく、うまくいかなかったはずだ。
今あなたが見つけることが出来たのは、
テレビや話し声など“ざわめき”だったり……
窓から拭いてくるかぜの“そよぎ”であったり……
淹れたてで香ばしいコーヒーの“香り”であったり……
なんとなく感じている“空腹感”であったり……
「ああ、腹減った、ラーメンたべたい」という思考であったり……
多分、そんな所だったのではないだろうか。
それらは“独特の感覚”とか“独特の質感”というべきものであり、
「あった! これが“私”だ!」
と確信をもっていえる代物ではなかったはずだ。
そうなのだ。
実は、僕たちがどんなに「この意識」の内を探してみても「私」という実体をつかむことはできない。
つかめるのは独特の“感覚”だけなのだ。
イギリスの経験論哲学者に「デイヴィッド・ヒューム」という大天才がいる。
彼の有名な言葉にこんなものがある。
「人間とは感覚の束である」
ヒュームが明らかにしたのは、
「あるのは、独特の“感覚”だけ。“私”という実体なんて、どこにもない」
ということだった。
ヒュームの言葉は、間違いなく真理であろう。
僕たちは「私は…」とか「僕は…」とか「俺は…」とか、普段何気なく口にしているけれど、実はそんなもの、「この意識」のどこを探しても存在していない。
では、なぜ僕たちは「私」とか「僕」という実体を信じて疑わないのか。
なぜ僕たちは「私」とか「僕」が実在していると思い込んでしまっているのか。
この記事を読んでこられたあなたは、もう分かるだろう。
人間が「言葉」を持っているからである。
人間が「言葉」に支配されているからである。
だから、言葉を知らない「赤ん坊」には“私”もなければ“世界”もないのだろう。
もしも、あなたが無人島で一人生まれ、一人で育ってきたとしたら、“私”もなければ“世界”も存在していないのだろう。
スポンサーリンク
この世界を経験している「主体」

「私」は「言語」が生み出した幻想である。
そんなことをヒュームはいっていた。
そういえば「現代思想」も、
“自我”と“言語”には限界がありますよ
なんていっていたではないか。
だけど、そう言われたって、(仮に理屈は理解したとしたって)、やっぱり僕たちの実感から大きくかけ離れている。
なぜなら、
目の前に広がる景色とか、聞こえる音とか、感じる味とか、空腹とか、だるさとか、苦しみとか、痛みとか……
そういう具体的な“感覚”は、はっきりと「ここ」にあるからだ。
そもそも、この“感覚”が「ここ」にあることが、僕には不思議でならない。
どうして、この世界が「ここ」にあるんだろう。
どうして、この“僕”は存在しているんだろう。
ふとした瞬間、僕はこの不思議に絡めとられてしまうことがある。
そんなときに、先ほどのヒュームの言葉を思い出す。
ヒュームは僕にこう言ってくる。
「“僕”なんてね、そもそもが思い込みなんだよ。“僕”なんて実体のないフィクションなんだよ」
なるほど。
確かにそうなのかもしれない。
だけど、1つだけ言わせてくれ。
じゃあ、この世界を認識しているのは、一体全体だれなんだ?
この世界を生み出しているのは、この世界を経験しているのは、この世界の中心は“僕”でなければ、一体全体だれだというのか。
よし、わかった、百歩譲って“僕”は実在しないとしよう。
だけど、この世界を経験している“主体”というのが、現に「ここ」にいるじゃないか。
それは一体だれなのか。
そこで、僕はふと、こう思ったりする。
ひょっとしてそれは“神”なのかもしれない。
唐突に“神”と聞いて嫌悪感や抵抗感を抱いた人も多いと思う。
それなら“神”を「超越」とか「神秘」とか、遠藤周作風にいえば「たまねぎ」とか「にんじん」とかに言い換えてもいい。
大体、こんなにも科学や生理学が発展した今だって、人間の「自我」とか「心」の正体を明らかにできていないのだ。
この「心」の存在からして、そもそもがとてつもない謎なのだ。
だから、そうした「神秘的」な主体を持ち出さない限り、この不思議な世界を説明することはそもそも不可能なように僕には思われるのだ。
僕の「ここ」にある世界
あなたの「そこ」にある世界
これらを「経験」しているのは、“僕”でも“あなた”でもないとしたら。
それはきっと何か「神秘的」な主体なのではないか。
スポンサーリンク
「宗教」の基礎は「神秘体験」
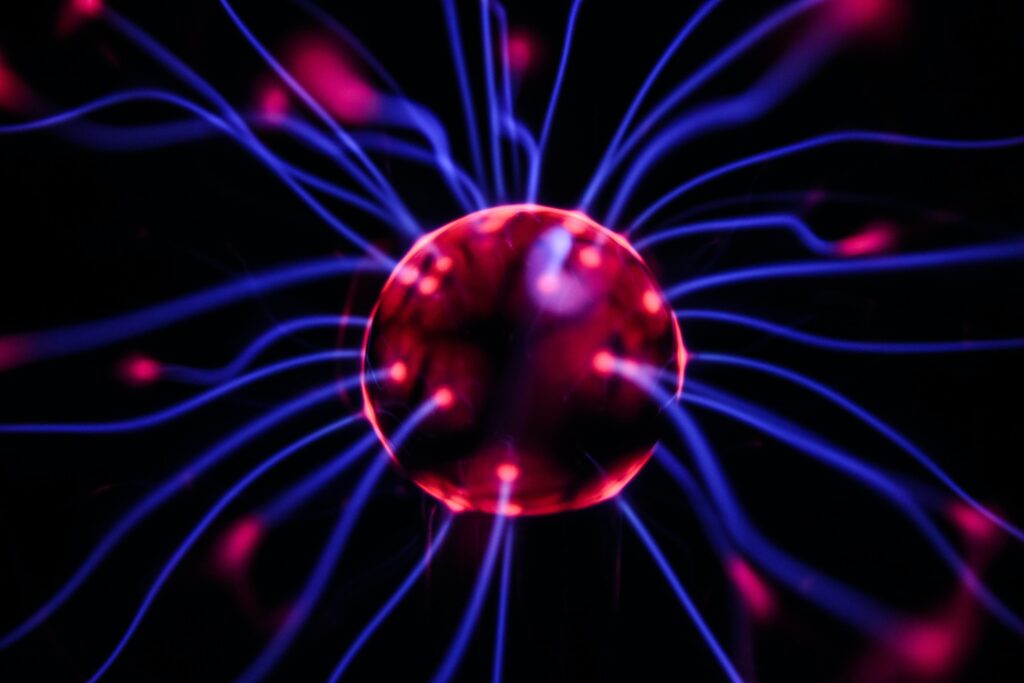
ここで直接経験Cの話に戻そう。
「自我―自己」直接経験が意味しているのは、まさにこの「内なる神」の自覚なのだ。
“僕”が消滅して“神”だけが残る。
世界は“神”だけになる。
それは「神秘的な体験」といってもいいだろう。
ドイツの宗教学者に「ルドルフ・オットー」という人物がいる。
彼は主著『聖なるもの』において、その神秘的な体験を「ヌミノーゼ(聖なるもの)」という概念を用いて説明している。
オットーによれば、「ヌミノーゼ体験」とは以下のもの。
- 人間には“絶対他者”の存在が直覚されることがある。
- そのとき自らの内から、“原始的”な感情が沸き立つ。
- その感情は“畏怖”と“恍惚”がないまぜになったようなものである。
- その体験は言語化が不可能であり、説明もできない。
このオットーの説明はとても示唆に富んでいる。
えてして、「宗教」は「文化」とか「習慣」とか「倫理」の別名のように考えられがちだ。
たとえば、
「正月になったら神社にお参りに行きましょう」とか、「お盆になったらお寺に墓参りに行きましょう」とか、「殺生をしてはいけません」とか、「隣人を愛さなければいけません」とか……
だけどそれらはあくまで「宗教」の一側面であり、誤解を恐れず言えば「枝葉」の部分だといっていい。
宗教の本質というのは、あくまで、その人自身の「神秘体験」にあるといっていい。
そして繰り返しになるが、その「神秘体験」とは、
「“私”と“超越”が一体であることを自覚すること」であり、仮にキリスト教の文脈で言い換えるならば、「“私”と“神”の一体を体験すること」なのである。
スポンサードリンク
この章の“まとめ”

さて、以上が「宗教とは何か」についての解説だ。
ここではヒュームの哲学を援用し、「自我」の頼りなさについて確認した。
ただ「自我など幻想だ」と言われても、それはやはり、僕たちの実感から遠くかけ離れて居る。
なぜなら、現に「この世界」は存在しているし、それを経験している「主体の存在」への直感を、僕たちは捨てられないからだ。
この「世界」を生み出している“主体”……
それは「超越者(神)」なのかもしれない。
「宗教」の本質とは、その「内なる超越者との一体を自覚すること」にあるといえる。
超越者は、キリスト教で「神」と呼ばれている。
つまり、宗教とは、
「(神などの)超越者と一体化する」という「神秘体験」なのである。
これはちょうど、西田哲学の「直接経験タイプC」(自我―自己直接経験)と同じ経験だといえる。
ではその「宗教」とは、どんな風に語られうるのだろうか。
次章でこの問いに答えていきたい。




コメント