日本仏教史の概要を把握したい人は、まずはこちらから
大正時代:「個人の救済」を目指す時代
説明するのが難しい「日本仏教」を、時代ごとに外観しようというのが、この記事の目的。
これまでの記事では、
と、各時代の日本仏教の展開を確認してきた。
簡単に振りかえると、
- 奈良時代では、知的エリートたちによる学問であり、
- 平安時代で、貴族を中心に根付いていき、
- 鎌倉時代で、民衆たちへと爆発的に広がりだし、
- 室町・安土桃山時代で、武士を中心に世俗化していき、
- 江戸時代で、葬式仏教化が決定的になり、
- 明治時代で、排斥にあうが、なんとかそれを乗り越えてきた。
そして、今回は大正 (ときどき明治) 時代。
大正時代の仏教の立ち位置を説明するうえで、絶対に避けては通れない話がある。
それは、人々の「自意識」についてだ。
その辺を説明するためには、明治時代について、あらためて確認すべきことがある。
ただ、そこをおさえることができれば、仏教を、ひいては宗教全体の意義を理解することができるかもしれない。
だから、まず、その辺を詳しく説明しようと思う。
ちょっと長くなるが、ぜひ読んでほしい。
「近代的自意識」の発見

明治時代に、欧米の文化がドガッと日本に流れ込んできた。
文化、学問、科学、キリスト教などなど。
日本はこれらを、あっという間に吸収し、スピーディーに近代化を推し進めていった。
そんな中で、日本人は、あることに気が付きはじめる。
それは「個人の自由」である。
「欧米では、生まれとか、家とか、性別とか、そんなに大事じゃないらしいよ」
「欧米では、とにかく『自分自身』の気持ちを優先するみたいだよ」
そんな風に、日本人は「個人の自由」という価値観を獲得していったといわれている。
それと同時に、芽生えたものがある。
それが、「ぼく・わたし」という新たな自意識である。
「えっ? 何を今さら。『ぼく・わたし』の意識なんて、江戸時代以前にもあったんじゃないの?」
と、思う人も多いと思うので、もう少し詳しく説明する。
もちろん、江戸時代以前にも、「ぼく・わたし」という自意識は存在していた。
むしろ、日本人は、「ぼく」がすべきこと、「わたし」がすべきことを考え、それを忠実に守っていたとさえ言える。
ただ、その「ぼく」というのは、あくまでも、
「〇〇藩に所属する、ぼく」であったり、「〇〇家の長男である、ぼく」であったり、「農民の息子である、ぼく」であったりしたわけだ。
ここには、
「藩のため、家のため、長男として理想的な『ぼく』になろう」
という意識が、ねっとりとこびりついている。
これは、明治以前に見られた身分制度、いわゆる封建制度の影響が大きい。
「武士の息子は武士!」
「農民の息子は農民!」
「長男は家を継ぐ!」
「女は家で家事をする!」
みたいな感じで、この時代は、生まれながらにして、その人の一生が決定された時代だった。
しかし、明治時代になると、「個人の自由」という欧米の思想が日本に入ってくるわけだ。
「どこに住んでようが、家業が何だろうが、誰の子どもだろう、何番目に生まれようが、男だろうが、女だろうが、君は君だ。自由に生きていいんだよ」
という価値観が、ゆっくりではあるが、人々に浸透していくことになる。
だけど、急にそんなこと言われても、困ってしまう。
たとえば、
「なんでも好きにやっていいよ」
とか、
「なりたいものに、なっていいよ」
とか言われても、
「え、おれ、何したいか分からないんだけど」
とか、
「え、別になりたいものとかないし」
なんていう風に、結局、自分では何も決められないってこと、結構あると思う。
「自由」といえば、とっても聞こえはいいのだが、ちゃんとした自分を持っていない人にとっては、「自分じゃ何も選べません」と、結局、悩みの種を与えられることになってしまう。
それだけじゃない。
たとえば、今までであれば、「ぼくは越後藩出身、山本家の長男で、将来は農家をつぐんだ」という意識のおかげで、「自分が何者か」、はっきりとわかっていたわけだ。
しかし、明治以降「個人の自由」を獲得した結果、それはこうなる。
「ぼくって何者だ?」
しかし、その問に対して、時代はこう答える。
「あなたが何者か。それは、あなた自身が決めればいいよ」
こうして、人々は「ぼくは何者か」に対する答えを自分自身で探さなければならなくなった。
冒頭で述べた「ぼく・わたし」という意識は、こういう事情から生まれた。
どんなものからも自由で、純粋無垢な「ぼく・わたし」という意識、
これを「近代的自意識」という。
明治・大正とは、この意識が日本人に広まりだした時代なのだ。
人によっては
「よっしゃー! 農家の子どもだけど、東大いって偉くなるぞ!」
と思うが、人によっては、
「え、ぼくって何をしたいんだろう? 自由ってなに? ぼくってだれ?」
と、困惑し、苦悩し、煩悶することになってしまう。
スポンサーリンク
「自意識」で苦悩した人たち
おもに苦悩したのは、こんな人たち。
- 最先端の西洋思想に触れられる。
- 抽象的で高い思考力がある。
- 時間と金がある。
つまり、「自由」を語った書物に触れ、「ぼくって誰?」と高度な問題意識を持ち、時間をかけてじっくりと自問自答ができる人たち、ということになる。
ありていに言ってしまえば、高学歴エリートたち、ということだ。
煩悶少年「藤村操」

有名なのは、藤村操(ふじむらみさお)という、東大生の男の子だ。
近代的自意識に悩まされた彼は、一日中、煩悶し続けた。
ぼくって誰だろう。
どうして、ぼくは存在しているのだろう
どうして、ぼくは生きているのだろう
どうして、ぼくは死んでいくのだろう
いったい、ぼくは、どこからきて、どこへいくのだろう………わあああああああああああああああああああああ!!!!!
となったのかもしれない。
彼は、日光の華厳の滝のてっぺんに立ち、傍らの木に、自作の詩を刻み込んだ。

万有の真相は、ただ一言にして、ことごとくす、曰く、「不可解」
この世界の全ては、ぼくにとってはこの一言に尽きる……
「なんも分かんねえ!」
そう記した藤村少年は、その身を華厳の滝に投げ入れ、命を絶った。
若干16歳の、あまりに早すぎる死であった。
将来が約束された東大生の自殺は、センセーショナルに報道された。
多くの人たちが、
「なんで? まだ若いのに。しかも、東大生だなんて、将来は安泰じゃない……」
と首をかしげる中、やはり、共感する人たちも一定数いたようだ。
「わかるぜ、藤村君。ぼくも、きみに続くよ」
そうやって、華厳の滝から身を投げた少年が数多くいたらしい。
ちなみに、藤村少年は、あの文豪、夏目漱石の教え子でもあった。
漱石は、名著『吾輩は猫である』で、藤村少年の自殺について触れている。
漱石も藤村少年の死を悼んだ大人の1人だった。
苦悩する文学者たち

こんなふうに、明治から大正にかけて、「ぼく」であることに苦しむ人たちが増えていった。
ぼくたちは、彼らの悩みをいろんな書物によって触れることができる。
たとえば、文豪、芥川龍之介。
彼の作品には、人間のエゴや自意識を扱ったものが多いのだが、そのほとんどに強い厭世観が表れている。
芥川も自殺をした作家なのだが、彼はその遺書にこう残している。
「ぼくが死ぬのは、ぼくの将来に対する、ぼんやりした不安のためだ」
ここには、
「自分は一体誰なのか」
「この苦しい世の中で、自分はどう生きていくべきなのか」
それが分からず苦悩する芥川の姿が表れている。
芥川もまた、「ぼく」であることに苦しんだ人間の1人だったといえる。
それから、北村透谷(トウゴク)。
この人は、ちょっとマニアックかもしれないが、実は「近代的自意識」を発見し、日本中に発信した人物である。。
彼の主著、『内部生命論』
そこには、「近代的自意識」と、そこから生じる「苦悩」と、そこからの「救い」について描かれている。
北村透谷も、「ぼく」であることに悩み、25歳で自殺をしている。
芥川と北村とには、「文学者」と「自殺」という共通点がある。
が、その他にもう1つ、この記事にとって、とても重要な共通点がある。
それは、「キリスト教に関心を持っていたこと」だ。
芥川は、晩年、キリストをモチーフに作品を数多く残しているし、服毒自殺をしたその枕元には聖書が置かれていたといわれている。
北村は、キリスト教徒であり、自分の信仰と神の愛によって、自分は救われると考えていた。
彼ら2人が示している通り、大正時代になると、「個人の苦悩」と「宗教」とが、次第に結びついていくようになる。
スポンサーリンク
主な思想内容① 清沢満之の思想

では、ようやく本題に入ろう。
このころの仏教は、「個人の苦悩」と、どうかかわっていったのか。
まず紹介したいのが、清沢満之という浄土真宗の僧侶だ。
彼自身は、明治の終わりに活躍した僧侶なのだが、彼の業績は大正時代にも大きな影響を与えている。
むしろ、大正以降に活躍した僧侶たちのほとんどが、彼の思想的DNAの後継者だと言って良い。
だから、彼の思想を知ることは、現代仏教を知るうえで大いに役立つと思われる。
精神の充足 = 人間の幸福
清沢満之は、若くして浄土真宗・真宗大谷派の僧侶となる。
彼を紹介するとすれば、まず、なんといってもその明晰な頭脳だ。
東京大学の哲学科を首席で卒業した、正真正銘の天才だ。
卒業後は大学で教鞭をとるのだが、すぐ辞めてしまう。
そして、狂気的といっていいほどの禁欲生活に入っていく。
その徹底ぶりはすさまじく、肉を食べない、酒を飲まないは言うに及ばず、煮炊きもしない、塩も取らない、そば粉と水だけで、その生命活動を維持するというものだった。
彼の体はガリガリに縮み、頬はこけ、目元はくぼんでいく。
一体、何が彼をそうさせたのだろうか。
そこには、「物質的な豊かさには限界がある」という彼の信念があった。
たしかに、彼が言うことには一理ある。
なぜなら、どんなに、おいしいご飯を食べ、おいしい酒を飲んで、ぜいたくな生活を送ったとしても、人間は絶対に満足できないだからだ。
「まだ足りない、まだ足りない」
「もっと贅沢を、もっと贅沢を」
と、人間の欲望なんて、際限なく湧き上がってくるものだ。
それが理由に、事業に成功して、大金を稼ぎ、自家用ジェットを購入し、芸能人と付き合うなど、地上でありとあらゆる欲望を満たした人というのが次に目指すのは、月である。
だけど、たとえ月へいったとしても、彼らの欲望は、きっと満たされることはない。
庶民の幸福度と、大富豪の幸福度――
仮に比べられたとして、両者には大した差はないんじゃないだろうかと、ぼくは思っている。
物質的なものでは、人間が心から幸福にはなるってことはない。
だから、清沢満之は考えた。
「人間が真に幸福になるためには、心の充足が必要である」
この立場は「精神主義」と呼ばれる。
たとえ、物質的に満たされなくても、精神が満たされれば、人間は幸福になれるとする立場だ。
その信念のもと、清沢満之は、必要最低限の暮らしを続け、あらゆる欲望や物質的な豊かさを排除し、その代償として、どんどんと痩せこけていった。
その暮らしは、彼の妻子をも巻き込むほどの徹底ぶりで、傍目にみても、狂気以外のなにものでもなかっただろう。
スポンサードリンク
清沢満之の思想の転換点

さて、清沢満之の禁欲生活を眺めると、それは徹底した「自力」の修行であるということが分かる。
まさに、「心頭滅却すれば、火もまた涼し」の発想で、精神を徹底して鍛え上げれば、あらゆる苦悩に打ち勝てる、というものだ。
が、そんな生活を続けていれば、結果は目に見えている。
彼は、不治の病、結核にかかってしまう。
ここから、彼の思想は少しずつ、変わっていくことになる。
どんなに、自力を尽くしたところで、自分の心に穏やかさが訪れることはなかった。
それが理由に、結核になった今、自分は死の恐怖に打ち勝つことができていないじゃないか。
あれだけの狂気的な生活を送ったところで、自分の心に変化などなかった……
そんな風に、清沢は、「自力」の限界に気が付き始める。
結核が、彼の思想に影響を与え始めたのだ。
ただし、彼の病は療養生活のかいあって、一時的には回復する。
きっと、彼も、喜んだに違いない。
だけど、その喜びも空しく、結核は再発してしまう。
さらに、彼の苦悩に追い打ちをかけるように、妻と、長男が他界する。
そして、清沢は失意のどん底で、自分自身の無力さを悟った。
これは、頭の上での表層的な悟りなんかではない。
心の奥底、身体の隅々、腹の底から、強烈な実感を伴った悟りだった。
こうして、彼の思想は大きくシフトしていく。
これまでの「自力で物質に打ち勝つ」というものではなく、
「無力な自分」や「有限な自分」が救われる道、というのを求めるのである。
このプロセスは、実は、浄土真宗の開祖、親鸞聖人とまったく同じなのだ。
親鸞もまた、比叡山での苦しい修行を続けてきた。
それこそ、不眠不休、飲まず食わずの修行で、生命の危機もあったという。
徹底した「自力」を尽くして、親鸞が悟ったもの、それが、「自分の無力さ」だった。
だから、二人に共通しているのは、
「自力」を通過し、「他力」の思想へとたどり着いたという点である。。
くしくも、清沢満之は、その浄土真宗の僧侶だ。
彼もまた、親鸞と同様に、自分自身を阿弥陀如来に委ねる「絶対他力」の思想へと接近してく。
が、彼の思想が、これまでの浄土真宗と違うのは、西洋哲学を自らの思想に吸収しようとした点だった。
この「仏教と哲学の融合」
明治時代の仏教で紹介した、井上円了と、まったく同じ発想だ。
それもそのはず、清沢満之は、井上円了の弟子だった。
彼は、井上円了の手法を応用し、自らの信仰を深めようとしたのだった。
ただ、井上と清沢の態度には、大きな違いがある。。
井上は、仏教と西洋哲学の融合をはかった「学者」だった。
彼はあくまでも「学者」であって、彼が目指すのは、キリスト教に対抗できる、超論理武装された無敵の仏教の追求である。
それは「井上自身の救済」とは、ある意味で無縁だったといっていい。
しかし、清沢には、それ以上の切実さががる。
彼は、彼自身が救われるために、浄土真宗と西洋哲学を融合させなければならなかったのだ。
つまり、清沢は「学者」ではなく「信仰者」であった。
清沢は言う。
「盲目的な信仰は、信仰ではない。本当の信仰は、徹底した合理性の先になければならない」
つまり、
「阿弥陀如来を信じなさい」
「はい、わかりました、信じます」
なんていうのは、本当の信仰ではないというわけだ。
彼にとって真の信仰とは、その明晰な頭脳を使って、疑って疑って疑って疑った果てに得られる信仰でなければならなかった。
だから、彼には、どうしても、哲学の明晰さ・合理性というものが必要だったのだ。
その合理的な思考による徹底的な懐疑の果てに得られた「他力」でなければ、それは真の「他力」とはいえないからだ。
曖昧な根拠で、自分の存在を阿弥陀如来に委ねることは、清沢にはできなかった。
清沢はこういう。
「哲学の役目が『無限』の追求にあるとすれば、宗教の役目は『無限』の受容にある」
つまり、哲学によって得られた「無限」とか「真理」を、自ら信じて生きることこそ宗教であるということだ。
「他力」を得るためには、徹底して「自力」を尽くさねばならないのだ。
スポンサーリンク
清沢満之の信仰告白

晩年の清沢満之は、自分自身の信仰を告白している。
その要旨をぼくなりにまとめると、以下の通りになる。
私は阿弥陀如来に心から帰依している。
私が阿弥陀如来に帰依するのは、私の徹底した思索の果てのことだ。
自分はとにかく、「自分」とか「世界」とか「人生」とかについて考え続けた。
だけど、考えれば考えるほど、それは全くの「不可解」であった。
自分は、その「不可解」で悩みに悩んだ。
悩んで疑って答えが出て、悩んで疑って答えが出て、そしてまた悩む。
その繰り返しだ。
その中で分かったことは、1つだけだ。
それは、「自分には、この世界のことなんて1つも理解できない」ということだ。
自分は自分の力だけでは救われない。
自分は、ただただ、阿弥陀如来に、全てを委ねるしかない。
そう思った時、今まで暗闇の中に置き去りにされたような自分の心に、安楽と平穏が訪れた。
いま、ここにあるのは、無力な自分と、阿弥陀如来への感謝だけである。
だから、自分はやすらかな気分で、この世界を生き、そして死んでいくことができる。
清沢の一生は短く、彼は39歳の若さで結核によって逝った。
彼の苦悩は「信仰」によって、救われたのだろうか。
それは彼にしか分からない。
だけど、彼がぼくたちに示していることは、確実にある。
それは、
「人間は救われなければならないし、救われる道はきっとある」
ということだろう。
いまほど紹介した、清沢の言葉。
「この世界は不可解だ」
気が付いただろうか。
実は、これ、あの藤村少年の言葉とまったく同じなのだ。
巌頭に立った彼は、傍らの木にこう刻んだ。
「この世界の一切は、不可解だ」
そして、滝の底めがけて跳躍した。
- 信仰もなく、華厳の滝へと飛び込んだ藤村操。
- 信仰によって、安らぎを手にした清沢満之。
この対称は、宗教の本質というものを、ぼくたちに教えてくれているような気がする。
仏教が「家の宗教」となってしまった昨今、ぼくたちは清沢満之の信仰の声に、耳を傾けなければならないと思う。
スポンサーリンク
主な思想内容② 暁烏敏の思想
暁烏と『歎異抄』との出会い
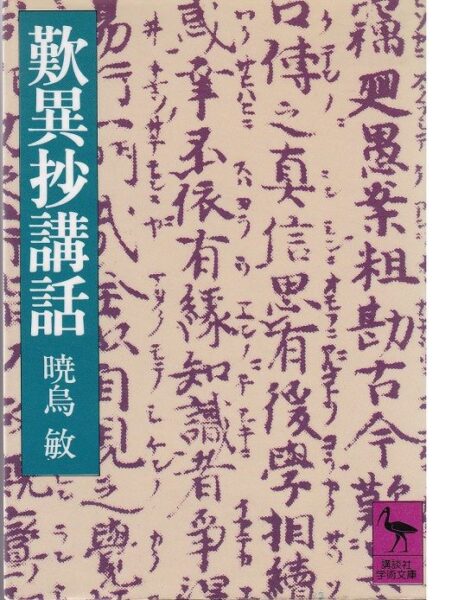
清沢満之の思想的DNAを受け継いだものに、暁烏敏(あけがらす はや)という僧侶がいる。
暁烏は石川県にある、浄土真宗・真宗大谷派の寺の長男として生まれた。
優秀な彼もまた、京都へと進学し、清沢満之と出会った。
とはいえ、清沢から教わったのは、わずか数か月に過ぎなかった。
だけど、清沢が暁烏に与えた影響は計り知れなかった。
暁烏は、清沢が開いた私塾にも通い、清沢の死後も、彼を一生涯の師匠として尊崇していた。
そんな暁烏もまた、「自意識」によって苦悩し、「自らの救済」をもとめた人間だった。
特に彼を悩ませたのは、強烈な性欲だったと言われている。
ひよっとして、これは、現代の日本人の感覚からは、すこし理解できないかもしれない。
だけど、「理想と現実のギャップ」といえば、だれにだってあてはまると思う。
暁烏は、寺の長男としての在るべき自分の姿と、自らの醜い心のありようのギャップに苦しんでいたのだ。
そんな彼が救いを求めた先、それは「読書」だった。
ほら、こうなると、一気に暁烏に共感しないだろうか。
自分の醜さとか、弱さとか、みじめさとか、そういう部分が、読書によって慰められた経験は、だれにでもあると思う。
ちなみに、大正時代というのは、読書に救いを求める人たちが増えた時代でもある。
沢山の教養を身に着けて、「近代的自意識」や、その苦悩を乗り越えようという考え。
これを、「教養主義」という。
暁烏はまさに、教養主義的な立場から、むさぼるように読書を続けた。
そして、出会った運命の1冊。
それが、『歎異抄』だった。
『歎異抄』とは、親鸞の教えが書かれた書である。
そこには、「悪人が救われていく道」が、わりとセンセーショナルに記されている。
「善人でさえ救われるのだから、悪人ならなおさら救われる』
という、悪人正機と呼ばれる、有名なアレだ。
いまでこそ、『歎異抄』は、比較的人々に知れ渡っているものの、明治・大正時代には、まだまだマニアックな一冊だった。
それは、『歎異抄』の巻末に記しされた言葉のためだ。
曰く、
「これは、あまりに危険な書だ。浄土真宗の教えを勘違いする連中が生まれると悪いから、むやみやたらに人に見せるんじゃないぞ」
要するに、
「悪人でも救われる? じゃあ、悪いこと好き放題やっても、OKってことね」
というヤカラが続出すると悪いから、それを厳しく戒めているわけだ
こうして、禁断の書として、世に埋もれていた『歎異抄』
それを、再発見したのが、この時代の清沢満之や暁烏敏たちだったわけだ。
暁烏は、『歎異抄』について、次のように言っている。
「この書は、自分の弱さや無力さに苦しまないものが読んだところで、得るものはない。本書は、自分の弱さ・無力さ・浅ましさ、そういうものに悩み苦しむものや、大切なものを失って絶望しているものや、自分が死ぬことに恐怖を感じるもの……そういう人間たちが救われていくための書なのである」
彼の『歎異抄』に対する理解は、鋭い。
なぜなら、「苦悩」と「信仰」と「救済」との関係を的確に言い得ているからだ。
「うぇーい、悪人正機サイコー、何をやってもOKらしいぞ」
といって、好き放題やっている連中に、「苦悩」はない。
「苦悩」がないものに「救い」などない。
「救い」のないものに、『歎異抄』は必要ない。
宗教とはそもそも、この世界で生きづらさを感じている人や、苦しんでいる人に寄り添う教え。
生きづらさを感じない人も、自分を全面的に肯定できる人も、死ぬのが怖くない人も、彼らには、救済も信仰も必要ない。
信仰が必要なのは、生きづらい人、自分が大嫌いな人、死ぬのが怖い人たちだ。
『歎異抄』は、そんな彼らにこそ刺さる書であり、そんな彼らを救ってくれる書なのだ。
だから、暁烏の言葉というのは、『歎異抄』どころか、実は宗教の本質を言い得たものとさえいえる。
暁烏は生涯かけて、この『歎異抄』をよりどころに、自分自身が救われる道を模索した。
暁烏はこう言っている。
「『歎異抄』さえあれば、ほかのどんな聖典も経典も必要ない」
実は、この当時から『歎異抄』を高く評価する思想家は少なからずいた。
ちなみに、日本近代哲学の代表格、あの西田幾多郎も、
「家が火事になったら、ぼくは『歎異抄』だけは絶対持ち出す」
と言っているし、あのドイツの哲学者ハイデガーも、
「日本に『歎異抄』という書があることを知っていたら、ぼくはギリシア語なんか学ばず、日本語を学んでいたのに」
と、言っている。
いかに、この本が宗教的、哲学的な力を持っているかがわかると思う。
スポンサーリンク
宗教にはらむ危険性

明治時代になって、井上円了や清沢満之が「仏教と西洋哲学の融合」に取り組んだのは、すでに見てきたとおりだ。
その根底には、「盲目な信仰」ではなく、「理性に裏付けられた信仰」を求める姿勢がある。
「あれもこれも」と、なんでもかんでも求めるのでは救われない。
「あれかこれか」と、理性や合理性で真理を追い求め、最終的に、
「これだ!」
と、確固たる信仰を得なければならないと、2人は考えていた。
が、打って変わって、暁烏はかなり原理的で、かたよった一面を持っている。
彼の信仰には、
「信仰は、自分にとっての真実であれば、それでいい」
という考えが根っこにある。
「哲学や、キリスト教や、科学に、あれやこれやと批判されようが、自分には関係ない。自分が正しいと思ったものこそが真実で、それを生きるのが信仰だ」
こういう論理が、晩年の暁烏の思想に色濃く見られる。
大正時代は、「教養主義」の時代だと先ほど述べた。
暁烏にもそういう傾向があって、彼はとんでもない読書家で、その本棚には20万冊ほどの書物があったと言われている。
暁烏は古今東西の書物を読みあさり、『古事記』や『聖書』や『ギリシア神話』や『ギリシア哲学』を吸収し、独自の信仰のスタイルを形成していった。
そこには、どこか独りよがりの嫌いがあり、実際、彼の思想には、親鸞とは異なる点が多くみられる。
その最たるものに、
「阿弥陀如来 = 天照大神」
という発想がある。
こういった、彼独自の信仰スタイルは過激化していき、仏教と神道を勝手気ままに融合させていく。
その結果、阿弥陀如来の信仰は、そのまま天皇への崇拝であるという思想へたどり着く。
彼は戦時中、それを至るところで喧伝し、戦争に大きく加担した。
浄土真宗における、戦争責任の一つである。
ここに、信仰の持つ危うさがあるように、ぼくは思う。
確かに、信仰ってのは、最後の最後「ぼくにとっての真実」こそが最も大切なのだと思う。
「ぼくが救われる」ためには、「ぼくにとっての真実の物語」が必要であり、それを「ぼく自身」が信じなければならないからだ。
親鸞もそれについて、
「阿弥陀如来による誓いと救済というのは、このおれ、親鸞ただ一人のためのものだった」
と、その宗教体験を語っている。
だから、宗教の本質として、ほかでもない「自分自身の真実」というものがあげられる。
だけど、そればかりを絶対視して、ほかの価値観との対話を失ってしまったとき、宗教は排他主義や原理主義といった危険思想へとつながっていく。
キリスト教やイスラム教などの一神教に比べて、本来、仏教はそういう原理主義とは遠いところにある思想だった。
だけど、阿弥陀如来を信仰し、救いを求める浄土真宗には、これらの一神教との共通点があるといえる。
自分の信仰を守ることと、他者との対話を捨てないこと。
なかなか共存が難しいこの2つだが、暁烏の思想を知る中で、ぼくたちはこの2つの両立の大切さを学ばなければならないと、ぼくは思う。
理性や合理性ばかりでは信仰ななりたたない。
だけど、理性や合理性のない信仰もまた危うい。
宗教家は、それを肝に銘じなければいけないと思う。
さて、時代は戦争へと突き進んでいく。
大正も終わり、昭和へ、そして現代へ。
そんな時代に、仏教はどんな立ち位置にあったのか。
仏教は、人々に何を与えることができたのか。
次回は、現代編として、いままさにぼくたちの近くにある仏教とは何なのかを考えてみたい。
次の記事はこちら
仏教を学ぶならオーディブル

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、宗教関連の書籍が月額1500円で“聴き放題”。
宗教以外にも、哲学や思想系の書籍も充実している。

 ・
・
それ以外にも純文学、エンタメ小説、海外文学、新書、ビジネス書、などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。
これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。
・
・
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、軽い気持ちで試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・






コメント