はじめに『羅生門』の凄さ

高校時代、国語の時間で『羅生門』を読んだって人は多いと思う。
ただ、あれがどういう話だったのか、ちゃんと理解しているって人は案外少ないのではないだろうか。
かつての僕もそうだった。
実際恥ずかしいのだけれど、僕の場合は、
「なんか“ニキビ”が出てきたよな」とか
「なんか“猿”が出てきたよな」とか
そんな阿保みたいな印象ばかりで(しかも猿出てきてないし)、作品の「本質」に関しては記憶の片隅にさえ残っていないという体たらくだった。
だけど、大人になって改めてこの『羅生門』をきちんと読みこんでみると、その「人間理解」の鋭さに唸らされてしまう。
それだけじゃない。
この作品には、文豪「芥川龍之介」の天才的な「分析」や「テクニック」が随所で光っているし、作品を書くにいたった芥川の悲しい事件を知るにつけても胸が痛むし、あの有名なラストシーンに隠された芥川の「人間観」に思いを馳せるとゾクゾクとした感覚に襲われてくる。
とにかく『羅生門』は「にきび」の話でもなければ、「猿」の話でもない。
近代文学史上の「傑作」とも呼べる作品なのである。
さて、この記事ではそんな『羅生門』に関する解説と考察をしていく。
おそらく、作品に関する大半の情報は網羅しているのではないかと思う。
「最近、あらためて羅生門を読み返しました」って人も、
「昔読んだけど、意味が解りませんでした」って人も、
「読み直したいので、内容を確認したいです」って人も、
お時間のある方は、ぜひ最後までお付き合いください。
元ネタ「今昔物語」との比較

“違い”を簡単に確認
そもそも『羅生門』には元ネタがあることをご存知だろうか。
本作は、平安時代の説話『今昔物語』に材をとり、芥川がその類いまれな知性によって再構築したものだ。(詳しくは後述する)
この元ネタと『羅生門』を比較することには、とても大きな意義がある。
なぜなら、芥川が『羅生門』で何を描こうとして、そして何を伝えたかったかが明確になるからだ。
ここでは主に、両作品の違いについて紹介するが、それを一覧にしたのが次の表である。
| 〇タイトル | 『羅生門』 | 『羅城門ノ上層ニ登リテ死人ヲ見タル盗人ノ話』 |
| 〇字数 | 約6000字 | 約600字 |
| 〇描写の特徴 | 下人の内面の変化を入念に | 事実のみを淡々と |
| 〇主人公 | 仕事を失った下人 | 盗みのために上京した男 |
| 〇主人公が羅生門に上った理由 | 雨風をしのぐため | 人目を避けるため |
| 〇老婆と死人の関係 | 明示されず | 下女と主人 |
スポンサーリンク
“違い”を丁寧に解説
まず、当然っちゃ当然なのだが、両者の文章量は全く違う。
『羅生門』はオリジナルの約10倍もの字数ということなのだが、ここに書き加えられた部分に、芥川の「意図」というのが表れていると思われる。
その意図は何かを端的に言えば、
「下人の内面の動きを克明に記すこと」である。(これについても後述する)
それから、主人公の「男」の設定というのも、大きく異なっている。
ここで『今昔物語』の冒頭を引いてみたい。
今は昔、摂津の国の辺りより、盗みせむが為に京に上りける男の日の未だ明かりければ、羅城門の下にたち隠れて立てたりけるに――『今昔物語』より
『今昔物語』の主人公の方は、「盗みをするために」上京したとされ、冒頭からすでに盗む気まんまんである。
それに彼が「羅城門」にのぼった理由の根底にも、この「盗み」がある。
人共のあまた来たる音のしければ、「其れに見えじ」と思て、門の上層にやわらかかづり登りたりけるに――『今昔物語』より
要するに、「大通りには人が沢山いたので、人目を避けるために羅生門にのぼりました」というわけだ。
そもそも、タイトルも、
『羅城門の楼にのぼったら死人を見ちゃった盗人の話』
と、かなり露骨なもので、主人公はハナから「盗人」と紹介されている。
これらは明らかに芥川の『羅生門』と異なる点だ。
一方の『羅生門』の主人公については、冒頭でこう記されている。
ある日の暮れ方のことである。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。『羅生門』より
一読して分かる通り、主人公は身分の低い「下人」と紹介されているし、彼が羅生門にいたのも「雨やみを待っていたから」だという。
読み進めていけば、彼が職を失ったために途方に暮れていることも分かってくる。
結果的に「盗み」を犯してしまう彼は、はなっから「盗人」だった『今昔物語』の男とは、根本的に違っているのだ。
こうした違いは、作品のエンディングにおいても見られる。
元ネタの『今昔物語』が、
「羅生門の上には死体がたくさんあって、それは人々が捨てていったものなのでした」
という感じで終わっているのに対して芥川の『羅生門』の方は、
「下人の行方は、誰も知らない」
と、あの有名な一節で終わっている。
前者が明らかに「羅生門に捨てられた死体」にフォーカスしているのに対して、後者は「主人公の男」にフォーカスしている。
それから、「老婆と死人」の関係の違いも興味深い。
芥川の『羅生門』において、死人は「詐欺を働いた女」ということになっていて、老婆との関係は具体的に明示されてはいない。
ところが元ネタの『今昔物語』の方では、老婆によってこう説明されている。
「己が主にておはしましつる人の失せ給へるを、あつかふ人のなければ、かく置きたてまつりたるなり」『今昔物語』より
つまり、「私の主人が死んでしまったのに、それを葬ってくれる人がいなかったので、なくなくここに捨てに来たのです」
といっているわけで、しかも死人の生前における「罪」に関する記述もいっさいない。
さて、芥川はこれらの違いを書き込むことで、オリジナルにはない「深み」を作品に生み出しているのだが、それこそが初期の「芥川文学」の特徴と言われている。
スポンサーリンク
「理知」で作られた小説世界
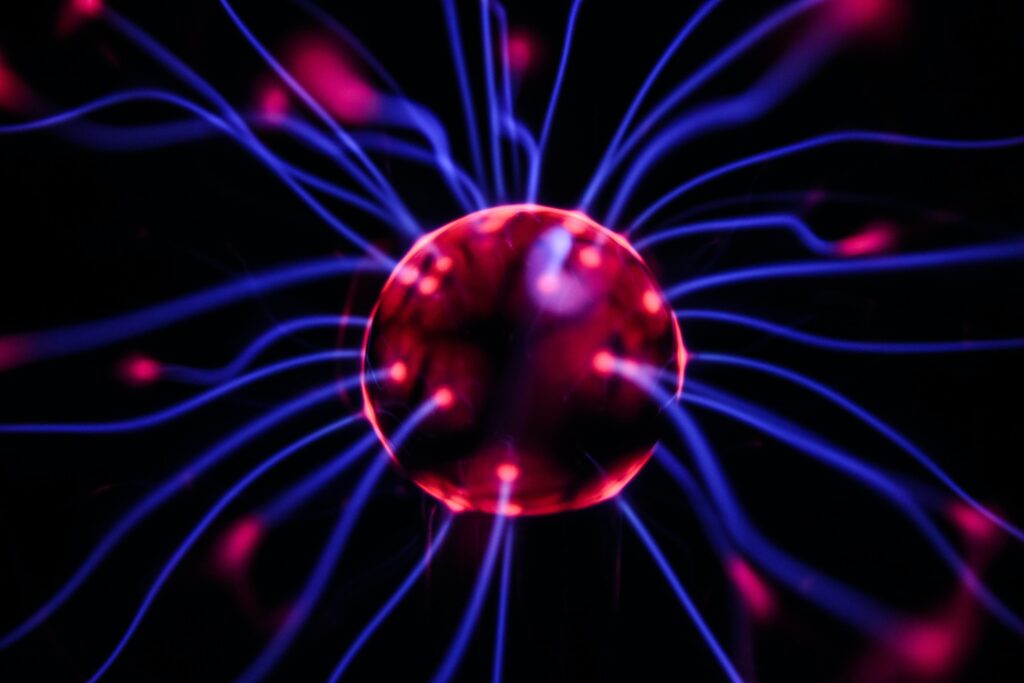
芥川龍之介の初期の代表作の中には『鼻』や『地獄変』、『芋粥』など、古典を題材にしたものが多い。
そもそも、芥川龍之介が活躍したのは主に大正時代なので、別段「古典」にこだわる必然性というものはないように思われる。
それでは、なぜ彼は「古典」を題材にした作品を書き続けたのだろう。
結論をいえば、
古典を題材にしたほうが、彼の文学の「テーマ」を効果的に表現できたからだ。
『羅生門』をはじめ、彼の初期の作品の多くには、
「このテーマを描くために、時代、場所、状況をどのように設定すれば良いのだろう」
という、彼の天才的な頭脳による徹底した分析が光っている。
要するに、初期の芥川は小説を「頭」で書いていたのだ。
そして、その「分析」も「テクニック」も、どちらも天才的なレベルにあった。
ちなみに、当時の文壇では「日常をありのまま書こうぜ」という「自然主義」が主流。
そんな中で彼は「明晰な頭脳」と「巧まれたテクニック」によって、完璧な小説世界を構築しようとしていたわけだ。
だから初期の芥川は文学史的に、
反自然主義
(※ “ありのまま”を否定する立場)
と呼ばれ、その中でも、
新理知派
(※ 明晰な理知で小説を構築)
新技巧派
(※ 巧まれた技術で小説を構築)
と呼ばれている。
そして『羅生門』は、まさしく芥川の「理知」と「技巧」によって作り上げられた、完成度の高い作品といえるのだ。
では、なぜ芥川は『羅生門』の舞台を“現代(当時は大正時代)”ではなく“平安時代”に設定したのだろうか。
それは、平安時代というのが、天変地異の連続よって、町も人々も荒廃していた時代だったからだ。
『羅生門』の冒頭にはこう説明されている。
この二、三年、京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。『羅生門』より
もちろんこれは歴史的事実だ。
いや、厳密に言えば事はもっと悲惨で、そこに更に津波、噴火、疫病、内戦が加わり、かつての日本は、僕たちの想像を絶するほどの“ディストピア”状態だったわけだ。
人々の「平均年齢」も、30歳から40歳程度。
それだけ「死」は身近な存在だった。
となれば、羅生門に関する次の記述も、十分納得できるだろう。
- 修理されずボロボロ。
- 動物や盗人が住んでいる。
- 引き取り手のない死体が捨てられている。
実際、当時の鴨川には、行き倒れになった人々の死体がうず高く積まれていたらしく、しかも、それらを野良犬やキツネやタヌキがついばんでいるという地獄絵図。
ほら。
こんなだから、人々の心は完全に荒廃しきっている。
それは「仏像や仏具を打ち砕」くほど。
神も仏もクソくらえじゃ! ってなレベルまで、人々は絶望しているってわけだ。
ここまでの「極限状況」を作り出すことは、「大正時代」を舞台にしては絶対に不可能だ。
だからこそ芥川は、物語の舞台を「平安時代」に設定したというワケ。
では、そんな「極限状況」を設定して、芥川は一体どんな「テーマ」は書こうしたのか。
スポンサードリンク
芥川が「伝えたかったこと」とは

芥川が『羅生門』で描こうとしたものは何か。
早速、その結論を言ってしまうと、
- 人間のあてにならなさ
- 人間の弱さと身勝手さ
の2つと言えるわけだが、この2つはさらに、次の言葉に要約される。
- 人間の「エゴイズム」
実際、『羅生門』に関する数々の論考を読んでみても、その多くは、
「芥川は羅生門において、人間のエゴイズムを描きました」
というのが前提となっているようだ。
ということで、芥川が「エゴイズム」の問題に関心があったのは、間違いない。
スポンサーリンク
『羅生門』執筆のきっかけ

ところでそもそも、どうして芥川は「人間のエゴイズム」を作品化しようと思ったのか。
そこには、彼自身が経験した、ある「悲しい事件」が大きくかかわっている。
その事件とは、ある女性との「失恋事件」 である。
当時、芥川は、「吉田弥生」という才女と真剣に交際をしていた。
好きな子には、やたらに手紙を書くのというのは、芥川の気質みたいで、彼のラブレターというのが現存している。
手紙はこんな感じ
「これで弥あちゃんへ手紙をあげるのが二度になるのですが、二度とも ある窮屈さを感じてゐるのは事実です」
「眠る前に時々、東京の事や、弥あちゃんのことを思ひ出します」
どうだろう。
およそ、「文豪」らしからぬ、かわいらしい手紙だと思わないだろうか。
芥川の純粋な恋心や、恋ゆえのもどかしさ、切なさみたいなものが、ほんのりと表れている。
芥川は弥生を純粋に愛していたのだ。
そして、彼は自然と弥生との結婚を意識していく。
その意思を、養家である「芥川家」に伝えたのは、22歳のことだった。
これまで、「自分の思い」を押し殺して生きてきた芥川。
養家の親に「自分の本心」を伝えたのは、これが初めてのことだったとも言われている。
ある晩のこと、芥川は意を決して、弥生との結婚の思いを養家の人々に伝えた。
が、養家の人々は、彼の思いを受け入れなかった。
2人の結婚に強く反対をしたのだ。
その理由には諸説があって、
- 弥生が「士族」出身でなかったから
- 弥生が婚外子だったから
ということらしいが、いずれにしても、養家の人たちは自分たちの「世間体」を優先したのには変わりない。
芥川は夜通し泣いて、愛する弥生との結婚を認めてもらおうと訴えかけたという。
が、養家の人々は芥川の思いを拒絶。
結局、彼は弥生との結婚を断念することになる。
芥川は友人に手紙を送り、その時の心境をこう言葉にした。
エゴイズムのない愛がないとすれば 人の一生ほど苦しいものはない
周囲は醜い、自己も醜い、そしてそれを目のあたりに見て生きるのは苦しい
たしかに、これまで養家の人たちは、親に見捨てられた芥川を大切に育ててくれた。
そんな彼らであっても、ひとたび利害関係が生じてしまえば、優先するのは「自分たちの保身」だった。
「実の親」だってそうだったではないか。
表面的には自分を愛してくれてるように見えても、その愛情の裏には いつだって身勝手な「自己愛」や「自己保身」といった、「人間のエゴイズム」が隠れている。
こんな人の世を生きていくのが、人生だとしたら、人生とはなんと苦しいものなのだろう。
芥川はこの「失恋事件」をきっかけに、厭世思考を強めていき、彼の内からは創作のエネルギーがフツフツと湧いてきた。
『羅生門』という作品は、こうして生まれた。
だからこそ、ここには「人間のエゴイズム」という主題が徹底して描かれているってわけだ。
作品にみなぎる熱量も、それだけ、芥川の悲しみが強かったという証拠なのだろう。
【 参考記事 天才「芥川龍之介」のまとめー人物と人生の解説・代表作の紹介ー 】
「下人」に見られるエゴイズム

芥川は『羅生門』において「人間のエゴイズム」を描こうとした。
そして、それを効果的に描くために「平安時代」という、極限状況を舞台に設定した。
では、芥川によって描かれた「エゴイズム」というのは、どういったものだったのか。
結論をいえば、
「どんな人間でも、最後の最後に優先するのは、自分自身である」
というものだ。
まず、この作品に「分かりやすい悪」は存在していない。
それは、元ネタ『今昔物語』との一番の違いでもある。
元ネタでの主人公は、のっけから「盗人」と紹介されていて、彼がどんな経緯で、どんな心理的なプロセスを経て「盗人」になったかは全くもって不明。
つまり、とってもわかりやすい「悪人」なのである。
だけど、一方の『羅生門』では主人公の置かれている状況が丁寧に書き込まれている。
それをまとめると以下のようになる。
主人公は年若い下人(主家に使える雑用係) ↓ 数日前に仕事をクビになってしまった。 ↓ 行く当てもなく羅生門の下で雨宿りをしている。 ↓ これからどうすべきかを、とりとめもなく考えている。 ↓ とにかく今夜は安全な場所で過ごそう、と楼に上った。
こんな感じで、主人公の「下人」には、今のところ「よし! 盗みをしよう!」などという明確な意志は見られない。
雨の中たたずむ彼が考えていたのは、
「仕事クビになったし、これからどうしよっかなあ」
ということであり、
「このままじゃ飢え死にするし、さいあく泥棒になるしかないのかなあ、だけど勇気がでないなあ、どうしよう」
ということなのである。
しかも、楼に上ったのだって
「とりあえず、一晩だけ安全に過ごそう」
という思いからだ。
元ネタ『今昔物語』で「盗人」が、
「大通りは人目につくから、いったん隠れよう」
と思った点と大きく異なっている。
繰り返すが、芥川の『羅生門』においては「分かりやすい悪」というのが存在していないのだ。
なんなら、この下人の思考は「極限状況下」にあれば、たいていの人間が少なからず考えてしまうことなのではないだろうか。
そういった意味でも「下人」はあくまで平凡な、どこにでもいる青年だと言って良いだろう。
だけど芥川は、そんな下人を、最後は「盗人」にする。
その理由は、芥川が『羅生門』という作品を通して、
「どんな人間であっても、最後に優先するのは“自己保身”なのだ」
ということを描こうとしていたからだ。
もっと言い換えれば、
「どんな人間だって、その本質はエゴイストなのだ」
ということになるだろう。
このことは、芥川が「失恋事件」の際に強く実感したことだった。
では、この「平凡な青年」が「盗人」になるプロセスとは、いったいどういったものだったのだろう。
もちろん「極限状況下」というのが、一番の要因であることは間違いない。
たとえば、災害時や戦場において、他者を蹴落としてでも生き残ろうとすることは、( 良い悪いはひとまず置いておいて )人間の一つの行動例である。
そう考えてみれば、人間というのは「たよりない存在」であり「弱く身勝手な存在」だということもできる。
まぁ「極限下で他者を蹴落とすことは善か悪か」については議論の余地はあるだろうが、いずれにしても、下人もまた「極限状況下」で、他者を蹴落として生き残ろうとする類の人間だといえる。
ただ、少なくとも作品冒頭で彼は「どうしよっかなあ、泥棒になろうかなあ」と葛藤をしているのだ。
じゃあ、そんな下人の背中を押したものとは、いったい何だったのだろう。
それが、次に見る「老婆の論理」なのである。
スポンサーリンク
・
「老婆の論理」に見られるエゴイズム

「下人 VS 老婆」の図
楼の中で下人が見たもの。
それは、死人の髪を抜く「猿のような老婆」だった。
あの老婆は、なぜ髪を抜いているのだろう。
下人はそう疑問に思いつつ、老婆が「良いヤツなのか、悪いヤツなのか」分からない。
ただわかっているのは、老婆がガリガリでヒョロヒョロであること。
「まあ、なんかあったとしても、あれなら勝てるっしょ」
と下人は判断。
下人は、両足に力を入れて、いきなり、はしごから上へ飛び上がった。そうして聖柄の太刀に手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。『羅生門』より
それを見た老婆は、ばね人形みたいに飛び上がって逃げ出す……が、なんといっても彼女は「猿のような老婆」である。
下人は老婆に追いつくと、「トゥン!」ってな具合に、いとも簡単に彼女をねじ倒し、白い鋼の刀の先を老婆の目の前に突きつけながら、横柄にこう尋ねる。
「何をしていた。言え。言わぬと、これだぞよ」
こうしてマウントをとった下人は(相手はガリガリの老婆なのに)、得意と満足感に満たされた。
ところが、老婆が死人から髪を抜く理由を聞くと、下人はなんとも拍子抜けしてしまうのだった。
「この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かつらにしょうと思うたのじゃ」
んだよ、そんな理由かよ。
下人は、とんでもなく「悪い理由」を期待していたのか、老婆のその言葉を聞いて一気に失望する。
が、その後に続く老婆の「驚きの論理」を聴くや、事態は一変するのだった。
さて、この老婆の論理とは、どんなものだったか。
老婆の「論理」の要点
とっても長くなってしまい恐縮なのだが、ここにまるっと引用してみたい。
「成程な、死人の髪の毛を抜くと云う事は、何ぼう悪い事かも知れぬ。じゃが、ここにいる死人どもは、皆、そのくらいな事を、されてもいい人間ばかりだぞよ。現に、わしが今、髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを、干魚だと云うて、太刀帯の陣へ売りに往んだわ。疫病にかかって死ななんだら、今でも売りに往んでいた事であろ。それもよ、この女の売る干魚は、味がよいと云うて、太刀帯どもが、欠かさず菜料に買っていたそうな。わしは、この女のした事が悪いとは思うていぬ。せねば、饑死をするのじゃて、仕方がなくした事であろ。されば、今また、わしのしていた事も悪い事とは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば、饑死をするじゃて、仕方がなくする事じゃわいの。じゃて、その仕方がない事を、よく知っていたこの女は、大方わしのする事も大目に見てくれるであろ。」
「メッチャしゃべるじゃん、この老婆」という、このシーン。
さすがにこれだけじゃ、読者もチンプンカンプンだと思うので、以下に「老婆の論点」をまとめてみたい。
① 死人の髪を抜くことは確かに悪いことだ。 ※「自分の悪」をとりあえず認める ② だけどこの女はそのくらいされてもいい人間だ。 ※「悪に対する悪」は許される ③ というか、そもそも女がしていた行為は悪ではない。 ※「仕方なくする悪」も許される ④ とすれば、自分の行為だって悪ではない。 ※ 結局は「自分の悪」を正当化
この老婆の論理はとても興味深いので、もう少し説明を加えたい。
スポンサーリンク
「悪に対する悪」は許される?
まず②「悪に対する悪は許される」という点について。
ざっくりと言い換えれば、
「悪いことしたやつは、それ相応の罰をうけて当然」
ということになる。
これは、なかなか答えのない問いだといえるだろう。
なぜなら、老婆の論理は現代における「死刑制度」に通じるものがあるからだ。
「凶悪犯罪者に対する(国家による)殺人は許される」
これが死刑制度の論理なわけだが、これは老婆の言うところの「悪に対する悪は許される」という発想と根底でつながっている。
死刑制度を認めるか否か。
それは「老婆の論理を認めるか否か」と同じだと言って良いだろう。
「仕方なくする悪」は許される?
それから③「仕方なくする悪は許される」という点について。
これについては、すでに軽く触れたが、
「極限状況下で、他者を蹴落とすのは悪なのか」
という問いに通じている。
生々しい例になってしまうのだけど、たとえば「戦時中における殺人行為」とか「遭難時におけるカニバリズム」など、現実世界においても、これらの「倫理問題」はつねに議論の的となる。
どうやら芥川はこれを「エゴイズム」と批判的に見ているらしい。
芥川は養家の「エゴイズム」を目の当たりにして、こんなことを言っていた。
周囲は醜い、自己も醜い、そしてそれを目のあたりに見て生きるのは苦しい
ただ、そうきれいごとばかり言っていられないのもまた事実。
時には自分自身を守らなければならない、そういうことが僕たちにはあるからだ。
ここで唐突だが、僕はかつて、友達のアメリカ人と『羅生門』について議論したことがある。(彼は日本文学に造詣が深い!)
僕は彼に対して、次のような趣旨の説明をした。
「人間って極限状況になると、どんな酷いことでもしちゃう存在なんだよね。芥川はそんな人間の“エゴイズム”をこの作品で書いたんだよ」
すると、友人は、
「や、それはエゴイズムじゃないでしょ」
と、きっぱりと否定をしてきた。
「じゃあ、エゴイズムじゃなきゃ、なんだっていうの?」
少しムキになって尋ねた僕に、
Survival
彼は、たった一言だけ、そう言ったのだった。
つまり、彼は、
「下人がしたことって、自分が生存するために、仕方なくした行為だよね」
と、いうことをいいたかったわけだ。
さて、これを聞いて、あなたはどう思うだろうか。
もし日本人の多くが「下人の行為はエゴイズムだ」と答え、欧米人の多くが「下人の行為はサバイバルだ」と答えるのなら、そこに興味深い文化的な差異があるような気がしてならない。
要は、
- 集団主義的な日本人
- 個人主義的な欧米人
という、典型的な対立がここに見られるのかな、と、僕は思ったりするワケだ。
閑話休題。
とにかく、この「仕方なくする悪は、悪なのか」という議論も、なかなかに興味深いものなのである。
スポンサーリンク
・
つまり「下人の悪」も許される?
さて、これで老婆の論理は大体分かった。
彼女は、
②「悪に対する悪は許される」
③「仕方なくする悪は許される」
というダブルパンチで、「自らの悪」を見事に正当化したのだった。
つまり、
「罪人の髪を抜くことなんて、ぜんぜん悪じゃないよね」
というのと、
「そもそも自分が生き残るためなんだからしょうがないよね」
というのが、彼女の論理なのである。
が、皮肉にも、その論理は「下人の悪」も正当化するものでもあった。
だって、下人だって「盗み」をしなければ、生き残ることができないのだ。
つまり「老婆の論理」を認めるならば、下人にとっての、
「髪の毛を抜いているお前に対する悪は許されるよね」
というのと、
「そもそも自分が生き残るためなんだからしょうがないよね」
という論理も成り立ってしまうわけだ。
ただし「死人の髪の毛を抜くこと」は、はたして「罪」なのかという点に立ってみれば、正直ちょっと怪しい論理ではある。
が、いずれにしても、「老婆の悪の正当化」は「下人の悪の正当化」につながるものだった。
こうして背中を押された下人。
彼は老婆に向かってこう言い放った。
「では、俺が引剥ぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ、飢え死にをするからだなのだ。」『羅生門』より
下人は、すばやく老婆の着物を引きはがし、しがみつく老婆をけり倒す。
そして瞬く間に、急なはしごを駆け降りると、夜の闇へと消えていくのだった。
スポンサーリンク
「エンディング」にまつわる創作秘話

以上が、「芥川が伝えたかったこと」の説明となる。
最後にここで、羅生門のラストシーンに関する「創作秘話」を紹介して、この記事を締めくくりたい。
『羅生門』は、あまりに有名なこの1行でエンディングを迎える。
下人の行方は、誰も知らない。
これを読んだ読者は、きっとこう思う。
「下人はこのあとどうなるんだろう?」
それは具体的には次のような問いに組み替えられるかもしれない。
下人はこのあとどこへ行ったのだろうか…
下人は自らの罪をどう受け止めたのだろうか…
下人はこのあとも罪を犯し続けたのだろうか… などなど。
さて、『羅生門』のこのラストシーンは、実は2度書き換えがなされている。
そもそも『羅生門』が初めて発表されたのは、同人誌『帝国文学』において。
その当初は、こんなラストシーンだった。
下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつつあつた。
ここでは、下人が「盗人」になる予感が描かれている。
その2年後。
『羅生門』は、芥川にとって初の「短編集」に収録されることとなる。
このとき彼は、エンディングにちょこっとだけ手を加える。
下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急いでゐた。
こうなると、先ほどの「急ぎつつあった」よりも、下人が「盗人」になる予感が一層強くなっているといえる。
が、さらにその一年後、『羅生門』は新たな作品集に収録され、出版されることとなる。
この際に書き直されたのが、僕たちにお馴染みの、
下人の行方は、誰も知らない。
というものだった。
では、なぜ芥川はこのようなエンディングに変更したのだろうか。
きっと芥川は、
「下人が盗人になるかどうかなんて、結局のところ俺にはわからん」
そう思ったのではないだろうか。
だって、『羅生門』で描かれたのは「人間のたよりなさ」とか「人間の不確かさ」だったではないか。
人間というのは、条件さえそろえば、どんな行為もしてしまうのだ。
極限状況における人間なんて、まったく当てにならないのだ。
これらが芥川の基本的な人間理解だった。
繰り返すが、「条件さえそろえば」どんなことだってしてしまうのが人間だ。
僕たちは「善人だから」ものを盗まないのではない。
僕たちは「善人だから」人を殺さないのではない。
物をぬすまない
人を殺さない
ただその条件がそろっているから、現状、僕たちは犯罪を犯さないだけなのだろう。
仮に、今が「平安時代」のような時代だったとしたら。
仮に、とつぜん仕事を失い路頭に迷ったとしたら。
仮に、「悪を正当化」してくれる何者かに、背中を押されたとしたら。
果たして僕たちは、「悪」と無縁でいられると言い切れるのだろうか。
僕は言い切れない。
だから、この後の下人がどうなるかなんて、僕にはわからない。
条件がそろえば悪いこともするだろうし、条件がそろわなければその限りではない。
きっと芥川だって、分からなかったのだ。
だからこそ、「下人」のその後に関して、判断を保留したのだと思う。
――下人の行方は、誰も知らない――
そのラストは、ある意味で、人間に対する「謙虚さ」の表れともとれるだろう。
が、それよりもこの場面が僕たちに訴えているもの、それは、
「人間の不気味さ」
「人間の不可解さ」
そういう類のものなのだろう。
『羅生門』の解説・考察記事は以上です。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
「Audible」で近代文学が聴き放題

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、夏目漱石や、谷崎潤一郎、志賀直哉、芥川龍之介、太宰治など 日本近代文学 の代表作品・人気作品が 月額1500円で“聴き放題”。
対象のタイトルは非常に多く、日本近代文学の勘所は 問題なく押さえることができる。
その他にも 現代の純文学、エンタメ小説、海外文学、哲学書、宗教書、新書、ビジネス書などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。
これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。
・
・
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、気軽に試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・





コメント
こんばんは はじめまして
最近山月記絡みでここのブログを発見して
鋭角な洞察と、すごい読みやすい展開に楽しませてもらってます。
また改めて&これをきっかけに読んでみようと思う本がたくさんできました
羅生門を高1のとき担任の先生のゴリ押しで文化祭の劇することになったとき
脚本係になり
原作どおりではラストの持って行き方が難しかったので
下人が死体で運ばれてきてお婆さんが出てきて髪をぬくって話にしたのをこれ見ながら思い出しましたw
これからも楽しみにしてます
あらあらかしこ
ながもさん、はじめまして! そして、嬉しいコメントありがとうございます。執筆・運営の励みになります。
高校生の時の演劇、、、
ラストシーンが衝撃ですね。
どういう経緯で下人は死んだのか?
誰が下人を羅生門に運んできたのか?
髪を抜く婆さんは同一人物なのか?
色々な疑問が頭に浮かびました。
いずれにしても、なんとなく「因果応報」を感じさせるラストシーンですね。発想が豊かだなぁと感心いたしました。
こちらはまた思いつくままに記事を更新していきます。またお時間のある時に遊びに来て、気軽にコメントいただけると嬉しいです!
あなかしこ、あなかしこ