作者について

乗代雄介は1986年に北海道に生まれた小説家だ。
小学校卒業後に千葉県の私立中学校に進学をし、その頃から「ブログ」の執筆を始めた。
その「ブログ」こそ、彼の文学の「原点」であるという。
「ブログへの執着」を物語る「受験時代のエピソード」がある。
とにかく彼は、受験勉強に「ブログ執筆」を邪魔されたくなくて、あえて模試で低い点数をとっていたというのだ。
国語であれば「センターレベル」で満点近く採れたらしいが、そこをあえて50点ほど間違えて、点数をコントロールしていたらしい。
こうして「もっと上の大学を目指せ」と言われることもなく、それが功を奏して(?)自宅から通える「法政大学」に入学した。
すべては「ブログ」の為であり、引いては「文学」の為だった。
また彼の文章力は抜群で、大学時代に提出した「レポート」で、担当教授の心を奪ったという逸話さえある。
大学卒業後は塾講師になり、仕事の合間を縫って執筆し、文学賞に応募した。
- 2015年『十七八より』で第58回群像新人文学賞を受賞しデビュー。
- 2018年『本物の読書家』で第40回野間文芸新人賞を授賞。
- 2019年『最高の任務』で第162回芥川龍之介賞候補(初)となる。
- 2020年『旅する練習』で第164回芥川龍之介賞候補(2度目)となる。
- 2021年、同作で、第34回三島由紀夫賞を授賞。
そして2022年の第166回芥川賞の候補として『皆のあらばしり』が3度目のノミネート。
村田沙耶香や今村夏子に次ぐ「三冠達成」(野間賞、三島賞、芥川賞)が期待された。
登場人物について

以下、登場人物についてまとめる。
「ぼく」 ……物語の「語り手」。高校2年生。歴史研究部に所属している。研究調査のために「皆川城址」に訪れた際に謎の中年「男」に出会い、男と共に、幻の書『皆のあらばしり』の調査をすることになる。男のうさん臭さに警戒しつつも、その博識に惹かれていく。
「男」 ……30代くらいの中年男性。大阪弁をしゃべる。出張のついでに皆川城址に訪れているという。が、彼の説明は全体的にうさん臭く、どこまで本当でどこまで嘘か分からない。ただ、博学で洞察力や記憶力に長けているため、次第に「ぼく」を魅了していく。ぼくを焚き付けて『皆のあらばしり』の調査に引き込んだ。
「竹沢」 ……高校1年生の女子。歴史研究部では「ぼく」の後輩。「竹沢酒屋」の娘でもある。
「竹沢のひいじいちゃん」
……竹沢の曽祖父で、年齢は90歳前。『皆のあらばしり』について重要な情報を持っていると思われる。
スポンサーリンク
あらすじ

以下、あらすじを紹介する。
・高校の歴史研究部に所属している「ぼく」 ・ある日、皆川城址で調査をしていると、謎の中年「男」に出会った。 ・男は「ぼく」が入手した竹沢酒屋の「蔵書目録」を奪い取ると、そこに記載された『皆のあらばしり』(小津久足 著)という書について言及する。 ・博学な男によれば、小津久足の『皆のあらばしり』といった作品は、記録上存在していないという。 「まだ世にでてないものだってことか」 「もしそうなら大発見やのー」 ・満面の笑みでそう言う男に焚き付けられて、「ぼく」は幻の書『皆のあらばしり』の調査を始めるが……
作品の魅力について

『皆のあらばしり』は第166回芥川賞の候補作で、乗代雄介にとっては3度目の候補ということになる。
前回は2021年の上半期のこと。
候補作『旅する練習』は文章も滑らかで、作品の“企み”もバシっと決まっていて、完成度の高い作品だった。
【 参考記事 あらすじ・解説・考察『旅する練習』(乗代雄介)―人生を全うすることー】
だけど、この時は宇佐見りんの『推し、燃ゆ』に敗れてしまい(これは仕方がない)、残念ながら受賞には至らなかった。
とはいえ、選考委員の評価は高く、乗代雄介は『旅する練習』で文壇に確かな爪痕を残したといっていいだろう。
そして今回紹介する『皆のあらばしり』は、前回同様に、いやそれ以上に作者の“企み”が効いている。
この記事では、『皆のあらばしり』という作品の魅力について紹介していきたい。
前半ではネタバレを避けつつ紹介していくので、「未読」の方もぜひ安心して読んでいただければと思う。
作品の魅力は次の3つだ。
- 魅力➀「実験的な手法」
- 魅力➁「どんでん返し」
- 魅力➂「ほどよいエンタメ感」
では、以下、具体的に説明していこう。
スポンサーリンク
魅力➀「実験的な手法」

『皆のあらばしり』がこれまでにない作品であるとすれば、間違いなくこの「実験的な手法」によっている。
その手法とは、物語の「語り手」を利用した一種の「叙述トリック」である。
たとえば「語り手」を利用した叙述トリックの一つに、「信頼できない語り手」というものがある。
これは、「語り手」がそもそも嘘をついていたり、自分に都合が良いように語ったりするというものなので、物語における「真実」が曖昧になってしまったり、読者が煙に巻かれてしまったりする。
過去の受賞作品の中に『むらさきのスカートの女』(今村夏子)という作品があるが、これこそ「信頼できない語り手」という手法を見事に成功させ、満場一致で芥川賞を受賞した作品だ。
【 参考記事 解説・考察『むらさきのスカートの女』―「語り手」を信じてよいか― 】
今回の『皆のあらばしり』も、「語り手」による叙述トリックが使われているのだけれど、これが今までになかったような独特なトリックなのだ。
しかも、それが見事に成功している。
ネタバレになるので、ここでそのトリックについて詳しく説明はできない。
興味のある方は、この記事内の【考察「語り手」がもたらす効果 】をぜひ参考にしていただきたい。
魅力➁「どんでん返し」

魅力➀の「実験的な手法」とも深く関係している点なのだが、この作品のラストには驚きの「どんでん返し」が待っている。
実は、前回の候補作『旅する練習』にも驚きの「どんでん返し」があった。
もちろん「どんでん返し」があれば良いというわけでもないし、文学において「どんでん返し」なんて別段 珍しいわけでもない。
ただ、前作『旅する練習』が、その辺の文学作品と異なっているのは、その「どんでん返し」が単なる「驚き」に終わっていなかった点だ。
読者は

え? どういうこと?
と困惑しつつも、それを何とか飲み込もうと、もう一度作品に目を通してみる。
すると、いままで気にも留めなかった「何気ない描写」や「何気ない場面」が意味を持ちはじめ、物語全体がこれまでと全く異なる表情を持って、読者の前に立ち上がってくる。
『旅する練習』のどんでん返しは、そういう類のものだった。
そして、今回の『皆のあらばしり』でも、まさにそんな「どんでん返し」が待っている。
しかも、その「どんでん返し」があるからこそ、作品全体に深みが生まれているのだ。
そこからの読後感も爽快感たっぷり。
魅力➀の「実験的な手法」と、この「どんでん返し」がダブルパンチとなって、読み終えた読者に気持ちのいい余韻を与えてくれる。
この辺りが『皆のあらばしり』の一番の魅力だろう。
スポンサードリンク
魅力➂「ほどよいエンタメ感」

物語のメインは「幻の書『皆のあらばしり』の調査」だ。
——はたして『皆のあらばしり』は「新発見」なのか、はたまた「偽書」なのか——
「ぼく」と「男」は、それを明らかにしようと秘密裏に調査を進めていく。
そのプロセスが、まさに「謎解き小説」さながらで、作品に程よい「ミステリー要素」を与えている。
さらに「男」の博識さや、洞察力、記憶力にも見どころがあり、ここにも「探偵小説」のような趣がある。
そんな「男」の「探偵」っぷりに「ぼく」は魅了されていくわけだが、物語を読めばそれも十分納得できるに違いない。
また、「ぼく」と「男」の掛け合いも、読んでいて面白い。
まず会話のテンポがいい。
物語の「謎解き」も、主に2人の会話を中心に進んでいくので、サクサク読み進めることができる。
また「男」の「本気なのか冗談なのか」分からない言動が随所に挟まれ、それに翻弄される「ぼく」の姿なんかも読んでいておかしい。
そうかと思えば、前述したラストの「どんでん返し」シーンでは、スリリングな会話劇が展開される。
この緩急ある「会話」の応酬も作品の魅力の1つだ。
この記事の冒頭「作者について」でも乗代雄介の文章の巧みさを紹介したが、それは「会話文」にも見て取れる。
「ミステリー要素」と「テンポの良い会話」
総じて『皆のあらばしり』には、「程よいエンタメ感」があるといえるだろう。
「程よいエンタメ感」はある意味、近年の芥川賞らしい性格なのだが、『皆のあらばしり』もまた「純文学」という冠が付きつつも、「おもしろい」作品に仕上がっている。
スポンサーリンク
”難点”があるとすれば……

以上、
- 実験的な手法
- どんでん返し
- ほどよいエンタメ感
が、『皆のあらばしり』の魅力だ。
ただ、(個人的には)難点がないわけでもない。
それを上げるとすれば、
「歴史研究」というニッチなモチーフを採用している点
である。
言ってしまえばこれはオタク的であり、もっといえば「ペダンチック」でさえある。
なんせ、この物語の中心は「『皆のあらばしり』の真偽の追究」なわけで、だから、どうしても読者は「歴史的にマニアック話」とか「論理的で緻密な考証」とかに耐える必要が出てきてしまう。
たとえば作中には「朱子学」や「国学」など、江戸時代の学問なんかが登場するのだが、そういうのが無理な人にとって、物語を読み進めていくのは正直きびしいかもしれない。
もちろん、そういった前知識が必ずしも必要という訳ではないが、文学における「ぺダントリー」というのは、いつだって読者を遠ざけてしまうもの。
この辺りは、読み手を選ぶ部分だと思うので、ぜひ参考にしていただければと思う。
考察「叙述トリック」について
“物語”を書いている人物

最後に、この記事でも紹介した「実験的な手法」、つまり「語り手」を利用した「叙述トリック」について考察してみたい。
ここから先は、完全なるネタバレを含んでいるので「ネタバレOK」って方や、「既読の方」のみ読んでいただければと思う。
まずはじめに「この“物語”を書いている人物」について確認をしておきたい。
結論を言えば、
“物語”を書いているのは、例の博識の「男」である。
『皆のあらばしり』のラスト3ページには、「男」による告白が書き込まれている。
そこで、この“物語”の真の「語り手」は「男」自身であることが明かされる。
どうやら私は(中略)素数の木曜日を指折り数えて待ち、その日のうちにICレコーダーに録音した二人の会話を再生して愉快に笑いながら、この私的記録を書き継いでいたのだった。(単行本P131より)
つまり、「男」は「ぼく」とのやりとりをコッソリと録音し、その内容をもとに“物語”をその都度その都度、書き継いでいったというのだ。
では、なぜそんなことをしたのか。
それは、青年をだましている「優越感」や「快感」や「悦楽」に浸りたかったからだ。
コイツ、まんまと俺にだまされてやがる、かわいそうになあ、ぷぷぷ……
「男」にはそういった「おごり」と「満足」とがあり、そういった思いから“物語”を書き継いでいったわけだ。
しかも、被害者である青年(ぼく)を「語り手」にして。
過信と遊び心が語り手に青年を選んだ(P131より)
男は、被害者である「ぼく」を語り手にした。
そして、「まんまと青年をだましてやったぜ、俺スゲエ」話を書くことで、詐欺師としての自らの「自尊心」を満たしつつ、愉快な気持ちに浸っていたのだった。
ところが“物語”の結末は、「男」の予想をはるかに裏切るものとなる。
スポンサーリンク
・
“物語”の思わぬ結末

男の予想を裏切る結末、それは、
実は「男」の方が、青年(ぼく)に騙されていた
というものである。
物語のクライマックスで、ついに「ぼく」は竹沢家から『皆のあらばしり』を盗み出す。
それに対して「男」が、
「竹沢のひいじいさんは、さすがに『皆のあらばしり』が盗まれたことに気づくんじゃないか?」
と心配するシーンがある。
それにたいして、「ぼく」はこう切り返して「男」を困惑させる。
「竹沢家の人間は、『皆のあらばしり』がなくなったことに気付かない」
「ひいじいさんが気づくに決まってるやろ」
「気付かないよ」
「なんでやねん、これまでのこと考えたら——」
「嘘だ」
「あ?」
「嘘だよ」とぼくは言った。「これまであんたに話してたこと」
「な」固まりかけた顔は、それでもなんとかいつもの馬鹿にするような笑いの相に流れた。(P124より)
要するに、「男」の方が「ぼく」に騙されていたのだ。
そして、「男」はそのことに最後の最後まで気が付かなかった。
だからこそ、この“物語”の隅々には「男」の「おごり」とか「満足」とか「過信」とか、つまり「男」の「純粋な青年をだましてやってるぜ、ぷぷぷ……」感 が色濃く表れちゃっているのである。
しかも、語り手の「ぼく」に、次のように語らせる始末。
ぼくが疎みながらも惹かれているのは、男の知識のためなのだ。(P50より)
ぼくは勉強しなければならないんだろう。この男のようにとは言いたくないけれど、この男ぐらいに、知識を溜め込んで、自在に使わなければならない。(P65より)
つまり、「男」は「ぼく」に
「こ、この男、うさん臭いがタダもんじゃねえ」
と語らせることで、自画自賛に浸っているわけだ。
「男」は「青年」に会う度、そういう“物語”を延々と描き継いでいった。
だけど、フタをあけてみれば、
「実は騙されていたのは僕の方でした」
という悲しい結末になってしまったわけだ。
こんな間抜けで滑稽なことはない。
スポンサーリンク
“おめでたい語り手”とは

自らの「天狗」っぷりと「無能」っぷりを露呈させてしまった「男」
だからこそ彼は、ラスト3ページでこう告白をしている。
過信と遊び心が語り手に青年を選んだせいで、その出来上がりは、私の無能ぶりを歴然と示しているようだ。「信頼できない語り手」は腐るほどあれ、「おめでたい語り手」というのは滅多にお目にかかれるものではない。(P131より)
「男」は「騙されているくせに自画自賛していた」自らの無能っぷりを認めている。
そして、そんな無能な男によって生まれた「語り手」を「おめでたい語り手」と呼んでいる。
「俺はやっぱりスゲエ詐欺師なんだぜ」と有頂天になっていた自らを、「おめでたい奴だ」と自虐しているわけだ。
だけどここには、妙な清々しさがある。
なぜか「男」には「悔しい」とか「みじめさ」とかいった負のオーラはないし、もっといえば「自己弁護」とか「自己欺瞞」のような姿勢というのも皆無だ。
言い訳したり、誤魔化したりするのは簡単なはずだ。
「いや、本当はだまされてたことくらい、薄々勘づいてましたけどねえ」
そういったことを書こうと思えば書けるわけだし、なんならこれまで書き継いできた“物語”を捏造したっていいわけだ。
だけど、「男」はそうすることなく、自らの無能っぷりを臆面もなく発表した。
そこには、「男」の「ぼく」に対するリスペクトがある。
私はこの美しい法螺貝城に、世にも得難い詐欺師の姿を埋め残したいのだ。(P131より)
この「詐欺師」とは、言うまでもなく「ぼく」のことである。
「男」は自らの「負け」を完璧に認め、自分を負かした青年の才能を素直に称賛している。
だからこそ、その「世にも得難い詐欺師の姿」を、うそ偽りなく書き残そうと考えたわけだ。
『皆のあらばしり』は、読後、不思議な清々しさを感じる作品である。
その清々しさの正体は、「完膚なきまで負けました」と、高校2年生の若者に対して堂々と負けを認める「男」の潔さだと言っていい。
特に最後の「空気ヘビ」のくだりは最高だ。
頭を打たぬようしばらく前にこらえていた首は、自分を襲ったのが例の空気ヘビだと気づいたとき、観念したように脱力して地に置かれた。
(中略)
缶の中に収まっているのは紛れもなく目的のもので、断トツに優秀な同僚候補の連絡先まで添えられていたというのに、私はそれに見向きもせず、しばらく愉快に笑っていた。(P133より)
「男」の心には、いかなる屈託もない。
それはまるで、すっきりと晴れ渡る空のようだ。
そんな「男」の笑い声が、 大きく広がる澄みきった青空に響く。
このラストシーンが、うなるほど上手い。
スポンサーリンク
・
「叙述トリック」がもたらす効果
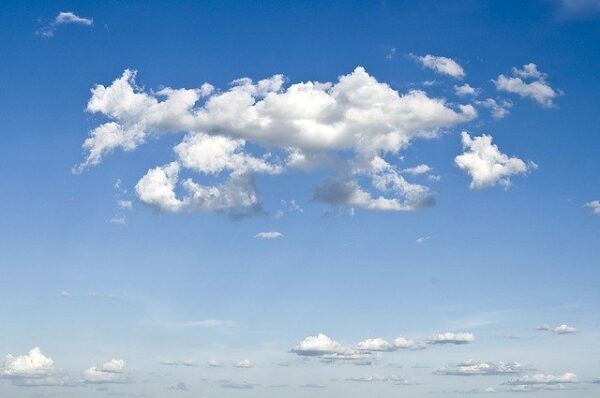
『皆のあらばしり』の一番の魅力は、この「おめでたい語り手」にある。
最後まで読んだ方は、ぜひもう一度はじめから、「ぼく」と「男」のやり取りを読んでみてほしい。
ここに書かれているのは、あくまでも「おめでたい」男の一つの解釈にすぎない。
結局「ぼく」という人物については、ほとんど分からずじまいなのだ。
- この青年はいつから「男」をだましていたのだろうか。
- この青年は、本当に「男」に惹かれていたのだろうか
- この青年は、いったい何者なのだろうか。
それについては、読者が想像力を働かせて再構築するしかない。
最期の3ページで小説世界を一気に広げてしまう。
それが『皆のあらばしり』に仕掛けられた叙述トリックなのである。
スポンサーリンク
オススメの本を紹介
『旅する練習』(乗代雄介)
第164回芥川賞候補作。
サッカー少女と小説かによる旅を描いた「ロードノベル」で、読後は温かく、やさしく、そして切ない、なんとも言えない余韻に包まれる。
すでに、この作品の中に『皆のあらばしり』の芽が潜んでいる。
- 「語り手」の設定
- 最後の「どんでん返し」
この辺りの技巧は、『皆のあらばしり』と共通している。
個人的な感想を言えば、僕は『旅する練習』のほうが文学らしい作品だと思う。
何よりも、僕は最後の最後で泣かされてしまった。
『皆のあらばしり』とはまた違った読後感を、ぜひ堪能していただきたいと思う。





コメント