「文化人類学とは」を簡単に

まずは「文化人類学とは何か」について、簡単に述べておこう。
以上が、文化人類学についてのシンプルな定義だ。
……が、これだけでは、この学問の奥深さや面白さをちっとも説明したことにはならない。
以下では、文化人類学が歩んできた歴史を踏まえつつ、もう少し踏み込んだ解説をしていこうと思う。
「文化人類学とは」を詳しく
「人類学」の下位分野の1つ

さて、ここでは、先ほどのシンプルな説明を、もう少し膨らませて「文化人類学とは何か」について解説をしたい。
そもそも、文化人類学とは、広義の「人類学」の中の1つの分野(つまり、下位分野)である。
人類学には「文化人類学」を含めて、大きく次の4つの分野がある。
こんな風に、一口に「人類学」といっても、そのアプローチは様々であり、その違いによって「〇〇人類学」と区別されている。
「先史考古学」とは、主に先史時代の人類の遺跡などを研究することで、「人間とは何か」に迫ろうとする学問であり、「生物人類学」とは、文字通り生物学的に、あるいは医学的に、「人間とは何か」に迫ろうとする学問であり、「言語人類学」とは、人類の言葉に注目して「人間とは何か」に迫ろうとする学問である。
そして、「文化人類学」とは、人間の文化や生活様式、行動様式を観察・分析することで、「人間とは何か」に迫ろうとする学問なのである。
扱われる研究テーマ

ただ、「人間とは何か」という問いは、あまりにも曖昧で大雑把である。
そこで、文化人類学で頻繁に扱われるテーマとして、次のものを紹介したい。
これまで文化人類学の多くが、近代化以前の文化が残る社会(いわゆる「未開社会」)を主な研究対象としてきた。
たとえば、国家や法律を持たない未開社会を研究することで「近代社会」の本質を明らかにしようとしてきたし、貨幣を媒介としない贈与経済を研究することで「市場経済」の本質を明らかにしようとしてきた。
あるいは、自然物を崇拝するアニミズムやトーテミズムを研究することで、キリスト教などの「世界宗教」の本質を明らかにしようとしてきたし、呪術による治療システムを研究することで「西洋医学」の本質を明らかにしようとしてきた。
つまり、文化人類学が目指すこととは、
- 人間はどのように秩序を保つのか
- 人間はなぜ経済活動をするのか
- 人間はなぜ神秘的な力を信じるのか
- 人間は病と死をどうとらえるのか
こうした問いに対する答えを見つけることであり、これらの問いは、
「人間とは何か、人間の本質とは何か」
という大きな問いに集約することができる。
基本的な方法論
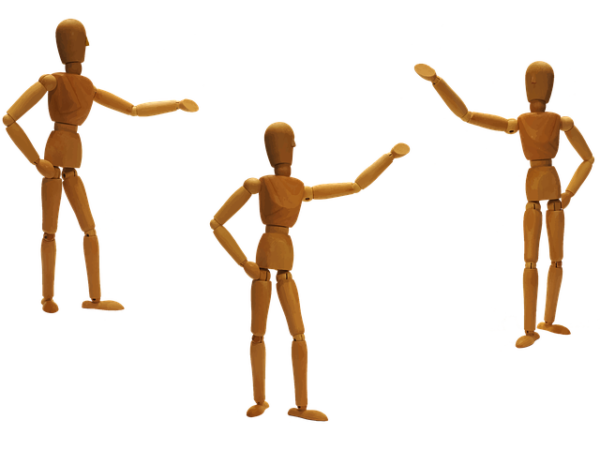
文化人類学とは、特定集団の生活、習慣、活動などを観察・分析することで「人間本質」に迫る学問である。
そして、これまでの文化人類学は、多くの場合、「未開社会」と呼ばれる、前近代的な集団を研究の対象としてきた。
文化人類学にはこういう性格があるため、その研究の方法として、長らく「フィールドワーク」が採用されてきた。
つまり、研究対象の現場に赴き、通訳を介さず、長期間現地の人と過ごすなかで、その文化を観察・分析しようという方法だ。
なお、フィールドワークは、文化人類学の用語で「長期参与観察」と呼ばれている。
これは1922年にイギリスの文化人類学者「マリノフスキ」によって提唱されたもので、現在の文化人類学でも採用されている最もオーソドックスな方法である。
実地で「生きたデータ」を得られる点が大きなメリットとされてきた一方で、「どのデータを切り取るか」や「得られたデータをどう分析するか」については研究者の主観が大きく影響するため、その科学的な信ぴょう性について批判されてきた。
つまり、長期参与観察という方法を用いつつ「客観性はどう確保できるのか?」というのが、文化人類学の大きな課題となってきたのだ。
とはいえ、「そもそも客観とは何なのか?」や「科学的方法論は本当に正しいのか?」といった声もあり、文化人類学の方法をめぐっては現代においても議論が続いている。
スポンサーリンク
文化人類学の歴史
「進化主義」の登場

文化人類学の始まりには、次のような問いがある。
――人間は同じなのか、違うのか。違うなら、何がどう違うのか――
これまでの文化人類学者はみな、この問いに正面からぶつかってきたのだといっていい。
文化人類学の始まりは、一般的に1922年頃と言われている。
先ほど紹介したマリノフスキの『西太平洋の遠洋航海者』と、ラドクリフ=ブラウンの『アンダマン島民』の出版がスタート地点である。
とはいえ、それ以前にも、文化人類学的な研究者は存在していた。
その代表的人物が、アメリカの人類学者「エドワード・タイラー」だ。
「文化人類学」の父と言われる彼は、1871年に『進化主義』という著作の中で、「人類は1つの種である」ことを主張した。
以上が、進化主義の思想内容なのだが、これは当時としては凄い思想だった。
なぜなら、1871年というのは、西洋中心主義が色濃い時代であり、
「白人でなければ人ではない」
といった価値観が、大げさではなく西洋社会の常識となっていたからだ。
それが理由に欧米社会では、人間を標本として展示する「人間動物園」なんて信じられない催しがあったし、主に西欧社会による「奴隷制」や「植民地政策」なんかも、基本的に白人以外を人間として認めない思考が根っこにある。
そんなかで、エドワード・タイラーは、
「西洋人も東洋人もアフリカ人も、みんな祖先は同じ。人類みな兄弟!」
と、言い放ったわけで、これが当時の西洋社会に大きな影響を与えたということは想像に難くない。
「進化主義」への批判

エドワード・タイラーは、これまで露骨な差別や排除の対象となっていた人々の権利を取り戻そうとした。
そうした点において、彼は「文化人類学の父」と呼ばれるようになり、ここから文化人類学がスタートしたと語られることもある。
が、エドワード・タイラーの主張には、まだまだ西洋中心主義の名残があった。
彼は次のように説明する。
「われわれ西洋人の社会と非西洋人の社会の違いは、文化の発展段階の違いである」
つまり、
「非西洋社会は時間の経過によって、いずれは西洋社会のように進化する」
と、エドワード・タイラーは主張しているのである。
ちなみに、エドワード・タイラーもまた、研究対象を非西洋社会(いわゆる「未開社会」)に定めていた。
それは、未開社会に、「西洋人が失ってしまった人間の本質」が、いまだに残っていると信じたからだった。
「未開社会にこそ、人間とは何かを説くカギがある」
こういえば聞こえはいかもしれないが、だけどやはり、エドワード・タイラーの人間観には、依然として「西洋は進んでいる(優れている)、非西洋は遅れている(劣っている)」といった考え方がぬぐい去りがたく存在している。
こうしたことから、エドワード・タイラーの『進化主義』は批判されることになる。
「世界には“進んだ文化”と“遅れた文化”があることを前提にしているのか!」
「西洋社会が進んでいて、非西洋社会は遅れていると言いたいのか!」
「けっきょくは、自民族中心主義じゃないか! 西洋中心主義じゃないか!」
こうした経緯があるので、「近代的文化人類学」の始まりは、エドワード・タイラー(1871年)からではなく、先ほど紹介したマリノフスキ(1922年)以降とされるのが一般的だ。
とはいえ、エドワード・タイラーが西洋社会に投じた一石、
「非西洋社会に光を!」
といった主張は、人類において大きな大きな一石だったといっていい。
スポンサーリンク
「文化相対主義」の登場

エドワード・タイラー以降、彼の『進化主義』を発展的に乗り越えようとした文化人類学者が次々と登場してくる。
その代表者が、アメリカの人類学者「フランツ・ボアズ」や「ルース・ベネディクト」である。
フランツ・ボワズはコロンビア大学に、アメリカ最初の人類学部を創設し、その発展に貢献した人物だし、ルース・ベネディクトは、日本では名著となっている『菊と刀』で優れた日本人論を展開した人物である。【 参考記事 分かりやすく解説『菊と刀』ー「恥の文化」と「罪の文化」とはー 】
両者に共通しているのは、主流となっていた「進化主義」を批判し、文化相対主義をとなえた点だ。
あらためて、文化相対主義とは何かといえば、
こうした思想は、現代においては、ほぼ常識となっているが、これも当時としては画期的な発想だった。
西洋中心主義は「白人だけが人間! 白人が一番!」と信じて疑わなかったし、進化主義は「人類はみな同じ人間! だけど、現状、白人が一番進んでいる!」と、西洋文化の優位性を信じていた。
そこにきて、文化相対主義は、
「いや、そもそも、優劣なんかをつけること自体が間違っているんだよ」
と、西洋中心主義も進化主義も痛烈に批判したのだった。
「世界にはいろんな人たちがいるけれど、その行動だけを見て優劣をつけることはできない。なぜなら、人間の振る舞いは遺伝ではなく、環境によって決まるからだ」
こうして、「人類に優劣はつけられない。表層的な文化の違いは環境の違いに過ぎない」といった考え方が、次第に西洋社会にひろがっていく。
そして、マリノフスキが登場し、「文化人類学」の方法論を確立したことで、文化相対主義は次第に西洋社会にも影響を与えていった。
そしてついに、それを爆発的に広めたレジェンドが現れる。
それが、フランスの文化人類学者「レヴィ・ストロース」である。
「構造人類学」の登場

レヴィ・ストロースが活躍するのは1950~1960年代のことだ。
レヴィ・ストロースといえば、哲学の文脈で話題にされることが多い文化人類学者で、文字通り西洋社会に「革命」をもたらして偉大な人物である。
彼の哲学的な功績については、ここで詳しく説明することができないが、彼の文化人類学的功績については以下でしっかりと説明をしようと思う。
基本的にレヴィ・ストロースも「文化相対主義」に立脚し「文化に優劣など存在しない」という姿勢を徹底している。
レヴィ・ストロースいわく、
「文化の違いは環境の違いであって、しかも偶然性に基づく」
こんな風に、進歩主義を徹底的に批判している点は、先ほどのフランツ・ボアズやルース・ベネディクトと大きく変わらない。
では、レヴィ・ストロースの何が画期的だったかといえば、文化人類学に「構造」という概念を導入したことだった。
では、その「構造」とは一体何か。
それをシンプルに定義すれば、およそ次のようになる。
これがレヴィ・ストロースの導入した“構造”の定義であり、この“構造”を中心に展開した人類学を「構造人類学」と呼ぶ。
以上が、レヴィ・ストロースの“構造人類学”の説明である。
レヴィ・ストロースもまた、フィールドワークによって、いわゆる「未開社会」に身を置いて、彼らの文化を観察・分析した。
そこで、レヴィ・ストロースはある不可解な点に目をつけた。
それは、いわゆる「近親相姦」(インセスト)の禁止だった。
しかも、そこには独特のルールがあった。
それは、
「平行いとこ」同士の結婚はNGだけど、「交叉いとこ」同士の結婚はOK
というルールだった。
これは、たとえば、「父の弟から生まれた子」とは結婚OKなのに、「父の妹から生まれた子」とは結婚NGというルールである。(要するに、一見して、非合理的なのだ)
この不可解なルールは、一体なんなのだろう……
ちなみに、西洋人たちの目には、次のように映った。
「え? なんで、そんな意味わからんルールがあるの? あ、そっか、未開人だから頭が悪いんだね、ぷぷぷ……」
しかし、レヴィ・ストロースは、この未開社会の「婚姻ルール」こそ、人類が共通して持っている構造の1つだと考えた。
要するに、人類の行動を規定する、共通した原理のようなものである。
さて、未開社会がなぜ、こんな不可解なルールを採用していたのか。
結論をいえば、
「流動的に人間関係を営むため」
ということだった。
言い方がメチャクチャ不適切なのだが、要するに、「互いに“人間”を交換し合うことで、コミュニケーションの輪を絶やさないようにしていた」のである。
しかも、そのルールには、まるで計算しつくされたような合理性があって、それは当時の西洋社会の高度な数学的考え方と、ほぼ一致していたとも言われている。
つまり、未開社会には未開社会の「高度な合理性」が働いていて、それは、西洋社会の合理性となんら変わらなかったのである。
ただ、違いがあるとすれば、それは環境に基づく「表面化の仕方」の違いだけだった。
こうしてレヴィ・ストロースは「構造」という概念を導入し、「人類はみな“構造”という普遍的な原理に支配されている」といったことを論理的に明らかにしたのだった。
この「構造人類学」が西洋社会に与えた影響はとてつもなく大きく、ここから「西洋中心主義」や「自民族中心主義」が本格的に見直され、「文化相対主義」というのが現実的に語られるようになっていく。
レヴィ・ストロースの功績は絶大だった。
ただ、こんなレヴィ・ストロースの考え方にも、次第に批判が集まることになる。
スポンサードリンク
現代の文化人類学

1950年代以降、レヴィ・ストロースの「構造人類学」は、自文化中心的な西洋社会に大きな反省を迫った。
ところが、そんなレヴィ・ストロースの思想も、現代の文化人類学においては批判を受けることがある。
それらを分かりやすく、ざっくりと趣旨を述べれば次のようになる。
「西洋社会はああだとか、非西洋社会はこうだとかいうけど、そういうのを語るのって、いつだって西洋人のほうだよね」
「未開社会について観察したり分析したり、分かったような口をきいたりしているけど、いったい何様なの?」
これは、レヴィ・ストロースの中にいぜんとして残り続けている、ある種の傲慢さを批判したものである。
いや、もっといえば、「文化人類学」という営みすべてに向けられた批判だといってもいい。
西洋人が非西洋人を観察する傲慢さ、分析する傲慢さ、解釈する傲慢さ……
そうした文化人類学そのものが持つ「権力性」を批判したものなのだ。
たしかに、これまでの文化人類学が果たした功績は大きい。
多くの文化人類学者は「非西欧社会に光を!」という信念のもと、未開社会を研究し、そして「文化相対主義」を西洋社会に訴えてきた。
だけど、そんな文化人類学でさえ、ある種の「権力」に絡めとられてしまっていたのである。
そうした点を批判する、現代の文化人類学者は少なくない。
たとえば、2000年代あたりから注目され出したのは「ブルーノ・ラトゥール」というフランスの文化人類学者だ。
彼は「未開社会」ばかりを研究してきたこれまでの文化人類学を批判し、なんと「近代社会」を文化人類学的な手法で観察・記述する研究を打ち出した。
中でも「近代科学」を中心に研究した彼の学問は、「科学の人類学」と呼ばれている。
こうしてラトゥールが目指したのは、「近代/非近代」とか「西洋/非西洋」といった二分的な考え方を乗り越えることだった。
「僕たちと、僕たちとは違う人たち」
この二分法にとらわれ続ける限り、西洋社会の権力性は否定できないからだ。
ラトゥールはレヴィ・ストロースを批判して、次のようにいう。
「すべての文化は同等だっていうけど、分析し解釈するのはいつだって西洋側だよね、そこに権力性が認められるよね、そもそも、他者を理解することや、解釈することなんてできるの?」
さぁ、こうなってくると、もはや文化人類学は八方ふさがりの感がいなめない。
現代の文化人類学が直面している課題は、決して容易なものではないのだ。
スポンサーリンク
まとめ「文化人類学の前途」

最後に、僕の思うところを簡単に述べて、記事を締めくくりたい。
ラトゥールが明らかにしてしまったように、「語る側/語られる側」といった二分法には、ある種の権力性が否定しがたく存在している。
となると、そもそも「他者を理解しよう」という態度や「他者を解釈しよう」という態度は、どこまでも傲慢な行為ということになってしまう。
……ってことは、もう、人類の相互理解は不可能ということになるのだろうか。
――人間は同じなのか、違うのか。違うなら、何がどう違うのか――
先人たちが挑み続けてきたこれらの問いに、現代の文化人類学者たちは口を閉ざさなければならないのだろうか。
もちろん、答えは “否” である。
さきほど紹介したラトゥールのほかに、「ティム・インゴルド」、「デヴィッド・グレーバー」といった現代を代表する文化人類学者たちが、こうした難問に挑み続けてきたからだ。
文化人類学は、まちがいなく、公正な社会や人類の平和のために必要不可欠な学問だ。
そうした学問が歩みを止めてしまうことは、「人類に対する絶望」だと言っても過言ではないだろう。
僕たちが“隣人”を大切にするために、そして、自分の傲慢さや暴力性を自覚するために、文化人類学の歩みは、決して止まってはならないものなのだと僕は思う。
そして、それらの知見に触れることは、僕たちひとりひとりにとっても大きな意義があるはず。
この記事で一人でも多くの方が、文化人類学の面白さはもちろん、学ぶ意義について考えることができたのならとても嬉しい。
また、この記事の終わりに、文化人類学を学ぶ上で、おすすめの参考書をいくつか紹介しているので、良かったらぜひ参考にしていただきたい。
以上で「文化人類学」の解説を終わります。最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
文化人類学のオススメ本
これからの時代を生き抜くための 文化人類学入門
とにかく読みやすい、文化人類学の入門書的エッセイ。
分かりやすさもさることながら、扱うテーマは「文化人類とは何か」にはじまり、「性」、「共同体」、「経済」、「宗教」など、文化人類学の勘所をしっかりとおさえたものばかり。
筆者の奥野克巳氏は、フィールドワークを基軸に研究するゴリゴリの文化人類学者で、滞在した場所はメキシコ、バングラデシュ、トルコ、インドネシア、ボルネオ島焼畑民カリスと様々だ。
本書はボルネオ島の狩猟民プナンにおけるフィールドワークをもとにした作品となっているが、読み進めていくうちに、自分自身の凝り固まった常識がほごされていく感覚を覚える。
文化人類学を学んだことのない、まったくの初心者にオススメ。
旋回する人類学
こちらも、文化人類学の入門書ということだが、かなり踏み込んだ内容なので、対象は初心者から中級者向けといった感じ。
タイトルに“旋回する”とあるように、文化人類学の歴史を“行ったり来たり”しながら、文化人類学という学問の全貌を明らかにしようとする。
本書を読み終えれば、過去から現在にいたるまでの文化人類学の営みをおおむね理解することができると思う。(ちなみに、この記事は本書を大いに参考にしている)
ラトゥール、インゴルド、グレーバーなど、最新の文化人類学者について学べるのも、本書ならではの利点。
これまで文化人類学は どのような課題に挑んできたか、そして、現代において どのような課題に直面しているか。
そうしたことを知りたい方にはオススメの1冊。
レヴィ=ストロース入門
この記事でも彼の思想について触れたが、本書はより広く、より詳しく、より丁寧に解説してくれる良書。
もはや説明不要、文化人類学の巨人「レヴィ・ストロース」の入門書。
レヴィ・ストロースの入門書ではあるが、彼の思想を学ぶことで、文化人類学という学問の本質も同時に学ぶことができる。
また、西洋哲学に与えた影響についても詳しく知ることができるので、哲学に興味がある方にもオススメの書となっている。
思想や哲学を学ぶなら
耳読書「Audible」がオススメ

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、哲学書・思想書・宗教書が月額1500円で“聴き放題”。
例えば、以下のような「解説書」も聴き放題の対象だし……

・
以下のような「原著」も聴き放題の対象となっている。

・
それ以外にも純文学、エンタメ小説、海外文学、新書、ビジネス書、などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。
これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。
・
・
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、軽い気持ちで試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
.
・





コメント