はじめに「作者」について

作者の川上未映子は、大阪府出身の小説家であり、詩人であり、しかも元歌手。
2007年に、『わたくし率 イン歯-、または世界』で作家デビューし、続く『乳と卵』で2008年 第138回芥川賞を受賞している。
その他の受賞歴も華々しくて、
小説家としては、紫式部文学賞、谷崎潤一郎賞、毎日出版文化賞をはじめとした数々の文学賞を受賞しているし、詩人としての活躍もめざましく、中原中也賞も受賞している。
彼女の作品のうち、今回紹介するのがこれ。
作品のかんたんな紹介

『ヘヴン』は川上未映子の長編小説だ。
芸術選奨新人賞や第20回紫式部文学賞を受賞し、さらに、2022年にはイギリスで最も権威ある文学賞「ブッカー賞」の翻訳部門にあたるブッカー国際賞の最終候補作品に選ばれた「傑作」の呼び声高い作品だ。
「いじめ」を扱った作品なので、むごたらしく凄惨な描写もあって、読んでいて胸が締めつけられる思いがする。
だが、それ以上にこの作品が凄まじいのは、そのテーマの「重さ」だといえるだろう。
そもそも、川上未映子の作品の魅力はそのテーマにあるとぼくは思う。
処女作の『わたくし率 イン歯-、または世界』と、続く『乳と卵』で扱ったテーマも凄かった。
そのテーマとは、
- 「心」
- 「存在」
- 「不条理」
といったものであり、要するにゴリゴリの「哲学」的なものだったのだ。
そして、こんかい紹介する『ヘヴン』もまた、まさしくゴリゴリの哲学的なテーマを扱った作品である。
では、『ヘヴン』が扱うテーマとは何だろう。それは、
- 「宗教」ってどうして生まれたの?
- 「善」とか「悪」って何なの?
といったものである。
こう書くと、

うっ、じゃあ自分とは無縁の小説だ(さよなら……)
と、引いていってしまう人もいるかもしれないが、大丈夫、そんな心配は全くいらない。
というのも、『ヘヴン』には哲学的な言葉も概念もいっさい登場しないからだ。
そもそもストーリーだけでもグイグイ読ませるし、登場人物たちもキャラが濃くて生き生きしているし、要するに「おもしろい」作品なのだ。
別に構える必要はないので、安心して作品を手に取ればいい。
ただ一方で、『ヘヴン』で扱われたテーマをじっくりと考察する意味はある。
じっくりと考えることで新たな発見もあるだろう。
ということで、ここからは『ヘヴン』で扱われたテーマについて解説・考察をしていこうと思う。
ここで改めて「ヘヴン」のテーマを振り返ると、
「宗教」はどうして生まれたのか
「善」や「悪」とはそもそも何か
というものだった。
そして、『ヘヴン』において、これらの問いに対する一定の解答らしいものが提示されているのだが、まずそれを明示しておきたい。
それは、
- 「宗教」は弱者の「怨恨・憎悪・嫉妬」(ルサンチマン)から生まれた。
- そもそも「善悪」(=道徳)など存在しない、あるのは人々の「欲求」だけ。
というものである。
まぁ、これだけではさすがにチンプンカンプンだと思うので、以下くわしく説明して行こうと思う。
と、その前に、まずは主な登場人物の紹介と、簡単なあらすじの確認から。
登場人物とあらすじ

登場人物
「僕」
…主人公。14歳の中学生。“斜視”を理由に「ロンパリ」と呼ばれ、クラスの男子たちから凄惨ないじめを受けている。「コジマ」と文通をはじめ、次第に仲を深めていく。
コジマ
…「僕」と同じクラスの女子。家が貧乏で容姿が“不潔”という理由から、クラスの女子たちからいじめを受けている。ある日、「僕」に「ヘヴン」という絵画を紹介する。
二ノ宮 …「僕」をいじめるリーダー格。中性的で端正な顔立ちをしていて、クラスの中心的な存在。“人間サッカー”など「僕」への残酷ないじめは、主に二ノ宮の提案による。
百瀬
…「僕」と同じクラスの男子。二ノ宮と一緒に「僕」をいじめる一員だが、彼は基本的にいじめを傍観することが多い。「あらゆることに意味はない」という独自の「哲学」を持っている。
あらすじ
“斜視”が原因でいじめを受けている「僕」 ある日〈わたしたちは仲間です〉と書かれた手紙を受け取る。 その差出人は、同じくいじめを受けている同級生のコジマだった。 そこから「僕」とコジマは文通をしながら次第に仲を深めていく。 コジマは僕に言った…… 「自分たちがいじめられるのには意味がある」 「弱いことは強く美しいことなのだ」 「“斜視”は、その強さの“しるし”なのだ」 しかし「僕」が「斜視の手術」についてコジマに話すと、態度が一変。 コジマは「僕」を拒絶し、手紙の返事もくれなくなった。 それでも手紙を出し続ける「僕」そしてあるとき、「公園で待っている」という返事が「僕」に届く。 公園でコジマに再会した「僕」だったが、突然そこに二ノ宮たちが現れて……

コジマという人物
コジマにとって「神」

改めて『ヘヴン』のテーマには、
- なぜ「宗教」は生まれたのか。
- 「善」や「悪」とはそもそも何か
というものがある。
これらを考察していく上で、まず取り上げたい人物がコジマだ。
コジマには独自の「哲学」があり、後述する百瀬の「哲学」と、真っ向から対立している。
ここでは、次の点について1つ1つ考察していきたい。
・コジマにとって「神」とは ・コジマにとって「しるし」とは ・コジマにとって「弱さ」とは ・コジマにとって「ヘヴン」とは
まずは、1つ目、コジマにとって「神」とはどんな存在なのだろう。
先に結論を言えば、
「苦しみ」に必然性と意味を与えてくれる存在
ということになる。
コジマは「僕」同様に、クラスメイトらから凄惨ないじめを受けている。
あるときコジマは「僕」に対して、こんな質問を投げかける。
「ねえ、神様っていると思う?」(講談社文庫P117より)
唐突な質問に「僕」は困惑したように
「神様? 神さまってどんな?」
と問い返すのだが、コジマはこう続ける。
「全部のことをちゃんとわかってる神様よ。見せかけや嘘をちゃんと見抜いて、ちゃんとわたしたちのことを分かってくれている神様のことよ」(P177より)
ここでコジマの言う「神様」というのは、あらゆる「悪」を見抜き「不当に苦しむ者」たちを理解してくれる存在のことだ。
悪いヤツを許さない
弱い者を助けてやる
コジマのいう「神様」とは、そんな「弱者の味方」とでも言い換えることができるだろう。
コジマはなぜ、唐突に「神様」などを持ち出したのか。
その理由についてコジマは言う。
「そういう神様みたいな存在がなければ、色々なことの意味がわたしには分からなすぎるもの」(P177より)
どうやら「神様」は、色々なことに「意味」を与えてくれる存在らしい。
ではコジマは一体、何についての「意味」を求めているのだろうか。
それは「いじめ」をはじめとした、彼女自身の「苦しみ」である。
「なにもかもぜんぶ見ている神様がちゃんといて、最後にはちゃんと、そういう苦しかったこととか乗り越えてきたものが、ちゃんと理解されるときが来るんじゃないかって、……そう思っているの」(P178より)
そしてコジマはこう口にする。
「苦しみや悲しみには必ず意味がある」(P118より)
「これを耐えなきゃたどりつけなかったような場所やできごとが待っている」(P119より)
こんな風に、コジマにとって「神様」とは「苦しみ」に「意味と必然性」を与えてくれる存在なのだ。
スポンサーリンク
コジマにとっての「しるし」

次に2つ目、コジマにとって「しるし」とは何か。
これも結論を先に言えば、
自分に「苦しみ」を与える原因である一方で、「自分自身」を形作っているもの
ということになる。
作中で、コジマは「僕」に対して繰り返し、
「苦しみには意味がある」
「苦しみはいつか報われる」
と、彼女の信念を伝える。
そして、こう念を押すのだ。
「わたしは、君の目がとてもすき」(P122より)
コジマがそういうのは、「僕」の斜視が“しるし”だからだ。
「君は斜視で、そのせいでわたしとおなじようにまわりからひどい目に遭っていて、つらいことだけれど でもそれがいまの君っていう人をつくっているってこともたしかだと思うの」(P121より)
コジマも「僕」同様に“しるし”を持っている。整理すると、
- 「僕」の“しるし”=斜視
- コジマの“しるし”=貧乏(汚い容姿)
ということになる。
コジマに言わせれば、“斜視”も“汚い容姿”も、どちらも自分たちに苦しみを与える根源であると同時に、「自分を自分たらしめている」ものであるわけだ。
自らの「アイデンティティ」だといってもいいだろう。
しかも「苦しみ」には必ず意味があり、苦しみ続ける自分たちが報われる日が来るのだと、コジマは信じている。
コジマの「苦しみ」についてのロジックを整理するとこういうことになる。
「この苦しみにどんな意味があるのか、私には分からない」
↓
「だけど、きっと神様が私の苦しみを理解してくれている」
↓
「だから、今はどんなに辛くても、この苦しみが報われる日はきっとくる」
↓
「その日まで、私はこの苦しみを受け入れて、耐えていかなければならない」
↓
「そして、私は苦しみの根源である“しるし”を守っていくのだ」
こうしてコジマは「苦しみ」と「自分自身の根拠」である「汚い容姿」という“しるし”を守り続けていくわけだが、コジマのその姿勢は、物語が進むにつれて常軌を逸していくことになる。
スポンサードリンク
コジマにとっての「弱さ」

次に3つ目、コジマにとって「弱さ」とは何だろう。
結論を言えば、
弱さ = 強く美しいこと
ということになる。
コジマによれば、「受難」とは「加害側への愛の行為」だという。
コジマは「僕」への手紙でこう書いている。
わたしがあの子たちの犠牲者だとしたら、あの子たちもまたなにかもっと大きなものの犠牲者なのじゃないかと、そう思ったりもするのです。
中略
わたしがあの子たちの仕打ちから学んだように、あの子たちもいつか自分たちの行為から自力で学び、そして知る必要があるのだと思います。(P131より)
自分をいじめる同級生たちも、哀れむべき存在なのだ。
自分はあえて「受難」を選ぶことで、「あの子」たちに学びの場を与えているのだ。
そうコジマは言っているのである。
ここまで読んで気づいた人もいると思うが、コジマのロジックには「逆転の発想」が見られる。
それは、
弱い → 美しい
弱者 → 強者
と捉え直すものである。
ここには、苦しみを受け入れる者は 神からの試練に耐える強さを持っている、という論理がある。
物語の後半で、コジマは「僕」に「弱さ」について必死に説明するシーンがある。
「……美しい弱さなのよ。わたしと君が、いまもそれぞれの場所で守りながらたちむかってることが、美しい弱さなの」(P240より)
「この弱さで、このありかたを引き受けて生きていくのは世界でいちばん大切な強さなんだ。これは……(中略)……世の中にあるすべての弱さのための、そしてほんとの意味での強さのための、儀式なのよ。」(P241より)
コジマは自らの「弱さ」の“しるし”を守るため、食事を絶ち、風呂に入らず、ガリガリに痩せこけて異臭を放つまでになる。
それは“不潔”でいることが、彼女にとって自分が「強く美しい」存在であることの証だからだ。
スポンサーリンク
・
コジマにとっての「ヘヴン」

最後に4つ目、コジマにとって「ヘヴン」とは、いったい何を意味しているのだろうか。
その結論を言えば、
苦しみが酬われ、自分自身が救われる境地
ということになる。
まず「ヘヴン」とは、街から少し離れた美術館にあって、コジマが「いちばん好きな絵」のことらしい。
オリジナルの名前は「つまらない」ので、コジマが勝手に「ヘヴン」と名づけなおしたという。
ある日「僕」はコジマに誘われて、その「ヘヴン」を見に出かけていくことになる。
では「ヘヴン」とは一体どんな絵なのだろう。
コジマの説明によれば「恋人たちが部屋でケーキを食べている絵」ということだ。
さらにコジマはそこに、次のような解釈を与えている。
- 2人には辛く悲しいことがあった
- 2人はいつでもくっつくことができる
- 2人はその困難を乗り越えることができた
- 2人はいま最高の幸せのなかにいる
- 2人がいる部屋こそが「ヘヴン」だ
これが「ヘヴン」という絵についてのコジマの解釈なのだが、まちがいなくコジマは「ヘヴン」に自分自身と「僕」の2人を投影している。
「ヘヴン」と「コジマの現実」は、こんな風に対応している。
- 辛く悲しい目(ヘヴン) = いじめと貧困生活(現実)
- いつでもくっつける(ヘヴン) = 自分と「僕」との連帯(現実)
そして「ヘヴン」の絵は、2人が困難の果てにたどり着く「幸せ」を象徴している。
だからこそ彼女は「仲間」である「僕」に ――同じ“しるし”を持っている「僕」に―― この絵を見せたかったのだ。
彼女にとって「僕」と一緒に「ヘヴン」を見ることは、2人の「苦しみの連帯」を改めて確認することを意味していた。
しかし、「僕」が「ヘヴン」を見ることは、ついになかった。
そのことが象徴するように、「僕」は自らの“斜視”を直すという決断を下すことになる。
それに対してコジマが怒るのは、「苦しみの連帯」を拒絶されたこともあるが、自分自身の「哲学」が否定されたことが大きいと思われる。
“貧乏”を病的なまでに突き通したコジマと、“斜視”の手術に踏み切った「僕」……
- “しるし”にまつわる「神話」にこだわったコジマ
- “しるし”を乗り越えようと主体的に決断した「僕」
といった具合に、2人の対照をはっきりと見て取ることができるだろう。
スポンサーリンク
百瀬という人物
百瀬の「ニヒリズム」

この記事では、『ヘヴン』で扱われているテーマ、
- なぜ「宗教」は生まれたのか。
- 「善」や「悪」とはそもそも何か
について考察している。
次に取り上げたい人物は「百瀬」だ。
ここでは、次の3点について考察していきたい。
・百瀬の「ニヒリズム」 ・百瀬にとって「善悪」とは ・百瀬にとって「意味」とは
まずは1つ目、百瀬の「ニヒリズム」について説明しよう。
彼にも独自の「哲学」があるのだが、それはコジマの「哲学」と真っ向から対立している。
百瀬はいわばコジマの「哲学」に対する「批判者」といった風に描かれているのだ。
では、百瀬の「哲学」とは一体どんなものなのか。
それは次の2つに要約できる。
- 社会通念としての「善悪」はフィクションである。
- 「意味」や「必然性」はフィクションである。
少しかみ砕いて説明すれば、
- 人に優しくすることは「善い」とか、人を傷つけることは「悪い」という考えは、人間が勝手に作った幻想に過ぎない
- 「苦しみ」や「悲しみ」に意味があるという考えもまた、人間が勝手につくった幻想に過ぎず、「たまたま」苦しんだり悲しんだりしているに過ぎない
ということになる。
百瀬のこの哲学を突き詰めていけば、
この世に普遍的な価値など存在しない
という考えにたどりつく。
こういう考えを哲学では「ニヒリズム」と呼んでいる。
まさに「物事には必ず意味がある」というコジマの哲学と真逆の思想である。
以下では、百瀬の発言をとりあげ、彼の意図について考えてみたい。
スポンサーリンク
百瀬にとっての「善悪」

次に2つ目、百瀬は「善悪」についてどう考えているか。
『ヘヴン』の山場は2つある。
1つは、最後の公園の場面で、もう1つは「僕」と百瀬が議論をする場面だ。
そしてぼくは、後者「僕」と百瀬の議論こそ、この作品の醍醐味だと思っている。
ドストエフスキーの長編小説に『カラマーゾフの兄弟』がある。
その中で
「神が作った世界を認めるかどうか」
「神はいるのか いないのか」
といった議論が展開される。
「大審問官」と呼ばれる文学史的にも超有名なシーンなのだが、「僕」と百瀬の議論というのも、大げさではなく この「大審問官」を彷彿とさせる。
「僕」はここで、百瀬の「哲学」に完膚なきまでに論破されてしまうのだが、では百瀬はどんな考えを持っているというのか。
結論からいうと、
人間の行動を決めるのは「善悪」の基準ではなく「欲求」と「状況」である。
これが百瀬の「善悪」に関する考えである。
では百瀬の発言をいくつか取り上げよう。
百瀬は「僕」をいじめることに対して、「なんの興味も意味もない」と言う。
「そんなことで、人をいじめていいのか」と反論する「僕」に対して、
「いいとか悪いではなく、状況の話だ」
と言い放つと、さらにこう続ける。
意味なんてなにもないよ。みんなただ、したいことをやってるだけなんじゃないの(P214より)
そして、「いじめる人間の心理」について、こう続ける。( 長くなるが、大事なところなので少し我慢してほしい )
まず彼らに欲求がある。その欲求が生まれた時点では良いも悪いもない。そして彼らにはその欲求を満たすだけの状況がたまたまあった。 (中略) それで、彼らはその欲求を満たすために、気ままにそれを遂行してるってだけの話だよ。君だってさ、やりたいことってなにかあるだろう? で、できることならそれをやってるだろう? 基本的に働いている原理としてはだいたいおなじだよ(P214より)
百瀬が言っていることを要約するとこうなる。
そもそも人間には「言い悪い」は別として「〇〇がしたい」という「欲求」がある。もしも状況がゆるせば、その「欲求」を行動に移す。人間は「善悪」ではなく「欲求」と「状況」に従う生き物であり、それがこの世界の基本的なルールである。
たとえば、これを読んでいるあなた。
あなたが「日常的に誰かを傷つけている」ってことは、まぁないと思う。
ただ百瀬によればそれは、あなたが普遍的な「善悪」の基準にのっとっているからではない。
あなたが人と傷つけない理由は、次の2つのどちらかだ。
- 人を傷つけたいという「欲求」がそもそもないから
- 人を傷つけたいという「欲求」を満たせる状況が整っていないから
つまり、人が行動するときに「道徳的に悪だ」とか「道徳的に善だ」とかは関係なく、人の行動は「欲求」と「状況」によって全て説明がつくのだ。
人の「欲求」なんて千差万別で、「人を傷つけたい」という積極的な欲求を持つ人もいれば、逆に「人を傷つけたくない」という消極的な欲求を持つ人がいる。
前者は人を傷つける傾向にあるし、後者は人を傷つけない傾向にある。
世界は、そんな一人一人の「欲求」が複雑にからんでいて、その中でたまたま「傷つく人」や「悲しむ人」や、もっといえば「虐げられる人」が生まれるだけなのだ。
この世界に「善悪」は存在しない。
あるのは、人々がそれぞれに持つ「欲求」と、その時々の「状況」だけ。
以上が百瀬の「善悪観」である。
スポンサードリンク
百瀬にとっての「意味」

次に、3つ目、百瀬はこの世界の「意味」とか「必然性」について、どう考えているのだろうか。
彼の考えを最初にいえば、
この世界に「意味」も「必然」も存在しない
それらは「弱い人間」が作りだした虚構に過ぎない
ということになる。
しつこいようだが、これはコジマとは真逆の考えである。
人間は「欲求」にしたがって行動する、と言い放つ百瀬に対して、「僕」は
「じゃあ、なにをしたって同じなのか? したいことをして生きればそれでいいのか?」と反論する。
人間には守るべき「正義」とか「正しい」価値観はあるんじゃないか?
「僕」はそう言っているわけだ。
だけど、それに対する百瀬は、
「こどもの頃にいわれた“悪いことをしたら地獄に落ちる”って話があるだろ?」
と前置きし、こういう。
「そんなもの、ないからわざわざ作ってるんじゃないか」(P223より)
そして、
「弱いやつらは本当のことには耐えられないんだよ。苦しみとか悲しみとかに、それこそ人生なんてものにそもそも意味がないなんてそんなあたりまえのことにも耐えられないんだよ」(P225より)
要するに、「苦しみの意味」とか「悲しみの意味」とか、もっといったら「人生の意味」とか「生きる意味」とか、そんなものはそもそもなくて、ないからこそ人々は「意味はあるのだ」と口々にいっているのであり、「意味」や「必然」なんてものは弱い者が作り上げた幻想である、というわけだ。
繰り返すが、百瀬にとって、世界のルールは「人々の欲求」と「ときどきの状況」だけである。
「苦しんでいる者」は、それらの組み合わせの中で「たまたま」苦しんでいるだけで、そこに「意味」とか「必然」など存在しない。
だけど、その事実に耐えられない人たちが「苦しみを乗り越えれば強くなる」とか「悲しみの先に救いがある」とか、「苦しみや悲しみは、神様がくれた試練なのだ」と言って、なんとか自分を支えようとしているだけ。
「理由のない苦しみ」を「不条理」と呼ぶ。
百瀬の「哲学」の根っこには「世界は不条理だ」というある種の諦めがあるのだ。
そして、人々がしがみついている「正義」とか「意味」とか「必然性」とかいったものは、その不条理に耐えられない「弱者」が泣く泣く作り上げた幻想なのだ。
以上が百瀬の「哲学」、すなわち「ニヒリズム」である。
スポンサーリンク
『ヘヴン』と「ニーチェ」

さて、ここまでコジマの哲学と、百瀬の哲学を考察してきた。
ざっくり言ってしまえば、
- コジマ……苦しみに意味がある。必ず酬われる日が来る。弱者は強く美しい。
- 百瀬……苦しみに意味はない。苦しむのは「たまたま」。弱者は弱者でしかない。
といった感じで、両者はまったく折り合わない。
それどころか、百瀬の「哲学」のほうが、この世界を上手に説明しているように見えてしまう。
辺りを見渡せば、正直者が馬鹿をみて、悪徳者がのさばっているではないか。
どうして、悪者はこの世からいなくならないのか。
どうして、悪者が正しく罰をうけないのか。
僕たちは、そんな憤りをいつも感じている。
「この悲しみには意味がある」とか、「この苦しみは酬われる」とか懸命に信じようとしても、「ほんとうにそうなのか?」と、疑いを捨てきることができない。
ぼくたちの世界は、そういう風にできている。
さて、ここまで読んでもらってうすうす気づいている人も多いと思う。
この『ヘヴン』を貫いている哲学は、ドイツの実存主義哲学者ニーチェの「ニヒリズム」ととてもよく似ているのだ。
というよりも、川上未映子はニーチェ哲学を作品に取り込もうと意識して創作したのだと、ぼくは断言したい。
『ヘヴン』というタイトルも、間違いなく、ニーチェが死刑宣告を下した「キリスト教」を意識したものだろう。
ニーチェは次のように断言した。
「キリスト教」は、弱者の「怨恨・憎悪・嫉妬」(ルサンチマン)が生み出したフィクションであり、「善」とか「悪」といった価値観もその延長にある価値観にすぎず、人々が大切にしている「道徳」なんてものは「弱者の道徳」(=奴隷道徳)なのだ、と。
「きっと神様が見てくれている」とか、
「苦しみが酬われる日はきっとくる」とか、
「悪いヤツには正しく罰が下る」とか、
そう信じている人たちに対して、
「それって弱者の現実逃避だよ」
と、無情にも「意味」とか「必然」とか、それらを与えてくれる「神」さえも完全否定してしまったわけだ。
「神は死んだ」
という、有名すぎるアレである。
このニーチェの道徳と『ヘヴン』の対応関係は、およそ次のようになる。
- コジマ = キリスト教徒(神はいる)
- 百瀬 = ニーチェ(神などいない)
「神はいる」と信じるコジマに対して「それはお前のルサンチマンだ」と百瀬が論破する。
これは今から約100年前に実際に起きた、思想的事件なのだ。
そして、その事件は現代においても大きな痕跡を残している。
というよりも、多くの人々が慢性的に抱えることになった苦しみ、悲しみ、空しさといったものは、ニーチェの「神の死」宣告によるところが大きいとさえいえる。
かつて人々に「生きる意味」を与えてくれた存在を信じられなくなった現代人は、まるで根無し草のようにこの不条理の世界を漂うしかない。
そんな中で、僕たちはいかにして「生きる意味」を見いだすことができるのだろう。
『ヘヴン』作中において、その難題を託された人物がいる。
それが主人公「僕」だ。
「僕」の実存的決定

世界の不条理や「ニヒリズム」を徹底的に書き上げた『ヘヴン』だが、この作品にはわずかな救いがある。
それは「僕」が自らの“斜視”について主体的な決断を下すからだ。
二ノ宮たちの凄惨ないじめをうけ、百瀬のニヒリズムに徹底的にやりこめられた「僕」が、それでも自らの運命に立ち向かい、強く生きようとする姿が最後の最後に描かれる。
もちろん、そこにいたるまでの「不条理」っぷりがあまりに凄いので、最後の描写の取ってつけた感は否めず、困惑してしまった読者も多いと思う。(すくなくとも、ぼくは困惑してしまった)
だけど、ここに『ヘヴン』が持つ、とても前向きなメッセージがある。
人々が「意味」や「必然」を失った今、それでも僕たちは、自らの運命を引き受けて生きていく強さが必要なのかもしれない。
自分を生きるのは、他でもない自分自身なのだ。
この取り替えのきかない自分、唯一無二の自分を生ききるための哲学を「実存主義哲学」と言う。
実は、「ニヒリズム」を解いたニーチェというのも、この「実存主義」の哲学者なのだ。
「神は死んだ」といったニーチェには、もう一つ有名な言葉がある。
「これが生きるということか、ならばもう一度」
たとえば、この不条理な人生が何度も繰り返されたとしても、その運命を受け入れて「人生」を強く肯定する大切さをニーチェは説いたのだ。
不条理な人生を肯定的に生きる者……
ニーチェはこれを「超人」と呼んだ。
主人公の「僕」には「超人」と言えるほどの強い覚悟はないかもしれない。
だけど、自分自身の人生を引き受け、実存的に生きていこうと決断を下したことに変わりはない。
『ヘヴン』は、人間が目を背けたくなるような虚無的な哲学を描いた「重い」作品である。
それでも「これが生きるということなんだ」と人生を肯定して生きる「僕」の姿を描くことで、読む人たちに勇気と力を与えてくれる、そんな作品なのだと、ぼくは思う。
川上未映子でオススメの本
『乳と卵』

第138回芥川賞受賞作。
作品の特徴はなんといっても、「大阪弁の冗長体」だ。
たぶん、はじめのうちは多くの人が抵抗感を抱くかもしれないけれど、読んでいるうちに その独特のリズムと詩的な趣で 次第にくせになると思う。
『乳と卵』の大きなテーマに、
「なぜ、世界は存在しているのだろう」
というものがある。
これもゴリゴリの哲学的なテーマなのだが『ヘヴン』同様に、グイグイ読ませる作品なので、構える必要はまったくない。
テーマとと文体が絶妙にマッチした、川上未映子の代表作だ。
なお、こちらで詳しく紹介・考察しているので、ぜひ参考にしてみてほしい。
【 考察・解説『乳と卵』(川上未映子)ー存在と不条理を哲学する「文学」ー 】
『夏物語』

『乳と卵』の後日譚といえる内容。
主人公は「夏子」はAID(非配偶者間人工授精)によって、子どもを産むことを決意する。
ここで問われるのは「命を生むこと」の是非だ。
「新たな命の誕生」は、一般的に喜ばしいことと捉えられている。
が、一方で、世の中には「反出生主義」といって、「この世界は苦しみであり、いかなる理由があっても、子どもを産むべきではない」と主張する人たちがいる。
作中においても「反主出生主義者」の女性が登場するのだけれど、作中においてもっとも悲しい存在として描かれている。(が、作中において最も吸引力があるのは、間違いなく彼女)
「存在することの苦しみ」
「存在することの不条理」
『ヘヴン』においても、これらのテーマが見て取れるが、それが深化拡充され、読者に提示される。
本書は読者にこう問いかけている。
「どうしてあなたは、人を産むのですか?」
川上未映子も注目! “Audible”とは
今、急速にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。
【 Audible( オーディブル )HP 】
川上未映子はそんなAudibleを高く評価している作家だ。
川上は「音声でしか表現できない世界」というものがあるとし、2021年に、
『春のこわいもの』
という、Audible本を書き下ろし、新潮社から配信した。

ここで強調したいのは、これが「音声先行」の作品だということだ。
これまでの【 書籍 → 音声化 】という流れではなく、作家が「音声」を前提に物語を創作したわけだ。
なお、朗読は女優の岸井ゆきの氏ということもあって、とても注目が集まる作品。
ちなみに、Audibleの最大のメリットは 月額1500円で人気作品が“聴き放題”となることだ。
たとえば以下のような作品が ”聴き放題”の対象となっている。

『推し、燃ゆ』(宇佐見りん)や、『むらさきのスカートの女』(今村夏子)や、『おいしいご飯が食べられますように』(高瀬隼子) を始めとした人気の芥川賞作品は、ほとんど読み放題の対象となっている。
しかも、芥川賞作品に限らず、川上未映子や平野啓一郎などの「純文学作品」や、伊坂幸太郎や森見登美彦などの「エンタメ小説」の品揃えも充実している。

それ他 海外文学、哲学、思想、宗教、各種新書、ビジネス書などなど、多くのジャンルの書籍が聴き放題の対象となっている。
対象の書籍は「12万冊以上」と、オーディオブック業界でもトップクラスの品揃え。
なお、Audibleの具体的なメリットは次の5つ。
1、時間を有効活用できる
2、新しい「文学鑑賞」ができる
3、貴重な講演が聞ける
4、月額1500円で“聴き放題”
5、30日間 完全無料で試せる
そして、今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、軽い気持ちで試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
・
・




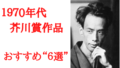
コメント