はじめに「愛する人と別れる」

たぶん、人生にとって、もっとも重大な事件は「愛する人」を失うことなのだ。
しかも、その重大な事件というのは「重大であるにもかかわらず」ある日、不意打ちみたいにやってきて、その人の人生を大きく変えてしまう。
もし、あの日が、最後の時間になると知っていれば……
もし、あの一言が、最後の言葉になると知っていれば……
どんなに悔やんでも、時の流れは残酷なもので、「あの日」に戻ることは決してできない。
まるで、自分だけが置き去りにされたみたいに、それでも世界は続いていくのだ。
吉本ばなな著『ムーンライト・シャドウ』は、不意打ちみたいに襲ってきた「愛する人との死別」に困惑し、苦しみ、悲しみ、そして祈る、「私」と「柊」の切ない物語だ。
(『ムーンライト・シャドウ』は、こちら『キッチン』に収録されている)
「愛する人」を突然失ったとき、きっと、誰しもがこう思う。
……せめてもう一度だけ会いたい。
作品の中で、柊が恋人「ゆみこ」の面影を追うように、テニスショップのショーウインドウの前に佇むシーンがある。
彼の姿をみた「私」は、柊の胸中を推し量って、こう考える。
彼の全身が、瞳が、ひとつの言葉を語っていた。彼は決して言葉にはしないだろう。しかし、それは もしも言うならつらい言葉だった。すごくつらい。それは、
――戻ってきてほしい――だ。
言葉と言うよりは、祈りだった。(P183より)
「戻ってきてほしい」という切実な祈りを言葉にしないのは、たとえそれを口にしたところで現実には起こりえないことを柊は知っているからだ。
その祈りが切実であればあるほど、言葉は虚しく響いてしまい、自分自身をいっそう苦しめることになってしまう。
だから、彼は、その祈りを決して言葉にしないのだろう。
だけど、その切実な祈りが、もしも何かに届くならば……
もう一度だけ、愛する者と言葉を交わすことができるならば……
1人の人間が、こんなにも苦しんで、こんなにも祈っているのだ。
きっと、多くの人たちは、こう思うはず。
それくらいのこと、この世界にあったっていいじゃないか
『ムーンライト・シャドウ』は、ぼくたち読者に、美しくて優しい奇跡を、そっとみせてくれる。
- 「愛する人と正しく別れること」
- 「愛する人とともに生きること」
そんなことについて考えさせてくれる。
この記事では、吉本ばななの傑作短編『ムーンライト・シャドウ』で描かれた世界について、ぼくなりに考えるところを、いくつか書いてみたい。
「私」と「柊」にとって死別とは

「私」と柊には共通の悲しみがある。
それは、「愛する人を失ったこと」だ。
「私」は恋人の「等」を、柊は恋人のゆみこと兄の等を。
彼らの死は、ある日突然やってきた。
ゆみこを乗せ、等が運転する車が事故にあってしまったのだ。
その死が突然だったからこそ、「私」も柊も、彼らの死を受け入れることができない。
そして、今もなお、前に進むことができないでいる。
たとえば、「私」と柊、2人はそれぞれ「恋人」の面影にしがみついている。
「私」がしがみついているものは、
- 最後の別れ場所となった「橋」
- 等の面影のある「柊」
である。
一方の柊がしがみついているものは、
- ゆみこのスカート
である。
もっとも、柊の場合は「ゆみこを連想させるもの」と言うことができるかもしれない。
その1つの表れとして、彼はテニスショップのショーウインドウに佇んでいる。
それは、まるで、子アヒルが母親の姿を追うように。
すり込みみたい、と私は思った。子アヒルが初めて動いたものを母と思い込んでついて歩く姿は、子アヒルにとってはなんでもなくても見る者の胸を打つ。
こんなに打つ。(P180より)
しかし、「私」だって、それは同じ。
続けて、こう思う。
テニスのもののそばにいると、彼は多分なつかしい気持ちになれるのだろう。私が柊といる時だけ、等の面影の分、落ち着くのと同じに。それは悲しいことだと思う。(P181より)
彼女もまた、まるで愛する等を追うように、柊の中に等の面影を探している。
2人が死んでから、2ヶ月が経った。
だけど、「私」と柊の時間は、止まったままなのだ。
私も、会いたい。等に。戻ってきて、ほしいと思う。せめて、ちゃんとお別れを言いたかった。(P183より)
2人の時間が動くために、2人が前に進むために、どうしても恋人に会わなければいけない。
不意打ちのように「愛する者の死」に襲われたものが時間を取り戻すためには、「愛する者」と正しく別れること、そして正しく悲しむことが必要なのだ。
スポンサーリンク
「うらら」について

苦しみを紛らわすように、「私」は早朝にジョギングをしている。
目的地は、等と最後の言葉を交わした、あの「橋」である。
あるとき「私」は、そこで不思議な女性と出会った。
その女性が普通の人間でないことを、すぐに「私」は直感として理解する。
あまりにも彼女は知的で冴えた瞳をしていて、まるでこの世の悲しみも喜びもすべて飲み込んだ後のような深い深い表情を持っていた。そのために、しんと張りつめた空気が彼女と共にあった。(P156より)
そして女性は、まだ出会って間もない「私」に、こんなことを言ってきた。
知ってる? もうすぐここで百年に一度の見物があるのよ。(P157より)
「うらら」と名乗るこの女性。
この不思議な女性に、「私」は興味を抱いていく。
彼女は、妙だった。彼女の言っていることはさっぱり分からなかったが、どうも普通に暮らしている人間ではないように思えた。
(中略)
――いったい、どういう人なんだろう。(P158より)
この「うらら」が、作品において果たす役割は大きい。
「私」が等に出会うために、うららの存在は必要不可欠だったからだ。
後に「私」は、百年に一度という「奇跡」を振り返り、こう述懐している。
後から思えば、運命はその時一段もはずせないハシゴだった。(P171より)
その「運命」へと続くハシゴの一段目は、まちがいなくこの「うらら」だったと言える。
さて、ではこの「うらら」は一体何者なのか。
彼女もまた「変な形」で恋人と死に別れ、その恋人と「最後の別れ」をするために、この街にやってきたことが 後々明らかになる。
どうやら、「私」と同じような境遇にありそうなのだが、やはり彼女は「普通に暮らしている人間」には見えない。
たとえば、突然うららが「私」に電話を掛けてくるシーンがある。
「突然ですけど、今ひまかしら。出てこれないかな」
「ええ……いいですけど。どうして? どうしてうちが分かったの?」
私はおろおろとした声で言った。電話の向こうは外らしく、車の音が聞こえる。彼女がふふ、と笑うのが分かった。
「どうしても知りたいな、と思うと自然に分かるようになってるの」
と呪文のようにうららは言った。
こんな風に、明らかに普通の人間と思われない「うらら」
繰り返すが、「私」が等と出会えたのは、そんな「うらら」の手引きがあったからだ。
「うらら」は、「百年に一度の見物」について、なぜか詳しい。
それが起きる時間と場所、それだけでなく、それが起きるための条件まで知っているのだ。
この辺りからも、うすうす察しはつく。

うららはこの世ではない「異界」の住人なんじゃない?

その「異界」とは、「死者の国」なんじゃない?
とすると、うららの言う「恋人との変な形での別れ」というのは、「うららの死によるもの」ということになる。
――もう一度会いたい。
こんな風に思っているのは、生きている者ばかりではない。
死んでしまった者もまた、同じくらいの熱量で、生きてる者を思っているのだ。
「うらら」はある意味で、死者の「思念」の具現としても描かれているのだろう。
そして彼女は、「生者の国」と「死者の国」とを結ぶ「仲介人」のような役割も果たしている。
「生者」と「死者」が出会うための条件は、「うらら」によってこう説明される。
死んだ人の残留した思念と、残された者の悲しみがうまく反応した時にああいうかげろうになって見えるのよ。(P195より)
「百年に一度の見物」は、等やゆみこが死してもなお「私」や「柊」を思っていたからこそ起きた奇跡なのだ。
スポンサーリンク
「七夕現象」の条件

死別してしまった「愛する者同士」が出会う奇跡を、うららは「七夕現象」と説明する。
その条件として考えられるのは、
- その日の天候
- その人のコンディション
- 互いの思念
少なくとも、この3つはあげられる。
そして、ここに、もう少し説明を加えるとすれば、
- 月が出るほど晴れていること
- 万全な体調であること(病み上がりであること?)
- 「会いたい」という互いの思いが反応すること
ということになるだろうか。
おそらく、これ以外にも条件はある。
しかも、うららの説明には「かもしれない」が連発する。
実際のところ彼女にも良くわからないところがあるのだろう。
ここで ぼくは、うららの説明にはない もう「1つの条件」をあげたい。
それは七夕現象が起こる場所に関する条件だ。
七夕現象が起こる場所、そこは、
「愛する人」と最後に別れた場所
だと思われる。
たとえば「私」が七夕現象に立ち会ったのは、つまり、等と再会できた場所は「橋」だった。
その「橋」とは、等が生きていたころ 2人がいつも別れた場所であり、あの事故の日も、最後の別れとなった場所である。
七夕現象の条件には「会いたいという互いの思いが反応すること」とある。
たぶん その思いが最も強く反応する場所は「2人が最後に別れた場所」なのだろう。
もっとも、うららは、七夕現象について「大きな川のところでしか起こらない」と説明をしているが、それはたぶん間違っているのだ。
そうぼくが考える根拠に、柊が立ち会った七夕現象がある。
「おとといの朝だったかな」
彼は続けた。
夢だったかもしれない。うとうと眠ってたら急にドアが開いて、ゆみこが入って来たんだよ。あんまり普通に入ってきたもので、死んだことを忘れて、ゆみこ? ってきいたら、しーっっと言って人さし指をたてて、笑った。……やっぱり、夢っぽいな。それから、ワタシの部屋のクロゼットを開けて、セーラー服をていねいに取り出して、抱えていってしまったよ。ばいばいって口を動かして、笑って手を振って。(P198より)
柊の七夕現象は、彼の部屋で起きた。
なぜ「大きな川」ではなく、「彼の部屋」だったのかと言えば、そこが2人にとって「最後の別れの場所」となったからだ。
ゆみこは、等の運転する車で駅に向かう途中、事故にあって死んだ。
おそらく、柊の家を出る際に、最後の別れの言葉を交わしたのは、彼の部屋だったのだろう。
死んでいった人の思いがこの世界に残るとすれば、それはどこか。
それはきっと、残された人たちとの関係性によって異なるのだろう。
ただ、間違いなくその1つに「最後の別れの場所」がある。
それは「私」にとって「橋」であり、柊にとって「彼の部屋」だった。
私と柊に共通しているのは、「心の準備も何もないまま、恋人と死別したこと」である。
あの日、あの瞬間が、自分たちにとって最後の時間になると分かっていれば……
「私」と柊の胸には、そんな後悔の念が強くあったはずだ。
七夕現象は、そんな2人の強い思いが、等やゆみこの思いと交わって起きたのだろう。
死者である等とゆみこにも、「私」や柊への強い思いがあるのだから。
スポンサードリンク
「赤」と「青」が表すこと

作中では、様々なものが象徴的に描かれている。
その中から「赤」と「青」という色について説明をしたい。
そもそも、「死んでいった人たちの思い」とは、一体なんなのだろう。
等やゆみこは、どんな思いで、私と柊のもとへ現れたのだろう。
それは、七夕現象における2人の様子を見ればあきらかだ。
等の場合、こんな風に記される。
等もまた、悲しそうに私を見つめる。時間が止まればいいと思い、――しかし、夜明けの最初の光が指した時にすべてはゆっくりと薄れはじめた。見ている目の前で、等は遠ざかっていく。私があせると、等は笑って手を振った。何度も何度も手を振った。青い闇の中へ消えてゆく。私も手を振った。(P194より)
次にゆみこの場合、柊の説明をもう一度 引用する。
夢だったかもしれない。うとうと眠ってたら急にドアが開いて、ゆみこが入って来たんだよ。あんまり普通に入ってきたもので、死んだことを忘れて、ゆみこ? ってきいたら、しーっっと言って人さし指をたてて、笑った。……やっぱり、夢っぽいな。それから、ワタシの部屋のクローゼットを開けて、セーラー服をていねいに取り出して、抱えていってしまったよ。ばいばいって口を動かして、笑って手を振って。(P198より)
ここから分かることは、明らかに彼らが「最後の別れ」をしようとしていることだ。
等も、ゆみこも、笑って手を振っているからだ。
ただしそれは、決して悲観的な別れではない。
それはちょうど、
「だいじょうぶ、あなたなら、ちゃんと生きていける」
と、そっと背中を押すような、優しさに満ちた別れなのだ。
そして、彼らは、「私」や柊が前に進むために、この世界に現れたのだ。
作中において「赤」と「青」という色が、とても象徴的にちりばめられている。
たとえば、一番最初に「赤」と「青」が印象的に描かれるのは、私と柊が、事故現場で立ち止まるシーンだ。
街を抜ける大きな交差点の所で、私も柊もほんの少し気づまりを感じる。そこは、等とゆみこさんの事故の現場だった。今も、激しく車がゆきかっている。赤信号で、柊と私は並んで立ち止まった。
(中略)
「青だ」
柊が私の肩を押すまで、私はぼんやりと月を見ていた。(P167より)
言うまでもないが、「赤」と「青」それぞれが表しているのは、
- 「赤」・・・そこに留まり続けること。
- 「青」・・・前に進んでいくこと
である。
そして、「赤」と「青」という色は、「七夕現象」の直前で繰り返し登場する。
たとえば、発熱する「私」の顔は「赤く」描かれるし、そこにやって来るうららは「青い」服を着ている。
そして、熱に冒され朦朧とする「私」の意識は、こんな風に描かれている。
夜明けの青と熱がすべてをかすませ、私には夢とうつつの境目がよくわからなかった。(P186より)
これは、「未来(=青)」と「過去(=赤)」の狭間で揺れる「私」を象徴する描写だ。
この後「私」は等と再会するのだが、「赤」と「青」はここでも象徴的に描かれる。
しんしんと凍りつくような、月影が空にはりつくような夜明けだった。私の走る足音が静かな青に響き渡り、ひそやかに吸い込まれて街に消えていった。(P191より)
星がひとつ二つ、消えそうにほの白く、ちらちらと青磁の空にまたたいていた。
それは、ぞっとするくらい美しい光景だった。川音は激しく、空気は澄んでいる。
「体まで青にとけそうに青いね」
手をかざして、うららが言った。(P192)
そして、等は、そんな「青い夜明け」のかすみの中で現れ、「だいじょうぶ、あなたなら前に進める」と言うかのように、「私」に優しく手を振り続ける。
スポンサーリンク
「夜明けの月」が表すこと

『ムーンライト・シャドウ』という作品で描かれるのは、
「過去にとどまる者が、未来に向かって歩いて行く姿」である。
言い換えれば、それは、
「2人の思い出に、ずっと留まっていたい」という思いと、
「前に向かって生きていかなくてはいけない」という思い、
その狭間で葛藤する人間の姿でもある。
そんなふうに揺れ動く「私」や「柊」の思いは、「赤」と「青」という象徴的な色で、巧みに、そして美しく描かれていることは、今まで見てきたところだ。
同じように「夜明けの月」もまた、前に進もうとする「私」の思いを象徴している。
「夜明けの月」は別名「有明の月」と呼ばれている。
夜が「明」けてもなお、空に「有」りつづけるのがその由来だ。
その名残惜しげな様子から「名残の月」とも呼ばれている。
さらに「有明の月」は、古くから日本の和歌や文学において「別れの名残」を象徴するものとして扱われてきた。
たとえば、平安時代の貴族たちの恋。
恋人たちが出会えるのは、日中ではなく夜であり、夜が明けてしまえば、彼らは別れなければならない。
まだまだ別れたくはないけれど、どうしたって別れなくてはいけない。
そんな思いを抱く恋人たちの頭上には、ぼんやりした影を持つ「有明の月」が浮かんでいる。
こんなふうに、日本では、夜明けの「月明かり」が「別れの悲しみ」にくれる男女を静かに照らしてきたのだ。
「私」と等が再会したときも、空には有明の月が浮かんでいた。
私たちはただ見つめ合った。二人をへだてるあまりにも激しい流れを、あまりにも遠い距離を、薄れゆく月だけが見ていた。(P193より)
運命はもう、私とあなたを、こんなにはっきりと川の向こうとこっちにわけてしまって、私にはなすすべがない。涙をこぼしながら、私は見ていることしかできない。等もまた、悲しそうに私をみつめる。時間が止まればいいと思い――しかし、夜明けの最初の光が射した時にはすべてはゆっくりと薄れはじめた。(P194より)
作品において「ムーンライト」つまり「月明かり」に託されたもの。
それは、
愛し合う者たちの「別れの名残」と、それでも前に進もうとする者の「哀切な思い」なのだろう。
スポンサーリンク
・
終わりに「 “なにか”について」

「生き残った者」にとって「死んでいった者」とは、どんな存在なのか。
それについて、ぼくが感じたことを書いて、この記事を終わりにしたい。
それを考える上で、作中のある箇所を引用したい。
それは、「私」と等が最後の別れを果たし、その後に続く場面だ。
別れの余韻に胸が痛む「私」だが、彼女は“なにか”の存在を強く感じる。
私はその時 目の前でほほえむうららを見ながら、薄いコーヒーの香りの中で、自分が非常に“なにか”の近くにいると強く感じた。風で窓ががたがた揺れる。それは、別れる時の等のように、どんなに心を開いて目をこらしても確実に通り過ぎていってしまうものだった。そのなにかは太陽のように闇の中で強く輝き、私はすごい速さでそこを通過する。賛美歌のように祝福が降りそそぎ、私は祈る。
“もっと、強くなりたい”と。(P197より)
この“なにか”とは、いったい何なのだろう。
「私」の説明をたよりにすれば、
「確実に通り過ぎてしまうもの」であり、
「太陽のように闇の中で強く輝くもの」だという。
もちろんここは、読者によって 色んな解釈ができると思う。
たとえば、その解釈として
- “なにか” = 「時間」
- “なにか” = 「運命」
というものもあげられるだろう。
実際、作中において「流れていく時間」とか「『私』を押し流す運命」は、「川の流れ」によって象徴的に語られている。
物語のラストで、「私」はこういう。
ひとつのキャラバンが終わり、また次がはじまる。(P200より)
こういう「私」の思いとは、どんなものなのだろう。
――等は死んでしまったが、それでも時間は流れていくのだ――
――自分はもっと強くならなくてはならない――
――等と決別し、前を向いて歩いて行かなければならない――
「私」の胸には、等との死別を「克服」しようという思いがあるのかもしれない。
だけど、と、ぼくは思う。
だけど、ぼくたちは死者と「決別」しなければならないのだろうか。
ぼくたちは愛する者との死別を「克服」しなければならないのだろうか。
いや、そんなことはない。
「死者」とは、生き残った人たちの傍で、ちゃんと実在しているからだ。
「決別しよう」とか、「克服しよう」とか、そんな風につよく生きようと願う人の近くで、彼らはずっと案じてくれているからだ。
たぶん、「私」が感じた“なにか”は、時間とか運命ではないのだ。
その“なにか”は、これからずっと「私」の近くにあり続ける「等」なのだ。
彼は確かに死んでしまったが、今度は生前とは違ったあり方で実在し続けていく。
そして、まるで「太陽のように」闇の中で輝き、「私」を照らし続けていく。
だから、「私」は等を通過する必要なんてない。
いや、たとえ「私」が「通過しよう」と思ったとしても、それでも等は傍にいてくれる。
愛する者は、ずっとずっと、生き残った者を、案じてくれているはずなのだ。
ぼくは『ムーンライト・シャドウ』を読んで、強く思った。
死者とは「決別」するものでも、「克服」するものでもない。
死者とは「共に生き続ける」ものなのだ。
映画「ムーンライトシャドウ」
映画「ムーンライトシャドウ」はU-NEXTで視聴ができる。
そして【 U-NEXTのHP 】から 31日間の無料体験が可能。

U-NEXTの動画配信数は 21万本以上と 数ある動画配信サービスの中でNO1。
さらに、映画・ドラマ・アニメなどの動画だけに限らず、マンガ・ラノベ・書籍・雑誌など、幅広いコンテンツも配信中で、ひとつのサービスで”観る”も”読む”も楽しむことができる。
1 月額2,189円で見放題・聞き放題
2 スマホ・タブレット・PC・TV、あらゆるデバイスで楽しめる
3 毎月新作レンタルに使える1200ポイントがもらえる
(実質月額990円になる)
4 31日間 完全無料で試せる
U-NEXT(ユーネクスト)のHP

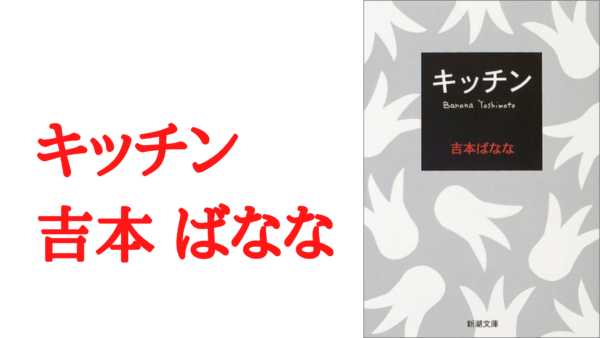


コメント
はじめまして。こんな風にコメントを書くのは始めてです。
高校生の頃読んだ作品で、私はさっと読み終えました。その後なんとも言えない感情が込み上げて泣いてしまいました。そのなんとも言えない感情を、こんなにも優しく明確に説明してくださったのはあなたが初めてです。ありがとうございました
コメントありがとうございます。そう言っていただけて、僕もとても嬉しいです。
僕自身も学生のころに読んだ作品で、当時は読み終えた後も余韻を引きずって、生活どころじゃなかったという思い出があります。
きっとしろしたもちさんも、似たような深い感動を味わったのでしょうね。こうして素晴らしい作品を通じて、色んな人と共感できることが僕にとってはこの上ない喜びです。また、お時間のあるときに、ブログをのぞいていただけると嬉しいです。改めて、嬉しいコメントありがとうございました。