はじめに「哲学」って何?
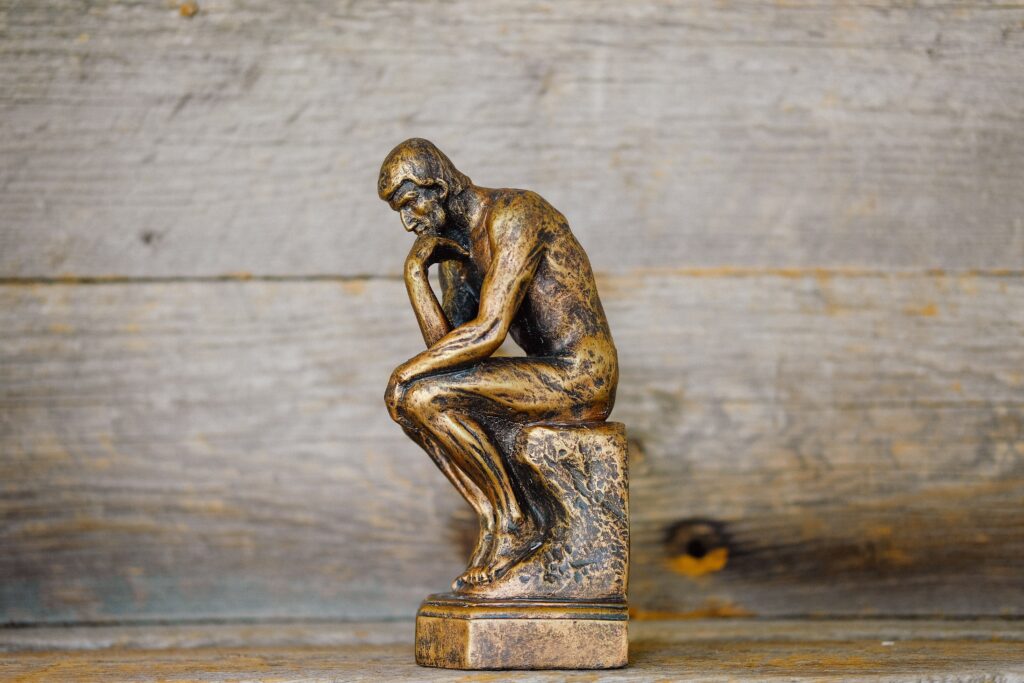
「哲学」と聞いて、あなたはどんな印象を持つだろう。
たぶん多くの人は、高校時代に勉強した「倫理」を連想したり、ソクラテスだのプラトンだのアリストテレスだのといった有名な哲学者を思い浮かべたりするかもしれない。
あるいは「無知の知」とか、「三角形のイデア」とか、例の哲学用語を思いだ出したり、『純粋理性批判』とか『精神現象学』とかいった有名な書物を思い出したりするかもしれない。
すると、人々の感情として、
「哲学=なんだか小難しいもの」とか
「哲学=自分とは無縁なもの」とか
とにかく、哲学に対する「あまりよくない印象」を持つにいたってしまう。
だから、急いで強調しておきたいことがある。
それらを全部「哲学」ではない。
あえて言えば、それらは全部「哲学史」なのである。
「ソクラテス」とか「イデア論」とか「純粋理性批判」とかを覚えることは、言うまでもなく哲学の本質なんかじゃない。
「哲学」というのは、本来もっとおもしろくて、スリリングで、ちょっと恐ろしいもので、つまるところ、ずっとずっと魅力的なものなのだ。
この記事では、そんな哲学の主要テーマについて紹介したい。
今回扱うテーマをざっくりと言えば、
「この世界は、ひょっとして存在していないのかもしれない」
といった問いである。
こうした問いは、哲学では「意識」とか「実在」とか「他者」とかいった言葉で議論されるものだ。
では、最後までお付き合いください。
意識上のコーヒーカップ

さっそくだが、とりあえずスマホ(もしくはPCの画面)から顔を上げ、いま眼前に広がるあなたの「世界」に意識を向けてほしい。
一体どんな「世界」が広がっているだろうか。
たとえば、今、あなたの目の前にコーヒーカップがあったとしよう。
そのコーヒーカップは真っ白い色をしていて、“theコーヒーカップ”ともいえる典型的なフォルムをしていて、中からは熱々の湯気が立ち上っていて、コーヒーの香ばしい匂いがあなたの鼻をくすぐってくる。
以上がコーヒーカップを前にしたあなたの具体的な体験なのだが、そうした体験ができるのも、あなたに「意識」があるからだといっていい。

いきなり何を言い出すかと思ったら、そんな当たり前のこと?
と、拍子抜けするのはちょっと待ってほしい。
さて、ここであなたに1つ質問を。
もしも、今、世界中の人間全員が突然死んだとしたら、目の前のコーヒーカップは変わらずに存在し続けるだろうか。
「?」で頭がいっぱいなあなたに対して、さらにこう問うてみたい。
そもそも目の前のコーヒーカップというのは、あなたが「知覚したまま」の姿で存在しているのだろうか。
スポンサーリンク
意識上の世界は絶対じゃない

目の前のコーヒーカップは「見たまま」の姿で存在しているのか?
さきほど、こんな突拍子もない質問をあなたにぶつけたわけだが、実はこれこそが哲学の主要テーマの1つ「存在論」と呼ばれる議論なのである。
一般的に人々は、
「世界は見た通り、聞こえた通り、感じた通りに存在している」
と、目の前の世界を信じて疑わない。(こうした考えを“素朴実在論”と呼ぶ)
「世界は客観的な姿をしているし、その通りに確かに存在している」というわけだ。
ところが、哲学ではそうした「客観的世界」や「世界の確かさ」について疑ってかかる。
すると、これまで自明視していた「世界」というのが、いよいよ怪しいものに思えてくる。
たとえば、僕たちはこの世界を「五官」を通じて認識しているワケだが、他の動物はといえば僕たちとは全く異なる方法で世界を認識している。
ダニを例に挙げてみよう。
ダニには「視覚器官」や「聴覚器官」がない。
彼らが世界を認識する際に頼りにするのは「嗅覚」と「温度感覚」、「触覚」、「光の方向」だけらしい。
とすれば、ダニたちは僕たち人間とは全く違う仕方でこの世界を経験していることになるだろう。
コウモリだってそうだ。
一部のコウモリは「視覚機能」が退化していて、目が見えていないと言われている。
では彼らがどのように世界を認識しているのかというと、口から超音波を出して、反射してきたそれによって世界を認識しているのだという。
彼らもまた、人間とは全く異なる仕方で、この世界を経験しているワケだ。
ほら、僕たちが信じる「客観的世界」なんてのは、なんら絶対的なものではないことが分かってくる。
とすれば、「五官」でしか世界を認識できないあなたは、目の前のコーヒーカップの「本当の姿」を知らないことになる。
なぜなら、あなたの目に映ったコーヒーカップは、あくまでもあなたの「視覚」によってとらえられ、あなたの「意識」に上ったコーヒーカップにすぎないからだ。
この事情は、なにもコーヒーカップに限ったことじゃない。
あなたが見ているスマホのディスプレイも、手にしたスマホの感触も、窓から入ってくる心地よい風も、つけっぱなしのテレビの音も、ちょいちょいつまんでいるポテチの味も……
あくまでもそれらは全て、あなたの「意識」に上った姿であって、あなたはそれらの「本当の姿」を知覚しているわけじゃない。
ここで改めて、先ほどの質問をしよう。
「もしも、今、世界中の人間全員が突然死んだとしたら、目の前のコーヒーカップは変わらずに存在し続けるだろうか」
「目の前のコーヒーカップというのは、あなたが「知覚したまま」の姿で存在しているのだろうか」
これらの問いは、
「世界は確かに存在しているのか?」
「世界は客観的に存在しているのか?」
と言い換えることができる。
スポンサーリンク
「意識の世界」と「実在の世界」
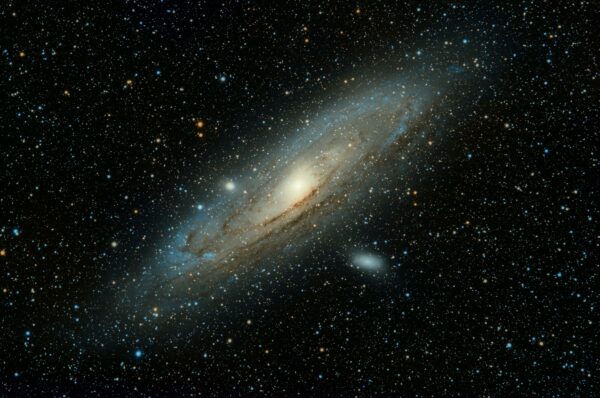
あなたが見て、聞いて、感じた世界——それを「意識の世界」と呼ぶ。
それに対して、あなたの「意識」に上る以前の世界——それを哲学では「実在の世界」と呼ぶ。
「実在の世界」とは、ザックリといってしまえば、人間の知覚以前の「本当の世界」のことであり、繰り返すが、あなたは普段その「実在の世界」に触れているわけではない。
あなたが触れているのは、その「実在」が引き起こしたと思われる「意識の世界」なのだ。
あなたが知覚する「日差しのまぶしさ」も、「うるさい蝉の声」も、「コーヒーの味」も、全てはあなたの「意識」でしかない。
とすると、あなたが経験できるのは、結局のところ「意識の世界」だけということになる。
ここでちょっと怖い話をしてみよう。
なるほど、僕たちは「実在の世界」を知ることができない。
あるのはただ「意識の世界」にすぎず、あなたが知りうるのも「意識の世界」だけだ。
そして、この「意識の世界」は、どうやら「実在の世界」がもととなって生じているらしい。
机の上にコーヒーカップがあったとすれば、「実在世界」にもコーヒーカップはあるはずで、コーヒーカップが「実在」しているからこそ、あなたの「意識」にコーヒーカップが現れるというわけだ。
だけど、本当にそうなのだろうか。
たとえば、こんなことは考えられないだろうか。
――実は、あなたの脳みそはコンピュータにつながれて、そこから直接「コーヒーカップ」の電子情報が与えられているため、あなたの「意識」上にコーヒーカップが立ち現れている――
どうだろう。
こんな話を聞くと、僕たちが信じる「この世界の確かさ」が、まるで指の間から砂がこぼれ落ちるように、ジワリジワリと失われていかないだろうか。
「あなたが見ているスマホのディスプレイも、手にしているスマホの感触も、窓から入ってくる心地よい風も、つけっぱなしのテレビの音も、ちょいちょいつまんでいるポテチの味も・・・・・・すべては、あなたの脳に直接流し込まれた電子情報である」
そう言われたとしても、それを打ち消すことはどうあがいたって、あなたには絶対できない。
「実在の世界」と「意識の世界」
その2つの間に因果関係を認めることは原理的にできないのだ。
いや、もっといえば、「意識の世界」にそもそも“原因”があるのかさえ、僕たちには分からない。
こんな感じで、哲学は「客観的な世界」どころか「世界の確かさ」までも疑ってかかる。
スポンサードリンク
「独我論」とは何か

「実在の世界」と「意識の世界」に因果関係なんてないんじゃないか?
「意識の世界」に“原因”なんてそもそもないんじゃないか?
そんな疑問を突き詰めて考えていくと、僕たちは次の根本的な疑問に行き着いてしまう。
――この世界は本当に存在しているのだろうか――
先ほど僕は「実在の世界 = 本当の世界」といった話をしたわけだが、そもそも、その「本当の世界」の存在さえ怪しくなってくる。
そもそも「本当の世界」なんてなくて、あるのはあなたの「意識の世界」だけ。
あなたを取り巻く「外界の世界」なんて、そもそも存在していない。
これは恐ろしいことだ。
だって、コーヒーカップ以外にも、あなたの家族、友人、恋人、というか「あなた自身の肉体」さえも、あなたの「意識の世界」の一部に過ぎないということになり、つまり全ては「本当は存在していない」ということになってしまうからだ。
「外界は存在しない。唯一存在するのはあなたの意識だけ」
このなんとも不気味で恐ろしい考えを、哲学では「独我論」と呼んでいる。
「独我論」に立った時、この世界は次のように結論できる。
――すべては「私」の死とともに終わる――
あなたの消滅とともに、家族も、友人も、恋人も、みんな消滅してしまうのだ。
どうだろう。
そうはいっても、この独我論は、僕たちの生活実感からあまりにかけ離れている。
それに心の底から独我論を信じてしまえば、僕たちが社会生活を送ることはまずできない。
だから、哲学の議論において、この独我論を持ち出すのはある種の“タブー”だといっていい。
それを言っちゃオシマイでしょう、ってな話なのだ。
もちろん、僕たちは、僕たちの「意識の世界」をスタート地点としなければならない。
哲学もそこから始まる。
哲学というのは「意識」の世界を認めながらも、その自明性を相対化しつつ、
「世界って本当に存在しているの?」
「他者って本当に存在しているの?」
こうした問いに、積極的に立ち向かっていく営みであるといっていい。
スポンサーリンク
おわりに「哲学」は“薬”にならない

以上、哲学のテーマとして「実在の世界」と「意識の世界」について解説をしてきた。
僕たちが経験している「世界」は、あくまでも「意識の世界」であって、僕たちは「世界の実相」に触れているわけではない。
というよりも、つきつめて考えていくと、「本当の世界なんて、そもそもないんじゃないか?」という考え(独我論)に陥ってしまう。
「哲学」というのはそれほどスリリングで、不気味で、怖ろしいものなのだ。
さて、ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
記事を読み終えたあたなは、ひょっとしてこんな風に感じたかもしれない。

いや、こんな問題、そもそも答えなんてでないし考えるだけ時間の無駄でしょ
はい、まったくもってその通り。
哲学なんてやったって、時間の無駄なのだ。
病気が治るわけでもないし、出世するわけでもない。
名声が手に入るわけでもないし、お金持ちになれるわけでもない。
いや、なんならこんなメンドクサイことを考えていたら 友だちが減るかもしれないし、彼女にフラれるかもしれないし、社会的な信用を失ってしまうかもしれないのだ。
哲学は「毒」にこそなれ、「薬」になることはない。
だけど、哲学することは、上記の通りとってもスリリングであるし、おもしろいと僕は思う。
というより僕自身、やっぱり不思議でならないのだ。この「世界」ってやつが。
「世界って本当は存在していないんじゃないの?」とか
「時間が“流れる”っていうけど、一体何が流れてるの?」とか
「僕が死んだら、僕は、この世界はどうなるの?」とか
少しでもそうした問いにとらわれてしまったことがある人にとって、哲学はとっても親和性のある世界だ。
この記事を読んで共感していただいた方は、ぜひブログ内の【哲学】の記事を参考にしていただきたい。
あなたの“ワクワク”や“ゾクゾク”のお供になれたなら、とても嬉しく思う。
オススメの本
『哲学の謎』(野矢茂樹)
この記事の多くは、本書を参考にしている。
筆者の野矢茂樹は、日本の哲学界を代表する哲学者。
著書が多く、読みやすいものから本格的なものまで幅が広い。
本書は、中でもとても読みやすい一冊で「対話形式」なので、議論がスッと頭に入ってくる。
小難しい哲学用語は一切出てこないが、本書を読めば「哲学の魅力」を理解することができるはず。
100の思考実験(ジュリアン・バジーニ)
タイトルの通り、100の哲学的な「思考実験が」が収められている。
「思考実験」というのは、現実にはあり得ない状況を想定し、その状況を突き詰めて考えていく「頭の中での実験」のことだ。
中にはデタラメで馬鹿げた実験もあるのだが、それらは例外なく僕たちの「あたりまえ」を覆す可能性を秘めている。
本書は、そんな哲学的議論をコンパクトにまとめ、議論の問題点や、様々な立場を整理してくれるので、哲学初心者から中級者まで楽しめる一冊となっている。
1項目が数ページで完結し、読み切りになっているのも嬉しい。、
超オススメ。
「哲学」をするなら……
耳読書「Audible」がオススメ

今、急激にユーザーを増やしている”耳読書”Audible(オーディブル)。【 Audible(オーディブル)HP 】
Audibleを利用すれば、哲学書・思想書・宗教書が月額1500円で“聴き放題”。
例えば、以下のような「解説書」も聴き放題の対象だし……

・
以下のような「原著」も聴き放題の対象となっている。
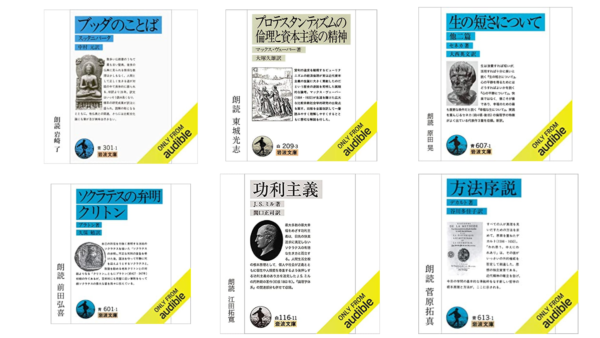
・
それ以外にも純文学、エンタメ小説、海外文学、新書、ビジネス書、などなど、あらゆるジャンルの書籍が聴き放題の対象となっていて、その数なんと12万冊以上。
これはオーディオブック業界でもトップクラスの品揃えで、対象の書籍はどんどん増え続けている。
・
・
今なら30日間の無料体験ができるので「実際Audibleって便利なのかな?」と興味を持っている方は、軽い気持ちで試すことができる。(しかも、退会も超簡単)
興味のある方は以下のHPよりチェックできるので ぜひどうぞ。
.
・
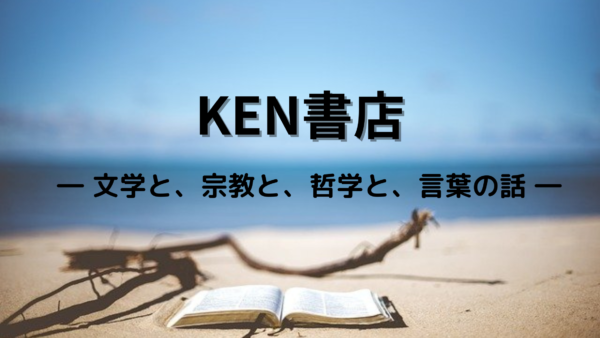
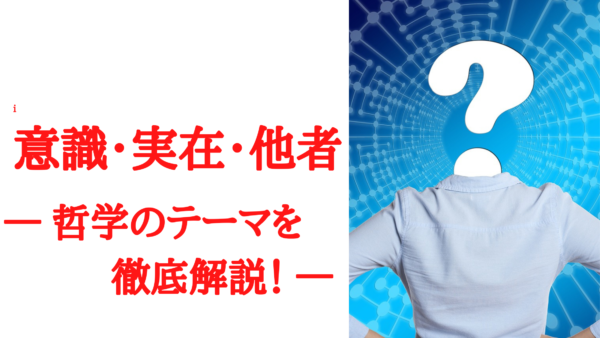
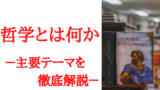

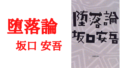
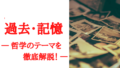
コメント